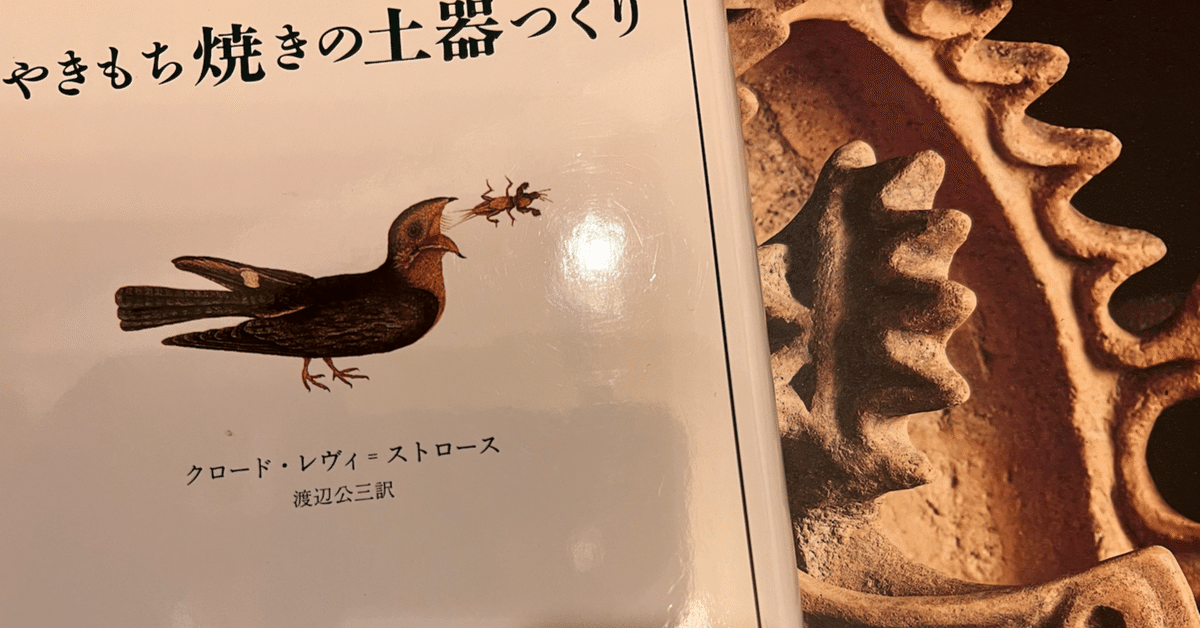
意味分節理論とは(7) 意味分節理論で読む「やきもち焼き」とアーレントの<超意味>と動きを象徴する土器と
クロード・レヴィ=ストロース氏の著書『やきもち焼きの土器つくり』の序文の一節に次のようにある。
「神話的思考が、すでにのりこえられた知的活動形態であるどころか、精神が「意味とは何か」を問うときにはつねに、そして今も働き続けているのではないか、という問いを提起する。」
”土器つくり”というのはその名の通り「土器を作るひと」である。
神話なので、その「ひと」はバイオロジカルなサピエンスに限らず、神であったり、動物であったり、天体であったり、植物の精のようなものだったりもする。
その「土器つくり」が「やきもち焼きである」という。
一体どういう話なのだろうか。
詳しくはぜひ手に取って読んでいただければと思うが、ヒントになるのは土器を作ることが「柔らかい」陶土を火を用いて「硬いもの」に「変換する」ことにある。
柔らかいものと硬いもの、Aと非A
捏ねられている途中の陶土と、焼成されて固まった土器。
*
前者は柔らかいものであり、後者は硬いものである。
柔らかいことと硬いこと、柔らかさと硬さは、感覚的に対立する事柄である。「柔らかいの反対はなんですか?」と問われれば「硬い」と答える人は少なくないだろう。
柔らかい / 硬い
土器をつくるということは、この柔らかいものを硬いものへと変換することである。土器つくりは、柔らかいものと硬いものという両極の間の媒介者である。
何を当たり前のことをと思われるかもしれないが、この両極の間の媒介者、対立し相入れない二項の間で変換作用を引き起こす者のイメージは、我々人類の精神を、「意味」を問わざるを得ない精神を、「問い」を発してはその「答え」を求めざるを得ない精神を、破壊者にもすれば創造的な調停者にもする。
そして意味分節の理論というのは、人類の精神が、破壊のための凶器にもなるし、創造のための道具にもなることを明るみに出しつつ、しばしば放っておくと狂気としての使われ方ばかりするようになる精神を創造の方へと振り向かせるための”方便”なのだと思う。
(意味分節の理論については下記の記事で
関連する文献をご紹介しておりますので、ご参考にどうぞ)
*
今、これを書いている時に、ロシアのプーチン氏が核兵器までチラつかせながら自分の命令に従う兵士たちをウクライナの領土に攻め込ませている。その口実の主要なものがウクライナの「非ナチ化」であるという。「アゾフ大隊」などの話もあるが、そういうのも含め”互いに取り付く島もないような多様性”を人類社会の前提条件として認めた上で、それでもどうにかして(殺し合うのではなく)共同性を立ち上げていくのだ…、ということを最近の人類は努力して模索ようとしてきたのではないのか。
それに比べると、氏の頭の中の意味分節体系は東ドイツはホーネッカー氏のシュタージの事務所でタバコを燻らせていた時のままのようにも見える。が、そこにはプーチン氏個人の問題としては片付けられない、とても深い根がある。
アーレントの『全体主義の起源』の結論部分とも読める場所に「超意味」という言葉が出てくる。
「全体的支配は、われわれが通常推論の手段とし、またわれわれが通常そのなかで行動している意味連関というものをことごとく破壊する一方、<超意味>とでも言うべきものを他方では作り上げる。最も不条理なものまで含めてすべての行動・すべての制度が、この超意味によって、われわれには思いもよらなかったほどすっきりとした形でその<意味>を与えられる。全体主義社会の無意味性の上に君臨するのは、歴史の鍵を握りあらゆる謎の解決を見つけたと称するイデオロギーの持つ<超意味>なのだ。
”通常”の意味連関=意味分節体系を破壊し、全く別の<超意味>の意味連関=意味分節体系を持ってくる。”通常”の意味分節システムの中では”無意味”な不条理でしかないことが、後者の超意味の分節体系の中では”あらゆる謎の本当の答え”のようなもの、「歴史の鍵」のようなもの、つまり極めて深く重い意味がある、万物の本当の意味のようなもの、として分節される。
全体主義の下ではこういうことが起こっている。そしてここでいう全体主義とはヒトラーとスターリンのものである。
* *
人間は、精神あるかぎり、悟性ある限り、意味分節をすることからは逃れようもない。
若い頃にたまたま生まれ落ちた環境で伝承された意味分節体系だけで、人生の無意味さや意味不明さに苛まれることなく”運よく”一生を走り抜けられる人もいる(このタイプの人の周囲の人は大変である)。一方で、与えられた意味分節が「妄想分別」に思えてならず、その無意味さと意味不明さに苦しむ人もいる。
どちらにしても、今日のようなありとあらゆる多様な環境で各自独自の意味分節体系を立ち上げてきた人々が、何の仲介者もなく直接言葉を交わし合ったりぶつけ合ったりする時代を生きていくにあっては、人類に可能な意味分節のやり方は複数あり、その間に優劣はない(仮にどう優劣を付けようにも、それらもまた優/劣のペアがくるくると向きを変えながらら、他の何かと何かの二項対立にくっついたり離れたりしていることである)ということを(渋々でも良いので)認めた上で、個々の(というか局所的な)分節システムは固着させずに柔らかく動かし、その柔らかくなった局所的な分節システムを複数の他の分節システムとくっつけたり引き離したりする、そういうことができる神経系とシンボルのシステムを作っていかざるを得ない。
意味分節理論というのはこういうことを考える手がかりを貸してくれるものなのである。
XはAであるー「本当のことが分かった!」
私たちは謎の何かや不可解な何かに直面した時に、しばしばその謎の何かの”意味するところ”を知りたいと思うことがある。
勉強する意味、働く意味、学校に行く意味、人生の意味。
あるいは、死の意味。
私たちはいろいろなことの「意味」を問う。それもおもしろクイズ的に答えを当てるというのではなく、もっと何か切実で切迫した問いとして問う。
”何か”の”意味”を問う、その問いに答えるということは、”何か”を別の事柄と結びつけることである。
「Aの意味とはBである。」
このよういうとき、私たちはAとBを結びつけている。
AをBに置き換えている、AをBに変換している、といってもよい。
この結びつけること、置き換えること、変換することは、AとBという互いに異なる別々のものを、異なったまま一つにする。別々のまま一つにする。一即二、二即一の関係を露呈させる。
A ー B
ではなぜ、人が意味のようなことを考えるときに、結び付け、置き換え、変換が行われるのだろうか。
と、このように問いたくなるところであるが、この問い方は混乱のモトになるかもしれない。意味するということと、結びつけること、置き換えること、変換することとは、同じ一つのことである。「結びつけること」と「意味すること」は別々の二つの事柄ではなく、もともと一つの同じことである。
意味するということ、結びつけること、置き換えること、変換すること。
レヴィ=ストロース氏はこれを「類比(アナロジー)を見出すこと」とも言い換える。
「往古から民衆の思考は、このような類比を見出すことに意を用いてきた。そこに、神話を創造する原動力のひとつを認めることもできよう。」
対立関係の対立関係を仲立ちする
ところで、このAとその意味するところBとの二項関係は、表面的には(Aの意味はBであるという字面の上では)AとBの二者関係であるけれども、実はAというのは非Aと分節される限りでのAであり、Bも非Bと分節される限りでのBである。
つまり、AとBの二者関係と見えるものは、実はAと非A、Bと非Bの四者関係を次元を減らして眺めた姿なのである。
A ー B
/ /
非A ー 非B
これについて『やきもち焼きの土器つくり』の最後の方でレヴィ=ストロース氏は次のように書く。
「比喩的言語も[…]隠喩も、二つの項のあいだの意味の転移には還元されない。なぜならこうした項は、最初、不分明な塊の中で融合しているわけでもないし、同じ濠の中に埋まっていて、そこからどんな項でも望むままに発掘してもうひとつ別の項に好きなように結びつけることができるというわけでもないのだから。意味の転移は項から項へ生じるのではなく、コードからコードへ、すなわち諸項の一つのクラスもしくは範疇から、別のクラスもしくは範疇へと生起するのである。」
意味の転移は項と項の間で生じるのではなく、諸項と諸項の間で、複数の項の配列の複数の配列として生じる。
何らかのAの意味をBであると言おうとしたり、Xの意味をYであると言おうとする時、Aそれ自体、Bそれ自体、Xそれ自体、Yそれ自体を眺めていてもよく「分からない」事になる。
Aは非Aとの二項対立として、Bは非Bとの二項対立として、あらゆる項を、二項のペア最小単位とする対立関係の網の目(構造)の中で考える。
ここでポイントになるのは、この網の目(構造)は、固定した安定した不動のものという表向きの顔を持ちながら、しかし実は常にゆらゆら動いていて、織り上げられつつある動態としての姿を深層に隠しているということである。
神話的思考は、この対立関係の網の目の表層から深層へと潜ってはまた浮上する技であり、固まった姿の向こうに動態を透視する術なのである。
この潜航と浮上、透視の技術の手段となるのが、対立する二項を一つにまとめたシンボル、二項のどちらでもあってどちらでもないような中間的で両義的な媒介項である。
*
ある謎の何かを、白か黒か、右か左か、敵か味方か、食べられるか食べられないか、硬いか柔らかいか、互いに対立する二つの事柄、Aと非Aの「どちらか」に振り分けることによって「意味づけ」て、理解できるもの、わかるもの=分かるもの=分けられたもの=分節されたものにする。
この時、ある謎の何かが「柔らかくもあるし硬くもある(Aかつ非Aである)」ということになると、結局なんだか分からない=対立する二項のどちらかに振り分けられない=意味分節できない事態になる。
そしてこのAと非Aの中間状態、Aが非Aでもあり非AがAでもあり、Aでもなく非Aでもない中間的で両義的なことは思考のエラーではない。エラーであるどころかむしろ逆に、意味するということ、意味分節ということの最も基本的なメカニズムを顕にしている。
*
*
あるAの意味を巡って思考したりコミュニケーションしたりするときに、私たちを大いに戸惑わせるのが、あるA(と非Aのペア)を、どのようなB(と非Bのペア)と結びつけー置き換えることができるか、その潜在的な結びつけー置き換えの相手のレパートリーがどうなっているかである。
日常の言語の場合、何らかのAと非Aのペアと結び付けられる相手のペアというのは習慣的にいくつかに凝固している。この全ての二項対立関係が同じ”重み”で結びつき得るのではなく、ある二項対立関係と”結びつきやすい”二項関係と”結びつき難い”二項関係との差がある。この差分の距離の長短を多次元のマトリクスに配列したものが、いわゆる「ハビトゥス」であると言ってみても良さそうである。
あるA(と非Aのペア)の置き換え先として選ばれやすいペアの候補・選択肢が少数に限られている場合、意味を問い答える営みが、出来合いのルールに従って記号と記号を置き換えたり、たまたま高確率で出現している記号と記号の組み合わせパターンをなぞるような事になる。
「食べられるか/食べられないか」
「役に立つか/たたないか」
「正義か/不正義か」
「良いか/悪いか」
「敵か/味方か」
たとえばこのような具合に日常の世界にはAと非Aの対立関係を置換する先の”どこかでよく見たような”対立関係の候補があらかじめセットされている。良いか悪いか、安いか高いか、美味いか不味いか、敵か味方か、安全か危険か、といった生物個体としての人間から死を一時的に遠ざけることに寄与しそうな事柄が、極めて高頻度に動員されてくる。
そこに何か新奇なXと非Xの対立関係が登場してくると、それはまず、こういう”よく見る対立関係”と”どちら向き”で重ねるべきかをテストされることになる。
* *
私たちが生きている限り、ありきたりな対立関係のどちらか一方に振り分けてしまえばもうそれ以上頭を使わなくて済むようなものではない、切実で、しばしば理解不能=分かることが不可能とも思える問いに答えを探さざるを得ないこともある。
そういう場合、私たちはX(と非Xの対立関係)の変換先・飛び先になる二項関係を、自分なりに仮設的に作り上げることを(ブリコラージュを)しなければならない。
ここで仮設的にブリコラージュというのは、人が言語でもって思考する限り、自分用(自分たち用)の独自の二項対立関係を作るための材料として使えるものは、既知の「ハビトゥス」と化した二項対立の重ね合わせのパターンに限られている。それを借りて、流用して、転用して、動かし、ずらし、組み替えることで(これをブリコラージュという)、自分にとっての切実な問いの答えとなる何かと何かの対立を仮に設営することになる。
「意味とは何か」を問うときに神話的思考が働き続けているというのは、このことである。
離れすぎることもなく、くっつきすぎることもない
ここで神話的思考における「土器つくり」の役割を見てみよう。
「類比を見出す」ことをアルゴリズムにして動く神話の思考では、「土器作りとその製品」は「天界の支配者と地上、水界、地下世界の支配者との仲立ちとなる」という役割、ポジション、力を持つものとして語られる(クロード・レヴィ=ストロース『やきもち焼きの土器つくり』p.13)。
天界 <・・仲立ち・・> 地上
天界 <・・仲立ち・・> 水界
天界 <・・仲立ち・・> 地下世界
天と地。
人間をはじめとする動物たちが歩き回り植物が繁茂したりしなかったりする地上と、太陽や月や星々の光と雲や雪や雨に満ち、立ちのぼる煙が行くところところとしての天空。
この二つは互いに鋭く対立する二つの事柄である。鋭く対立するというのは要するに、地は天ではないし、天は地ではない、ということである。
◇
鋭く対立する天と地は、互いに全くの無関係であるかといえばそうでもない。両者の間は不可分につながっている。
天界から降り注ぐ雨や、太陽の熱や光があってこそ、地上界は人類が生きていくに足る馴染みのある場所になる。天界と地上界の間が二つに分かれて対立しつつも、その間に適切な結びつきがあり、うまい具合に通路が開いていることで、はじめて地上の人界は人界になるといってもいい。
もしこの結びつきが壊れ、通路に不具合があると、たとえば地上は真っ暗闇になったり、暑すぎたり、植物が枯れたり、洪水で生活が流されたりする。つまり地上界が破壊されてしまう。
天と地の結びつきは、暑くもなく寒くもなく、明るすぎることもなく暗すぎることもなく、雨が多すぎもなく少なすぎもないように、離れすぎることもなくくっつきすぎることもない、適当適切、ちょうどいい加減であることが求められる。
この”ちょうどいい加減”を調整するのが天と地の「仲立ち」の役目である。
* *
そして「土器つくり」は、この天と地の仲立ちの役目を果たすことができる、と神話的思考は考える。それは土器つくりが「火」を用いて「柔らかいもの」を「硬いもの」へと変換させる、対立する二項の仲介者であり媒介者であるためである。対立する二項の間の変容や移行を司る者としての「土器つくり」の姿が、天ー地を仲立ちする者の類比(アナロジー)になる。
もちろん、古今東西の神話において、土器つくりだけが天地の媒介者に比類されるものではない。
陶土に、「ジャックと豆の木」や日本のスクナビコナの神話に出てくる蔓草や、鍛治の神の足に絡みついて転ばせる蔓草の類、竹や天に真っ直ぐ伸びる柱状の樹木、蛇や虹や稲妻、宮沢賢治の「よだかの星」のヨタカのような鳥類、さらにはナマケモノのような樹上の動物が、天地を仲立ちするモノに比類される。
日本の神話でも素戔嗚尊が埴土(陶土)で作った舟で出雲に渡ってくるという話がある。
そしてヤキモチ=嫉妬(独占しようとすること)もまた離れた二項を強力に結びつけようとする力であり、天と地ほど隔ったものを仲介する力のアナロジーになる。やきもち焼きは、ある項Xを自分だけのものとして、己の一部として、独占しようとし、Xを己と過剰に結びつけ一つに密着させると同時に、Xを己以外の他の全ての項から分離し遠ざけようとする。
神話の世界では、やきもち焼きの接着力は、離れすぎてしまった二項の間に付かず離れずの距離を取り戻すために利用される。このとき神話の思考は、やきもち焼きの接着力が強く働き過ぎて二項を区別できないほど密着させてしまうことがないように細心の注意を払う。
仲立ちたち、媒介者たちは、天と地のみならず、「形の定まったものと形の定まらぬもの」、「不連続と連続」などなど、あれこれの二項対立を次々と結びつけ、付かず離れずのいい具合の距離を保とうとする(クロード・レヴィ=ストロース『やきもち焼きの土器つくり』p.27)。
特にここでレヴィ=ストロース氏が挙げている「形が定まったもの」と「形が定まらないもの」、つまり固まっているものと動いているものの対立、静と動の対立、さらには連続と不連続の対立などというのは、他のさまざまな二項対立関係をそこに置き換えることができる拡張性の高い=二項対立関係の関係づけの「ハブ」になりやすいペアである。
硬 / 軟
静 / 動
連続 / 不連続
同じ / 違う
さらには有と無、存在と不存在、などもここに連なる。
井筒俊彦氏はあるところで次のように書かれている。
「通常の状態において、一方の項が”無”であるような両項間の関係について考察し、それを表現することは不可能なので、われわれは”無”を”有”と想定し、これらの両項の間に二項的関係(A←→B)を設けるのである。」
AとB、二項の関係というここまでの話に繋がるものであるけれども、ここにはとてもおもしろいことが書かれている。
すなわち「”無”を”有”と想定」するというくだりである。
「無を有と想定」
無を有だということにする。
無なのだけれども有、いや、有なのだけれども無。
無を、有/無の分節以前の絶対無分節としてではなく、あくまでも有/無の二項対立関係の一方のことだと考える場合、この二項関係は「有」なるもの(項)と「無」なるもの(項)のペアということになる。「項」が項であるということは、すなわち「ある」ということになる。
この有とペアになる無は、缶入りのクッキーをすべて食べ終わって缶が空っぽになってしまった、いつの間にか財布の中身が空っぽになってしまっていた、という具合に「満たされた状態」の”逆”として、空になった容器のようなものとしてしばしばイメージされる。そこには空っぽの容器という姿形で、「無」が「有る」。
*
これに対して、「無」と「有」の二項関係が分節される手前の絶対無分節を考えることもできる。絶対無分節からの意識分節・存在分節こそ、井筒氏が生涯探求し続けたテーマである。
この絶対無分節という観点に立つと、有と無、AとB=人間が意味分節に用いるあらゆる項は、「存在すると同時に存在しない」と言えることになる。
「この世に存在するあらゆるものは、”存在する”と同時にまた”存在しない”。」
私たち人間の意識にとって存在するあらゆるものは、”他ではない何か”として互いに他と区別・分節される二項対立関係の片方の項として存在するのであり、これらの項たちのペアは、いずれも、「存在する」と「存在しない」の二項対立とどちらの向きにでも重ね合わせることができる。
そういうわけで、人間にとっての全ての「項」は、存在するでもなく、存在しないでもない。
有と無、静と動、同じと違う。
こういう超高度に抽象的な二項対立の間のどちらでもあってどちらでもない中間項を懐に隠しておくことで、<超意味>のようなものを「妄想分別」の一種として払い除ける術が使えるようになったりならなかったりする。
例えば、揺らぐ一瞬の影のようなものをシンボライズするある種の縄文土器などは、まさにこういう中間的な何かとしてもその意味を分節できる。
土器つくりは、意味するということの正体へと人間が降りていくために必要な命綱のようなものであるからして、とても重要なのである。
関連記事
ここから先は
¥ 550
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
