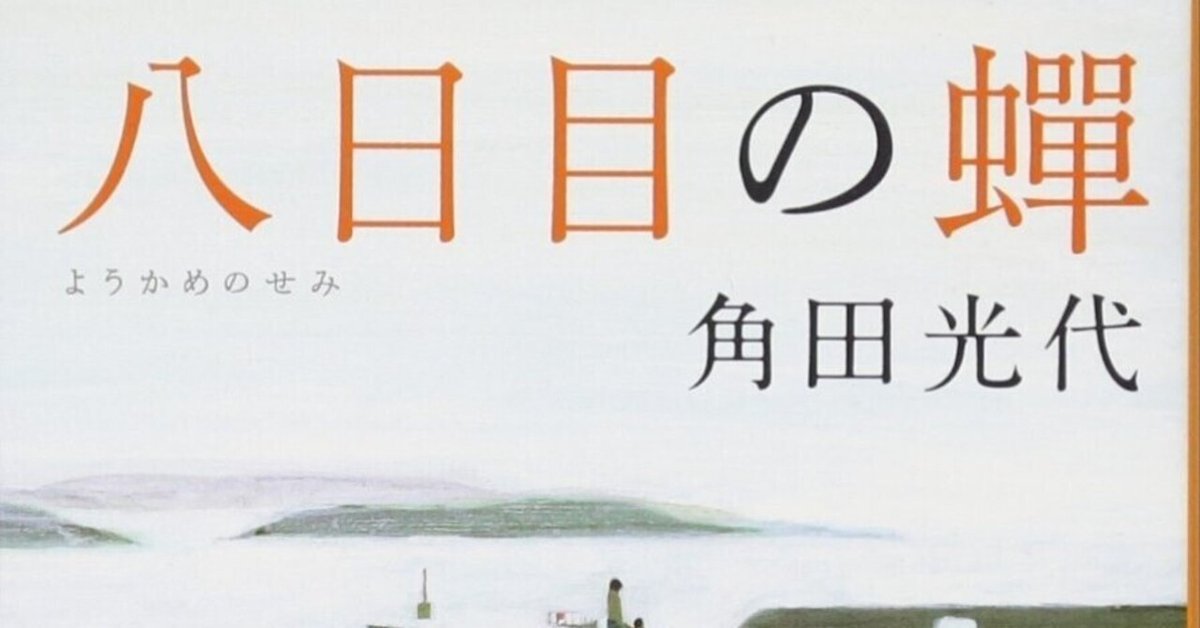
わたしの愛読書 角田光代『八日目の蝉』
角田光代『八日目の蝉』(中央公論新社2007,3)は「母性とは何か?」を問いかける、感動と衝撃のヒューマンミステリーです。
直木賞作家・角田光代が描く、血の繋がりを超えた「母と娘」の物語として有名ですし、ドラマ(檀れい、北乃きい)、映画(永作博美、井上真央)にもなっているので観た方も多いのではないでしょうか?
角田のもうひとつの代表作『紙の月』も同じようにドラマ化と映画化がされています。
ドラマや映画をご覧になった方も多いと思いますが、原作小説には、映像では描ききれなかった、より深く、より切ない感情の機微が描かれています。
誘拐犯に愛情を注がれて育った少女が、大人になり、自らのルーツと向き合う時、彼女が見出す真実とは? そして、彼女が最後に選ぶ道とは?
血の繋がりを超えた「母と娘」の絆、そして、母性の本質を問う、感動の物語を、ぜひあなた自身の目で確かめてみませんか?
第0章 衝動的な誘拐
主人公、野々宮希和子は不倫相手の子どもを一目見て帰るつもりで、侵入します。荒廃した部屋を見渡し、ベビーベッドに近づいた瞬間、赤ん坊を抱きすくめ、自分が「まもる」と言い聞かせて衝動的に誘拐してしまいます。
わずか4ページにも満たない0章では何ら動機は語られません。冒頭の、押し入った部屋の冷たく堅いドアノブの感触と、末尾の赤ん坊のあたたかくてやわらかい感触が対置されます。
第1章 希和子の逃亡と母への挑戦
不倫相手と正妻の子どもを誘拐した希和子には、不倫の果てに妊娠し、中絶した過去があったことが語られます。誘拐犯となった希和子は逃亡生活の中で、娘に「薫」と名付け、ひたむきに愛情を注ぎ、母としての自覚を深めていきます。実の母親以上に母親らしい希和子の設定を強固なものにするため、語り手は彼女に数々の試練をあたえていきます。
小豆島に逃亡しますが、そこでの生活は決して楽なものではなく、シングルマザーに注がれる好奇の眼差しや、健康保険証がないことによる医療問題、薫の就学など、様々な困難に直面します。逃亡犯となった希和子が直面する問題は、逮捕の恐怖より、社会的サービスを受ける権利喪失の方が勝るです。
しかし、希和子はこれらの困難を乗り越え、薫を大切に育てていきます。その姿を通して、読者は「母性とは何か?」「血の繋がりだけが親子関係を築く上で重要なのか?」という問いを突きつけられます。
逃亡劇の前半では、希和子は様々な試練を乗り越えながら、血縁に基づく母性の神話を覆していきます。しかし、後半では、希和子と薫が築き上げた「理想郷」が、希和子の逮捕によって脆くも崩れ去ってしまいます。
第2章 恵里菜の葛藤と自己の確立
出所した希和子が心の中で薫の名を呼び続けるのとは対照的に、恵里菜として生きる薫は幼時の記憶を実母と暮らすために忘れようとします。
誘拐事件の被害者である恵里菜(=薫)は、実の母親と育ての母親である希和子の間で矛盾を抱えて生きていくのです。
実母との生活では満たされない愛情を希和子から得ていた恵里菜は、彼女を「本当の母親」だと感じながらも、誘拐犯であるという事実を受け入れることができず苦悩します。
やがて、成長した恵里菜は、不倫相手の子供を妊娠し、シングルマザーになることを決意します。その姿は、希和子が辿った道と重なり、血縁を超えた連鎖を読者に予感させます。
その過程で、恵里菜は自身の出自やアイデンティティーについて模索します。決意をかためた恵里菜は、かつて希和子とともに暮らした小豆島を訪れます。思い出の地を巡る旅で、恵里菜は自分自身を受け容れ、新たな一歩を踏み出す強さを獲得していきます。
語り手は恵里菜と希和子の視点を入れ替えながら器用に交差させ、ふたりが思い出の地でこころの再会を果たすラストシーンは読者に深い余韻を与えます。
母性神話への再考
『八日目の蝉』は、従来の「母性神話」を覆すことを試み、母性とは何かを問い直します。母性とは、生まれ持った本能や血縁によってのみ規定されるものではなく、愛情や絆、そして育み/育まれる過程によって形成されるものであることを示します。社会が押し付ける「母親像」にとらわれず、それぞれの状況の中で最善を尽くす女性たちの姿を通して、多様な母性のかたちを提示しています。
女性への無言の圧力
角田光代は、本作を通して、女性にかけられる「母性への期待」や「無言の圧力」を浮き彫りにしています。
ネット記事にあふれている、実の母親である恵津子への批判的な意見は、こうした社会の風潮を反映していると言えるでしょう。
恵津子は、不倫や育児放棄という行為によって、社会が理想とする「母親像」から逸脱した存在として描かれているようにみえます。しかし、彼女もまた、社会の期待やプレッシャーに苦しむひとりの女性であることを忘れてはなりません。
もともと私が『八日目の蝉』を書こうと思ったきっかけは、世の中にある無言の圧力が女性を苦しめている、と感じていたからなんです。たとえば、子どもの虐待事件が起こると、父性は話題にならないのに、母性は必ず問われますよね。「実の母親なのになぜ」と。(中略)でも母親なら必ず母性に満ちていると、世間では思われる。それって本当なのか、と。
自由への渇望と喪失
本作は『紙の月』と同様に、主人公たちが抑圧された状況から逃れ、自由を求める姿を描いています。
希和子は、不倫という許されない愛と中絶のトラウマから逃れるために、そして母になるという夢を叶えるために、誘拐という罪を犯します。
一方、恵里菜は、実の母親との生活に息苦しさを感じ、自分自身の人生を生きるために、シングルマザーという道を選びます。
しかし、彼女たちが手に入れた自由は、決して完全なものではありませんでした。第1章において希和子は逃亡生活の中で常に恐怖と隣り合わせであり、第2章で恵里菜は誘拐事件のトラウマを抱えながら生きていかなければなりません。
本作は、自由を求めることの代償と、それでもなお自由を渇望する人間の複雑な心理を描いています。
こころと記憶で再会を果たす美しいラストシーン
物語の最後、恵里菜は小豆島を再訪しました。フェリーが島影を遠ざけるにつれ、恵里菜の心は静けさを取り戻し、過去の悲しみは薄れていくようでした。恵里菜は、希和子との思い出が詰まった場所をめぐり、ふたりで過ごした日々に思いを馳せました。
そのとき、ちょうど希和子も小豆島行きのフェリー乗り場へと向かっていました。しかし、乗り場に着いた瞬間、彼女の足はすくみます。過去の罪悪感が蘇り、希和子はベンチから立ち上がることができませんでした。
同じ場所で、恵里菜と希和子は別々に同じ夕日を見つめていました。海に沈む夕日が空を茜色に染め、美しい風景が広がっていきます。それは、ふたりが小豆島で見た夕日と同じでした。
物理的には離れていても、心の中では同じ風景を見つめるふたり。ふたりの紐帯を表すような感動的で美しいラストシーンです。
恵里菜と希和子の物語は、ここで幕を閉じます。
読者への問いかけ
この結末は、罪悪感や後悔を抱えながらも、前に進むことの大切さを教えてくれます。そして、心の繋がりは距離や時間を超えて存在し続けることをおしえてくれます。『八日目の蝉』は、読者それぞれに「母性とは何か?」「自由とは何か?」を問いかける作品です。
多角的な視点から描かれる物語は、深い余韻を残し、読者に様々な解釈を促します。血縁を超えた母子の絆、社会規範との葛藤、自由への渇望と喪失など、本作で描かれるテーマは、シングルマザーや女性への偏見があふれる現代社会において、それらを弾きかえす強い力感を持っています。
ぜひ、この作品を通して、あなた自身の価値観や人生観を見つめ直してみてください。
こちらの本、単行本だと1700円ですが、Kindleだと636円(+20ポイント)で爆安なので、Kindleで読んでしまうがおすすめです。
母性って一体何ですか?
この本を手に取って、再考してみませんか?
映画版『八日目の月』
『紙の月』の映画版は吉田大八により大きくサスペンス調に改変されていましたが、『八日目の蝉は』原作におおむね忠実で短くまとまっています。登場人物がカットされるくらいです。映画もほんとうに素晴らしいので、ぜひご覧になってください。
ドラマ版『八日目の蝉』
ドラマ版は原作の再現度が相当高く、原作そのままのセリフが登場するのでファンにはたまらないでしょう。しかし、この小説を彩る舞台、小豆島の風景は映画版の方が美しいと個人的には感じました。
いいなと思ったら応援しよう!

