
◆読書日記.《なだいなだ『民族という名の宗教 ‐人をまとめる原理・排除する原理‐』》
※本稿は某SNSに2019年9月6日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
なだいなだ『民族という名の宗教 ‐人をまとめる原理・排除する原理‐』読了。精神科医で作家でもあるなださんお得意の対話篇。
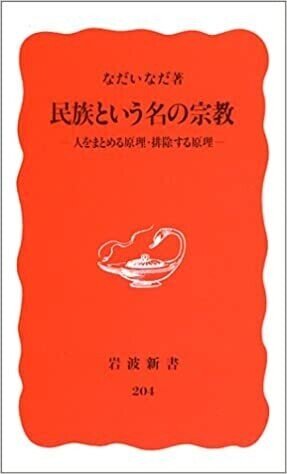
あるときなださんの所に『権威と権力』で対話したA君が訪ねて来る。
学生運動をしていたA君も今や社会人。彼はかつて希望を持っていた社会主義の理想が失敗した事に失望を隠せないでいた。
学生運動をしていた当時も社会主義の全部が正しいとは思わなかったが、半分くらいの正しさはあると思っていた。
いったい、社会主義とは何だったのか。
なださんは答える。
「もはや使い捨ての時代じゃないんだ。こんな捨て方はよくないと考えるんだ。(略)社会主義もリサイクルして使えないものだろうかってね」
「で、どんなふうにリサイクルするつもりですか」
「資本主義も、宗教も、ファシズムも、ぼくはみんな人をまとめる原理だと思うんだよ。もちろん社会主義というイデオロギーもその一つだった」
……そこからなださんとA君は、「人をまとめ、集団にする原理とは如何なるものか?」という切り口で話を始めるのだった。という、なださんと、A君という二人による対話篇という形で進んでいくイデオロギー批判論。
なださんの対話篇は小説のようにスラスラ読める上に非常に刺激的な考え方があちこちに出てきて、読むとちょっと賢くなったように感じられる。
こういう感覚は、ぼくが初めて高校時代になださんの対話篇を読んでから変わってない。
高校時代に読んだ、小説以外の思想書の中でも特に思い出深いのが、このなださんの対話篇の中でも、精神医学について考える『くるい きちがい考』だった。
高校時代のぼくでも読めるくらい分かり易くて簡単。
しかも専門的な知識や専門用語、学術用語などが出てこず、高度な知識が要求されるような障壁は一切ないのも良い所。
こういう親切設計がある本だからこそ、普段この手の思想書がなかなか読めない人にも、なださんの対話篇だけは広く読まれてほしいと思う。
なださんの『くるい きちがい考』を読んだとき衝撃的だったのはまず何よりも「そうか、頭のいい人っていうのは、こういう風に物事を考えていくのか」というのが分かった事。
高度な結論に至るまでの考え方の道筋を、実に丁寧に、高校生でも中学生でも分かるように説明していくのが、なださんの対話篇の特徴なのだ。
相手との話に齟齬があると感じたら、まずはお互いの使っている言葉の意味を確かめあって、その定義を考えてみよう。
物事がよく分からなくなったら、まずは大元の状態までさかのぼって考えよう。
物事は何でもかんでも「Aか?Bか?」と二分割にして考えると間違えるし、極論になってしまう事もあるから、「AとBの境界がない『連続的な分類』もあるのだよ」と考えると良い。
――こういった、今から思えば常識的な思考方法も、ぼくはなださんの『くるい きちがい考』で初めて理解したように記憶している。
そういう分かり易いのに、非常に高度な結論を導き出せるというなださんの対話篇の特徴は本書も健在。
まず「国家」や「民族」というのは、そういう確固たる動かせないものがあるのではなく、そういうのはある種の「人をまとめて、集団として結束を固めるためのイデオロギー」なのだ、という考え方が非常に魅力的。
まずA君と一緒に考えるのが、人類の状態を原始人の古代まで遡ってそこにある理屈を徐々に明らかにしていこうと言う事。
当然の事ながら「家族」という意識を持っているのはあらゆる生物の中で人間のみだ。
チンパンジーでも「群れ」や「ハーレム」はあっても「利害関係者で繋がる"集団"」はないのである。
「家族」の特徴とは何なのか?
一つは「インセスト・タブー(近親相姦の禁忌)」がある事。
本書の思想の面白い所の一つは、このインセスト・タブーについても「集団をまとめるロジック」で説明する所。
本書には「タブーが家族を意識させた」というくだりが出て来る。
タブーがある範囲が"家族/血族"という範囲なのだ。
つまり「近親相姦がタブーとなる範囲」というものが意識されれば、その範囲内が「アカの他人とは違う範囲――つまり"味方集団=家族"なのだ」という事を意識せざるを得なくなる。
自由恋愛が出来ない範囲というのが意識されれば、その範囲内は「アカの他人とは違う特別な関係の人間なのだ」と意識するようになる。
つまりは、人間が「個人」ではなく「集団」となって力を得るために利用されたロジックこそが「家族/血族」というイデオロギーなのだと言う事。
人間は「集団」となって力を合わせる事で絶大な力を得る。その「集団」は結束力が強く、人員が多い程、その力は強くなる。
だが普通、人間はアカの他人とは集団にはならない。
そのために「人をまとめるロジック」であり「イデオロギー」が必要になってくるのだ。
だから古代、人間をまとめて何らかの「集団」とするためのロジックが必要だったのである。
その一つが「家族/血族」だった。
だが、やがて「集団」は血族や部族同士の争いによって人員が増えていき、その「集団」の人員単位も徐々に増えていく事になる。
数百人、数千人、数万人という人々をまとめるためにはもう「家族/血族」というロジックではまとまりきらなくなった。
そのために「集団」をまとめ上げてきた権力者は、新たなイデオロギーを導入し始める。
それが「国家」であったり「宗教」であったり「民族」であったりというイデオロギーの数々なのだ。
このように、本書では「家族」や「国家」や「宗教」や「民族」というものを「人をまとめる原理」という切り口で説明していく。
後半、話は国際情勢などの話に移っていくが、相変わらず高度な知識はなるべく使わず、学生でも気軽に読めるレベルでこのような高度な思想を展開していくなださんの手際は素晴らしい。
この「人をまとめる原理」は、同時に「人を排除する原理」も生み出してしまうものなので、それが「イジメ」や「差別」という問題にもつながっていく。
「人をまとめる原理」から出発して、国際問題や政治思想、いじめ問題や差別問題まで広範な問題を説明していってしまうこの手並みも変わらず鮮やかなものだ。
と言う事で、何度も言っている通り、本書は学生でも手軽に読めるだけの面白さと分かり易さを持ちながらも実に深い思想を展開している優れた「イデオロギー批判論」になっている。
普段思想書のようなコムズカシイ本を読まない人も、是非とも騙されたと思ってなださんの対話篇を読んでみてほしい。
◆◆◆
なださんの『民族という名の宗教』には他にも面白いくだりが出て来る。
例えば、人類の歴史をたどってみてみると、人間とは戦争ばかりしていて、昔の日本の政治家が「人間は本能的に戦争をする生き物なのだ」とまで言っている人がいるくらいだ、とA君が嘆くのだ。だが、これにはある種のトリックが存在する。
教科書に掲載されている「歴史」とは、正確に言えば「権力史/政治史」なのだ。
国をまとめ上げている権力が移り変わっていくのをまとめた歴史を「歴史」と言っているのである。
だからこそ「日本史」の教科書も平安時代、鎌倉時代、室町時代……という時代区分になっている。これらは「政権の移り変わりの区分」だ。
では「政権の移り変わり」を記した「権力史/政治史」の重要なトピックとは何なのか?
例えば、政権の移り変わりのきっかけとなるクーデターや革命、国家同士の争い等々……大きな「戦争」はその歴史の重要なトピックになるのは当たり前の事ではないか。
だからこそ「歴史」なるものの記述には自然と「戦争」や「争い」がつきもののようになってしまう。
つまりは、まるで人間は古代から戦争ばっかりしている生き物であるかのような印象を受けてしまう事になる。
だが人間は常に、絶え間なく、どんな場所でも例外なく、全世界で戦争が起こっているわけではない。
殺し合いや争いがいつの時代にもあるように、いつの時代にも、例えば「束の間の平和」といったものも存在しているし、平和を求める運動や人を助ける活動も、いつの時代にも存在しているのだ。
それらは確かに「歴史」の上では重要なトピックにはなっていないのかもしれないが、歴史の中にある、人間のそちらの側面まで忘れてしまってはいけないのではないだろうか。
