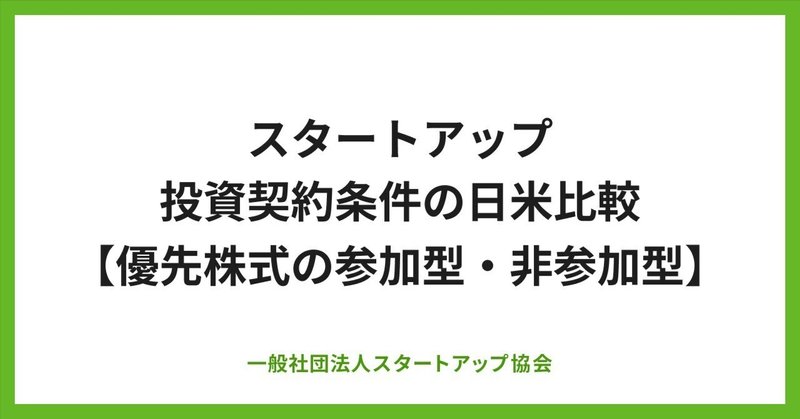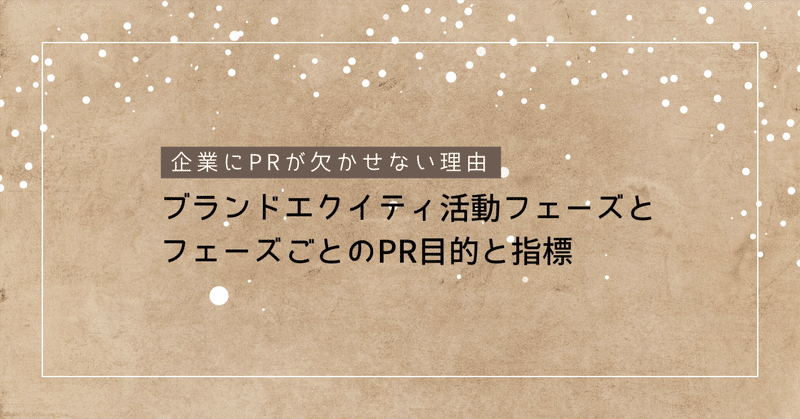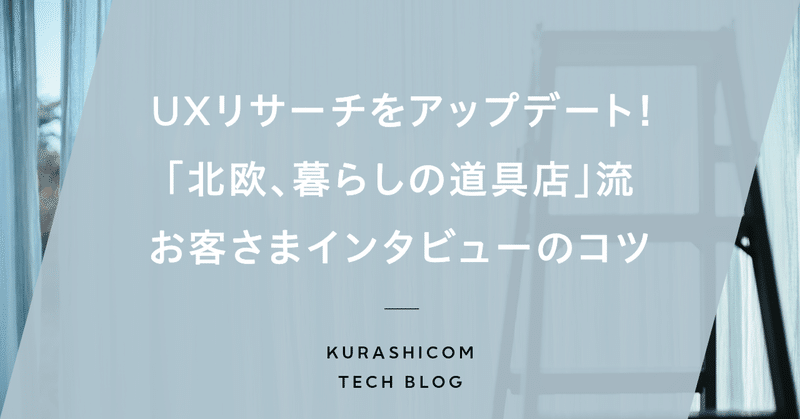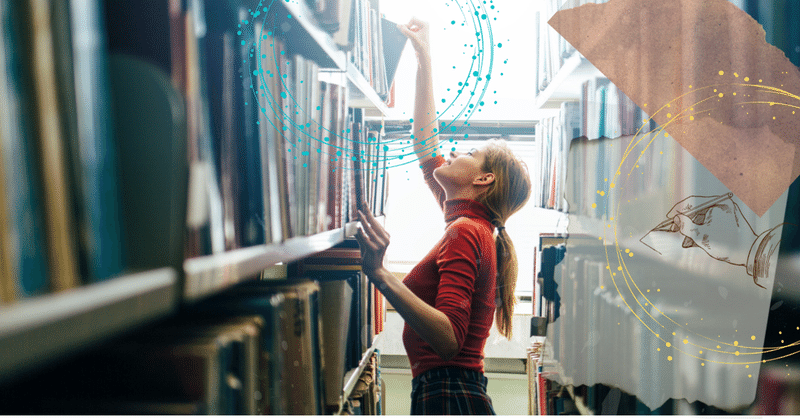記事一覧
急成長タイミーの礎はいかにして作られたか。小川代表と振り返る「タイミー創業期」の物語
スキマバイトサービスのパイオニアとして、2018年8月のローンチ時から“新しい働き方の選択肢”を広げてきたタイミー。2024年4月末の時点で同社のサービスに登録しているワーカーの数は累計で約770万人、登録事業者の数も25万拠点を突破し、その数は現在も増え続けています。
東京証券取引所グロース市場への上場を経て、さらなる飛躍を見据えるタイミーですが、2017年の設立直後から順風満帆に進んできたか
スタートアップ投資契約条件の日米比較:優先株式の参加型・非参加型
こんにちは、一般社団法人スタートアップ協会代表理事/株式会社スマートラウンド代表の砂川です。
先日、株式会社スマートラウンドの代表として、以下のようなプレスリリースを出したところ、関連Tweetが14万インプレッションに達するという大反響をいただきました。みなさんリツイートやいいねをありがとうございました。
このテーマに、皆さんとてもご興味をお持ちなんだな、意外に知られていないんだな、ということ
【企業にPRが欠かせない理由】ブランドエクイティ活動フェーズとフェーズごとのPR目的と指標
~「タイミー」でのキャリアからブランド・エクイティ活動を振り返る~前回の記事で「ブランド・エクイティ」の有用性について簡単に触れましたが、最初からこの概念を意識していたわけではありませんでした。この概念が日本に上陸したのは1994年ですが、ようやくここ数年で、ビジネスにおいて「ブランド・エクイティ」の重要性が問われ、少しずつ認知され、取り入れてきた印象があります。これまで事業の最大化というミッシ
デスクレスSaaSの未来、カミナシの賭け
昨日、カミナシはシリーズBで30億円(エクイティ25億円・デット5億円)の調達を発表しました。事業をピボットしてから約3年、この期間で40億円を超える資金調達をすることが出来ました。
この調達に至るまでの、シリーズA後を振り返ると、長期的なプロダクト戦略について考え続けた時間だった気がします。今回、この先、カミナシはどこへ向かうのかについて書きます。
前半はAll-in-One Product
非エンジニアが、エンジニア採用に向き合うその時。〜リアルなSlackを添えて〜
はじめまして。READYFOR株式会社でエンジニア・デザイナー採用担当をしております、西和田です。
このエントリーは、株式会社キャスターさん主催の「採用 Advent Calendar 2020」に当てた投稿で、私は2番目の投稿となります。壮々たる採用担当の方たちが寄稿しているので、是非他の記事も読んでみてくださいね!
今回、非エンジニアの私がエンジニア採用担当になり、日々苦戦しながらも得たT
UXリサーチをアップデート!「北欧、暮らしの道具店」流お客さまインタビューのコツ
こんにちは。デザイナーの白木です。早いもので入社して1年が経ちました。前回は入社3ヶ月目の印象とデザイナーの役割について書いたのですが、そのときに今後やっていきたいこととしてUXリサーチ(ユーザー体験に関わる調査)をあげていました。
その後、UXリサーチを少しずつ進めていき、現在では定期的にユーザーインタビューを行い、改善に繋げられるようになってきました。
今回はUXリサーチの立ち上げから半年間
富士のふもとから世界へ。人の五感と自然の力で生まれるウイスキーづくり
モノづくりの拠点である工場に密着し、あまり表立って語られることのない造り手たちの熱い想いや地域との関わりに迫ってきた特集『 #造る人たち 』。
今回はKIRINで唯一、国産洋酒をつくっている富士御殿場蒸溜所へ行ってきました。
富士御殿場蒸溜所が建てられたのは、1973年のこと。富士山のふもとの自然の恵みを活かしながら、日本人の口に合うウイスキーを目指して、これまでに数々の商品を生み出してきまし
ブランド価値を高めるSDGs時代のマーケティング|経営とマーケティングを結ぶ設計図
最近P&G APACフォーカスマーケット ヘアケアCMO・シニアディレクターを退職した、大倉佳晃です。本記事で、SDGs時代に企業・ブランド価値を高めるマーケティングの考え方について、私の13年のP&Gキャリアでの多くの成功と失敗から培った経験をベースに語りたいと思います。
本当は、キャリアの一区切りの備忘録として書籍を書き上げるつもりだったのですが、出版となると時間もかかってしまうため、あえて
【1時間で分かる】P&G流マーケティングの教科書
2020年5月末でP&Gのブランドマネージャーを退職しました。僕はこのNOTEで、P&Gで非言語的に受け継がれているマーケティングの思考法を、分かりやすい教科書のようにまとめようと思います。本気で読めば1時間かからず読めると思います。が、ちゃんと理解すれば知識レベルとしては本何冊分にもなることをお約束します。さらには、そのマーケティング思考の先に、僕がどんなマーケティングの進化を考えていて、そのた
もっとみる