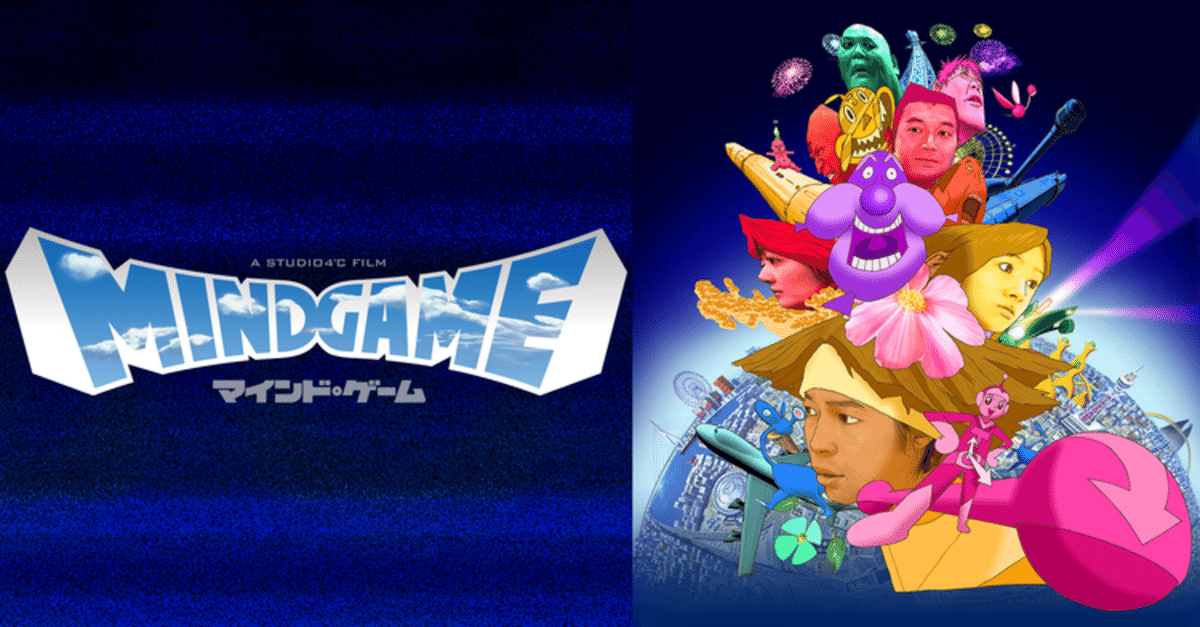
湯浅政明監督 『マインド・ゲーム』 : 〈臨死体験〉的な 超絶アニメ
映画評:湯浅政明監督『マインド・ゲーム』
湯浅政明監督の、2004年の劇場用長編。初監督作品である。
それまでに、小さな作品は監督しているが、湯浅監督の存在を世に知らしめたのは、この作品と言っていいだろう。
では、どのような点で、この作品が高く評価され、アニメーター湯浅政明が、「監督」として注目されるようになったのか。一一それは、この作品の「前衛的な作風」によって、といっても過言ではないだろう。
もっとも、湯浅監督自身は、この作品を「前衛的」だとは思っていないようで、あくまでも「面白い表現」を目指した結果、そのような評価を受けることになった、ということのようだ。
ただ、湯浅監督の「面白い表現」というのは、テレビアニメ的な「(ベタに)ありきたりのストーリーテリング」には飽き足らず、またユニークな原作のユニークさを生かす「表現」を求めた結果、いわゆる「前衛的」という印象を与える「表現」になってしまった、ということなのだ。
言い換えれば、今のアニメーション作品が、あまりにも商品化されて「パターンに安住する作品」が多すぎた、ということなのかも知れない。そして、その典型が、比較されることの多い、新海誠監督の『君の名は。』のような作品だとも言えるだろう。
ロビン西による原作コミックを、私はまだ読んでいないが、元本は全3巻と、そこそこの長さを持つ作品である。
したがって、この原作のストーリーを追おうとすれば、それなりにストーリーを整理した、普通のドラマ作品になっただろう。
だが、この原作は、どうやら「普通のドラマ作品」向きではなかったようだ。

あらすじを紹介すると、こんな感じになる。
「幼馴染の女性・みょんと、電車でたまたま再会した、二十歳の主人公・西は、そのまま、彼女の姉・ヤンの経営する飲み屋へ行く(※ たぶん、姉妹は在日であろう)。

そこで、みょんの今の彼氏を紹介されるなどしていたところ、遊び人である、みょんの父親に、女を取られたというヤクザ者(と、その兄貴分)が入ってきて、みょんの父親はどこにいると拳銃を振り回して威嚇し、あげく、みょんを強姦しようとする。

西は、みょんの救出どころか、すっかり震えあがり、頭を抱えて床に小さくなっていたが、それを見つけたヤクザ者が、西の尻に拳銃を突きつけて、西をからかった。そこでつい、西が「しばくぞ」と怒りの言葉を半ばまで発したところ、そのまま撃ち殺されてしまう。肛門から額まで撃ち抜かれたのだ。
西の霊魂は、そのまま天国にらしきところに登り、そこで姿形の定まらない奇妙な人物に出会うが、それは神さまであった。情けない死に方をしたことに納得のいかない西に対し、神さまは「もうすぐお前は消える」と冷たく言うが、西は、そこからの必死の逃亡を試み、神さまはその意志の強さを買って、西を、射殺される前の時間に戻して生き返らせる。

復活した西は、ヤクザ者の拳銃を躱すと、みょんとヤンを連れ、ヤクザの乗ってきた車を奪って逃亡する。
一度は死んだ身だから、もう好きに生きてやると決めて、無謀な逃亡劇に出たのだ。だが、ついにヤクザ者たちに追い詰められ、車ごと橋の上から転落するが、その車は、巨大なクジラに飲み込まれてしまう。

クジラの中で目を覚ました西たち三人は、そこで30年暮らしてきたという変な老人と出会い、彼に歓迎される。しかし、老人の話では、彼自身な何度も試みたものの、このクジラの中からの脱出は不可能であり、ここでの生活を受け入れるしかないと言う。事実、西も何度か脱出を試みるが失敗し、やがて、クジラの腹の中での生活にも、一種の安らぎを見つける。しかしそこで、昔、なりたかったマンガ家の真似事をしているうちに、やはり、人との関わりのある世界に戻りたいと思うようになり、最後は四人で力を合わせ、外の世界への脱出に成功する」

一一というところで、この物語は終わる。
つまり、この物語は、普通の「ドラマ」ではなく、きわめて「寓話性の強い、幻想的な物語」なのだ。だから、原作のストーリーをコンパクトにまとめるだけでは、原作の真の魅力を伝えることは困難だと、たぶん湯浅監督は、そう考えたのではないか。
そこで、湯浅監督は、ストーリーのわかりやすい説明は捨てて、この原作の寓話性を「絵として見せる」という手法を選んだ結果、「難解」で「実験的な手法」を多用した「前衛的な作品」ということになってしまったようなのである。
湯浅監督としては、当たり前に「筋を追うドラマ」よりも、こちらの方が「原作の長所を生かして、面白いもの」になると判断したのだろうが、「パターン化されたドラマ性や表現」に馴らされてしまったアニメファンには、これは「難解で前衛的」、だが「ユニークで面白い」作品だと評価されることになった。
無論「わけがわからない、独りよがりの実験的作品」と、反発したアニメファンも少なくなかっただろうが、本作が、優れた実験的アニメ作品に与えられる「大藤賞」を受賞し、『文化庁メディア芸術祭アニメーション部門を始めとする国内外の映画賞、映画祭で高い評価を受けた』(WIKIpedia「マインド・ゲーム」)結果、公式的には「前衛的な優れた作品」ということで、評価が定まったようだ。
一一だが、繰り返すが、これは湯浅監督が望んだこととは、少し違っていたのである。
だからこそ、湯浅監督はこのあと「一般に受け入れられる作品」を目指すことになる。あくまでも「自分のやり方」で、という(自明の)条件付きではあったのだが。
その後、テレビシリーズやOVA作品の監督をしながら発表した、劇場用長編作品は、次のようになる。
・『夜は短し歩けよ乙女』(2017)
・『夜明け告げるルーのうた』(2017)
・『きみと、波にのれたら』(2019)
・『犬王』(2022)
『マインド・ゲーム』は、「前衛的な作品」として高く評価されたものの、次の劇場用作品まで13年ものブランクがある。要は、『マインド・ゲーム』ような、商業的に難しい「表現」は、求められなかったということなのだろう。
○ ○ ○
そんな湯浅政明監督の個性が爆発した、ひとつの「原点」とも呼べる本作『マインド・ゲーム』とは、どう評価されるべき作品なのだろうか。
これまでの、私の紹介でも明らかなとおり、本作は「表現の面白さ」「見たことのない世界(表現)の面白さ」を、その魅力とする作品だと言えるだろう。
だが、そうした「面白さ」は、商業主義に毒された大多数の人の前では、「前衛的」ということで、体良く「敬して遠ざけられる」ことになった。明らかに、湯浅監督が「面白い」と感じるものと、一般のアニメ好きが「面白い」と感じるものとは、違っていたのだ。
湯浅監督自身は、決して「前衛作家」を気取るつもりはなく、「面白い」と言ってもらえるものを作ったつもりなのだが、世間はそれを「ピカソの絵」のように評価した。
高く評価する人は「非凡ですごい」と言い、評価しないものは「理解不能な芸術きどりの作品」だと否定した。
無論、湯浅監督にすれば、どちらの評価も、自分が目指したものとは違っていた。そして「どうやら、自分が面白いと思うものと、世間のアニメファンが面白いと思うものは、かなり違っているらしい」と気づいたのだろう。
そりゃそうである。湯浅監督の作品には「萌えキャラ」も出てこなければ「萌えメカ」も出てこないし、「燃えるストーリー」でもない。そうした「安心できる、ありきたりのパターン」を、湯浅監督は「面白い」とは思えなかったのだろう。

だが、プロの表現者である以上、自分の感性に忠実でありながら、しかし多くの人を「楽しませる」作品を作らなければならないと、そんな覚悟をさせてくれたのが、湯浅監督にとっての『マインド・ゲーム』という作品であり「経験」だったのではないだろうか。
○ ○ ○
さて、そこで私個人の評価だが、身も蓋もなく言ってしまえば、私自身も、こうした「表現重視」タイプの作品は、好みではない。
私が書くものを読めばおわかりのとおり、私が好きなのは「重厚なテーマ性のある作品」である。「表現」ではなく「意味」なのだ。
また、それでいて、普通に「可愛いもの」が好きだから、本作を、頭では「面白い」と「理解できる」ものの、素直に「面白い」と「感じる」ことはできなかったようだ。
そして、そんな私が、本作に感じた「面白さ」とは、その「臨死体験」にも似た、表現による、日常生活を超出した「寓意性」だ。
本作に対して「ドラッグ的」だと評する人は多い。なるほど、言い得て妙である。要は、「幻想的なイメージ」と「突飛な展開」と言ったところで、そう表現されるのだろう。
だが、この「ドラッグ的」という表現に注文をつけるとすれば、それが「現実逃避」的なニュアンスを持ってしまう点であろう。
だが『マインド・ゲーム』 に描かれているのは「現実逃避的な非現実」ではなく、「現実の寓話としての物語」だと、私は感じる。この物語には「納得できなかった現実や生き方」に対する「抵抗」の想いが込められており、決して「現実から逃げる」ための「幻想」を求めているわけではないのだ。
主人公の西は、自分が「ちっぽけな人間」であることを重々承知している。しかし、その自認において、無難に生きていくならば、結局は、後悔するしかない、虚しい人生を歩むしかない、ということにも気づいている。死んで、神さまの前に立たされた時、自分は「もっと挑戦すべきだった」と悔やむことになるだろう、と自覚している。
だから、作者であるロビン西は、主人公に自分を仮託して「後悔のない人生」を歩ませようとしたのではないか。

しかしそれは、単に「つまらない人生」について、だけではない。
本作で描かれたように、クジラの腹の中での「ささやかな幸福」に対しても、ロビン西は、あえて「否」を叩きつけている。しかしまたそれは、「ささやかな幸福」を積極的に否定するものではなく、そこに安住することで、あとで後悔することになるのを危惧するがゆえの、挑戦への決意である。

ヤクザ者を恐れて、みょんの危機に手も足も出ず、ただ小さく丸まって怯える、というのも、少なくとも「その瞬間」は「無難という意味で、安心な生き方」だと言えるだろう。だが、それで自分が助かるという保証はないし、助かったとしても、自分の目と鼻の先で、初恋の女性であるみょんが強姦されていたら、その後の人生は、恥と後悔に満ちたものになるだろう。
だから、やりたいこと、やるべきことがあるのなら、たとえ危険が伴おうとも、それに挑戦しなければならないという「決意」が、この作品には込められている。
しかしまた、それは、自身の「夢や理想」であって、現実には十分に実行できないものであることを、ロビン西は重々承知しているからこそ、その想いを、この作品に託したのではないだろうか。
また、そのような極限的な「分かれ道」を描いた作品だからこそ、主人公の西が一度は天国に登って神さまと対面するシーンに限らず、この作品には「臨死体験」に似た雰囲気があったのではないだろうか。
例えば、西にとって「安楽な居場所」となりかけていた「クジラの腹の中」とは、実際のところ「ささやかな天国(の一歩手前)」だったのではなかったか。
この作品の最初と最後には、登場人物たちの「過去」が、まるで「走馬灯」のように、脈略のない断片のつながりとして描かれる。
それは、西たちメインキャラのものだけではなく、やくざ者の過去(子供の頃)と思しき「記憶」なども含まれていて、きっと、原作マンガでは、これらの断片は、その人物の過去を描く回想シーンとして、物語に「厚み」を加えていたのではないだろうか。
例えば、ヤクザの兄貴分の方は、子供の頃「時間を操る、アニメのヒーロー」に憧れたけれど、今は「こんな人間になってしまった」という、そんな「やり直しのできない人生への諦観」を描いていたのではないか。

だが、湯浅監督は、そうした過去を、暗示的に提示はしても、ハッキリと描くことはしなかった。
二時間の作品に収めるという時間的な制約ももちろんあっただろうが、たぶん湯浅監督は、そういう「人間らしさ」という「根拠」を、あえてカットして、ギリギリの選択の前に立たされている人間の「今この瞬間」を描こうとしたのではないだろうか。「やり直せない人生」ではなく、「やり直しの決断をすべき今」である。
湯浅監督は、誰にでも楽しめる作品を目指しながら、しかしそれは「無難にウケるパターン」に安住するものではなかった。湯浅作品には、エンタメというには、いつでも「過剰」な部分や、人間的常識を「逸脱」した部分があって、エンタメを求めて観に来た観客を当惑させ、違和感を残した。
こうした特徴はたぶん、湯浅監督が「臨死」的なギリギリの場所に立って、その「表現」を選択しているからではないだろうか。
もちろん、多くの人に喜んでもらいたい。だが、そこには「多数派」だけではなく「少数派」や「異端者」も含まれての「多くの人」でなければならない。単なる「多数派」への迎合だと、きっと後悔することになる、そんな気持ちがあるから、湯浅監督の作品には「当たり前」をはみ出していく部分があり、本作『マインド。ゲーム』に限らず、どこか「臨死」的な表現が出てくるのではないだろうか。
日常生活に「頽落」して生きる私たちに、湯浅監督は、言葉ではなく「絵」で、「目を覚ませ」と呼びかけている。
一一私には、そんな気がしてならないのである。
(2022年6月30日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
