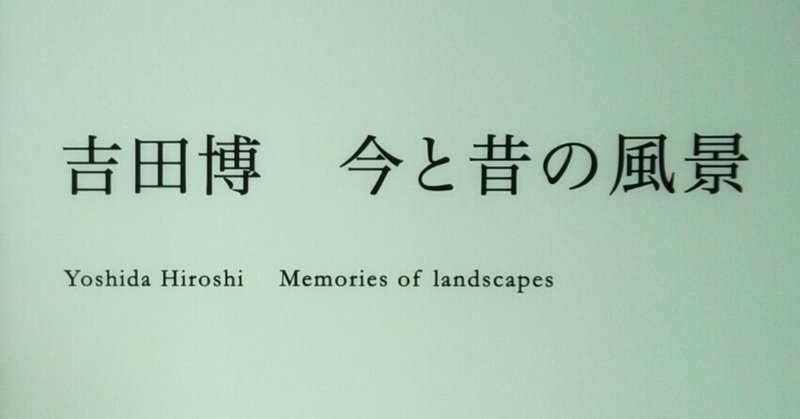- 運営しているクリエイター
記事一覧
「特別展 魂を込めた円空仏―飛騨・千光寺を中心にして―」(三井記念美術館)
個人的にも大好きな円空仏。しかし、こうしてまとまった数の円空仏を観るのは初めての体験でした。
基本的には稚気に富んだ魅力を楽しむもので、技術面"だけ"に関して言えばそこまで優れているというわけではないと思います。画像の両面宿儺像や親指大の小型作品など、「ひょっとしてものすごく上手なんじゃ…?」と思わせる作品はあるものの、一方で身体がほぼ棒だったり(-_-)みたいな顔面の、かなりラフな作品も存
「第78回東京藝術大学・修了作品展」(東京都美術館)
気になった作品を3つほど。
市原舞(建築)《きみのまち みんなのまち》
作者の地元・成田を舞台に、再開発により「こみち」を追い出された少年が魔法のチョークを手に、同じく「こみち」を追い出された猫のため、やがて街のみんなと「こみち」をデザインしていくという物語の絵本。実際に何をデザインするか以上に、そのデザインが誰のものなのか、誰のためにあるのか…それを考えさせられる内容でした。
私は大学
「宮脇綾子の芸術 見た、切った、貼った」(東京ステーションギャラリー)
戦後、アプリケ作家・エッセイストとして知られた宮脇綾子。手芸の分野では広く知られた彼女ですが、その仕事を一分野にとどまるものではないとし、彼女を一人の造形作家として、美術史的なアプローチで分類・構成しようというもの。
宮脇が題材としたものは野菜や魚など、主婦として非常にありふれたものばかり。彼女は二つに割るなどし、その断面をつぶさに観察し、それを並べて作品へと昇華していきます。構図としてはま
「生誕130年 青山義雄とその時代」(茅ヶ崎市美術館)
青山義雄(1894-1996)は近現代にわたり活動した洋画家。エコール・ド・パリの日本人画家の中でも西欧文化に適応する道を選んだ画家で、特にマティスからは「この男は色彩を持っている」との評価を獲得、生涯にわたる師弟関係を結ぶこととなります。
ただし作風や色彩が露骨にマティスっぽかったわけではなく(日本の近代画家を見ていると、師匠や憧れの画家に『寄せる』ケースも決して少なくないように見えますが
「現在地のまなざし」(東京都写真美術館)①
東京都写真美術館が2002年より継続している、新進作家の発掘を目的とした展覧会。
今回はかんのさゆりさんの写真に惹かれました。彼女は宮城県生まれで、今回のシリーズ〈New Standard Landscape〉は2016年から現在にわたり、東日本大震災の被災地であった宮城県・福島県の様子を撮影し続けております。一見それは、なんでもない新興住宅地の風景にも見えますが(実際そうですが)、一度更地
対話型芸術観賞、体験してきた。 - 「おしゃべり美術館」(平塚市美術館)
突如「対話式美術鑑賞」を体験してみたいと思い、平塚市美術館へ。予約制だったことを知らず、キャンセルで空いた枠に入り込む形での途中参加とはなってしまいましたが、一人の観賞とは違う、刺激的な体験ができました。
美術鑑賞に限らず、私は単独行動(ぼっち)をしてしまいがち。
作品の観る順序がだいぶランダムだったり鑑賞中にメモを取ったり、他人とは違うルールやルーティンが私にはあります。そういうものに他
「特別展 須田悦弘」(渋谷区立松濤美術館)
本物さながらの木彫の技術もさることながら、インスタレーションとの組み合わせが素晴らしかったです。
通常のガラスケースに収められた作品ばかりではなく、部屋の隅やガラスケースの下など、ある意味雑草らしくちょこんと作品が生えていて、そのたびに驚かされました。作品リストを持ってなかった自分は疑心暗鬼状態で作品を探すこととなったんですが(最終的に、庭に"雑草"として紛れていた一つを見落としてたみたいで
「吉田博 今と昔の風景」(MOA美術館)
今年最後の展覧会は熱海へ。MOAの場合、普段なら開館直後から1-1.5時間ぐらいはそれほど混雑とは無縁で楽しめるんですけど、今回(12/30)は開館直後からそこそこの人の数。いかにも年末、といった感じです。
個人的にMOAの吉田博展は今回で4回目ぐらいの訪問で、何度見ても新品同様の保存状態の良さ、そして度重なる摺りによって線が潰れておらず、より吉田の意図に近いと思われるクオリティの高さはピカ
「「不在」トゥールーズ=ロートレックとソフィ・カル展」(三菱一号館美術館)
三菱一号館美術館にとっては初となる現代芸術展。コロナ禍で開催延期となり、4年越しに実現した展覧会となります。今回は後半、カルのパートに話題を絞って。
最初に展示された映像作品《海》は、イスタンブールの海を前に、人生で海を観たことがない人達に海を見せるというもの。海を観たあとにカメラのほうを振り返る人々の表情は様々で、涙を浮かべる人もいれば表情を崩さない人も、中にはカル独特の「システム」に困惑して
「歌舞伎展」(川崎浮世絵ギャラリー)
タイトルの通り歌舞伎をテーマに、葛飾北斎、三代歌川豊国(初代国貞)、歌川国芳の三名を中心に構成。作風としてスタンダードな豊国作品が多かった印象でしょうか。個性的な作家に多く触れれば触れるほど、かえってスタンダードな存在がありがたかったりするのですが、ただ、今回に関しては北斎・国芳の作品に興味を持ちました。
北斎にかんしては「浮絵」と呼ばれる、一点透視図法を用いたものなのですが、北斎のそれは少