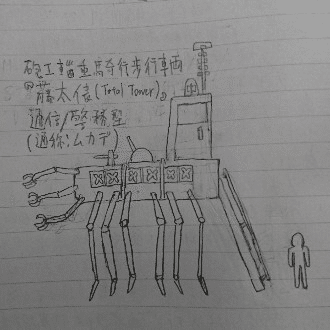随筆(2021/2/11):小学校算数水準での数の掛け算の「順序」という、しばしば「数学」「教育」上有害にはたらく、公理っぽい何か(E.数の掛け算の「順序」の、数学教育上の副作用の害とは、「生徒を数学教育そのものについていけなくする」ことである。これは致命的である)
2_8.副作用の害とは、具体的には何のことか(数学教育上の話)
2_8_1.副作用の害とは、具体的には何のことか(数学教育上の話)
数の掛け算の「順序」には、数学として見た時の、副作用の害がある。ここの話は今までしてきました。
それに加えて、数学教育として見た時の、副作用の害がある。
さらに、数の掛け算の「順序」は、社会生活に寄与するどころか、有害に働く。
これらは、実は、上で言った効果を全部無に帰す、恐るべき根本的な害だ。
そして、こここそが、ここまで大きな議論を招く要因になっている、大きな混乱の元だ。
***
さて。
差し当たり、数学教育の話をします。
数学教育として見た時の、副作用の害とは、何のことか。
もうちょっと具体的にいうと、小学校算数水準での数の掛け算の「順序」の、前提を無視した一般化を推し進めると、数学教育上、どんな害がありうるのか。
2_8_2.小学校算数水準での数の掛け算の「順序」という、しばしば「数学」「教育」上有害にはたらく、公理っぽい何か
少し、話は逸れますが。
数学における約束事である、公理の話を、以前しました。
小学校算数水準での数の掛け算の「順序」で要請される、
「異なる単位の順序が固定されていろ」
という主張自体も、そういう約束事でしかない。そこはせめて認めねばならない。
「別に約束事でもよいではないか。
数学は約束事の公理系の塊なんだろう?
それにこれを追加して、何がいけない?」
そう言いたくなる人もいるでしょうが、そこでやはり前言った話になって来ます。
つまり、数学で広く受け入れられている公理系は、メリットが顕著に目立つから広く受け入れられている。
メリットのない約束事を受け入れる理由はない。
あるいは、メリットがあっても、デメリットが直感的に
「同じくらいある」
「むしろ、より大きい」
「パッと見に比較不能だが、それはそれとして、デメリットそのものがあまりにも顕著に目立つ」
ものである場合、その約束事はやはり拒絶されて当然である。
***
私は、小学校算数水準での数の掛け算の「順序」のことを、
「しばしば「数学」「教育」上有害にはたらく、公理っぽい何か」
として見ています。
そして、露骨に有害な約束事は、採用できない。
そういう立場です。
だから上の話をしたのです。
この約束事、公理もどきを採用すると、大きなデメリットがある。
副作用の害として見た時に、およそスルーできないレベルのものが。
さて。
数の掛け算の「順序」による、数学教育上のデメリットとは、副作用の害とは、一体何なのか。
2_8_3.その副作用の害とは、「生徒を数学教育そのものについていけなくする」ことである
副作用の害、デメリット。それは、
「生徒を、数学に加え、数学教育そのものに、ついていけなくする」
ことです。
これは、マズイ。
2_8_4.その副作用の害は、期待し得る利益より、なぜ重大な害と言えるのか(数学教育上の話)
2_8_4_1.「数学や数学教育から脱落して、拒絶反応を示していても、単位の並び方だけは守ってくれる」というのは、およそ非現実的な期待である
その副作用の害は、期待し得る利益より、重大な害なのか。それはなぜそう言えるのか。
***
そもそも、メリットは
「せめて生徒が、やや高度な数学は難しくても、初等的な数学を社会生活で扱えるようにしたい。
そして、個々の条件や、その性質としての単位が複数あり、並び方に意味がある場合が、社会生活で数を扱う際にはよくある。
そこを間違えたら、何らかの問題が生じることも。
だから、それらの区別と並び方を、いい加減に扱ってはならない。
という、はっきりした認識を持ってもらいたい」
というところにある。
***
あんまり言われないことだが、これ自体がかなり
「あまり数や数学に苦手意識を持っていない人」
の発想だ。
単位にこだわることができるということ自体、
「初等的な数学を受容した人」
なわけだ。
で、脱落によって生じているのは、
「数学や、その導入としての数学教育に、拒絶反応を示すに至った人」
なんですよ。
「数学や数学教育から脱落して、拒絶反応を示していても、単位の並び方だけは守ってくれる」?
正直、非常に非現実的な期待に見える。
2_8_4_2.数学教育からの脱落は、数学教育において期待し得る利益を、全て無価値にする
前回書いたことだが、
「数学教育の方針上、この手の数学教育をやればやるほど、数学の正規の考え方からは逸脱していく」
という仕打ちを食らったら、生徒としては
「数学教育に拒絶反応を示すに至る」
し、結果として
「数学が何も分からなくなる」
ことになっても、まあしょうがないです。
残念ながら、よくある話です。
が、成功か失敗かで言えば、当然失敗でしょう。
***
数学においては、演算は根本的に重要なことの一つで、掛け算は演算の中でも頻出するものです。
そういう掛け算のどこかでこのように蹴つまづいたら、演算全体のどこかで蹴つまづいたことになる。
演算は数学全体でも呼吸のように使われるものなので、演算で蹴つまづいたら数学全体でも蹴つまづく。
掛け算は、かなり初期に教わる。
そのかなり初期で(無駄に)蹴つまづく羽目になった生徒たちにとっては、数学とは、まともにやってられないし、やりたい訳がない。そういうものだ。
「演算、何が何だか何も分からん。やってられっか」
と言う状態、まあ数学から脱落するに十分な原因であろう。
「数学、関わり合いになりたくない」
という風に、拒絶することになっていくの、ごく自然な成り行きだ。
現に、脱落する子供はとても多い。
私はそういう子を知っているし、これに限らず数学でつまづいている子に、教本を作って渡していた身だ。
脱落する生徒や、脱落した元生徒の増加が、数学教育上、特に数学サイドにおける、メリットかデメリットか、どっちか。
と聞かれると、それはもう明瞭にデメリットであろう。
数学教育の敗北としか言えない。
しかも、こんなの、自滅でしょう。
***
数の掛け算の「順序」を教えたがる人たち、
「数学そのものに拒絶反応を示すに至った」
元生徒たちが、
「それでも、初等的な数学を受容して、単位の違いを前にして、その分別を付けてくれる」
と、かなり非現実的な期待をしているようにしか見えない。
正直、
「数学そのものに拒絶反応を示した」
時点で、
「数学の鬱陶しい話である、単位の違いなんか、知るかボケ」
モードになる可能性の方が、圧倒的に高いだろう。
***
「骨身に叩き込まれた単位の考え方は、たとえその元生徒が数学やその残り香を拒絶しても、なおも意味のあるはたらきをする」
みたいな話を期待しているのだろうか。
単位。
数学の残り香の中でも、大きなつまづきの石となった、特に忌々しいもの。
心の底から苦手意識を植え付けられた、「やってられっか」と思ったポイント。
そういうの、理解に努めようとしている訳がないし、じゃあうまくやれる訳がない。
肝心要のここで、多くの元生徒たちがつまづいている。
じゃあ、ここの目的は、彼らの間では、達成されていない。
そして、忌々しさや苦手意識のあまり、これを達成しないで無視する動機の方がはるかに強い。
達成する動機はほとんどない。
***
じゃあ、要するに、数学と言う観点で総合的に見ても、単位という単一の目的に限定しても、
「教育としては失敗した」
ということだ。
これは、ダメだ。
2_8_4_3.教育の平準化は大事な話だが、それは「分かる人に分からなくなるように脳にゴミを詰める」ことで達成されてはならない
ここまでは、数学としての話を、もうちょっと掘り下げたところです。
数学教育そのものの事情には、まだ踏み込んでいない。
で、教育として見れば、もちろん平準化は大事な話だ。
「どうにもならない落ちこぼれの生徒」
とは、
「教師が生徒をどうにもできずに落としてこぼす」
ということとほぼ同義だ。
「教師が生徒を扱いかねる」
というの、今そこにある現実だ。
だが、もちろん問題だ。避けたい。
が、それは
「分からない人に分かるようにうまく教える」
ことで達成されるべきで(そりゃそうでしょう。だって、それが教育なんだから)、
「分かる人に分からなくなるように脳にゴミを詰める」
ことで達成されてはならない(だって、こういうことをする教育は、実際には脳にゴミを詰めているようなものなんだから)。
***
脳にゴミを詰める時間、まともな神経の持ち主なら、そりゃあバカな茶番劇みたいに見えるし、そんな教育法、かったるく見えて当然だろう。
そして、そんなかったるいものに、ついていく気になれる訳がないんですよ。
まして、そんなのについていくために、自主的な勉強なんか、やる気になれる訳がない。
これに関しては、「数学がどうこう」というより、「教育がどうこう」という話だ。
「これは中間期末試験や進学受験のテクニックだ。
進学受験によって自分の立場は良くなるかもしれない。
が、その内容なり実質なりは、意味や価値のない、ゴミみたいなパズルだ。
およそ茶番にしか見えない」
「18歳か22歳か26歳か28歳かは知らないが。
とにかくそれまで脳にゴミを詰める、ゴミみたいな時間を過ごすのか。
嫌だなあ。
こんなこと、シラフで付き合ってられないんだよなあ」
こうして、かったるくなった生徒はもう、数学教育や数学教師のことを何も信じてくれなくなるし、数学の勉強を「やろう」などとは思わなくなる。
教育あるあるだ。不毛な現実だ。
しかし、これが教育であり、そうである限りは人間の価値的な営為であり、成功か失敗かを問われるものだということを重く受け止めなければならない。
そういう観点からは、これは「失敗」でしかありえないだろう。
***
こういう状況を、出来るだけ招かないようにしたい。
この時点で、どう足掻いても、こういう状況を招いた人たちの責任以外の何物でもなくなってしまうからだ。
仲間内では誰も責めなくても。
外野の責めを「現場が分かっていないやつらのたわごと」と切り捨てて、まともに聞く気になれなくなっていたとしても。
本人の中では責めに値することとは思えなくなっていたとしても。
要するに責められているし、立場がどんどん悪くなっていくのは、今ここにある現実だ。何も変わらない。
感じ方は気の持ちようで変えられるかもしれないが、現実は気の持ちようではどうにもならない。
そこは、ちゃんと、認めなければならない。
2_8_4_4.快楽や、意味や価値のある苦痛ではなく、いつか二度と顧みなくてよくなる無意味で無価値な苦痛に、十数年も付き合わせないでほしい
個人的に推奨はしないが、
「スマホRPGでもスパロボでもパチスロでもやってた方が、はるかに精神の健康にいい」
というのは、残念ながらその通りなのだ。
少なくともそれは紛れもなく快楽と向き合っているのであって、無意味で無価値な苦痛と向き合っている訳ではないからだ。
人間は動物だ。動物はふつう、快楽を求めるものであって、苦痛と向き合おうとしていたら、それは余程無理をしているということだし、ストレス反応もふつうものすごいことになる。
***
「でも、そんなことをしていると、頭はバカのままになってしまうではないか」?
そうですね。
***
でも、じゃあ、
「脳にゴミを詰める時間を強いる。
これをやればやるほど、あなたの脳はゴミの塊になる。
平たく言うと、あなたは『無知なバカ』から『勘違いしたバカ』にクラスチェンジする」
という、およそバカみたいな話、せめてやめなきゃならない。
そんな説明に、意味も価値も、まして説得力も、ある訳ないんだから。
***
意味や価値のある苦痛ならまだいいでしょう。
そうした意味や価値は、後の人生で、何らかの実りがあるかも知れない。
だが、
「あなたは人工衛星で、これは巨大なブースターで、打ち上げられたらこれは打ち捨てられる。
打ち捨てるもののために頑張れ。
その努力は、終わったら、二度と顧みなくてよくなる性質のものだ」
という話をされると、
「宇宙開発めいた困難な十ヶ年(を超えてかかる)計画を、
後で巨大なゴミになることが分かっていて、
しかも子供であるこの自分が、
この手で、そして頭を働かせて、やるべきだというのか?
そんなもん嫌に決まっているが?
十数年後の自分自身の大気圏突破のため?
それを今イメージしろと?
今、正に、これのせいでキツイのに、
「こうすればいつか幸せになれるかも知れません」
って夢みたいな話、聞いてる自分としては、何一つ納得行かないんだが?」
という気分には、そりゃあなる。
今まで勉強してきたことは、私(これを書いている人)にとっては無駄ではない。いくつかは役に立ててきたし、いくつかはこれから役に立つだろう。
だが、
「勉強してきたことは、自分にとっては無駄だった」
と言いたくなる人の気持ちは、まあ分かる。そりゃあふつうはそうなる。
「卒業したらもうこんな無意味で無価値なことはやらなくていいよ」
という希望の持たせ方、
「じゃあ最初からやらせるなよな。無意味で無価値なことに、十数年も付き合わせないでほしい」
という反応には、そりゃあなるでしょう。
中身の無意味や無価値を、全部無視して、努力ができる人は、大人でもかなり珍しい方だ。
子供にそれを期待しているのだろうか? なぜそんな期待をしているのか? あまりにもハードルが過酷すぎる。
2_8_4_5.極力早めに一里塚となる成功体験を用意する、ある種のプロトタイプ型開発は、有益である
だから、本当は、
・極力早めに、一里塚となる、成功体験をもたらし、
・しかも応用の利く、
・簡単な知識体系を、
作物として植えたい。
そのために即効性のある、肥やしとなる知識を詰めたい。
それに寄与する、土となる基礎知識も詰めたい。
早期の成功体験やプロトタイプ的な知識体系があると、そのための手段となる知識や、間接的に効いて来る基礎知識の有難みが、そのうち信じられるようになる。
学習的無力感があり、知識体系がないと? 知識も基礎知識も有難みが分からないままになる。
そんなので、まともな知識や基礎知識を詰めても、生徒にとっては、それは肥やしや土ではなく、ゴミを詰めているのと区別出来なくなってしまう。
ちなみにこれは、詰めているのが「本当に」まともな知識や基礎知識であることを前提としています。
これは本当に惨い話なんですが、たとえ知識や基礎知識が「本物」でも、教育において、生徒に一里塚となる成功体験を実感させなければ、学習的無力感で台無しになる。
そういう話です。
そして、そういう話、実際に、あります。
だから、是非とも回避せねばなりません。
(次回は、数学教育と社会生活の間における副作用の害の話をします)
(「いや、この数学教育は、社会生活に寄与するためにやっている」という話が根強くあるので、「いやいや、そこで弊害があるから、結局ダメなんだ」と言う話をします)
(社会生活に寄与するために、数の掛け算の「順序」みたいな特殊な数学教育をやっているんなら、ここがダメならそりゃあダメだ。という話になります)
(ということで、乞うご期待)
いいなと思ったら応援しよう!