
小谷野敦 @jun-jun1965による、故・津原泰水への誹謗について
本年(2022年)10月2日に、59歳の若さで亡くなった小説家・津原泰水について、没後半月ほどで、早くも故人を誹謗するネット日記を、あえて公開したのが、文学研究者の「小谷野敦」である。「死人に口なし」を意識したとしか思えない、非常識なタイミングだ。
小谷野の、このおぞましい所業について、私は「昨年、私と小谷野の間で交わされたやりとりの、全ログを公開する」というかたちで、小谷野を批判する記事を、昨日アップした。
そちらにも書いたことだが、小谷野敦という著述家は、どうしようもなく「歪んだ」人間である。ものの考え方が、まともではないのだ。
もちろん、大学教師を曲がりなりにも務められる程度には、世間に合わせることもできるのだが、およそ「常識」や「良識」というものが、小谷野には無い。
私自身、一読書家として、世間的な「常識」や「良識」というものを、必ずしも鵜呑みにはしないし、むしろそれへの懐疑を重視する立場であって、その意味では、私自身「変わり者」の一人であることを認めるに、やぶさかではない。
しかし、小谷野の場合はそうではない。
小谷野の場合は、単純に、自分の気に入らないものを「冒瀆」するのが、好きなのだ。
他人に見る「気に入らない」部分に対し、その根拠を示して論理的に「批判」するのではなく、単純に「誹謗中傷」することで、人を貶めるのである。
例えば、今回の、津原泰水誹謗した日記、
・ 津原泰水と私
(https://jun-jun1965.hatenablog.com/entry/2022/10/18/133000)
では、次のような調子である。
『津原はこのように、そうであってほしいという願望を事実と取り違える傾向があり、統合失調症か人格障害の疑いがあると思った。』
『津原は「烏賊娘」が高橋源一郎のところへ駆けて行って質問していたのを「かわいいんですよー」と言っていたから、やっぱりゲイなのか、と思った。』
『百田著(※ 百田尚樹『日本国記』)には大勢の批判があり、その尻馬に乗って騒ぐ行為は、花村萬月が津原をさして言った「美意識」はまったく見られなかった。』
これだけでも、いかに小谷野敦が「非常識」かつ「他人の痛みがわからない人間」であるかが、容易に察していただけよう。
私は何も、「ポリティカル・コレクトネス」を振りかざすような「正論家」ではないつもりだ。
それは、次のレビューにも明らかだと思う。
だが、だからと言って、「無用に人を傷つける」ような人間は、文字どおりに「有害な変態」であり、許すまじき存在だというくらいの「常識的感性」は持ち合わせている。
同じ「変わり者(変人)」だと括れるとしても、私と小谷野とでは、その点が決定的に違う。
小谷野は、遊び半分で、さしたる理由もなく、まるでそれが生活の一部ででもあるかのように、「人を貶す」ことを楽しむ人間なのだ。
しかも、小谷野の許しがたい点は、彼の臆面のない「二枚舌」だ。
小谷野は、私についての「陰口」ツイートで、
『赤江瀑を好きだというあたりでかなりヤバイ人だとは思っていた』
などと書いていたし、津原泰水についても、上のように、
『津原は「烏賊娘」が高橋源一郎のところへ駆けて行って質問していたのを「かわいいんですよー」と言っていたから、やっぱりゲイなのか、と思った。』
と書いている。
赤江瀑という作家は「ゲイ」なのだが、小谷野は、「ゲイ作家」が好きだというのは、それ即ち「ヤバイ人」であるとの判断の「根拠」になると思っている。要は、「ゲイ」自体も、「ゲイ作家」を高く評価する者も、どちらにしても「まともではない」と、そう言いたいのである。
このように小谷野は、あまりにもあからさまに「男性同性愛者(ゲイ・ホモセクシャル)」を「気持ち悪い存在」だと見て疑わず、しかもそれ、大した必要性もないのに「公然と語る」人であり、さらに言えば、むしろ、そうした行為に喜びを感じるような人間なのだ。こんな歪んだ人間を、どうして「まとも」と呼べようか。
もしも小谷野が、こうした評価に抗弁して「そうではない。ただ、自分の実感を、悪意なく書いた(話した)だけなのだ」とでも言い訳するのであれば、それは小谷野が「他者(異質な人間存在)」に対する当然の配慮を欠いた「社会不適応者」だ、ということにしかならない。
「常識のない子供」がツッパって、こうした「挑発的発言」をするのなら、まだしも「未熟だから」ということで大目に見ることもできようが、小谷野は、私と同じ、今年還暦の60歳になった「大の大人」なのだから、「その気はなかった」とか「そこまで考えなかった」で済まされる話ではない。
それに、小谷野敦の場合、こうした「同性愛者への侮蔑発言」は、故意に「やり続けていること」であって、気づかずにやってしまったというようなこと(過失)ではない。
それは、「Wikipedia−小谷野敦」を確認すれば、すぐにわかる。
小谷野には、過去に次のような事実があるからだ。
『1998年12月12日、大阪大学吹田キャンパスのコンベンションセンター・MOホールで開催された「ジェンダー・フリー社会をめざす若者セミナー'98」主催のシンポジウム「「ダンジョサベツ」なんてカンケーない?──ジェンダー論の言葉はどうしたら社会に伝わるか──」にパネリストの一人として出席。この席上、小谷野は「私は以前、レズビアンからレズビアンだと告白されてそのあと三日間吐き気が続いた」と発言したところ、同じパネリストの伊藤悟からホモフォビア肯定と受け止められ、猛烈な非難を受けた。ただし、伊藤からの非難について小谷野は誤解であるとし、反論と弁明のメールをメーリングリストに投稿している。』
見てのとおりである。
小谷野は、20年以上前にすでに『私は以前、レズビアンからレズビアンだと告白されてそのあと三日間吐き気が続いた』などと、わざわざ人前で発言して顰蹙を買い、それを批判されて立場が危うくなると、それは『誤解であるとし、反論と弁明のメールをメーリングリストに投稿している』ような、みっともない「前歴」を持つ男なのだ。
要は、小谷野は、オーソドックスな「異性愛者」であり、男女を問わず「同性愛者」や、非オーソドックスな人たちに対して、古風なまでの「生理的嫌悪感」を持ち続けているのであろう。
事実、前記「Wikipedia」には、次のような記述もある。
『小谷野は小谷野 (2004a, p. 60)で自らを「ワーキング・クラス出身」と位置づけ、「比較的貧しい家の生まれ育ちで、保守の論客になる人というのがいる。福田恆存であり、西部邁であり、渡部昇一であり、谷沢永一である。どうも私は、根っこのところでこういう人達に共感しているところがあるようだ」小谷野 (2004a, p. 58)と述べている。』
要は、小谷野は自分を「真正保守」的な「リアリズム的感性」の持ち主だと、そうアピールしたいのだろう。
だが、こんなところで引き合いに出すのは、せいぜい『西部邁であり、渡部昇一であり、谷沢永一』止まりにしておいてもらいたい。なぜなら、「福田恆存」は、私も好きな作家で、ありがちなことは言え、そのあたりや、ましてや小谷野などと、ひと続きに語って欲しくないからだ。
小谷野が、「非オーソドックスな性愛者」に対し、ことさらにケチをつけたがるのは、きっと「自分は保守的な感性の持ち主であり、何でもかんでも新しいものを支持したがる、阿呆なリベラルとは違うのだ」という程度のことを考えているからだろう。一一だが、この程度の発想は、所詮「ネトウヨ」レベルに、幼稚なものでしかない。
たしかに「非オーソドックスな性愛者」に対し、「気持ち悪い」と感じる人は少なくないだろう。私だって、相手によってはそう感じる。
だが、「そう感じる」ということと、それを「口に出す」ということは、言うまでもなく、別の話だ。
例えば、行きすぎた「ポリティカル・コレクトネス」が「ポリコレ」の略称で批判されるのは、それが「紋切り型の正義を、問答無用で振りかざす」ような人(単純幼稚な人間)が少なくないからで、そうした者に対しては「おまえの考えは、幼稚かつ気持ち悪い」と、あえて言うべき時もあるだろう。
だが、そんな場合でも、批判した相手が「どうして、そんな誹謗中傷をするのか!?」と問えば、私なら、待ってましたとばかりに、その理由を、嫌というほど聞かせてやり、相手の反省と思考を促すはずである。
だが、小谷野敦の場合は、そうではない。
小谷野の場合は、いつでも言いっ放しであり、求められても「自身の発言の、根拠説明ができない」無能力者なのだ。
だから、こんな人物には、ことさらに「他者を挑発したり、傷つけたりするような発言」を、決して許してはならない。大人として、あるいは言論人としての「説明責任」を果たせないような者を、その責を問うこともなく、野放しになどすべきではないのである。
このように、自身の発言についての「責任」も取れないような無能力者だからこそ、小谷野は、自分の立場が危うくなれば、平気で嘘をつく。
つまり、前記のとおり、小谷野敦は、昔も今も、つまり昔からずーっと、継続的かつ意識的な「性差別主義者」なのだ。
だが、それを認めるのが社会的に不利だと判断した場合には、臆面もなく『誤解である』などという「嘘」も平然とつける、そんな卑怯未練な男なのである。
「小谷野敦」の名前を知っているのは、一部の純文マニアか、さもなければ、小谷野の「内容空疎かつキャッチーなタイトルの本」の読者だけなのだろうが、小谷野を知らない多くの人が、前記の小谷野の日記「津原泰水と私」を読めば、多かれ少なかれ、津原についての「好ましくない印象」を刷り込まれてしまうだろう。だがそれは、「反論できない故人」に対する、許すまじき冒瀆行為なのだ。
だから、小谷野敦という男が、いかに「卑怯」で「嘘つき」な「歪んだ性格の持ち主」かということを知っていただくために、先にご紹介した「私と小谷野敦とのやりとり全記録」を、ざっとでもいいから読んで、感じて取って欲しい。
小谷野がどういう人間であるかを知った上で、小谷野の日記「津原泰水と私」を読めば、それがいかに、当てにならない記述に満ちた「お話」でしかないかが、わかるはずだからである。
私は、津原泰水の追悼文を、早々に書いた人間ではあるけれども、津原とは一面識もないし、何の利害関係もない。
そのことは追悼文にも書いている。
私の津原への興味は、もっぱら、津原の「クセの強い性格」にあったのであり、津原の小説に対しての評価は、これも読んでいただければわかるとおり、小谷野の津原の小説に対する評価と、それほど大きな違いはないはずだ。
だが、小説を評価できないから、その人間性まで否定して良いということにはならない。
もちろん、小説を読み解くことで、著者の人間性を剔抉して、それを批判するというのなら、それは「文芸批評」の使命でもあるから、大いに結構なことなのだが、小谷野がやっているのは、そんな高級なものではない。
二流の文学研究者が、こけおどしの「専門家」ぶりで、根拠も示せないくせに、子供のような「好き嫌い」を語って、威張って見せているに過ぎないのだ。
小谷野は、小説家になりたくて小説家になれなかった、小説家としての才能のない人間なのだが、では、彼が「文学研究者」として、いちばん自慢できる「勲章」は何かといえば、それはたぶん、2002年に『聖母のいない国』で受賞した「サントリー学芸賞」なのではないだろうか。
だが、この賞自体が、それほどのものなのかどうかを、どれだけの人が知っているだろう?
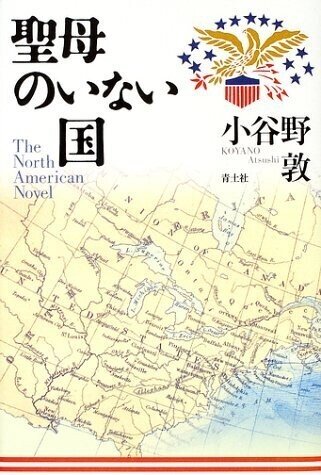
この種の「賞」の現実を知らない一般人(例えば、芥川賞が「年間ベストワン小説に与えられる賞だ」と思っているような、ナイーブな門外漢)は、とにかく「優れた作品に与えられるのだろう」と単純素朴に思い込みがちなのだが、そもそも賞の選考委員というのは、「肩書き」で選ばれるのであって、その「鑑識眼」で選ばれるのではない。著名な選考委員たちが、かなずしも「優れた鑑識眼の持ち主」だとは限らない、というのは、どんなジャンルの「賞」だって、たいがいは同じなのだ。
例えば、下のレビューは、「サントリー学芸大賞」を受賞した、宗教学者・阿満利麿の『宗教の深層 聖なるものへの衝動』(ちくま学芸文庫)についてのものだが、これを読んでもらえば、この本がいかにひどい内容かを、きっとご理解いただけるはずだ。
つまり、山ほど著作のある小谷野敦を代表する著作に与えられた「権威ある賞」とは、実のところ、この程度に「当てにならないもの」でしかないのある。だから、あと著作など「推して知るべし」ということでなのだ。
○ ○ ○
多くの著述家が、小谷野敦を敬遠するのは、小谷野が「力量のある書き手だから」ではない。単に「訴訟マニア」だからだ。
小谷野は、元「いじめられっ子」だったそうで、その点で同情の余地はあるものの、しかし、そのせいで「性格をこじらせたまま」成長し、今では「ノーマルではない人」をバカにすることに喜びを見出すような、倒錯的な人間になってしまったのはないだろうか。ザ・ブルーハーツではないが『弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩く』(「TRAIN-TRAIN」、作詞・真島昌利)か、さらに一般的にな言葉で言えば「虐待の連鎖」というやつだろう。
しかし、残念ながらそのような根深さを持てばこそ、普通の人が「恥ずかしい」と思うことが、小谷野にとっては、そうではなくなる。
『裁判をやってもらうために税金を払っていたわけで、これは納税者の重要な権利である。どうも日本人は訴訟狂でなさすぎる傾向があるね』
などと、殊更にうそぶく人間になったのだ。
正々堂々と戦う力が無いからかこそ、小谷野は「子供の喧嘩に、親や教師を引っ張り出してこなかったことを後悔」し、さらに今では「親でも教師でも国家権力でも、利用できるものなら何でも利用しよう」という考えなのだろう。
それが、言論人として「恥ずかしい」などという発想は、所詮「力のある者」のそれでしかなく、小谷野のような「負け犬」は「どんな手でも、使えるものは使って、それで勝てばいい」くらいのことしか考えられなくなったのではないか。そんな、哀れまれるべき人間に育ってしまったのではないか。可哀想に。
だかそれでも、こうしたことを野放しにすべきではない。そうでなくても、この世の中はそのような、手段を選ばぬ「勝てば官軍」に流れているのだから、せめて「言論の世界」では、「筋論」を尽くすべきだろう。
しかしまた、そうした「歪んだ人間」たちのほうに、その気がないというのであれば、例えばこの「故人冒涜者」に対抗するために、いま流行りの「クラウドファンディング」で資金を集め、喧嘩してみるのも、悪くないのではないか。
さすがに「死者を冒瀆する」ような、わかりやすく卑怯な男に対する批判なら、世間の理解だって協力だって得られやすいはずだ。
「言論」や「話し合い」ができないのは悲しいことだが、しかし、それが不可能なのであれば、他の手段だって選ばなければならないし、今の日本は、善かれ悪しかれ、そういう方向に動いているのである。
(2022年10月20日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
