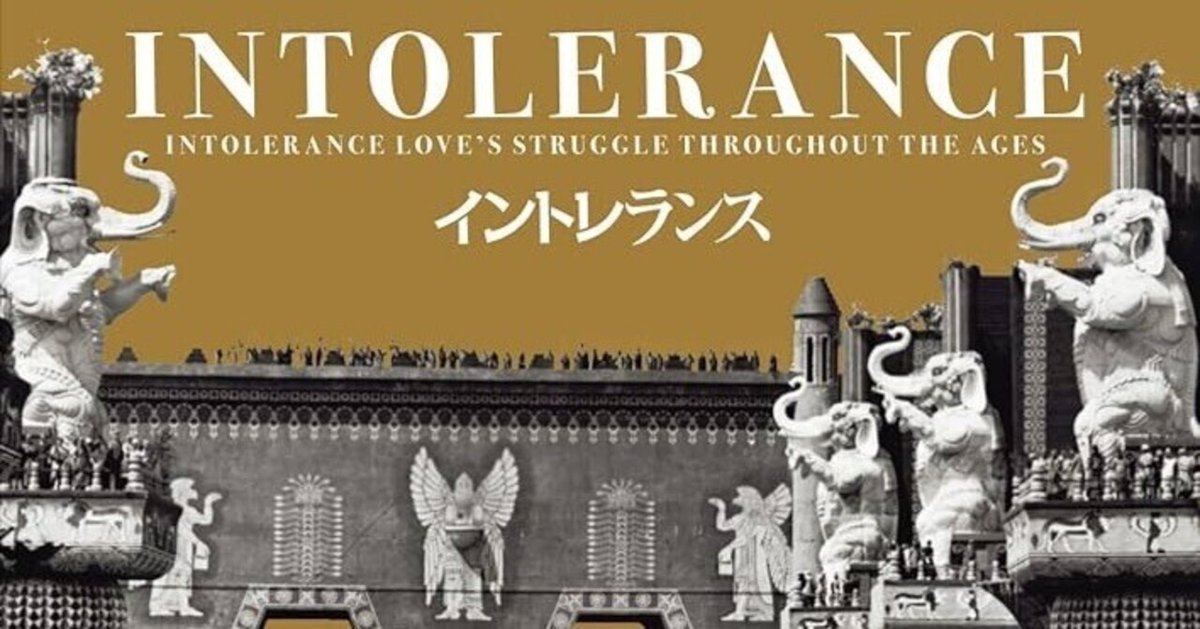
D・W・グリフィス監督 『イントレランス』 : ひと言でいうと「セットが凄い」映画
映画評:D・W・グリフィス監督『イントレランス』(1916年・アメリカ映画)
本稿のタイトルにも示したとおりで、本作が「歴史的名作」となり得ている理由は、次の2点に尽きる。
(1)とにかくセットの規模が凄い。
(2)映画技術史的に意義のある作品。
これである。
つまり「お話(ストーリー)」の中身は、どうでもいい。
今から見れば、いたって「通り一遍」のものでしかないのだが、それだって「昔の作品だから、大目に見ないとね」ということで、特に問題にされることはないから、もっぱら上の2点において、本作は「歴史的名作」になりえているのである。
しかし、特に「映画マニア」だというわけない現代の観客が見て、純粋に感動できるのは(1)だけ、である。
なぜなら、(2)については、今やなんら珍しいものではないからだ。そうと説明されなければ、べつに何とも思わないし、説明されても「そうなんですか」という程度の感想にしかならない。
例えば、(1)の「バビロン篇」に登場する巨大セットを「斜め俯瞰で撮ったショット」など、今の私たちが見たら、別に何とも思わない。
だが、かなりの高さからの撮影が必要であるこのショットが、どのようにして撮られたかというと、無論、今のように「ドローン」でお手軽に取られたのでもなければ、「飛行機」などを使っての 「空撮」でもない。もちろん、風景そのものが「CG」や「マット画」だというわけでもない。映像に動きがあるから、櫓台を組んでその上から撮ったのでもない。もちろん、巨大な「クレーンカメラ」などもなかったから、いわゆる今のクレーンショットではない。
では、どのようにして撮ったのか?

おどろくなかれ、なんと「気球」を飛ばして、それを上下させて撮ったのである。
だから、この「何の変哲もないショット」だって、当時としては驚くべき映像であり、新技術による撮影だったのだが、今の目で見てしまうと、別に何とも思わないようなものになってしまっているのだ。
つまり、この映画が高く評価される理由の(2)とは、「映画史的な価値」というものを重視する「映画マニア」にとっての価値であり、「今の目で見て、面白いか否かが問題なのだ」とする、当たり前の観客には、(2)は「教養的な価値」はあっても、映画そのものを高く評価する理由にはならない。
「猿が、初めて動物の骨を、道具として使ったのか。それは凄いね」という話と、これはまったく同様の意味しか持たないからだ。「たしかに、学術的には凄いだろう。だが、だからどうなのだ」という話にしかならないのである。
『4つの物語を並行して描くという構成や、クロスカッティング、大胆なクローズアップ、カットバック、超ロングショットの遠景、移動撮影などの画期的な撮影技術を駆使して映画独自の表現を行い、アメリカ映画史上の古典的名作として映画史に刻まれている。そんな本作は映画文法を作った作品として高い芸術的評価を受けているだけでなく、ソ連のモンタージュ理論を唱えた映画作家を始め、のちの映画界に多大な影響を与えた。』
(Wikipedia「イントレランス」)

そんなわけで、こうした「豆知識」は、今や「映画史的な価値」でしかなくなっており、知ったかぶりするのには良いネタであっても、映画そのものを「純粋に」鑑賞するという観点においては、あまり意味はないのである。
だが、(1)の方は、「今の目で見ても」凄い。これは、文字どおりに、「本物」だけが持つ迫力、としか言いようがない。

今なら、同じような風景を「3DCG」で作ることが容易に可能なのだが、私たちは、それが「本物」ではないと知ってしまっているから、もはやその「3DCGによる絵」に感動することはできない。
以前に論じたことだが、
私たちの目は、意外に敏感なもので、頭(理屈)では気づかないことであっても、感覚的には気づくということがあって、それで、その目にしているものが、「本物か否か」を判断しているのだ。
「3DCG」で描かれた「架空の壮大な風景」に、しばしば「リアリティ」が感じられないのは、例えば、無意識に「空気感の不自然さ」を感じているとか「建物のデザインから、構造的な不自然さや、そうしたものが産み出される必然性が感じられない」とか「森林の描写が、どこか美しすぎ、まとまりすぎている」とか、そういったことまで感じ取ってしまうからなのであろう。絵画とは違って、リアルであることが必要となる「映画の映像」は、美しければ良い、というものではないのだ。
「3DCG」が、どんなものでも(金と手間さえかければ、表現できる=再現できる)とは言っても、それを「絵」として「創造する」のは、あくまでも、主観の中で生きる、人間である。
そのため、当然のことながらそこには、そのCGクリエーターの「センス」が紛れ込んでしまうので、決して「自然そのまま」というわけにはいかない。
要は、その「絵」には、クリエーターの「美意識」「嗜好」「願望」といったものが混入してしまうため、そうしたものを「共有する人」にとっては、その絵は「自然以上に美しい、不自然な風景」になってしまうし、逆に、そうしたものを「共有しない人」にとっては、単に「不自然なもの」と感じられてしまうのである。
だが、「セット」として実際に作られたものは、たとえそれが「本物の建物」ではなくても、「セットという本物」であり、それが美しかろうが醜かろうが、「現実の存在物」であるという意味では、「本物」そのものなのだ。

たしかに、「本物の建物」と「本物そっくりのセット」では「構造」的には違っているのだが、しかし、日頃、私たちが見ているものは、例えば「建物の構造」ではなく、「そうした構造によって生み出された、外観」でしかないために、その「外観」さえそっくりに再現されてしまうならば、私たちの脳は、そこに「リアルな構造」まで、補完的に感じてしまうのである。だから「セット」は、その意味で「リアル」そのものなのだ。

私たちには、「見た目のリアルさ」よりも、「リアルと感じられること」そのものの方が重要なのである。
それは、先のレビューなどでも論じたとおりで、アナログ技術としての「SFX」を用いて作られた、ジョン・カーペンター監督の『遊星から物体X』(1982年)に登場するモンスター「スパイダーヘッド」は面白いのに、その続編映画での「3DCG」で描かれたモンスターは、ぜんぜん面白くないというのと、同様の事態なのだ。
それは単に、私たちが「SFX」の「手作り感」に共感しているというようなことではなく、「SFX」によって作られたものは、現にそこに「物として実在している」という点でのリアルにおいて、実在しない「3DCG」の「リアルさ」よりも、魅力を感じる、ということなのである。

したがって、私たちが「嘘としての映画」を見る際にも重視しているのも、じつは「本物そっくり」という意味での「リアルに見えるか否か」なのではなく、「それそのものとしての存在感」であり、その意味での「リアルさ」なのだ。
一一だからこそ、本作における「巨大セット」の迫力は、今の目で見ても、今もって、まったく古びてはいないのである。
『「バビロン篇」ではサンセット大通りの脇に高さ90メートル・奥行き1200メートルにも及ぶ巨大な城塞のセットをつくり、城壁は馬車2台が余裕で通れるほどの幅があった。石造建築を含むこの古代バビロンのセットは解体に費用がかかりすぎて、何年も放置された。』
(Wikipedia「イントレランス」)
したがって、この作品のテーマとして語られている「不寛容」の問題だとか、そのテーマに沿っての物語が、今やいかに陳腐なものであったとしても、この「セット」の迫力だけで、本作は十二分に見る価値のある作品だと言えよう。
こんなセットは、もう誰にも作ることはできない、「本物」だからである。
言い換えれば、「CG」とは、たしかに革新的で素晴らしい技術ではあるのだが、しかしそれは、言うなれば「貧乏人の工夫」であって、その意味では、やはり「貧乏くさい」という事実は、否定できないものなのだ。「貧乏」自体は、悪くないとしても、である。
この映画で、もっとも金のかかった「バビロン篇」は、バビロン王に肩入れした悲劇物語となっているが、これは当然のことであろう。
なぜなら、この映画自体が、多くの人の犠牲の上に成立した「贅沢な美の結晶」としての、「バビロン(贅美)」そのものだったからである。
○
(以下は、内容紹介)








(2024年11月1日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
