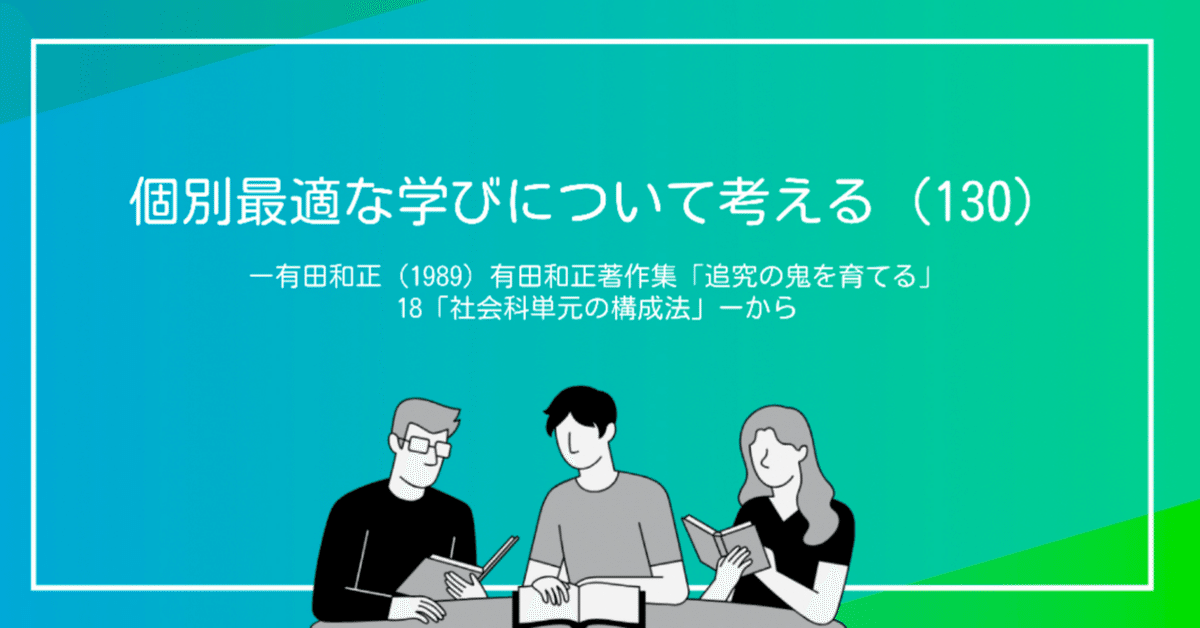
個別最適な学びについて考える(130)ー有田和正(1989)有田和正著作集「追究の鬼を育てる」18「社会科単元の構成法」ーから
おはようございます!
だいぶ、あたたかくなり春っぽさを感じてきました。2月も半ばになり、もう半分かよって思ってしまいますが残りの時間を大切に取り組んでいきたいですね!
本日は「有田和正(1989)有田和正著作集「追究の鬼を育てる」18「社会科単元の構成法」.明治図書,東京」です。では,早速読んでいきましょう!
1問いを深める導入
学習が深まるということは、一人ひとりの子どもの問いが深化する、ということである。図表1の「わかる」(既知)ということは、学習前の「わかる」(既知)①に比べて、質的により深い「問い」が形成されている、ということである。学習が深化していくためには、導入段階で質のよい問題をもたせなくてはならない。わたしは、このために、導入のしかたをいろいろと工夫してきた。研究会の授業なども、導入部分にしぼって行ってきた。
導入に力を入れるわけは、導入がうまくいけばその単元の七〜八割は成功したも同然であるからである。子どもたちは、導入時につかんだ問題を雪だるま式にふくらませたり、より質の高いものを求めて追究することになるからである。
導入に力を入れるのは、問題をもたせることだけではなく、その後の学習を動かす意欲とエネルギーをもたせることができるかどうかがかかっているからである。
導入を改善することは、社会科の授業過程全体の改善につながるのである。
たとえば、これまでの導入には、単元について調べたいことや勉強してみたいこと、疑問などを出させて、それから問題を構成して授業を進めることが多かった。
これでは、追究すべき問題に角度や方向性がなく的確な発展的な問題をもたせることはできなかったように思う。
少なくとも中学年以上の学年では、単元の導入時に、指導内容の核心部分にふれる具体的事例を提示して話し合わせた方が、学習意欲も高まるし、単元全体の展開の見通しもたち、的確な学習問題をもたせることができる。
導入に命をかけていきたいですね。
特に社会科は!追究を目指すのであれば余計にという感じです。
ポイントは中学年以上は話し合いを少し踏まえて取り組んでいくことの重要性ですよね。
そこまで鍛えることも必要だと思います。
この後書かれていますが、ただ導入をしてもダメだそうで、日頃からはてなを見つけることに取り組むことが必要だそうです。
とにかく気になったら調べるということを意識させて取り組むことで人によっては追究の力がついていくということです。
1日1はてな、ちょっと面白そうなのでやってみようかなと思います。
以前書きましたがお年寄りにはならないよう頑張っていきたいですね。
本日はここまで!また次回の記事でお会いしましょう!
いいなと思ったら応援しよう!

