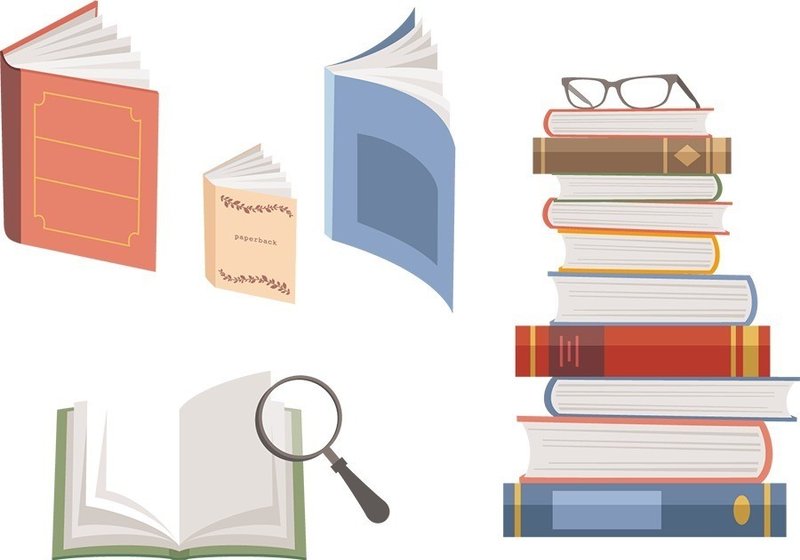
- 運営しているクリエイター
#メディア論
リーチから深さへ。日経とラジオに学ぶ、メディアのコミュニティ戦略
かつて、雑誌はコミュニティを作り出した昔のメディア、特に雑誌は、コミュニティを作り出す力を持っていました。
例えば、「Hanako」という雑誌からは「Hanako族」というムーブメントが生まれ、流行語大賞にまでなりました。Hanako族は、海外旅行に行ったり、ブランド品を買ったり、自分の生活を豊かにしたい女性像を描いていました。
さらに、強いコミュニティを形成していたのが2000年代前後のギャル
インフルエンサー依存を脱却してもNewsPicksが日経電子版を超えられない理由
自らスポットライトを当てた落合陽一氏の上場廃止を特集する「NewsPicks」ニュースメディア「NewsPicks」が、「落合陽一氏のピクシーダスト、1年で上場廃止になった真相」という特集動画を公開し、話題になっています。
NewsPicksは、カリスマ的なビジネスインフルエンサーを発掘してスポットライトを当て、アクセスを集めてきた経緯があります。落合陽一氏もその一人で、NewsPicksでは「W
ラジオで16万人を集客!?音声コンテンツがねらい目な理由
熱量の高いラジオリスナーあるタレントが「ラジオ番組は自分の庭のような感覚がある」と語っていたように、タレントにとってラジオって特別な場所なんですよね。
結婚報告や不祥事の謝罪など、重要な発表の場としてラジオが選ばれることが多いのは、タレントがリスナーを一番のファンだと思っているからです。
今の40~50代の方々は、思春期に深夜のオールナイトニッポンに夢中になった経験がある人も多いでしょう。ラジオ
コンテンツ配信は「情報」から「人」にシフトせよ
コンテンツを見るフォロワーの心理は2種類あるコンテンツを見るフォロワーの心理には、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、「情報重視型」のフォロワーです。これは配信される情報そのものを求めているケースです。ビジネスインフルエンサーが配信するコンテンツがまさにこれに当たります。ビジネス書の要約や時事解説、投資情報、不動産取引の情報などを見るフォロワーは、その「情報」自体に価値を見出しているんですよね
コンテンツマーケティングは、やり続けた人が勝つ
チャンネル登録200万間近のYouTubeチャンネルも、やり続けたから成功したコンテンツマーケティングを始めても、すぐに成果が出ないと諦めてしまう人が多いのが現状です。しかし、粘り強く続けた人だけが最終的に成功を収めることができています。
その好例が、現在では200万人の登録者を抱える堀江貴文氏のホリエモンチャンネルです。今では数十万回、時には100万回を超える再生数を記録していますが、開始当初
テキストコンテンツが読まれない時代に、提供できる価値とは
能動的なテキストコンテンツから、提案型の動画コンテンツへ主軸が移る2010年代前半まで、テキストコンテンツは非常に人気がありました。「ブログ飯」という言葉が生まれるほど、ブログを通じて生計を立てる人も多かったのですよね。また、言論系のテキストメディアがバズることも頻繁にありました。
しかし、2010年代半ば以降、テキストコンテンツが徐々に読まれなくなったように思います。その理由は、人々が能動的に
新しいコンテンツを作り続ける必要がない理由
コンテンツマーケティングには、量が必要?
コンテンツマーケティングを行う際に、コンテンツの量が必要になってきます。これは、SNSプラットフォームのアルゴリズムが関係しています。
例えば、YouTubeやインスタグラムといったプラットフォームでは、アカウントが投稿するコンテンツをプラットフォームが分析して、「どんなコンテンツを発信するアカウントか」を特定します。
その特徴に基づいて、興味がありそうな
コンテンツマーケは"何を”発信するかで99%決まる
コンテンツマーケティングは”何を”発信するかで正否は決まる世の中のコンテンツマーケティングのメソッドは、コンテンツの作り方や、バズるタイミングなど、どのように発信するかにスポットを当てたものが多いです。
しかし、コンテンツの発信方法は実は、そこまで重要ではありません。コンテンツマーケティングの成否は、ほとんど何を発信するかで決まります。
需要のないコンテンツを上手な方法で配信するよりも、需要のあ
コンテンツがバズるための絶対条件
コンテンツをバズらせるための絶対条件があります。それは、必ず突っ込みどころを作ること。言い換えると、コンテンツに余白を持たせるということです。
突っ込みどころがある、つまり余白があるコンテンツは、とてもバズりやすいんです。なぜでしょうか?
失敗は最大の突っ込みどころ最大の突っ込みどころは、「失敗」です。例えば、以前Xを中心にバズったこんな話がありました。
スペイン北部ボルハの教会に「Ecce
宮崎駿、モネに学ぶ、クリエイターが世に出る方法
一度映画化を断られた「風の谷のナウシカ」「風の谷のナウシカ」は、宮崎駿の初期の代表作です。
しかし、その前の「ルパン三世 カリオストロの城」が興行的に大コケしてしまい、当時は宮崎駿に映画撮らせるのが難しい状況でした。
ナウシカの企画出しても、「原作があって、それが売れてるならともかく」と、門前払いをされたといいます。
そこで、当時アニメージュの編集部員であり、後のジブリのプロデューサーとなる鈴
伸びるコンテンツは、情報をワンパン化している
ワンパン化=コンテンツの情報密度を上げる
コンテンツのワンパン化というのは、コンテンツの情報密度を上げることです。
ワンパン料理というものがあります。ワンパン料理というのは、一つのフライパンで作れる簡単な料理のことです。
伸びるコンテンツは、フライパンに料理を詰め込むように、1つのコンテンツの型に情報を詰め込んでるんです。この結果、コンテンツの情報密度がものすごく高まります。
例えば、YouT
コンテンツ初心者が、初めに手掛けるべきコンテンツとは
一般向けの易しいコンテンツは、レッドオーシャン
クリエイター初心者がコンテンツ作成をするとき、分かりやすくて一般向けのコンテンツを狙いがちなんですよね。YouTubeとかでよく見かける人気コンテンツって、有名なYouTuberさんやお笑い芸人さんのネタ動画とかですよね。数百万再生されることも珍しくないんです。
X(旧Twitter)でも、猫や犬の動画がすごくリポストされるんですよね。つまり、バラ
Webメディアは、今すぐYouTubeに手をだすべき理由
テキストメディアは飽和している?
WebメディアがYouTubeに進出したら、メリットしかないと思うんですよね。その理由を説明します。
テキストメディアにおいてはWebが登場して以降、ずっとPVを伸ばす競争が繰り広げられてきました。しかし、ネット回線が発達してユーザーが動画視聴に移行したことで、テキストメディアの力は相対的に弱まっています。
とはいえビジネスメディアにおいてはまだ活字が強いんです















