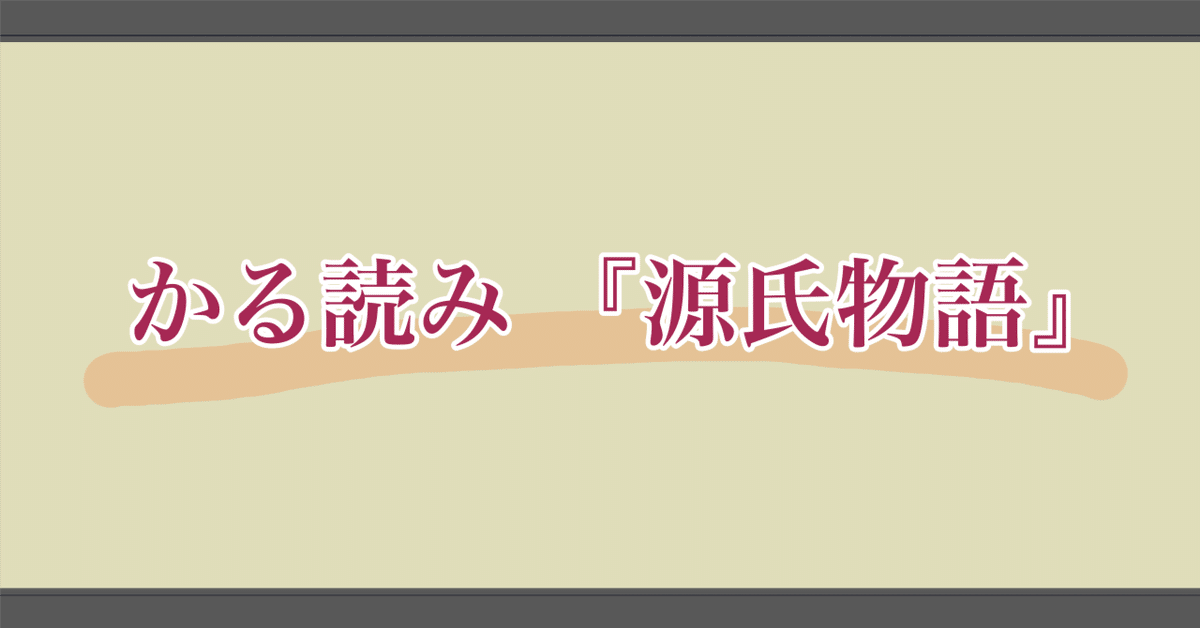
かる読み『源氏物語』 【御法】 紫の上について綴る
どうも、流-ながる-です。『源氏物語』をもう一度しっかり読んでみようとチャレンジしています。今回は【御法】を読み、この物語における紫の上について考えてみようと思います。
読んだのは、岩波文庫 黄15-15『源氏物語』六 になります。ただ専門家でもなく古文を読む力もないので、雰囲気読みですね。
中の品物語を振り返る
『源氏物語』の話題のひとつとして”中の品”の物語があるかと思います。これは【箒木】の雨夜の品定めにおいて大きなトピックでした。"中の品"とは何かを考えた時、紫の上を示すのではないかと考えました。
紫の上は源氏の女君のうち最上級の女性という認識ですが、振り返れば紫の上は品が上の女君ではないです。この世界にはごくわずかな上の品に属する人間がいて、そこから外れた人たちの物語がメインということになり、紫の上もそうした一人ですね。
紫の上の父の式部卿宮(【若紫】では兵部卿宮)は藤壺の宮の兄で【桐壺】では后の宮を母としていることがわかります。その高貴な父の脇腹の娘が紫の上です。紫の上の母は父の正妻に追いやられた末に早世しています。ここだけの話ならば、源氏の幼少期と被りますね。上の品から外れた位置にいる姫というのが紫の上のはじまりでした。
【若紫】で紫の上は源氏に引き取られます。面影が似ている、藤壺の宮の血縁である、ただそれだけで彼女の運命は変わります。
この【若紫】の話は、継母に引き取られるの回避した『落窪物語』の姫だと感じています。『落窪物語』の姫は継母と暮らしているがために長年虐げられ続けました。こうなる運命が紫の上には待ち受けていて、源氏が介入することで運命が変わり、やがて紫の上は継子を慈しむ清らかな心の持ち主に成長し、その最期に娘の明石中宮に看取られます。
ここからは想像になりますが、作者は『落窪物語』の姫の物語に批判的で、継母にいくら仕返しをしたとしても、いびられ続けた年月の長さに憤りを覚えたのではないだろうか、と思ったのです。
自分なら"引き取られるより前に救い出させる"と書いたのではないでしょうか。『落窪物語』で、いじわるな継母が仕返しされてスッキリするのは読者で、姫そのものは舞台装置とも言えなくはないです。本来なら、継母とは関わらないほうが良かったということになります。
【若紫】は『落窪物語』のifストーリーで、まだ親元に引き取られるような年齢の少女を無理にでも引き取らせる事情が源氏サイドにあるからこそ成り立つ話なんですね。こうなると藤壺の宮の存在は紫の上救出ストーリーの仕掛けにも見えてきます。
理想と好みは異なる
藤壺の宮について整理しますと、彼女が最上級の女性であることは間違いありません。内親王で母も后の宮ともなると、物語で匹敵するのは、明石中宮を母とする今上帝の女一の宮ではないでしょうか。この姫宮は後に、薫の憧れる高貴な女性として登場します。
藤壺の宮は源氏の臣籍降下が決定した直後に登場します。源氏にとっては絶対に届かない領域の貴人、つまり上の品の女性です。そのボーダーを越えた結果、冷泉帝が誕生し、源氏は帝の父となりました。
藤壺の宮への思慕は最上級の憧憬であったように思います。皇族から外れた源氏が決して戻れぬ領域に藤壺の宮はいる。そうして理想は形作られて、少女・紫の上を得る理由となりました。
理想は藤壺の宮です。しかし紫の上は彼女とはとても重ねることが出来ないのがはっきりしています。藤壺の宮は決して踏み入れることの出来ない、帝の妃、かつ内親王なのです。それは全くもって紫の上にない性質で、源氏はあくまで慰めとしての期待を持っていました。
源氏のもとで育てられた紫の上はどうなったか、理想ではなく"好み"に育ったということなのでしょう。
谷崎潤一郎作品の『痴人の愛』にナオミという人物がいますが、主人公の譲治はこのナオミを淑女に育てようとして失敗しています。しかし反面、失敗ではなく成功しているとも思えてきます。ナオミは主人公・譲治の好みに育ったのではないかと。源氏もまた紫の上を理想にしようとしながらも、最後には好みの女性に育てたと考えています。そこに本人の意識はなく、半ば無意識というところでしょうか。
紫の上が桐壺の更衣に回帰する
後半の紫の上は苦しむことが多かったように思えます。女三の宮の存在が紫の上が持っていないものを浮き彫りにし、"中の品 "の物語を思い出させました。
源氏は臣籍となりましたが、後に準太上天皇となり、上皇並みの扱いを受けることになります。これは領域を越え、六条院と呼ばれ、臣下の立場から脱したということになります。しかし、それはすなわち紫の上との距離を生じさせました。
源氏が上皇並みの扱いに変化したことで、紫の上が再び"中の品"であることを意識させられました。女三の宮と源氏の結婚でそれが表面化し、紫の上の立場は変化します。
紫の上は女三の宮が登場しても源氏(六条院)に重んじられました。それは読者からすれば当然であるけども、物語内の人物たち全員がそうであるわけがないのです。女三の宮は世間で重んじられる内親王で、強力な後見がついています。女三の宮を重んじることを当然とする考えの人物も多くいる。
この身分による歪みは【桐壺】を思い出させ、紫の上は桐壺の更衣そのものへとなっていったと思いました。【桐壺】では実像が見えなかった桐壺の更衣ですが、紫の上のように周囲の人々には慕われていたのかも知れず、紫の上を通し実像が見えてくるような心地がしました。さすがに紫の上が桐壺の更衣のように虐げられることはありませんが、六条院という場所が政治とは無関係であったというのが大きいですね。しかし紫の上に対する静かな圧は彼女の心にじわじわと疲労をもたらしたことだろうと思います。優れていることが人々の鬱屈を煽る、それが紫の上の心労につながったのではないでしょうか。
本来なら皇族から離された源氏が、同じく宮家の脇腹の姫として苦難が待ち受けていた紫の上を救うといった物語のはずが、後に源氏が院と呼ばれる存在に格上げされることで、紫の上を苦しめることになる。それが、源氏の母が直面した問題に近かったというのはどうにも虚しさも感じました。
出家を果たせなかった紫の上
紫の上は出家を望みましたがそれをとうとう果たすことが出来ませんでした。だからとて、救われなかったとは思えません。『源氏物語』において多くの人が出家していますが、それぞれに明確な理由があり、その中には自らの罪と向き合って何とか救われたいと願ったものもあります。
藤壺の宮や六条御息所、女三の宮など、出家した女性たちにはそれぞれ罪があります。紫の上にはそれがありません。むしろ長年徳を積み、清廉であり続けました。そうして源氏の望みの通り、許しを得ずに出家することもしなかったのです。
紫の上に先立たれ、嘆く源氏の姿はあまりにも物悲しいです。これは紫の上が清廉であるがゆえのことだとつくづく感じます。紫の上が罪と呼べるものもなく生きて死んだからこそ、源氏の悲痛がダイレクトに伝わってくるのでしょう。しがらみから逃れられなかったものの、それから逃れることなく清廉であろうとし、そう在り続けた紫の上の死が深い悲しみとして読者に響き渡る。あくまで一読者の感情として、紫の上は救われ美しい世界へ旅立ったと思いたいです。【御法】において描かれる夕霧を通した紫の上の死に顔からもそうであると思わせられます。
紫の上は藤壺の宮の影ではない
源氏の求めた理想と紫の上は異なります。『源氏物語』は"中の品"が主役で、源氏自身もまた皇族から外された者です。紫の上はそうした"中の品"の物語のヒロインで、藤壺の宮はきっかけとなります。
つまり、紫の上を主体とするか、藤壺の宮を主体とするかで『源氏物語』の見え方は異なるということですね。よく紫のゆかりという表現がされますが、"中の品"の物語として見ても面白いというのが、新しい発見となりました。
長くなりましたが、ここまで読んでくださりありがとうございました。
参考文献
岩波文庫 黄15-15『源氏物語』(六)柏木ー幻
続き。光源氏の物語が終わりを迎えます。
いいなと思ったら応援しよう!

