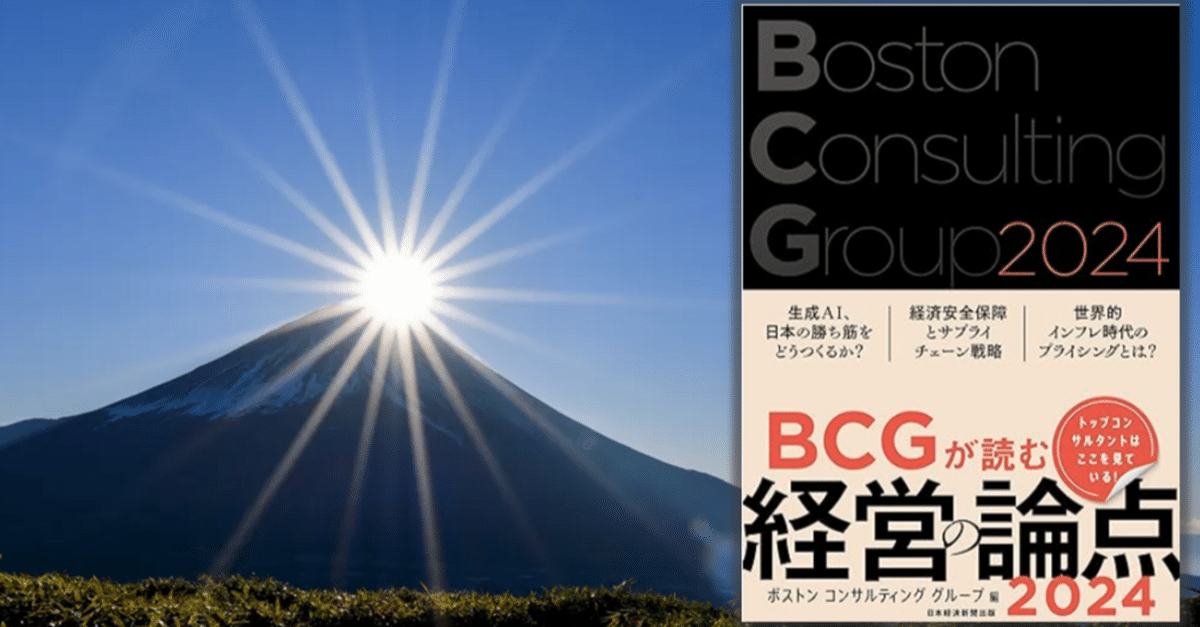
BCGが読む経営の論点2024⑥:「事業開発」、今こそアンゾフの成長マトリクスの多角化戦略に挑戦すべし
読書ノート(156日目)
昨日に引き続き、今日も
こちらの本を紹介していきます。
もはや毎年恒例とも言える
「BCGの経営の論点」シリーズ
2024年版の注目テーマ(目次)は
以下の通りです。
・2024年に注目すべき大きな潮目の変化
第1章 エネルギーシフト:日本企業は”賢い需要家”を目指せ
第2章 生成AI:日本の”勝ち筋”と導入の5つのポイント
第3章 サーキュラーエコノミー:気候変動の次は生物多様性が問われる
第4章 経済安全保障とサプライチェーン:
リスクの見える化で意思決定の仕組みづくりを
・競争優位を築くために必要な組織の能力
第5章 事業開発力:新たな成長に向けM&Aをどう活用するか
第6章 イノベーション:進化する手法と日本企業復活へのポイント
第7章 プライシング:インフレ時代の「値付け」戦略
第8章 人材戦略:「人事」を越えた経営課題へ発想の転換を
そして今日からは
本書の後半のテーマ
競争優位を築くための組織の能力
ということで、
第5章 事業開発力
についてです。
第5章:事業開発力
新たな成長に向けM&Aをどう活用するか
・2023年、経営者の方々との議論で最も多く話題にのぼったのが
「どう成長するか」というシンプルな問い
・過去の成功の方程式の限界
・アンゾフの成長マトリクスでの従来の成長戦略の中心は
①市場浸透戦略、②新市場開拓戦略、③新製品開発戦略であり、
④多角化戦略はハイリスク・ハイリターンだと考えられることが多かった
・しかし今は、①②③の既存の延長線上の成長戦略は行き詰まり、
④多角化戦略を具現化するための、周辺や飛び地に参入し、
既存事業のビジネスモデルを変革する「事業開発」が
成長戦略の中核に位置づけられつつある
・従来の成長戦略が行き詰っている背景
・①市場浸透戦略(既存市場において既存商品のシェアを上げる)
国内市場に関しては、人口減少で市場のパイが大きくならず、
業界再編がない中でのシェア争いは価格競争を誘発し、
利益を毀損する結果につながることも多い
・②新市場開拓戦略(既存の商品を新規市場に展開)
海外市場の開拓は今でも重要な経営アジェンダだが、
この20年で現地企業も成長し競争環境も激化
新興国=未開拓の新市場という構図は完全に失われている
・③新製品開発戦略(既存市場に新商品を投入)
成熟市場においては新商品の投入は既存商品とのカニバリゼーションを
生み、財布や時間の取り合いとなるケースが多く、「真水」としての
売上拡大の貢献は従来ほど期待できない
・「多角化」を軸とした事業開発を全社としての成長に結びつけていく
切り札としてまず考えられるのはM&Aの活用
・「創る」「造り替える」「手放す」、それぞれの実行手段として
M&Aや事業売却を活用する
・具体的な”核”となる事業を獲得するうえでのM&Aの3つの視点
・成長市場アプローチ
・成長が予想される市場への参入・事業拡大に必須となる
技術や機能を核として獲得
・例として、オランダに本社を置くグローバル化学企業DSMは
石油化学事業を切り離し、付加価値の高いプレミックス領域
(各種栄養素などをニーズに応じカスタマイズして提供する事業)
で核となる技術を持つ企業をM&Aで獲得し、
最終市場を含め周辺領域への拡大を果たしている
・技術アプローチ
・これから発展・高度化する新技術を核として獲得し事業開発を行う
・GEは2016年に欧州の3Dプリンターメーカー2社を買収し、
自社の航空機エンジンの部品点数を減らす などの効率化を実現
・オペレーショナル(事業運営)エクセレンスアプローチ
・高度な事業オペレーション能力を武器に、核となる新たな事業を獲得
・米ダハナーはトヨタのKaizen方式をベースに
ダハナー・ビジネス・システム(DBS)という
オペレーショナル・エクセレンスの方法論を構築し、
買収した企業にDBSを導入し収益を向上させている
・既存事業の事業モデルを変革する上で最初に考えるべき問いは
「自らの中核事業をディスラプト(創造的破壊)するとしたら」
・ディスラプターが現れる前に自らディスラプトすればいいという発想
・製品の高付加価値化、ソリューション・サービスの一方か
双方を組み合わせて「造り替える」ことで、売上利益の向上だけでなく、
消費者が他の製品・サービスに乗り換えにくくなるスイッチング障壁を
つくることも可能となり、中核事業から生まれる
トータルキャッシュインフローの拡大につながる
・事業開発するためのキャッシュの創出、マネジメントの複雑性解消に
向けては「手放す」事業を決めて売却やスピンオフを進めることが必要
・ポイントは、聖域を設けず、高く売却するために定常的に事業価値を
高めておくこと、いつでも売却できる前提を整えておくこと
・2024年のアクション:一歩踏み出すための工夫
・まずは事業開発を成功裏に進めるための「準備」に早急に取り掛かること
・自社の実力を見極める
・市場浸透戦略、新市場開拓戦略、新製品開発戦略でどこまでいけるのか
「客観的」な評価を行う
・いつまでにどの程度の事業開発を行うべきか、時間軸と規模感を把握する
・推進体制を構築する
・事業開発チームの設立がその第一歩で、事業部から切り離した
出島組織を準備する
・M&A以外にも必要な費用に対する予算も付与する
・CVCには50億円や100億円単位で予算をつけ意思決定も一定程度権限委譲
する企業が多いが、社内の事業開発部門もビジネスリターンを
求めるための投資として同等の費用や権限を付与すべき
・人材は社内から集めるだけではなく、実行上必要な体制を社内外から獲得
・意思決定のレベルアップを図る
・新しいことを創る、中核事業を造り替える、今ある事業を手放す、
これらは極めて難しい意思決定が求められるため、
組織的な「決める力」のレベルアップを図る
・意思決定のレベルアップのための3つの実用的なアクション
・決めないリスクへの意識を高める
取り組む領域・テーマが決まれば「アドバイザリーボード」を設置し、
業界専門家やアナリストなど、その分野の知見を持つエキスパートから
の”気づき”を得る機会を設け、決めないことのリスクに対して
目を開かせる場として活用する
・「決めない場」で決めることを議論して理解を深める
・非公式な会議体、信頼できるメンバーで「決めるべきこと」の
議論を行い、理解を深めるとともに、何がクリアにあれば判断できるかを
議論し、そのインプットを得たうえで決める場で意思決定をする
・決めることのハードルを下げる
・意思決定が難しいトピックは、小さい領域からのスタート、
見極めのための期限を設ける、リスクを他社と共同でシェアすることで、
決めることのハードルを下げることも一案
・M&Aを活用し、
「創る」(新たな成長の多面をまく)、
「造り替える」(既存事業の変革)、さらには
「手放す」(事業の売却及び撤退)取り組みを推進し、
戦略的に組み合わせ、持続的な成長の道筋を描く
今回のテーマは事業開発でした。
私にとっては、
アンゾフの成長マトリクスの話が
分かりやすく、従来は
ハイリスク・ハイリターンとされた
多角化戦略に、今こそ挑戦すべきだ!
という内容だと理解しました。
私自身も今の部署では、
グループ会社全体のDXを
推進する仕事を担当しており、
本書の中での
・既存事業の事業モデルを変革する上で最初に考えるべき問いは
「自らの中核事業をディスラプト(創造的破壊)するとしたら」
・ディスラプターが現れる前に自らディスラプトすればいいという発想
という言葉は特に印象的でした。
日々、仕事に追われていたり、
売上や契約が順調に取れていると
ついつい忘れがちですが…
「顧客が感じる本当の価値とは何か?」
「顧客はなぜ自社を選んでいるのか?」
というドラッカー先生の言葉を
定期的に、強制的に自問自答することが、
この創造的破壊へのアイデアのヒントに
なりそうだと感じました。
今日も最後まで読んでくださり、
ありがとうございました!
それではまたー!😉✨
