
日本の限られた国土と、日本人の適応能力の関係
地理を学ぶこととは、単に、主要な都市や島を暗記することではない。
『Geography for Life』が、1994年に、全米地理教育評議会、ナショナル・ジオグラフィック協会、アメリカ地理学者協会、アメリカ地理協会の地理教育実施プロジェクトにより、出版された。(2012年に改訂)
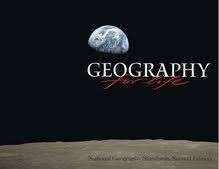
地理で探求すべき18個の基礎知識が、6つのグループに分類されている。
・空間用語における世界
・場所と地域
・物理的システム
・人間システム
・環境と社会
・地理の用途
4年生まで・8年生まで・12年生までと、何をどのくらいの年に学ぶと適切かのガイドラインも、示されている。
米国各州で、この『Geography for Life』にもとづいて、地理のカリキュラムが教えられている。
17)地理に詳しい人は、過去を解釈するために地理を適用する方法を知っており、理解している。
18)地理に詳しい人は、現在を解釈し、将来の計画を立てるために地理をどのように応用すればよいかを知り、理解している。
すなわち。過去を知り現在に活かす、現在を知り未来に活かす。
私はこの概念に賛成だ。
1億2500万人以上の人口を抱える日本の国土面積は、人口約3100万人のカリフォルニア州よりも、わずかに小さい。

耕作可能な土地は、日本の国土の15%ほどか。必然的に、資源の効率的な利用が求められる。
西洋の文化が入ってくるまで、日本には、家具という発想がほとんどなかった。
江戸時代の終わり頃、桐のたんすが使用されたが、日本の生活様式に密着した家具だった。


昔のたんすは、サオを通して持ち運べるように、棒通しという金具が横側についていた。移動させることが前提の家具だったのだ。
火事の時にもち出して逃げるためーーと、よくいわれているが。もっと、根源的な理由があるのではないか。
日本人は、そもそも、物を押入れにしまう。


ふろしきのように袋と呼ぶ。



いざ食事をする時に、箱膳などを出していた。寝る前に布団を敷いて、起きたら片付けるのと同じだ。


日本の伝統的な家は欧米のそれと違い、寝室や居間や客間といった、部屋の明確な区別がない。間仕切りが、ふすまでなされている。
ふすまは軽い。現代では、ふすまを外したりはめたりしたことがない人も、多いのかもしれないが。女性1人で、物によっては何枚も重ねて運べるほど、軽い。
こういうことが、当時のたんすのつくりにも、通じているといえるだろう。

伝統的な草履や下駄には、左右の区別がない。
はいている内に鼻緒が伸びて、左右の足に、別々にあうようになるからだ。

小指やかかとがはみ出してるのが正式。
甲州印伝の特徴は、鹿革に漆で模様を付ける伝統技法にある。
鹿革は、手に馴染む柔軟性と強度と軽さを備えていることから、武具にも使われていた。経年で光沢が増す。


紗綾型は卍の連続。石器時代のインドにて卍は太陽が光を放つ様子。
日本の伝統的な衣服は、変化に1着で対応できるように、設計されている。サステイナブルだ。
着物は平面で仕立てられている。体型が多少変化しても、着方で調整できる。縦も。身長プラマイ5cmまで全てジャスト・サイズ。=差10cmは差にならない。
体格のかなり違う人が着るというのであれば、仕立て直せばよい(立体裁断の服より断然に容易)。
また、1枚の反物に戻すことも可能。長方形に裁断された、8枚のパーツでできているため。衣服としての役目を終えても、さまざまな活用法がある。

着物をもんぺに直すヒロイン。とろい子などではない。

戦争反対。
徳川時代。日本の都市における公衆衛生システムは、発展途上でありながらも、西洋のそれと比較して良好であった。
18世紀初頭には、江戸の人口は、100万人近くに達していた。
都市が多くの人口を抱えれるように発展すると、人が密集して、流行病や疫病が蔓延する可能性が上がる。衛生環境が悪くはなかった日本でも。そのあたりはジレンマである。
日本人は、限られた国土の中で、うまく適応してきた。逆に言うと。国土が限られているからこそ、解決策や打開策を考え出し、日本人の適応能力は上がっていった。
