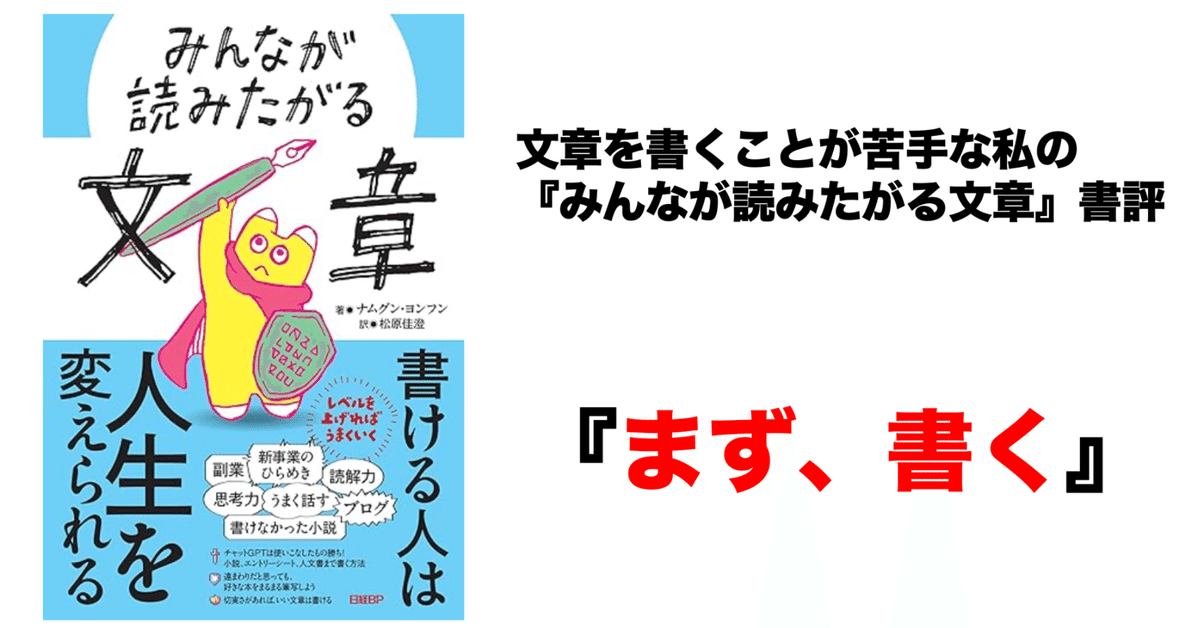
【要約・読書記録】みんなが読みたがる文章:ナムグン・ヨンフン(前半)
ご覧いただきありがとうございます。
記念すべき1冊目は、『みんなが読みたがる文章』について書きました!
1.本を読んだきっかけ
読書をする人は年収が高い傾向にあるという話をよく聞く。自分も読書をしたら年収が上がるのではないか、そう思いなんとなく読書をしていたが、自分の力になっているかわからなかった。ただ読むだけでは何も身につかないのではと感じた。読んだ記録を形に残した方がいいことはわかっていたが、具体的な行動はできていなかった。たまたま本屋を歩き回っていたら、偶然目に飛び込んできた。記録に残すために、まず文章の書き方を読書を通して学ぼうと思い、『みんなが読みたがる文章』を読むことにした。
2.著者紹介
著者:ナムグン・ヨンフン 翻訳:松原佳澄
大量の本を読み、独学で書くことを覚えた。文章を書きつづけていたら本を何冊か出版。書き方の講義や個人授業もしている。休まず書くことで、一日一日ちがう自分に成長している。「特許 知的財産権で一生稼ぐ」、「ハーバードキッズ上位1パーセントの秘密、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングに集中せよ」、電子書籍で「航空整備士回転翼免許 口述試験対策」など韓国のさまざまな分野で本を出版。ベストセラーおよびステディセラーになった。また、小説や童話で韓国のさまざまな賞に入賞する。
3.内容の要約(前半)
本書では文章を書くための内容をレベル1からレベル7に分けて述べています。
レベル1 文章を書ける人が勝つ時代
レベル1では、文章を書かなければならない理由や文章を書く利点を述べています。文章は人間が創造するものの中で、もっとも素敵なものであるとし、文章を書くことで得られる満足感を「5つのよろこび」で表現しています。
①成長のよろこび
書けば書くほどいい文章を作れるようになり、素敵な文章が書けるようになれば成長を感じよろこびに包まれる。
②創造のよろこび
人間は生れながらにして創造せずにはいられません。文章を書くことは創造の塊。偉大なコンテンツの始まりは、小さな言葉、短い文章から。
③没入のよろこび
没入は人間だけが享受できるよろこび。没入すると、時間・空間・すべてのものが止まってしまう感覚になり、頭が冴え体がすっきりするのを感じられるでしょう。
④感情を排出するよろこび
文章を通じて自身の感情を表現すると、不思議なことに心が安定する。
⑤知ることと気づきのよろこび
さまざまな知識があり、たくさん考える人だけが深みのある文章を書くことができる。勉強して文章で表現すると、知識と合わさって新しい気づきを得る。
レベル2 あなたの思考を爆発させる基礎7つ
本章で7つある内容を3つに凝縮しました。
①まず書く
超大物作家でも書くことは苦痛であり、文章を書く子はとても面倒くさい。才能がある人はまず描き始める人である。
②インプット
文章は0からの創造ではなくマネするところから始まる。マネするために資料を集めたくさん読むことが大事。また深みのある文章を書きたいなら、古典を読む。
③質問をする
文章を書けない理由は、自分が考えないせいであり、自分の考えを練って育てたものが質問になる。常に考え、練り上げられた思考は文章のネタになる。
レベル3 文章が上手い人が書く前にしていること
文章をうまく書ける人が、行うこと・意識することとして、3つにまとめました。
①短く簡単に書く(短いことが正義)
絶対原則その1:文章は1行の70%が適切。最長でも一行半を超えない
絶対原則その2:1文に1概念、一段落に主張は1つだけ。
②冒頭と最後の一文が、その文章を歴史に残す
タイトルはストーリーの羅針盤である。「30-3-30」の法則があるように、30秒間、タイトルと副題をみて読者は読むか読まないか葛藤します。
最後の一文は、気持ちと行動に変化を与えるものにする。
③『推敲』は文章の始まり
見直して修正することを「推敲」といいます。一度で文章を完成させることができるのは優れた文筆家だけです。文章の完成度を高めるのは繰り返された「推敲」だけです。
具体的な推敲の方法について。
・自分の文章は直すところがあると思って見る
・多様な視点から見る
・目的意識を持って見る
・初稿の70%を残す
・吐くまで見る
4.新しく知った事柄や気づき
『みんなが読みたがる文章』の前半部分だけでも多くの気づきを得ることができた。要約を書くために、何度も読んで書いてを繰り返したおかげで内容が頭にこびりついた。こういうことか!とまだ前半しか読んでいないが感動した。前半部分で学んだことを活かして、この記事をまずは書いてみた。今まで文章を書くのが嫌いな私が、文章を書いたということで、本書にもあるように「まず書く」はクリアできたと思う。今後後半部分についても、前半の内容よりもわかりやすく書けるように、繰り返し読み、推敲していきたいと思う。
最後まで読んでいただきまして、
ありがとうございました。
後半部分についても掲載予定ですので、
ぜひ後半の投稿もご覧いただけると嬉しいです!
