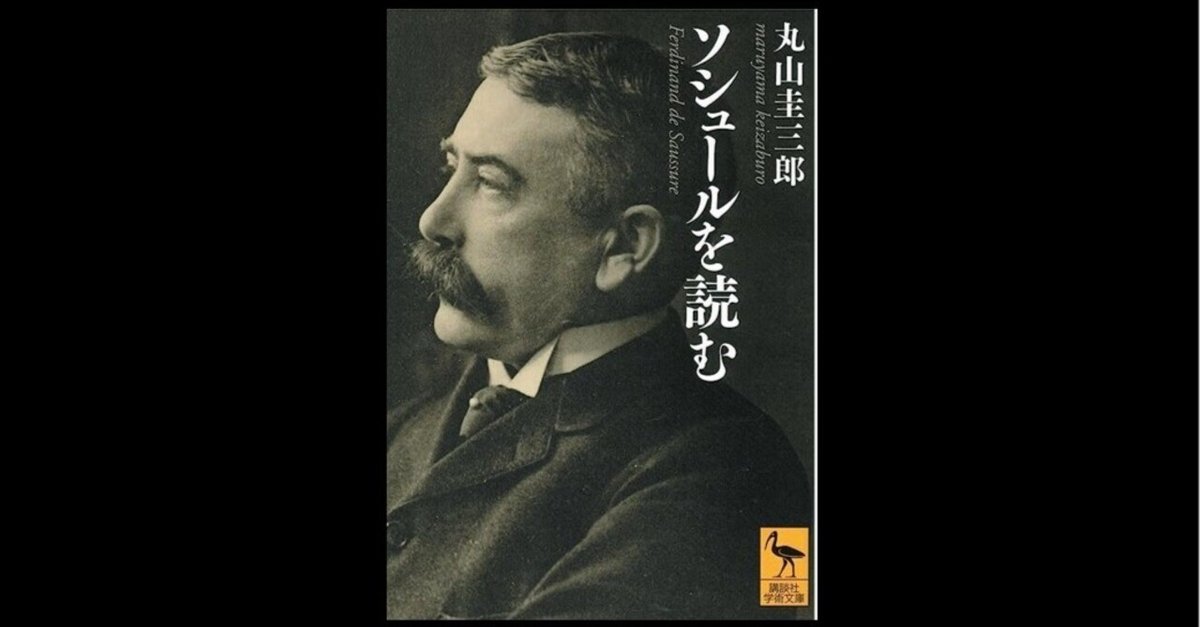
◆読書日記.《丸山圭三郎『ソシュールを読む』》
<2023年6月24日>
丸山圭三郎『ソシュールを読む』読了。
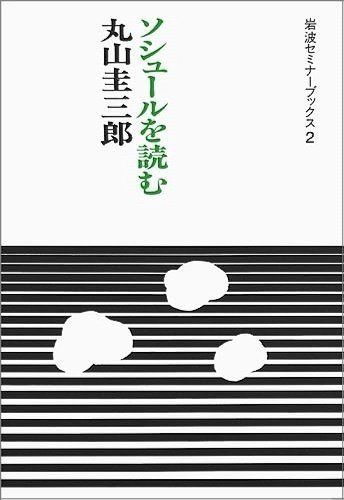
以前もご紹介したが、著者の丸山圭三郎は日本のソシュール研究の第一人者で言語学者・フランス語学者。
80年代のポスト構造主義ブームでは主著『ソシュールの思想』(1981年)で一躍言論界で注目を浴びた思想家でもあり、本書はそんな丸山圭三郎の主著のひとつでもある。
本書は岩波セミナーブックスからの著作という事で、セミナーの内容をまとめた講義録と、その講義録を踏まえて丸山なりの思想を展開する「ソシュールと人間学」「ソシュールと文化記号学」の2論文を掲載する内容。
本書のソシュール思想の説明部分については、以前ご紹介した『言葉とは何か』にもかなり内容がかぶってくる。本書は『言葉とは何か』をより詳しく説明したといった形でもある。
日本はソシュールの唯一の主著『一般言語学講義』が発表された時期は世界に先駆けて非常に早かった。
1928年には既に日本語訳が出版されていて、これは英語訳・ドイツ語訳よりも早かったというのだからかなり早い。
そんなに早い時期から紹介されていたソシュールに関する研究を行っていた丸山圭三郎が、何故80年代になってから注目されたのか?というのは、ぼくにとってちょっとした謎であったと言っていい。
これは本書を読むと納得するのだが、ソシュールを知らない一般読者に説明するとなると、そもそも『一般言語学講義』の成立過程から説明しないといけなくなる。
ソシュールの『一般言語学講義』は「講義」と名前が付いている通り、ソシュールの講義録となっている。
この『一般言語学講義』は、ソシュールがジュネーブ大学で1907年から3回に渡って「一般言語学」のテーマで行った講義の内容が元になっている。
このソシュールの講義は当時の言語学としては先進的な考え方を持っていて、それを後にシャルル・バイイとアルベール・セシュエが講義ノートを集め、ソシュールの残していた草稿などもまとめて編集して一冊の形にしたのが『一般言語学講義』であった。
つまり、『一般言語学講義』はソシュール本人が書いている訳ではない。
そのためソシュール自身の考え方とは違っていたり、ニュアンスが変化していたり、といった部分が見受けられるのだという。
丸山圭三郎の『ソシュールを読む』は、その『一般言語学講義』をそのまま読むのではなく、ソシュール本人が残した原稿の原典にあたって、『一般言語学講義』という「本」ではなく「ソシュール」その人の思想を「読もう」というのが特徴と言えるだろう。
というのも、日本ではこの『一般言語学講義』に書かれた内容を元にソシュール批判や言語学的な論争が発生したという状況もあったため、そういった言語学会の状況を整理するための「原典を読む」でもあったようだ。
「何故いま(1980年代に)ソシュールを読むのか?」という問いに、丸山圭三郎は冒頭に三つの答えを提示してみせる。
そのひとつ目が、上に書いたソシュール思想に対する誤解と歪曲、それに伴う論争の混乱状況を整理し、ソシュール思想の原典を読むという理由があった。
ふたつ目は、ソシュール思想の持つ、丸山が言う所の「エピステモロジー」の側面をとりあげるためである。
この「エピステモロジー」というのは、マックス・ウェーバーの「科学は思想を批判する(価値批判)」の考え方と対照的な概念として挙げている、「思想は科学を批判する」――つまり思想の側からによる<科学批判>である。
19世紀は、科学が文明を飛躍的に発展させたが、その反面、その手の「科学」や「論理」や「客観性」といったものに無反省に信頼を寄せ過ぎた部分があった。
では、そもそも「科学的」とはどういう事を言うのか。「客観的」とはどういう事を言うのか。――そのようにして思想の側が、科学というものを批判的に吟味する。
20世紀になってから、そういうスタンスで科学や諸学問や論理を再検討するタイプの思想が多く出てきた。
丸山は、ソシュールの言語学にはそういう側面もあると言っているわけである。
即ち、ニーチェが古代ギリシア思想のスタンスから西洋的な伝統的主知主義を批判し、フッサールがヨーロッパ諸学の危機を唱え、ハイデガーが古代ギリシア思想にまで遡って伝統的西洋思想の転覆を計った――そういった「エピステモロジー」の流れの一つにソシュール思想も組み込まれているというわけである。
みっつ目は、ソシュール思想を現代的な問題に応用し、丸山が主張している<文化のフェティシズム>の乗り越えとしてソシュールの記号学が利用できるのではないかと提案しているのである。
ただ、ここまで来るとソシュール思想は単に「言語学」の範囲を大きく超え、記号学的な色合いが非常に強くなる。
丸山の思想のユニークな所は、おそらくこの記号学的なスタンスからの現代文明批判を行った「文化の記号学」であった所だろう。
このふたつ目、みっつ目の内容が、丸山がソシュール思想を踏まえたポストモダニズム的な思想家として注目される事になる丸山なりの思想だと言えるだろう。
それが本書の末尾の2章「ソシュールと人間学」「ソシュールと文化記号学」にまとめられている内容となっている。
丸山圭三郎が何故単なる「ソシュール研究家」ではなく日本のポストモダニズムで「思想家」という扱いになっているのか、――ぼくは以前からその部分に興味があったのだが、本書を読んで何となく丸山の思想傾向が理解できた気がする。
丸山はある意味、ソシュール右派的なスタンスでソシュールを乗り越え、独自の思想を結実させた人だったのだと言えるだろう。
◆◆◆
ソシュールはジュネーブ大学でヴェルトハイマーから一般言語学の授業を任されたのを、いやいや引き受けたそうである。
以前ご紹介した『言語学を学ぶ』の千野栄一や『言語学とは何か』の田中克彦も、「言語」とは何かという問題について簡単に説明できないという事を繰り返し書いていた事が思い出される。
ソシュールが一般言語学の講義を行った時期は比較言語学が主流の時代だったからこそ、余計に「言語とは何か」という問題は非常に難しいものがあったのだろう。
ソシュール以前の比較言語学というのは、あまりに「科学」に拘り過ぎていたという部分があった。
だから、ソシュールが構想していた「思想は科学を批判する」エピステモロジーとしての構造主義言語学は、理解されにくいという事情があったものと思われる。
ソシュール以前の言語学は、「科学」で解明できない事には踏み込まないのが「科学的」である、というスタンスだった。
だから、言語学が「思想」であってはならなかったわけである。
しかし、「言語とは何か」という言語の原理を追求する「一般言語学」という授業を構想する場合、ソシュールからしたら「では、なぜ人間だけが言語を使うのか」という思想的な問題にまで踏み込まざるを得なかっただろう。
そのために、ソシュールは「言語を使う人間の思考システム」に手を付けた。それがランガージュという考えに繋がっていくわけである。
「言語にあっては何もかも心理的である」とソシュールは言う。
言語は人間の心的作用であり、フロイトの言う所謂「無意識」の働きでもある――だからソシュールは心的言語主義なのである。
しかし、ソシュール以前の比較言語学は、言語を使う人の心理的・内面的なシステムには決して踏み込まなかった。当時ブラックボックスであった人の心理的な側面を扱うというのは「科学」ではなかったと考えられていたからである。
ソシュールは最終的に、その考えを成立させるために『一般言語学講義』の冒頭で、比較言語学を批判せざるを得なかったのだろう。
◆◆◆
コトバなくして人間は「科学」を生み出す事は可能だったか?
人間の作り出した「科学」を成立させるものが論理的思考であるからには、おそらくコトバなくして科学は成立しなかっただろう。
そもそも論理的思考はコトバなくして成立はしないからで、だからこそソシュールのランガージュ論は人間の思考の基盤を考える思想でもある。
ソシュール思想の重要概念である「ランガージュ」とは、「言語」や「言語活動」等と訳される事が多いので、人間が言葉を作り出してそれを人々の間で交流させて行って発展させていく能力であるといったイメージがあるかもしれない。
が、丸山はその考え方を否定し、元々のソシュール思想ではランガージュはもっと範囲の広い概念だとして説明している。
ソシュールによると、ランガージュなる概念は単に言語能力とか言語活動という訳語から想像される意味をはるかに越えた<シンボル化能力>の謂である。すなわちランガージュとは「描く、彫る、歌う、身振る、話す、書く」という一切の像(イマージュ)能力であり、時間、空間的距離を作る抽象か能力であるという点で、動物のミメーシスとは本質的に異なるヒトの模倣行為を生み出す源である。
ヒトと動物を分ける能力は何だったのか。
ヒトも動物も共通して持っている能力として、世界を理解するために生物が身体でもって世界を理解し、身体をもってして世界を分節していく能力を丸山は哲学者・市川浩の思想から考え方を借りて<身分け構造>とした。
著者が<身分け構造>と呼ぶものは、ユクスキュルの環境世界 Umweitの概念と重なるもので、彼のひいた有名な例を挙げれば、明度覚・嗅覚・温度覚の三つの感覚しかもたないダニの行動によってダニ固有の環境世界が作り上げられ、それとダニの内的世界 Innenweltの間に円環的な適合関係が保たれることによって、生物体の生の機能が維持されるような構造を指している。交尾を終えたダニの雌は、皮膚の明度覚のおかげで木の枝にのぼる道を見出し、嗅覚と温度覚のおかげで枝の下を温血動物が通り過ぎる瞬間を知り、枝から離れてその動物の上に落ちて血を吸う。ダニは目も耳も味覚ももたない。必要としないのである。
動物の持つ<身分け構造>に加えて、人間は<言葉>を作り出す事によって世界を分節化し、様々な概念を発見していって自我を構築していき、ものを考える基盤を作り出した。
(因みに人間が言葉によって世界を分節し概念を作り出す事については以前の記事<◆読書日記.《町田健『コトバの謎解き ソシュール入門』>でもご紹介している)
ソシュールは「言語に先立つ概念はなく、言語が現れる以前は、何一つ明瞭に識別されない」と言っていた事を思い出してみてもいいかもしれない。
言わば人間は言葉によって世界を分節する<言分け>能力を持つ動物なのだと言って良く、この<言分け>こそが、人間が動物から分岐して大きく文明を発展させた原因だったと丸山は見ているわけである。
過去も未来も、コトバの産物であり、ヒトはコトバによって「今、ここ」ici et maintenantという時・空の限界からのがれ、ポジティヴな世界をゲシュタルト化する身分けに加えて、ネガティヴな差異を用いて関係を創り出す非在の世界を言分けする。この第二のゲシュタルトを<言分け構造>と呼び、その構造を生み出す構造化能力がランガージュとすれば、この過剰としての文化の惰性態こそ、ラングにほかならないことを明確にしておきたい。
自然物というものはもともと確固とした種類が存在していて、それぞれの種類に合わせて人間が名称を付けていったから、今の「言葉」というものがある。……ソシュールはそういった、古代からある言葉の「名称目録」的な感覚を、固定概念だとして批判した。
自然というものは、もともと何かしら分類されていたわけではないし、人はそれらの分類されている自然を整理して名前を付していったわけでもない。
もともと分類も整理もされておらず、カオスな状態である自然に対して、人間は言葉を付ける事によって同時にそれを分類し、それに意味を付与し、概念化していったのである。
言語化というものは、意味のないものに意味を付与するという側面がある。
これが過剰化すると、意味のないものに過剰な意味が発生してくるわけである。
例えば、単なる石ころでしかないものに神性を見出して拝んだり、鹿や蛇やフンコロガシを神だとあがめたてる「物神崇拝」は、こういった人間の「意味付与能力」――ランガージュによって<言分け>されたものに過剰性が現れたものの一例だろう。
人間には<言分け>という能力が備わっているがために、そのように「自然本来のもの」としての自然の姿が失われ、文化的な過剰性が現代生活一般に浸透しているのではないか。
例えばハイデガーは、西洋が「ものの見方」を古代ギリシアからどのようにして代々受け継いできたのかを解き明かす事によって、このような人間が恣意的に自然に意味付与を行い、分節化し、分類し、更には科学的な方法論によって自然を作りかえる西洋的な科学観を批判し、「ピュシス(=自然)」の概念でその乗り越えを図った。
それに対して丸山圭三郎は、ソシュールの概念を用いて「社会、文化、文明もラングである」というスタンスで現代を分析し、ソシュール的な記号学によってその乗り越えを図った。丸山圭三郎の思想とは、そういうものだったのであろう。
