
宿命的絶対性に抗する道
「人間の歴史が始まって以来、《神》との戦いを続けられてきた。その戦いの歴史があるからこそ、ぼくは今、《神》との戦いを受け継ぐことができるのだ。かつて、あなたがぼくたちに語ったように、《神》と戦おうとする人間は、結局は憤怒と絶望のうちに死んでいくことになるのかもしれない。だが、彼らの憤怒と絶望に意味を持たせるためには、《神》との戦いをあきらめるのではなく、続けていかなければならないのだ……」(山田正紀『神狩り』)
昨年(平成9年)暮れの関ミス連大会のゲストは、清涼院流水だった(※ 平成9年=1997年)。
大会参加者と彼との質疑応答を聞いていて、私がまず強く感じたのは、清涼院のどうしようもない「幼さ」ということであった。
たしか「なぜ小説の中で、ハートマークや従来の小説では使わないような記号を多用するのか?」という質問に対しだったと思う。清涼院はこれに、おおむね次のような趣旨の回答をした(と記憶する)。
「従来の文学は意味もなく権威主義的に保守的、制度的だった。小説というのは元来何をやっても良いジャンルなんだから、つまらない約束事に縛られる必要はまったくないと思う。僕はミステリをはじめ、小説は小説として大変好きですし、小説でしか表現できないものもあると思っています。だからそういう小説を書きたいと思って努力しています。しかし一方で小説同様にマンガも大好きで、その小説にはない長所を十分に認めています。だから特殊な記号の使用といったことに限定することなく、従来の小説作法を逸脱する行為であっても、それがより良い結果をに結びつくと思えるなら、僕はそうした技法の使用をためらうつもりはありません。僕は他のジャンルの技法も積極的に取り入れて、制度的な文学の殻を打ち破り、新しく、より面白い小説を書きたいと思っています。」

清涼院の言っていることは、決して間違ってはいない。原則としてそれは「正論」であるとさえ言えよう。けれども、彼の文学に対する認識がいたって浅薄であり、所詮は「半可通の知ったかぶり」でしかないということは、少しでも文学全体を見渡そうとしたことのある者には、あまりにも一目瞭然である。
無論、二十代前半の若者である清涼院に、文学に対する本格的な知識を要求するつもりはないし、私自身そんなことを要求できた義理でもない。けれども私と同様、無知なら無知で、謙虚にその事実を認識するくらいのことは、清涼院にも決して不可能なことではなかったはずだ。
にもかかわらず、(日本の)純文学に対する劣等感をその心理的背景とし、純文学の最も低劣な部分にだけ目を向けて、これまでのすべての純文学が基本的に「権威主義的に保守的、制度的」であるかのように語るのは、無知なミステリマニアが抱きがちな偏見で、明らかに彼の行き過ぎであり、誤りであると言えよう。いまさら清涼院が思いつく程度の「実験」的試みは、ほぼ例外なく既にアバンギャルドの文学者たちによって真摯に実行にうつされてきたはずなのだ。
したがって、例えば現在この日本で、いまだに「私小説」なるものを「(清涼院言うところの)権威主義的に、保守的、制度的」に書いているかに見える作家たちがいるとしても、(よほど程度の低い例外的存在以外)彼らはそうしたアバンギャルドの実験結果を承知の上で、あえて「私小説」を書いているのだと理解すべきなのである。
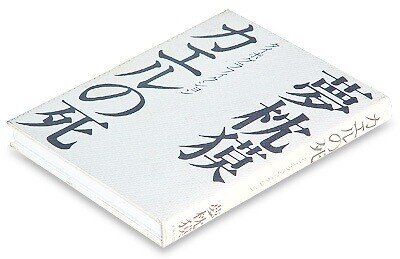
つまり実験的な小説の面白さも承知の上で、しかしそれでも、一見「保守的」に見える形式でしか書けないものがあり、またそうしたものを書きたいと思うからこそ、私小説家たちは、そうした一見「古い」形式を、あえて選んでいるのだと考えるべきなのだ。
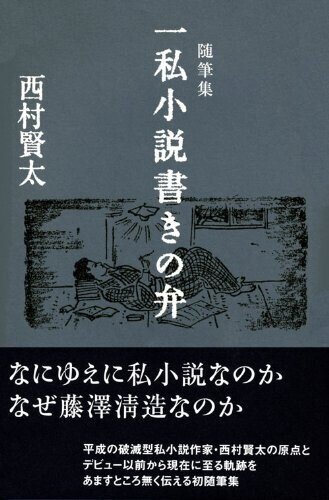
そうした、いわば「敵」への敬意と配慮を欠いた清涼院の態度は、それ故にこそ常識のある者にとっては「幼稚」なものとしか映らない。したがって「従来の文学」に対する彼の勇ましい決意表明も、実際のところ、微笑ましい「子供のツッパリ(の域をまったく出ないもの)」としか、私の目には映らない。そう映らざるを得ないものとなってしまっているのである。
(ミステリ作家やマニアの、純文学に対するこの手の決めつけは、往々にして自己の秘められた性格の「他者への投影」であるにすぎない。つまりミステリ作家やマニア自身の保守主義や権威主義といったものの、それは純文学に対する投影に過ぎない、と考え得るのである)。
……だが、私はこの「幼い」作家のことを、個別限定的に批判するつもりはない。本稿の意図は、そこにはない。
ここまで私の語ったことは、言わば「クズをクズ」と批判しただけに等しく、自明な事実の過剰な追認でしかないので、それ自体にさしたる価値はない。つまり、問題はこの先なのだ。
私は一年ほど前に「二枚のカード」と題し、京極夏彦と清涼院流水を比較的に語って、「新本格」作家たちの清涼院に対する冷淡な態度に秘められた問題点を、短く論じた。
(同稿は本来、京極を扱った同人誌に発表する予定で執筆されたが、内容が清涼院に重点を置いたものとなっていたため、編集人の提案で本誌に回された)
清涼院のデビュー作『コズミック』に付された竹本健治の推薦文(?)「ミステリという伝言ゲームの果てに咲いた異形の妖花。」が端的に指摘するとおり、『コズミック』は、本格ミステリの純粋培養的新種として、「新本格」を、その特性においてさらに純粋培養したかのような(あるいは、黄金期本格ミステリの三次生産物的な)作品である。

京極夏彦の作品が「新本格」の遺伝子を取り込みつつ、一方でその幅広い読書に裏付けられた多様な遺伝子をも同時に取り込んでいた結果「バランスのとれた怪物」として生まれ出たのに対し、清涼院のそれは、純粋培養ゆえの末端肥大的な歪みを生じさせてしまった。
この「誇張された歪み」が、たしかに「親」の世代たる「新本格」作家たちの嫌悪を招かざるを得ないものではあったろうことは、想像に難くない。
けれども、その嫌悪の根底にあるのは、その「歪み」が、たしかに自分たちのそれにどこか「似ている」という直観的自覚から出来したものであったことも、また論を待つまでもなかろう。自身の秘められた「歪み(倒錯的=フェティシズム的性向)」を誇張して突きつけられたときに惹起された「近親憎悪」の怒りが、『コズミック』に向けられた、「新本格」作家たちによる、過剰な反感・敵意の正体だったのである。
昨今、清涼院作品を凌ぐとまで言われる『六枚のとんかつ』や『A先生の名推理』といった作品、あるいはそれほどではないにしろ、一般的には「あんなものはミステリじゃない(あるいは、小説じゃない)」といった感じで評判の宜しくない「メフィスト賞受賞作」が、講談社のノベルスから次々と刊行された結果、千街晶之をはじめとする新本格に好意的なミステリ評論家たちが、これらの作品とこれらの作品を世に出した編集者を批判したりしているのだが、私のような局外者から見れば、これらの批判は、誤りではないにしろ、対症療法的に過ぎ、問題の本質をかえって見えにくくしてしまいかねない危険性が、感ぜられないではない(トカゲの尻尾切り)。

実際、生まれるべくして生まれたものは認知するしかない。
不出来な子を「不出来」と評価するのは誤りではないけれど、不出来だからといって「親」との関係を誤魔化すようなことがあってはならない(「メフィスト賞受賞作」的作品を評価し、公刊し得る編集者の感性があったればこそ、当時「反時代的」であった『十角館の殺人』などが刊行しえた、という事実を肝に銘じて、評価・考察すべき事柄である)。

無論、「子」の問題は、基本的には「子」自身が責任を持って主体的に取り組んでいかなければならないものだ。だが「親」には「親」の責任もあって、「親」は「親」なりに真摯に「子」の問題に取り組まねばならない義務がある。
「なぜ、選りに選って、うちにこんな不出来な子ができたんだろう」と「子」をヒステリックにひっぱたいてみても、何の解決にもならない。「親」がそんなバカであったなら、その家庭の行く末は「お先真っ暗」でしかありえないのである。
……ともあれ「親の因果が子に報い、可哀想なのはこの子でござる」などと嘆いてみても始まらない。
この「家庭の悲劇」を、局外者たる私が局外者たる私なりに考察した結果の助言を、以下に記して当事者親子の参照の用に供しよう。
前記「二枚のカード」の最後で私自身が提示した疑問『「子供を救え!」るのは誰か? そもそも「救う」とはどういう行為を意味するのか? 果たして我々は本当に「最後」のカードを引当てしまったのだろうか?』に対し、私なりの「解答」を示してみたいと思う。
まず、この「親子」二代に共通する問題点は、自分の「親」の世代の苦労(問題意識)を十分に学ばず、したがって本来「親」から十分に学んでおくべきことを学ばずに、その「若さ(怖いもの知らずの奔放さ、あるいは無邪気さ)」だけを売り物に、「親」を超えて「一人前」になったつもりになってしまったことである。
例えば、綾辻行人のデビューに始まる新本格ミステリ草創期の作家(とその周辺の作家)たちは、「親」の世代にあたる「社会派ミステリ」作家を、ややもすると安易に否定しがちであった。

たしかに現在の新本格自体がそうであるように、ひとつのムーブメントが頂点に達し、爛熟期をむかえると、客観的に見て「程度の低い作品」がどんどんと商品化され、またそれがそこそこ売れてしまうといった「末期的状況」が現れる。
「古典」的作品を読みながらも、そうした「社会派」の「末期的状況」の中で育ってきた「新本格第一期」の作家たちが、「社会派」がミステリ史において貢献してきた部分もあるのを理屈では承知しつつも(そうした既成事実への感謝よりは)、目前の現状への反発に傾きがちになるのは、あるいはやむを得ないことかことだったのかも知れない。
病床でいつも不機嫌でわがままな(つまり、無能であるが権威的な)「親」しか知らない「子」にとって、「親」がこんなになるまで働いてくれたから今の君があるのだ、とか、本当は(「親」は)立派な人なのだ、といった言葉は、あまり説得的ではなかったのである。
やがて「子」は「親」を捨てて、世に出ていく。世に出てみると、自分とよく似た境涯を生きてきた「同世代」が世に満ちていた。
彼らは共感し共闘し、やがて世間で主流をなしていく。そして彼らは叫ぶ。
「「親」たちは愚劣だ!「親」を捨てろ! でも、僕はわずかに記憶する(※ つまり、時を経て「美しい記憶」としてのみ存在する)「祖父母」は素晴らしいと思う。君たちもそうだろう? ならば僕らは「祖父母」の心を受け継ぎつつ、この家系を未来へと継承していこう!」。
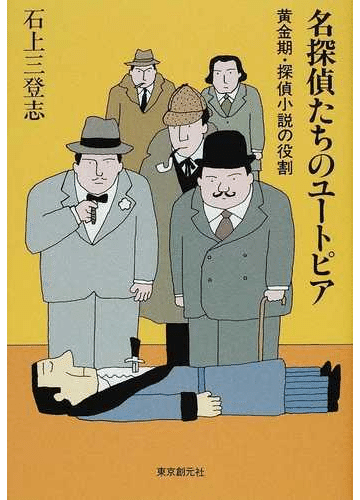
だが、その「泥臭さ」の中にこそ、厳しき現実(第一世代の構造的劣性)と戦い、生き抜いてきた第二世代(社会派ミステリ世代)の「知恵」もまた、含まれていたのだ。
今、「親(第二世代=社会派ミステリ世代)」を捨てた「子(第三世代=新本格第一期)」たちは、自らが「親」となり、その「子」世代の(自己認識として「さらに洗練され」、その実「お化け屋敷」に退行しつつある)「第四世代(清涼院流水以後)」によって、「泥臭い」といって切り捨てられつつある。
さらに「第四世代」にとっては、「第三世代」に好ましく感じられた「祖父母(第一世代=黄金期本格ミステリ)」世代の「洗練された美」も、すでに充分「古臭い」ものでしかなくなっているのだ。
だが、果たして「歴史」とは、こんなものでしかなかったのだろうか。常に「老兵は去るのみ」。単なる「伝言ゲーム」、つまり、ただ歪みゆくだけでしかない、修正(自律)能力の欠如した、不完全な情報伝達ライン。常に物事の価値は、新しい世代の「センス(快楽原則=不快感排除の原則)」によってのみ量られ取捨選択され、時代の波間を漂いながら変容していくだけしかない、そんな主体性のかけらもない「敗北主義的決定(宿命)論」のようなものだったということを言うのか。
……だが、もし私たちに、少しでも自分たちを突き放して評価し、現実の否定的局面を客観的に評価する能力をがあるのなら、私たちは、ただ手をこまねいて本能のままに流されるのではなく、ある「不変的・普遍的価値」言い換えれば「理想としての美(超自我的なるもの)」を、ある程度は主体的に設定しているのではないだろうか。
しかしそのためには、私たちはあらゆる「価値・美」に対しで謙虚でなければならない。
例えば、文学における「人間探求」「社会性」といった問題(超自我的傾向)を、「古い」といって切り捨てたり、「僕らは僕らのやり方の延長線上に、それを実現してみせる」などと威勢よく安請け合いをして「先人の労苦への無配慮」を安易に正当化してはならない。
かつて「志ある文学者」は「文学性と娯楽性を、芸術性と社会性を相備えた文学の確立」を目指した。
その結果は、その理想の困難性のゆえにこそ、必ずしも芳しいものではなかっただろう。だが、だからといって、こうした「先人の労苦」を「図式主義」だの何のと「自分のことしか考えず、ただ本能のままに生きただけの(自堕落な)人間」が、その浅はかな言葉で嘲笑しても良いものでは決してない。
彼ら先人たちの目指したことの本質は、快楽原則が最終的には「涅槃(ニルヴァーナ)」へと向かわざるを得ない「死(タナトス)の原則(刺激を無化・排除し、生物の起源である無機質に戻ろうとする傾向)」に従っていることの洞察からきた、「生(エロス)の原則(さまざまな要素と結合し、生命を活性化し維持しようとする傾向)」による対抗措置だったのである(ここに清涼院流水と京極夏彦の本質的な差がある)。
ともあれ、自分たちの「センス」をただ正当化し、突き進んだ結果が「新世代の裏切り(こんなはずではなかったのに)」であるなら、自覚可能な私たち「大人世代」は、ここで自分たちのこれまでの「無自覚」「無反省」、そして救いがたい「甘さ」を反省して、自分たちも主体的に担ってきた「新世代による裏切り」の連鎖という「繰り返される不幸」を、ここで断ち切る努力をすべきなのではないか。
たしかにまだ私たちの世代、つまり「新本格」世代は「幅広い支持」を受けているかに見える。だから私たちは、自身の「現状認識」さえも支持されているかのように、都合よく考えがちだ。しかし実は、その「幅広い支持者」のかなりの部分が、私たちには評価しがたい「新世代」をも支えているという事実もまた、否定しがたいことなのだ。

だからこそ「新本格」世代は、なかんずく「新本格」作家たちは、自分たちの「価値観」あるいは「認識(の正しさ)」の根拠を、世評に求めるべきではない。自分たちが、その自信の拠り所としているものは、実は自分たち自身が、支持しきれない存在でしかないのだという事実を、直視すべきである。
つまり私が言いたいのは、「世評を根拠とした傲慢に陥ることなく、冷静に歴史的パースペクティブを持って自分たちの位置を見定め、謙虚に理想を目指すべきである」というだけのことなのだ。
身内同士で、同世代的に褒め合い慰め合い「一期は夢」と生きるのもよかろうが、ならば「本格ミステリの未来」など、身の程知らずに語らぬことである。
しかし、それを本気で語るのであれば、私たちは「自己を精一杯生きる」のは当然のこととして、「過去と未来の橋渡し」としての重責を、つまり「過去の他者」と「未来の他者」への重責を全うすべく、自己の今あるべき姿を追求し、それを主体的に生きるべきなのだ。

言うまでもなく、私たちが「継承し、伝承していくべきこと」は、先験的に私たちに備わっているものばかりではない。私たちが案外「無知」であることは、少し冷静になってみれば、決して自覚できないことではないはずだなのだ。
だから、「批判的継承」というようなことも含めて、私たちはいったん自己絶対化の傲慢を捨て、謙虚に学び、そして伝えなければならない。
このわかりやすくはあれ、実行の容易ではない実作業の先にしか、私たちが主体的に「未来」を開く道はない。「退廃」を免れて、私たちの手で「子供を救う」手立てはないのである。
私自身はペシミスティックな人間の一人です。こう書くとわたしをあなたが笑わぬだろうとわたしは思います。しかしわたしは、「懸命な努力」は根本的にオプティミスティックなものだと思います。
(中野重治「渡辺一夫さんへ(第一便)」
そしてわたしは、われわれがいつも、ごく気軽に、快活な気持ちで、開き直っていなければならぬと改めて感じます。そこで次手に、わたし自身もペシミストだと言ったところをわたしとして撤回します。
(中野重治「渡辺一夫さんへ(第二便)」
平成10年6月21日
初出:1998年(平成10年)8月15日
『別冊シャレード37号 清涼院流水特集』(甲影会発行)

(※ 本稿の初出文は縦書きであったので、今回の横書きによる転載では、文頭の「一段落し」を止め、適宜改行を加えた。また、誤記誤変換を訂正し、言い回しも一部改めた。/2021年11月22日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
