
福本博文 『心をあやつる男たち』 : すべては脳内での 〈物理化学現象〉
書評:福本博文『心をあやつる男たち』(文春文庫)
本書(文春文庫版)の帯には『洗脳の恐怖!』という惹句が、オドロオドロしいフォントで大書されている。その下には、丸ゴシック体で小さめに『マインドコントロールの実態に迫る!』と、やはり「!」を付けた説明書きが添えられている。
いずれにしろ、本書の「売り」が、読者の「恐いもの見たさ=野次馬性」に訴えるものである、というのは間違いないところだろう。著者の意図は、もっと真面目なものだが、版元編集者は、読者が何を期待しているのかを、ほぼ正しく見抜いて、そこに訴える『洗脳』や『マインドコントロール』という言葉を惹句に用い、マインドコントロールしようとしたのだ。
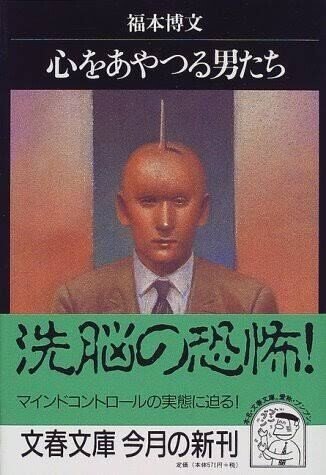
本書は、怪しげな特務機関やカルトによって「洗脳」や「マインドコントロール」がなされ、他人によって自由自在に操られるロボットかゾンビみたいな人間が作られた、とかいったサイコホラー映画のようなお話では、決してない。
基本的には、自分の心の弱さや性格的な弱点を克服しようとしたナイーブな人たちと、それをある種の「手法」によって実現しようとした人たち(あるいは、人の心を操ることに憑かれた人たち)のことを描いているにすぎない。それが、やがて金儲けなどと結びついて、極めていかがわしいものになっていったという、意外にありがちな話なのである。
著者の言葉で言えば、次のようになる。
『 本書は、牧師の再教育法として上陸した実験室訓練が産業界へ伝播し、やがてその流れをくむ自己開発セミナーが台頭してきた過程を、ひとりのトレーナーの半生を主軸にしながらその三十年間の足跡を描いたノンフィクションである。
私は、この米国産のトレーニングが日本的なものに解釈されてゆく変遷に興味をおぼえたが、とりわけ社員教育や精神修養、集団心理療法、宗教、カウンターカルチャー、マルチ商法といったものに関心があったわけではない。それらが複雑に交錯しながら、現代社会の不可思議な側面をかたちづくっていたことに関心があったのである。』(「あとがき」より)
本書に紹介される「訓練」手法は、第三者の目には「暴力的」であったり「宗教」がかっていたりして「奇異なもの」と映るのだが、そこでなされていたことは、決して「不思議」なものではない。
本書刊行の1993年当時は、まだ充分に知られてはいなかっただろうが、「脳科学」的な研究成果が一般にも知られるようになった現在では、これらの「訓練」や「セミナー」でなされた「人格改造」的な成果とは、きわめて「物理化学的なもの」であって、決して「神がかりなもの」ではなかった、ということがよくわかる。
つまり、「受講者」たちを、社会から隔離して、非日常的な環境に措き、そこで半ば強制的に本音を語らせたり、お互いの欠点を指摘し合わせたり、時には暴力を振るってまで、その人が心の中に秘めていた感情を引き出すなどし、言わば、受講者たちの「心の防御壁」を破壊して、感情の解放をもたらすというそれは、ある意味では極めて「合理的」な手法なのだ。
人は通常、自分の「本心」を他人に見せたりはしない。人に見せて「恥ずかしい」部分は隠し、その上で自分をすこしでも「良く見せよう」と腐心するものであり、それが「当たり前の人間」である。
しかし、こうした「当たり前の心理」の裏には「本当の自分を隠している」とか「他人を欺いている」といった「罪の意識」が、半ば無意識的に貼付いていて、その「自責の念」がストレスとなって、時に人を苦しめる。「どうして自分は、もっと正直に生きられないんだろう。どうしてもっと、自分らしく生きられないんだろう。自分はなんて弱くて卑怯な人間なんだ」と、真面目な人ほど、そうした悩みを抱えがちである。
そして、そうした人は、「弱い自分」を乗り越えるための「心の支えになるもの」を外に求めており、それが「信仰」である場合もあれば、「お金」や「地位・名声」あるいは「酒や薬物」である場合もあるし、本書に描かれるような「精神鍛錬のための訓練」や「自己開発セミナー」だったりもするのである。
彼らは、いろんな手法を用いて「自分の殻」を敗り、「強い人間」になって「開放感」を味わいたいと思っている。
自分がいま感じている「不全感」は、自分が「弱い人間」であるための「心理的自己防衛機構(心の殻)の過剰な強さ」による「囚われ」感(自己閉塞感)なのだと考える。そして、なんとかその「殻」を破壊したいと考え、「殻」を破壊して外へ出れば、そこには「自由な世界」が広がっていると「夢想」しがちなのである。一一しかし、無論それは、間違いだ。
「心の殻」とは、もとより「傷つきやすい心」を「守るため」に存在しているのであって、心を傷つけるためにあるのではない。だから、「心の殻」を破壊するという行為は、きわめて危険なのだ。
この種の「訓練」や「セミナー」で行なわれることを簡単に言うなら、「私の心の殻を壊してください」と思い、無防備になっている人たちの「心の殻」を、強引に殴りつけて、その「心の殻」にヒビを入れ、そこへ強引に指を突っ込んで、「心の殻」をひっぺがす行為だ、とでも理解すればいい。
そのとき多くの人は「生まれたばかりの赤ん坊」のように「柔らかく繊細な肌」を持って、この世に「再誕」する。「心の殻」を失った「剥き身の心」は、極めて感度が高く、「心の殻」を通して見ていた、これまでの「鈍くぼんやりした世界」は、「瑞々しく鮮明な世界」に変貌する。だから、人は、自分の能力がアップしたのだと感じて、感動しがちなのだ。
これは、喩えて言うなら、白内障の人が、手術を受けて、ハッキリくっきりと見えるようになった時の感動と同じようなものだと考えればいい。
しかし、「心の殻」をひっぺがすという手法は、白内障手術のように、その手法の安全性が確立されたものではなく、言わば「荒療治」でしかないので、当然、それには「施術ミス」や「副作用」といった「弊害」をともなうことも少なくない。
つまり、「心の殻」のひっぺがし方が強引すぎたために、心そのものを傷つけてしまうこともあるし、施術そのものがうまくいったとしても、「心の殻を失って丸裸にされた心」は傷つきやすいし感染症への抵抗力も低い。言い換えれば、事後的にも傷つきやすい状態に措かれてしまっているのである。
そして、その結果、自殺をする人や、精神を病んでしまうような人も、とうぜん出てくる。
「精神防衛機構」としての「心の殻」を強引な方法で破壊すれば、そうした弊害が出てきやすいというのは、当たり前の話なのだ。
この種の「心の殻を破る施術」というのは、白内障手術のような、安全性に配慮した、方法的に確立された手法ではなく、簡単に言ってしまえば、「覚醒剤投与」のように危険なものだと考えればいい。
たしかにこの種の「施術」には「薬物」を使わないから、一見「自然で安心」だと思えるかもしれないが、前述のとおり「脳科学」的に見れば、やっていることに大差はない。つまり、どちらも「外部からの物理的働きかけによって、強引に脳内快楽物質を分泌させる」という、物理化学的な「直接作用」なのである。
私が本稿のタイトルを『すべては脳内での〈物理化学現象〉』としたのも、そういう意味なのだ。
この種の「施術」やその結果が、どこか「宗教」がかって感じられるのは、じつは「宗教」のやっていることも、まったく同種の「物理的」なものだからである。
例えば、祈りの中での「見神体験」や、神の存在を実感する「回心(えしん)」といった「非合理的な体験」も、内容的には「特殊な心理状態に措かれた時に、脳内で発現する物理化学現象としての、脳内快楽物質の過剰分泌」でしかない。その「恍惚とした多幸感」は、「神」が与えてくれたものではなく、物理的な脳内作用でしかないのだが、人はそれに「自分好みの解釈」を当て嵌めてしまいがちなのだ。
たとえば、多くの人は「恋愛」を素晴らしいものだと考えるだろう。だが、その「合理的な根拠」とは、何なのか。
一一その根拠とは、「恋愛体験」がすべての人に、非日常的な「恍惚とした多幸感」を与えてくれるという事実である。つまり「理屈はどうあれ、何物にも代えがたいほど素晴らしい(と感じる)」という、ただそれだけの話。理屈ではなく、単なる「実感」でしかないのだ。
しかし、所詮「恋愛」というのは、生物として「種を残すため」に仕組まれた「物理的機構」であり、その意味では素晴らしい(=素晴らしくよく出来ている)と言えるだろうが、なにか「崇高なもの」としての価値を有するというわけではない。種を残すためには「異性を好きにならなければならないので、そういうふうに作られている」というだけの話であり、人類の存続に価値を見いださない人であれば、恋愛など「必ずしなければならないもの(それほどの価値のあるもの)」ではないのである。
この「恋愛」という事例において私が言いたいのは、「恋愛はつまらない」ということではなく、「人は、気持ちいいものについては、理屈抜きで素晴らしいという価値評価を与えてしまうようにできている」ということなのだ。
だから、「恋愛」は素晴らしいし、「宗教的回心体験」は素晴らしいし、自己開発セミナーなどでの「再生体験」なども、当人は「素晴らしい」と、そう考えずにはいられないのである。
しかし、「恋愛」が必ずしも人を幸せにするわけではないというのは、離婚する人の数を考えれば、簡単にわかるだろう。そうした人の多くは、「恋愛体験」が「一時の気の迷い」つまり「脳内快楽物質の一時的過剰分泌」でしかなかったことを悟ったはずである。
事は「宗教」も同じで、「神」を身近に感じて感動し、神の道を生きようと誓った人が、それゆえに「異教徒に対する冷酷無比な虐殺者」になるといった「無惨な現実」も、歴史上、決して珍しい話ではない。もしも彼が、本当に「神」に接していたのなら、「神」が存在していたのなら、「神」は彼にそんなことをさせるわけがない。
結局、彼は「神を見た」と勘違いをしただけなのだ。神を求めていた時に、なにかのきっかけで「脳内快楽物質が過剰分泌」され、その際の「恍惚境」を、彼は自身の願望にしたがって「神との接触体験」だと「誤解」しただけだったのである。だから、彼は、その誤解のまま、自身を「神の使徒」だと勘違いして、人間以上の力を振るうという過ちを犯すことにもなったのである。
○ ○ ○
このように見ていけば、本書に描かれた「精神療法的施術」や「その結果」が、けっして「不思議なもの」ではないというのが、ご理解いただけよう。
そしてそれが、「宗教」がかって怪しかったり素晴らしかったりするのも、故なきことではないというのがわかるはずだ。そもそも「宗教」も「恋愛体験」も、まったく不思議なものではない(物理化学的現象な)のだから、それに似ているものもまた、つまり似ていたとしても、それはまったく「不思議」でもなければ、ことさら「怪しいもの」でもないのである。
しかし、本書で描かれたような「精神療法的施術」と、「宗教」や「恋愛」には、大きな違いがある。
それは、「社会的な認知度」である。
つまり、「宗教」や「恋愛」にも、実際には、大きな「弊害」や「副作用」があるのだけれども、「宗教」や「恋愛」の場合は、人類の歴史のなかで「必要不可欠なもの」として、ほとんどの人に認知されたため、「弊害」には「しかたがない」と目を瞑るのが社会習慣化しているし、またその弊害対策を「生活の知恵」として構築してもきた。
ところが、「新興宗教」がそうであるように、「新しいもの」には、人は馴れていないので、「感動」も大きい反面、「反発」も大きくなる。派手に持て囃したかと思ったら、いきなり「悪の権化」呼ばわりしたくなったりもする。それはすべて、その「良い面」と「悪い面」に馴れておらず、「悪い面」への対処法を構築していないために、もろに「被害を被る」ことにもなるからである。
したがって、以上のような検討から私たちが学ぶべきは、「宗教」や「恋愛体験」も含めて「非日常的体験としての多幸感」には、客観的には、大した意味も価値もないし、それは「覚醒剤の作用」と、本質的には同様のものでしかない、といった「醒めた認識」である。
そういった「非日常的なもの」に過剰な価値を見いだすからこそ、人はそれを無批判に求めてしまうのだが、人間というものは、もともと「日常の中で、無難に生きていける」ように作られているのである。むしろそれこそが、「動物」として「正常」なあり方なのだ。
それなのに、頭でっかちになり、欲望に際限のなくなった「人間」という動物は、動物の「殻」を破って、それ以上のものになり、それ以上の「快楽」を得たいと望んで、動物としての安全圏から無理無闇に出ようとしてしまう。その結果、動物としての「自己破壊」を行なってしまう。
たしかに「自分の弱さ」に苦しんでいる人は多いだろうし、その苦しみから脱したいという気持ちは間違いではない。しかし、問題はその「脱出法」の安全性なのだ。いくら、いま居る場所が狭くて窮屈だといっても、断崖絶壁の奈落にむかって飛び出していくわけにはいかないのである。人間には、翼が無いのだから。
では、「人間としての苦しみ」に対し、どのように向き合うのが正しいのか。
ここで、「正解」ではないにしろ、ひとつの「ヒント」を紹介して、本稿を閉じることにしよう。
キリスト教プロテスタント、ルター派の牧師であり著名な神学者であったが、ヒトラー暗殺計画に加担して処刑された人、ディートリッヒ・ボンヘッファーの言葉である。
『 キリスト者の交わりはすべて、それが一つの理想像から出発して生きたために、何回となく崩れ去った。まさに初めてキリスト者の生活共同体に入れられた真面目なキリスト者は、しばしば、キリスト者の共同生活のあり方についての一つの極めて特定のイメージをそこへ持ちこむことがあり、またそれを実現しようと努力するだろう。しかしすべてのこのような幻想を速やかに打ち砕いて下さるのは神の恵みである。他者に対する、キリスト者一般に対する、そしてうまく行けばまた私たち自身に対する大きな幻滅が、私たちを打ちのめさなければならない。それは、神が私たちを真実なキリスト者の交わりの認識に導こうとしておられるのが確かだからである。
神は純粋の恵みから、私たちがわずか数週間であっても幻想の世界に生きることや、陶酔状態に入ったような満たされた経験、また高揚した幸福感に身をまかせることをお許しにならない。なぜなら神は、感情をかき立てる神ではなく、真理の神だから。たとえそれがどんなに不愉快でつらいことであるように見えても、そのような幻想が全く打ち砕かれることによって初めて、その交わりは神の前でのあるべき姿を取り始め、交わりに与えられた約束を信仰においてと把え始める。個人にとっても交わりにとっても、このような幻滅の時が早ければ早いほど、どちらにとってもよいことである。しかし、このような幻滅に耐えることができず、またそのことをくぐり抜けて生きることのできない交わり、したがって幻想が打ち砕かれるべき時にもなおそのような幻想の世界にとどまり続けようとする交わりは、その時から、キリスト者の交わりの確かな約束を失い、その幻想は遅かれ早かれ打ち砕かれてしまうに違いない。キリスト者の交わりの中に持ち込まれるすべてのこのような人間的理想像は、真正の交わりを阻害するものであり、したがって真正の交わりが存続しうるためには、そのような理想像は打ち砕かれなければならない。キリスト者の交わりそれ自身よりも、キリスト者の交わりについての自分の夢を愛する者は、たとえ個人的には正直で、真面目で、犠牲的な気持で交わりのことを考えたとしても、〔結局は〕すべてのキリスト者の交わりの破壊者となるのだ。
神は夢想(トロイメライ)を忌み嫌われる。なぜなら、夢想は人を高慢にし、要求ばかりする人にするからである。一つの交わりのイメージを夢想する者は、その実現を、神に、他者に、そして自分自身に求める。彼は要求する者としてキリスト者の交わりに入ってきて、自分自身の律法をつくり、それによって兄弟と神ご自身とを裁く。彼は、兄弟の群れの中で、他のすべての人たちに対してきびしい叱責者のように冷然と立つ。彼は、あたかも自分がキリスト者の交わりを造り出す者であるかのように、自分の幻想的イメージが人々を結び合わせるかのように行動する。自分の思い通りにならないときに、彼はそれを〈失敗〉と呼ぶ。』(『共に生きる生活』P26〜28)
『 そのように「人間的(ゼーリッシュ)な」回心が存在する。ひとりの人間の圧倒的な力の意識的あるいは無意識的な誤用によって、個人あるいは全体の交わりが最も深いところまで揺り動かされ、その呪縛の中へと引き入れられるところでは、それは真正の回心と少しも違わない現象形態をもって現われる。そこでは人間がほかの人間に直接的に働きかける。強い者が弱い者を圧倒する。弱い者たちの抵抗は他方の人間の影響の下に打ち砕かれる。弱い者は力でねじ伏せられるのであって、事柄そのものによって心から従うようにされるのではない。私が、自分を束縛している人物から独立し、あるいはおそらくその人物に対抗し、なさねばならない事柄に自分を関わらせることが求められる瞬間に、そのことは明らかとなる。そこでは人間的な回心を経験した人は挫折し、そのことによって、彼の回心は聖霊によるもの(※ 本物の回心)ではなく、ある人間の働きかけによって起こったことであり、したがって何ら持続性のないことが明らかとなる。』(前同 P36〜37)
初出:2020年5月13日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
