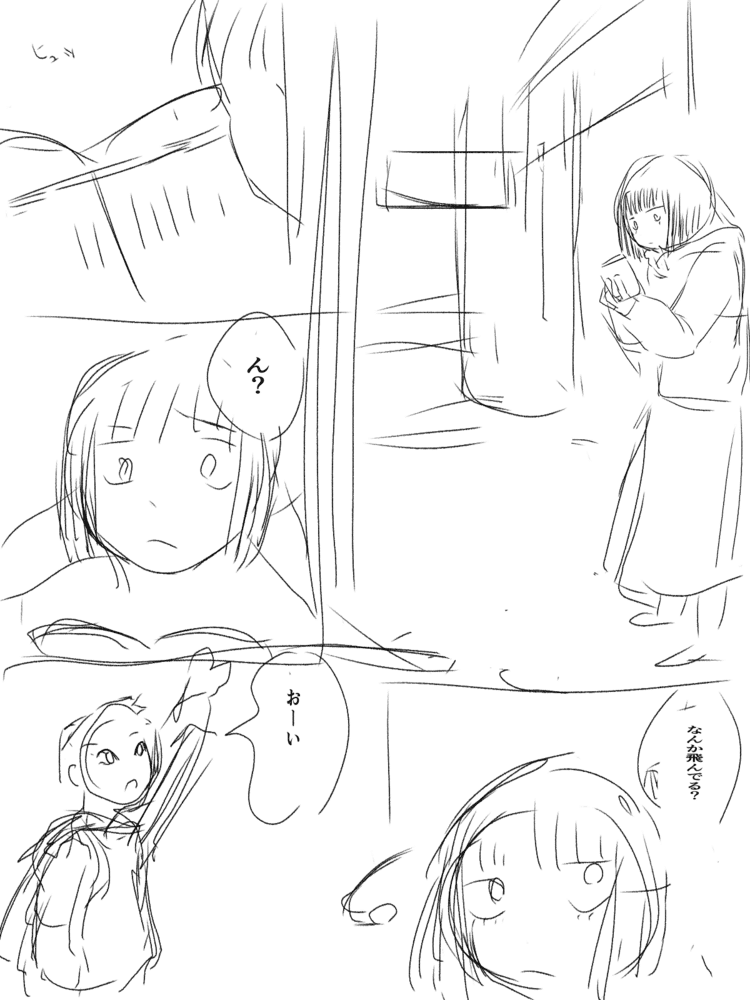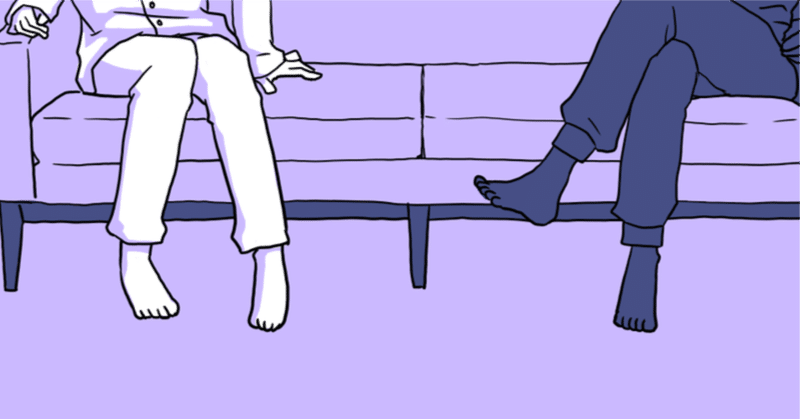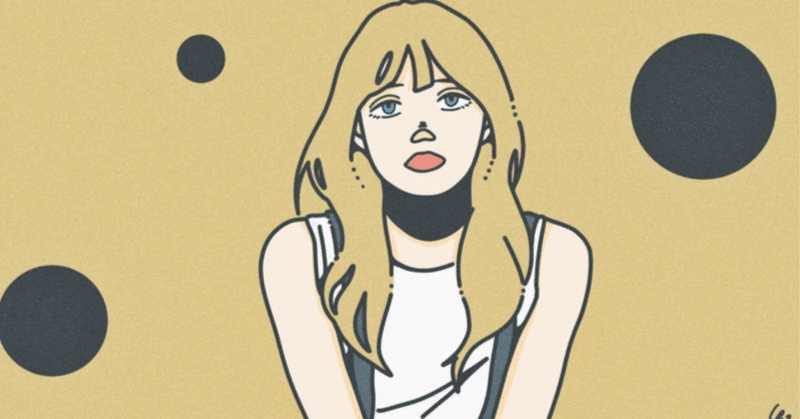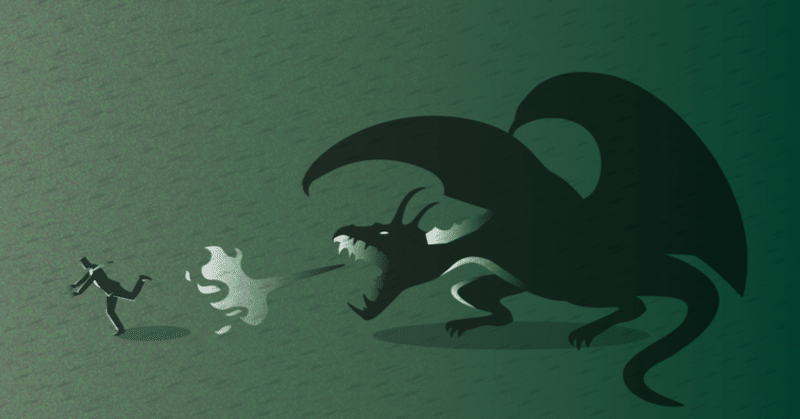記事一覧
ロックンロールと素晴らしき世界(仮) No.1
ロックンロール
ロックンロールが死んだ。
その知らせは一瞬にして街中に広まった。
この表現は正確ではない。正確にいこう。
それは水面の波紋のように広まったのではない。そういう同心円的に、中心から周縁に向かって広まっていくようなものではなかった。そういう広がり方ではなく、あらゆる人、あらゆる存在が、その死をその瞬間に知ったのだ。その瞬間。まさにその瞬間。それはある種の啓示のようなものに近
たったひとつの正しさ
朝の洗面所、鏡の前で弟が妙な動きをしていた。鏡と横向きに立ち、じっと動かず、横目で鏡の中の自分の姿を見ている。わたしはなにも言わず、しばらくそれを観察していた。まだ動かない。いったいなにをしているのか。わたしは少しイライラしはじめていた。なにしろ朝の忙しない時刻だ。わたしも洗面台を使いたい。声をかけようとした瞬間、弟は素早く顔を鏡の方に向けた。そして、自分のことをじっと見ている。
「なにしてんの
プロフェッショナルの夜
彼はプロ野球選手だ。野球をやって糊口をしのいでいる。プロフェッショナル。しかしながら、それはもうじき「だった」になるかもしれない。彼はプロ野球選手だった。過去形。いまは違う。そうなるかもしれない。
そもそものはじまりからして、どうにかこうにかその位置を掴んだのが彼だった。いくつかの球団のテストを受け、どうにかトレーニングキャンプに招待されるが、正式な契約にはいたらない。そんなことが何度か繰り返
賢い竜たちのした選択
かつて、地上は賢い竜たちのものだった。彼らはほんの数頭しかいなかったのだけれど、彼らは巨大で、屈強で、軽々と空高くを飛んだし、日の光の届かないような海の深くまで潜ることもできた。あまつさえ、炎を吐くことまでするのだ。他のどんな生き物たちが束になってかかっても絶対に敵わない。そんな存在である賢い竜たちを、他の生き物たちは畏怖の眼差しで見たものだった。虫も、魚も、鳥も、犬も猫も。そして、もちろん人間
もっとみる