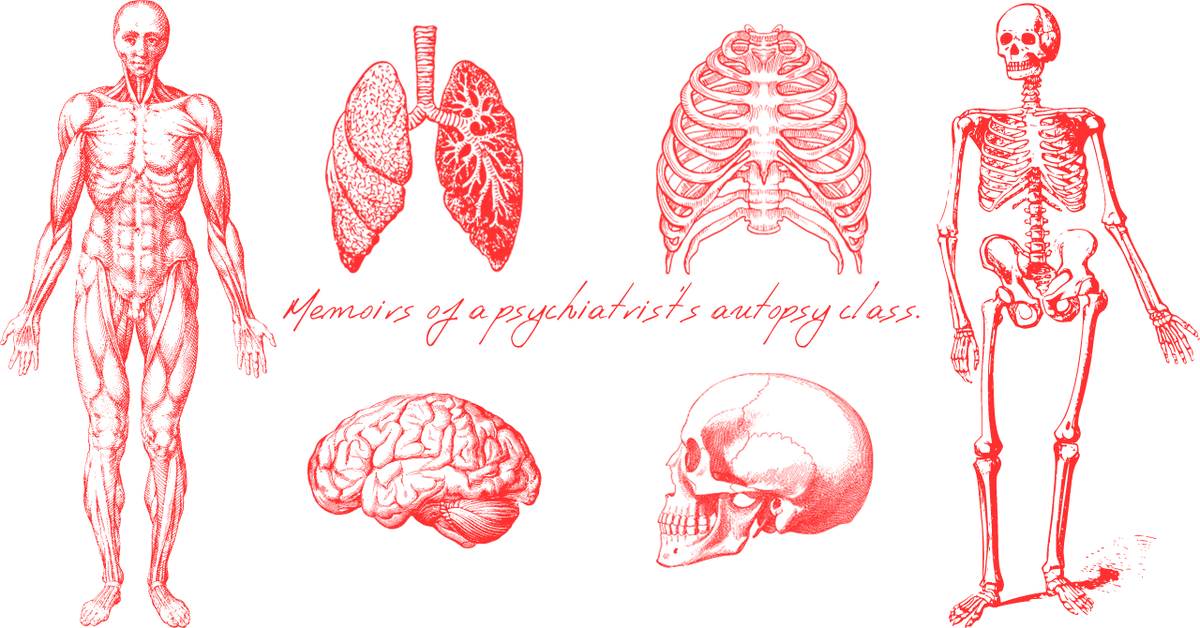
精神科医、解剖実習を思い出す(後編)
<前編のあらすじ>
娘の率直なリアクションが引き金となり、精神科医は走馬灯のごとく学生時代の解剖実習を思い出した。
“遺体の解剖"という体験は衝撃的であったが、存外早々に解剖に慣れ始める。
しかし予習をしてこなかった鹿冶は、迂闊にもご献体の腕神経叢を切り裂いてしまった…。
【鹿冶梟介、麻痺する】
“腕神経叢事件”の後、鹿冶梟介もBも予習して解剖実習に臨む様になった。
教員から怒られたこともあるが、それ以上にご献体に対してとても申し訳ないと感じたからだ。
「解剖実習の手引き」を前日読み込むことで解剖もスムーズに行うことができ、口頭試問で狼狽えることも無くなった。
何よりもこうやって人体について深く学ぶことこそがご献体への供養になるということが今更ながら分かったのだ。
…とはいうものの、解剖も佳境に入ると重労働になる。
特に骨盤内の臓器摘出、双鋸による脊柱管の露出、鋸とノミによる頭蓋冠の開放…といった行為は、”解剖”というよりは”解体”という言葉がふさわしく、多大な労力を要する作業であった。
季節は梅雨。
解剖室内は冷房が効いていたが換気のために窓は開けられ、湿気をたっぷりと吸った外気が嘲笑うかのように解剖室の不快指数を跳ね上げる。
加えて献体から漂うホルマリン・フェノール臭は、医学生たちの思考力をたやすく奪っていく。
『人間を解体し、それをひとつひとつ具に観察する』
解剖室という場でなければ、これは人倫にもとる禁忌である。
おそらく疲労・高温多湿・刺激臭という過酷な環境こそが、医学生たちの背徳感を麻痺させるのに必要な条件であったのだろう。
当初は白衣、エプロン、ゴーグル、マスク、ゴム手袋のフル装備で実習に臨んでいた学生たちも、そのうちエプロンやゴーグルを外し、中には素手で臓器に触る学生もいた。
以前は実習の合間にとる昼食は軽く済ましていたが、この頃にはホルマリンの匂いが染みついた服を着たままでもたらふく喫食できるようになっていた。
しかし、思い返すと学食で同席していた他の学生達はどう思っていたのだろう…。
「変な匂いがする集団」を訝しがり、席を遠ざけることはなかったのであろうか。
そんな気遣いを忘れるほど、当時の鹿冶梟介は麻痺していたと思う。
【精神科医、覚えていない】
その日の実習は「頭部」の解剖であった。
「前編」で宣言した通り、精神科医は脳の摘出担当となったため頭部の解剖を任された。
頭部の解剖のためにはまず頭部を切り出す。
平たくいえば”生首"をこしらえる必要がある。
頭部の切断の手順は、まずノミで第一頚椎(環椎)と上位頚椎の椎弓を切り、脊髄硬膜を露出させる。
そしてこの脊髄硬膜を第三頚椎の高さまで切り開くと脊髄が現れるので、この脊髄の第1-3頸神経の”根”を切り、脊髄を取り出す。
頸部周辺の組織(筋肉、靭帯など)を観察したのち、環椎のすぐ下で歯尖靭帯と翼状靭帯を切断すれば、頭部が頸部組織と環椎をつけたまま完全に軸椎からはずれる。
このように頭部を切り出すという作業は思いの外難儀であり、生首が出来上がった時にはある種の達成感があった。
頭部に巻いてあった包帯も一連の作業中いつの間にか解かれていた。
不思議と思われるかも知れないが、精神科医は献体のご尊顔をあまり覚えていない。
そして、はじめてその顔を拝した時に何かしらの感慨が生じたか否かも定かではない。
解剖実習が始まった頃は"包帯で覆われた顔"をとても意識していたはずだが、頭部の解剖をはじめる段になると顔を顔として認識しなくなったようであった。
人間は通常、人を人として認識する際に「顔」の情報を重視する。
しかし、解剖という背徳を受け入れるためには、「顔を認識する」という機能は妨げとなる。
"ゲシュタルト崩壊*"という知覚現象があるが、これに類似した現象が頭部解剖時には起こり、そのお陰で自分は正気を保ていたのでは…。
精神科医はご献体の顔を思い出せないことについて、そんな風に解釈している。
*ゲシュタルト崩壊: 全体性を持ったまとまりのある構造(Gestalt: 形態)から全体性が失われ、個々の構成成分にバラバラに切り離して認識し直される現象。ゲシュタルトとは、例えるなら星空を眺めた場合"星座"を知っていれ1つのまとまりとして星座を認識しますが、星座を知らなければランダムに並んだ星空にしか見えないようなこと。
【鹿冶梟介、安堵する】
実習も終盤に差し掛かかるころの話である。
「なぁ、みんな。こんな噂を知っているか?」
Bが頭部の解剖をしながら皆に聞いた。
"またBの与太話か?”と皆が軽く流していると、
「解剖実習がきっかけで、退学になったヤツがいたらしいね」
その言葉を聞き、皆の手が止まった。
「あっ、俺もその話はちょっと聞いたことある。●●大学の話でしょ?」
普段寡黙なEが話に乗ってきた。
「えっ?何、何?」
この手の話には乗ってこないAも興味津々の様子。
「そうそう!先輩から聞いた話だけど●●大学でさ、解剖実習中に献体の耳を切断して、それを壁にひっつけて”壁に耳あり”っていうギャグをかましたヤツがいたそうだよ。そんで、タイミング悪くその場面を教員が目撃して退学になったってさ」
「マジか…(一同)」
皆が騒然とした中で、Dだけ無言だった。
Dは検体から切り取った耳介を手にしてじっと見つめていた。
「これを壁にくっつけたら、僕は退学になるのですね… 」
マスクをしていたので表情はよくわからないが、Dは死んだ魚のような目をしていた。
「Dさん、大丈夫ですか?」
Aが思わず声をかける。
Dは2年留年した学生でAの部活の先輩でもあったことから、皆から「さん」付で呼ばれていた。
じっと手にした耳介を見つめるDがどのような行動をとるのか…、医学生たちは固唾を呑んで見守っていた。
すると…、
「鹿冶君、もう観察し終わったから次は君が見なよ」
Dはやおら耳介を鹿冶に手渡し、すぐに次の作業に入った。
「あ...、は、はい!」
鹿冶だけなく、他の医学生たちも安堵の表情を浮かべた。
【精神科医、”キモい"と言われたことを思い出す】
記事作成のために、書籍や論文を購入しております。 これからもより良い記事を執筆するために、サポート頂ければ幸いです☺️

