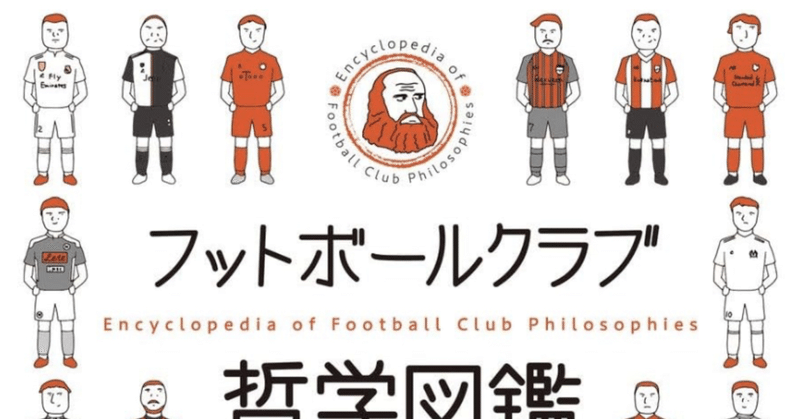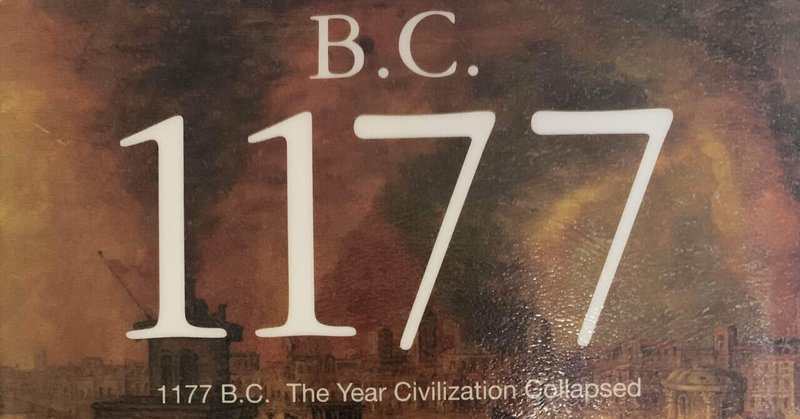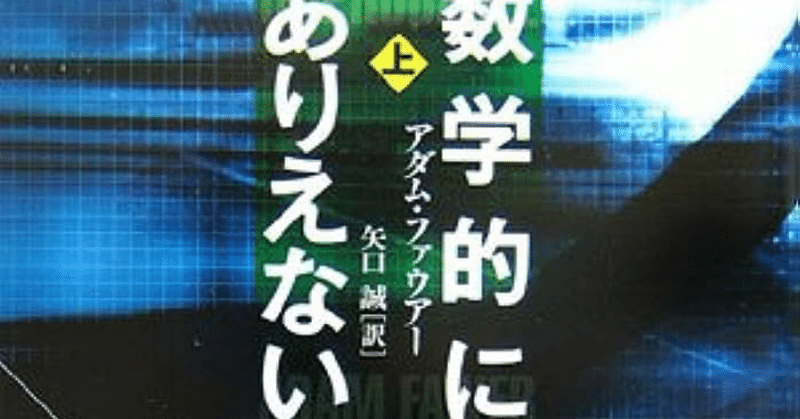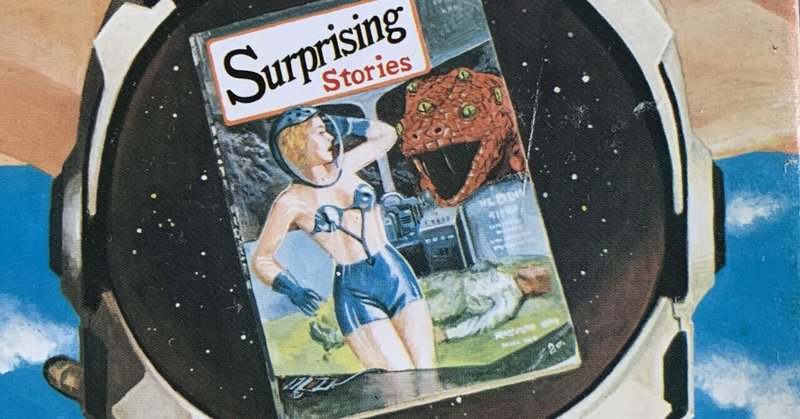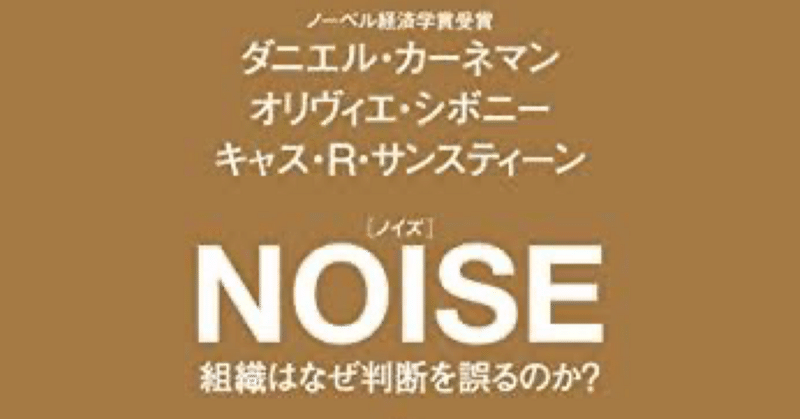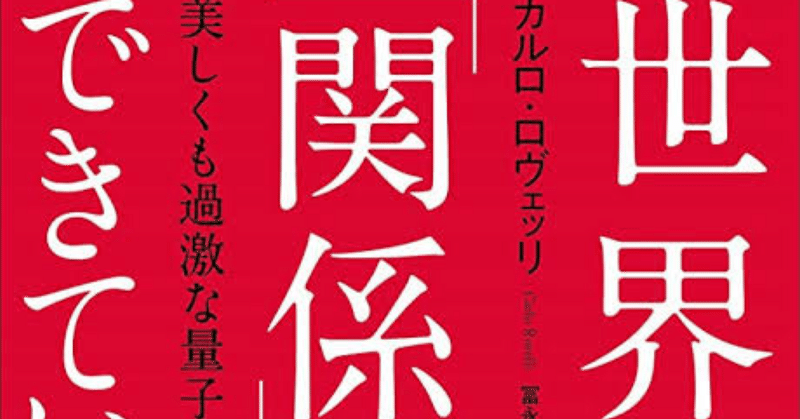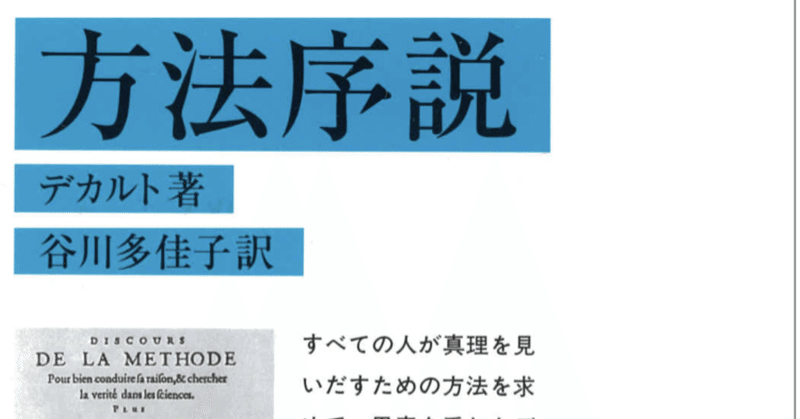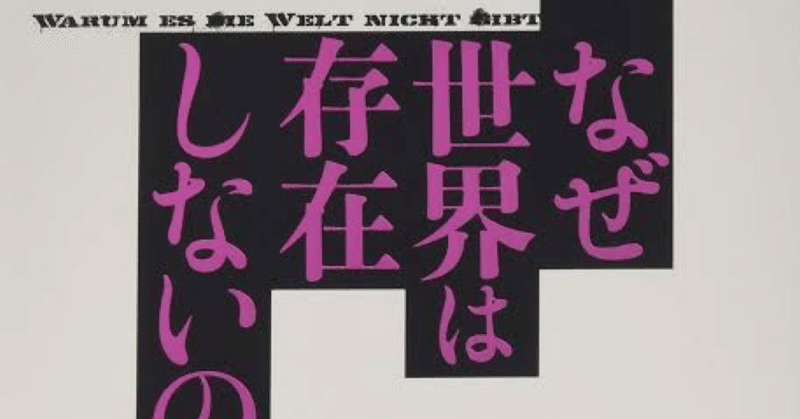記事一覧
最近読んで面白かった本。『フットボールクラブ哲学図鑑』他。
フットボールクラブ哲学図鑑/西部謙司有名クラブの哲学を歴史と絡めて紹介する本だ。
中でもレアル・マドリード、バルセロナ、リヴァプールが面白かった。
レアル・マドリードの哲学は「強い奴を集めてとにかく勝つ」。
戦術どうこうじゃなく、個の強さで圧倒していくスタイルらしい。あまりにも王者すぎて笑ってしまった。
そんなレアル・マドリードは「ときに理由なく勝ち、今も勝ち続けている」のだそう。かっこよすぎる
3000年前、彼らはなぜ滅亡したのか?『B.C.1177』の感想。
普段は歴史系の本は、しかもこんなガチそうなやつは読まないけど、安原和見が訳しているので読んだ。
「紀元前12世紀、およそ2000年間も繁栄した青銅器時代文明が、どこからともなくやってきた「海の民」という謎の集団によって滅ぼされた。」と、長らくそう言われてきた。
おいおい、なんなんだこのワクワクする通説は。
そんな海の民説は本書の中で否定されることになるんだけど、海の民のことすら知らない、つまり
最近読んで面白かった本。『数学的にありえない』
ハリウッドのノンストップアクション映画みたいな話だった。
最終的に主人公はスーパーヒーロー化するし、オプションでなんか可哀想な生い立ちを持った強い美女も付いてくるしね。
気になる点が多少あるけど、それなりに面白かった。
『数学的にありえない』とかいう大仰な邦題だけど、数学が破綻した世界の話というわけではない。ありえないくらい低確率の事象が起きてます、くらいの意味。
雑なあらすじ。統計学講師でポ
海外ファンタジー小説Tierリスト!
小さい頃に読んだ海外ファンタジー小説を、好きな順にランク付けしました。
これは暫定的なもので、入れ替えたり、思い出したら追加したりしていきます。(読んだ時期が時期なので、内容は覚えてるのに題名を思い出せない本がかなり多い)
計30作(同一シリーズは1作にカウント)
ファンタジーTierS
ダークホルムの闇の君/グリフィンの年
ハリーポッター
パーシージャクソンとオリンポスの神々
バーティミアス
『発狂した宇宙』(フレドリック・ブラウン)の感想。
以前、安原和見が訳したフレドリック・ブラウンSF短編全集を読んで、めちゃめちゃ面白かったので、長編の方も読んでみた。こっちも面白かった。
原題は"What Mad Universe"
内容からすると、『発狂した宇宙』って訳は間違ってるんだけど、それでも発狂なんて単語にはワクワクさせられるし、これはこれであり。というか凄くいいタイトルだと思う。
内容はシンプルで、ひょんなことからスペースオペラ的
最近読んで面白かった本。『NOISE:組織はなぜ判断を誤るのか?』他
NOISE、キドナプキディング、数学ガール
ネタバレがあります。
NOISE:組織はなぜ判断を誤るのか?上下面白かった。判断を間違える原因として、バイアスだけではなく、ノイズにも注目しなきゃだよね、って本。
上巻では
・ノイズとは何か
・ノイズはどんな種類に分けられるか
・ノイズは何故発生、増大するのか
といった内容が語られる。
上巻の結論を死ぬほど雑に要約すると「人間ってクソ、アルゴリズム様
最近読んで面白かった本。『世界は「関係」でできている』他。
世界は「関係」でできている、アポロンと5つの神託、物語とふしぎ
・世界は「関係」でできているループ量子重力理論の提唱者、カルロ・ロヴェッリによる量子論の本。
最近読んだ本の中でダントツで一番面白かった!
面白すぎる本を読んでいると、読むスピードに感情の処理が追いつかなくなってしまい、思わず本を閉じて、気持ちが落ち着くまで待つことがある。
小説以外の本を読んでいるときにそんな風になるのは稀なんだ
最近読んで面白かった本。『なぜ世界は存在しないのか』マルクス・ガブリエル
世界で最も注目を浴びる天才だとか言われているドイツの哲学者、マルクスガブリエルの『なぜ世界は存在しないのか』を読んだ。
「世界は存在しない」だなんて、ずいぶん大きく出たな、という感じのタイトルだ。しかし読んでみたら「それなら確かに世界は存在しないね」と思えた。(それなら、というのが肝だ)
世界、存在しないんだってよ。ガブリエルは本書の中で「意味の場の存在論」というものを提唱していて、そこから世
最近読んで面白かった本。「ウィトゲンシュタイン入門」他。
最近読んで面白かった本を挙げていく。
ウィトゲンシュタイン入門ずーっと気になってたのをやっと読んだ。
ウィトゲンシュタインの哲学は語れるものと語りえないものとを切り分けるのを目的として、論理→文法→言語ゲームという変遷を辿っている。
後期の言語ゲームにおいては、もはや語りえないものについての言及はないんだけど、それは語りえないものが本当に語りえなくなったという意味であって……っていう終盤の展開が
『フーコー入門』の読書メモ
面白かった。各章でフーコーの著作を時系列順に解説して、更に各論がフーコーの中でどんなふうに一貫性を持っていたのかも教えてくれる。
特に2章と3章の前半は歴史の授業みたいで楽しい。
しかし3章の後半では論敵への再反論としてギチギチな論理武装が始まってかなりつまらなかった。
4章は規律権力やそのモデルとしてのパノプティコンだとかのTHE・フーコーって感じ。
5章と6章で生権力の話が出て来て、7章と終
『人体、なんでそうなった?』の読書メモ
『人体、なんでそうなった?』(2019、ネイサン・レンツ=著、久保美代子=訳)を読みながらとったメモ。
人体のもついろんな欠陥をカタログ的に紹介する本。まず大雑把な感想として、面白かった。
1番みんなが読むであろう1章で、1番キャッチーな形質的な欠陥を紹介していて上手いなと思った。
1,2,3,4章とエピローグが好き。中でも3章の、鎌状赤血球症とハンチントン病についての箇所が特に印象的だった。
「ファンタジーの秘密」の読書メモ。
ファンタジーの秘密/脇明子を読みながらとったメモ。
はじめにどういう本なのか?
著者はファンタジーの根幹の条件には不思議さの気配が必要と考えている。
その不思議さの気配とはなんなのかを定義するのが今作の狙い。
不思議さの気配とかいうあやふやなものが、読み手側の感想ではなく、作品の内に客観的に存在していることを示そうということ
1章 魔法の復活魔法には語りの能率化と視覚化のはたらきがある。登場人
最近読んで面白かった本。「ファンタジーの秘密」他。
最近読んで面白かった本を挙げていく。
・ファンタジーの秘密/脇明子
不思議の国のアリス/鏡の国のアリスを翻訳してきた著者の、ファンタジーについてのいろいろな考察。
著者はファンタジーの根幹の条件には不思議さの気配が必要と考えている。
その不思議さの気配とはなんなのかを定義するのが今作の狙い。
不思議さの気配とかいうあやふやなものが、読み手側の感想ではなく、作品の内に客観的に存在していることを示