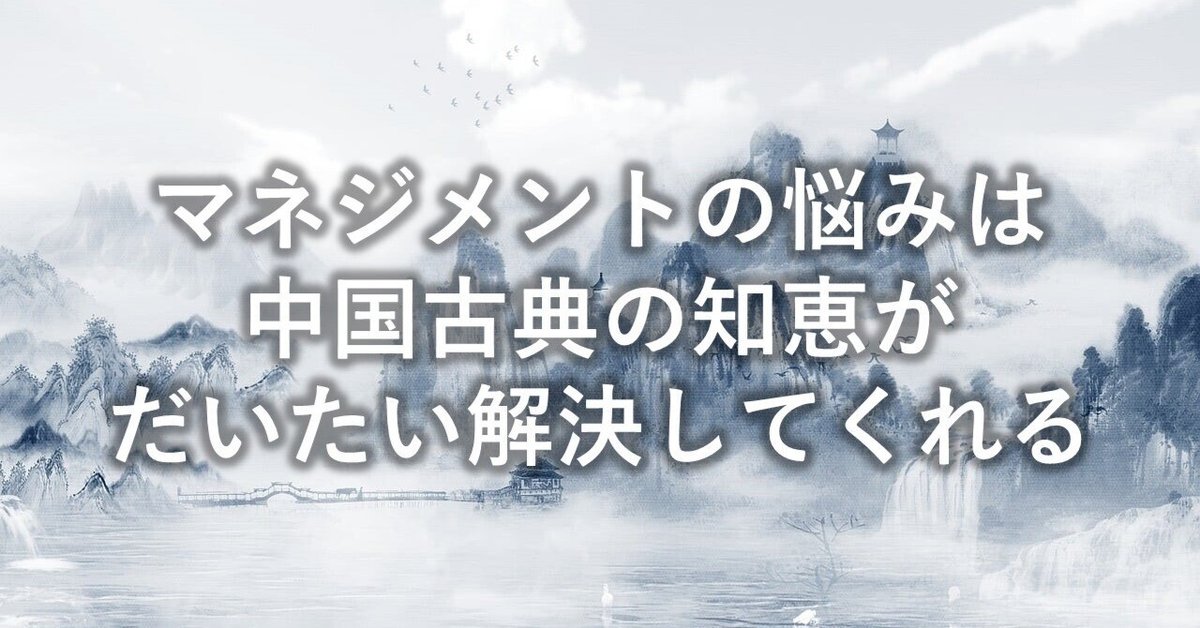
マネジメントの悩みは中国古典の知恵がだいたい解決してくれる
中国古典は、多くの方々に歴史書としてのイメージを抱かれることが多いですが、実はその本質はもっと普遍的で、現実において非常に役に立つ知恵の宝庫といえる存在です。
先日行ったセミナーでも、論語と韓非子の比較を通じて、組織運営に役立つ"目線“をお話させて頂きましたが、参加された方それぞれが気づきを得て頂けたように思います。
中国古典との向き合い方
中国古典は難解な書き下し文の解釈にとらわれてしまう場合がありますが、一つひとつの言葉が全体の中でどのような位置づけで語られ、個々の事象に対してどんな考えを以て語られているのかを感じ取り、また時代やその国の状況などにも思いをはせてみるとすうっと頭と腹に落ちてくるような気がします。
何も学者や研究職でもないのですから、ありがたいと思われる言葉を暗記するような勢いで読んでいるとその膨大な量にうんざりしてしまいますし、覚えられるはずもありません。かくいう私も諳んじられる故事成語などごく僅かに過ぎません。
それよりも、現代の世の中でとりわけ仕事や人生においてどう役立てるのかをじっくり考える時間にあてることの方が有益だと思います。

古いものでは2500年以上前に書かれたものもある中国古典がなぜ今もなお読み継がれているのか。それは人の営みや人の本質に対する深い洞察を通じて不変の原理原則が語られていて、人を魅了してやまないからではないでしょうか。
中国古典は人生におけるあらゆる課題や悩み、不安を取り上げ、かつその答えを示しているといっても言い過ぎではないので、中国古典に親しむことで、現代の私たちが直面するビジネス上の課題やリーダーシップ、さらには人生そのものに対する答えを見つけることができると思います。
イントロがだいぶ長くなってしまいましたが、今回は、中国古典の根幹にある本質的なテーマを軸に、悩みや課題に対してどんな中国古典が役に立ちそうかを解説していきます。
中国古典の本質
1.経世済民/社会や組織を動かす知恵
「経世済民」とは、社会を正しく治め、民を豊かにすることを意味します。『論語』や『孟子』をはじめとする古典は、単に思想や道徳を説くものではなく、実際に社会を運営するための指針を示しています。
例えば孔子の言葉にある「仁」を基盤としたリーダーシップは、現代の企業運営にも通じるものがあります。単なる利益追求だけでなく、社員や顧客、そして社会全体を豊かにする視点が長期的な成功に繋がるという教えです。
現代において、企業や組織は社会の一部としての責任を負っています。中国古典から学べるのは、短期的な利益を追求するのではなく、持続可能で調和の取れた成長を目指す視点です。これはCSR(企業の社会的責任)やサステナビリティを重視する現代のビジネスにも深く関わる考え方です。
2.応対辞令/人間関係を円滑にする技術
次に、「応対辞令」は人と人との関わり、つまりコミュニケーションの技術を示します。中国古典は、単なる理論的な哲学にとどまらず、日常生活や仕事においての具体的な対人スキルも教えてくれています。
例えば『論語』には「忠恕(ちゅうじょ)」という言葉があります。これは、相手の立場に立って物事を考え、誠意を持って応対するという意味です。このような考え方は、現代のリーダーシップや人間関係の構築においても重要です。
現代社会はコミュニケーションが複雑化していて、リーダーが組織の中で信頼を築くためには、感情や状況に応じて柔軟に対応するスキルが求められますが、中国古典はどのように相手と接し、どのタイミングでどのような言葉を選ぶべきかについても実践的なアドバイスを提供してくれます。
3.修己治人/自己修養から始まるリーダーシップ
「修己治人」とは、まず自分自身を修め、それから人を治めるという意味で、もっと平穏な表現を用いるなら人間的成長を図るということです。
『大学』では、「修身斉家治国平天下」という言葉がありますが、これはまず個人が自身を高め、次に家庭を整え、最終的に国家を治めるという順序を説いています。現代においても、リーダーが他者を導くためには、まず自分自身の成長が不可欠です。
この「修己」の部分は、単なる自己啓発にとどまらず、倫理観や人格の成長を含む広範な意味を持ち、自己管理、自己反省、そして自分の行動に対する責任を持つことが、真のリーダーシップの基盤となります。これは、現代のリーダーシップ論の基本的な心得に相当する部分といえます。
一方で、「治人」の部分は、リーダーがどうチームや組織を統率し、社会をより良い方向に導くかというテーマです。リーダーシップにおいては、自己修養が欠けていれば、どれだけ優れた戦略やスキルを持っていても信頼は得られません。中国古典は、個人の内面的な成長と他者への影響力が一体となって機能することを教えてくれます。
4.実学としての知恵
中国古典の最大の魅力は、その普遍性と実学としての実用性です。時代を超えて生き続ける知恵は、私たちの生活や仕事に直接役立ちます。中国古典が説く教えは、単なる理想論ではなく、現実の社会やビジネスに応用できる具体的な手法や態度を示してくれています。
経世済民、応対辞令、修己治人といった基本的な概念を通じて、リーダーシップ、戦略、人生哲学など、さまざまな分野で古典の教えは今もなお輝きを放っていると思います。
現代は変化の激しい時代ですが、こうした古典の知恵を取り入れることで、時代や環境に左右されない揺るがない自分にとっての軸を持つことができ、古典の知恵を借りて、目の前の課題にどう取り組むかという視点を持つことが、成長や成功への大きなヒントとなると言えます。
*
後半は中国古典の中から、特に実生活やビジネスに役立つ書物を分野ごとに紹介し、その魅力と実学としての活かし方についてお伝えしてみたいと思います。
実学として役立つ中国古典セレクション
1. 理想的な人生を歩むための指針
まず、人生における目標や生き方について考えるとき、中国古典は数多くの指針を提供してくれます。以下に紹介する書物は、個々の価値観や人間性を高めるためのヒントが満載です。

『論語』
孔子の教えをまとめた論語は、道徳的な生き方や人間関係の調和について学ぶことができます。人としてどうあるべきか、リーダーとしてどう振る舞うべきかについて組織論としても深い洞察を与えてくれます。
『老子』
老子の道教の思想は、自然と調和しながら、無理なく生きることの大切さを説きます。競争社会においても、自分らしく柔軟に対応するしなやかな生き方を学べます。なお、老子は道徳だけではなく、物事を成し遂げるための謀略術もあわせて説いている点は押さえておきたいポイントです。
『荘子』
荘子の思想は、老子と合わせて老荘思想と言われ、同じく道教の教えに基づき物事にこだわらず、自然体で生きる重要性を教えます。人生における心の自由や、外部の評価に縛られない生き方を追求する上での指針となります。
『菜根譚』
明代末期の思想家である洪自誠が書いたこの書物は、逆境を乗り越え、困難な中でも心の安定を保つための知恵が詰まっています。困難に直面したときにこそ真価を発揮する教えが得られます。
2. 組織戦略の指針:成功を導く戦略
ビジネスや組織運営において、戦略的な思考は不可欠です。特に中国古典の兵法書は、現代の競争環境においても応用できる貴重な洞察を提供してくれます。

『孫子の兵法』
戦略の基本書として名高い『孫子』は、状況分析と準備の重要性を強調しています。「負けない戦の仕方」、「己を知り、相手を知る」という孫子の有名な教えは、現代のビジネス戦略でも非常に重要です。
『韓非子』
法家思想を説いた韓非は、組織の秩序や規律を重視し、法や制度による統治の重要性を説いています。管理や運営の厳しさと公平性について学ぶことができます。
『六韜三略』
六韜と三略は、戦略と統治においてリーダーがいかにして大局を見据え、長期的な視野を持つべきかを教えてくれる兵法書です。戦略の大枠と具体的な戦術を総合的に学ぶことができます。
『李衛公問対』
唐代の名将李靖による兵法書で、適切な戦略の立て方や資源の効率的な配分を学ぶことができます。貞観政要でお馴染みの李世民が配下の将軍と兵法について議論しています。ビジネスやプロジェクト運営における効果的なリソースマネジメントのヒントが得られます。
3. リーダーシップの指針:信頼されるリーダーになる
リーダーとしてどうあるべきかは、古典に多くの教訓が含まれています。信頼と戦略を持ったリーダーシップを発揮するための書物として、次のものを紹介します。

『貞観政要』
唐の太宗、李世民の治世に基づくこの書物は、リーダーとしての人間性、部下との信頼関係の築き方について深く掘り下げています。特に長期的な視野を持ったリーダーシップを学ぶ上で必見です。
『三国志』
三国時代の英雄たちが示すリーダーシップのスタイルは、現代にも通じるものがあります。劉備の仁徳、諸葛亮の知恵、曹操の冷徹な判断力、孫権の人材登用など、さまざまなリーダーのタイプを通じて、自分に合ったリーダーシップスタイルを見つけることができると思います。
『諸葛亮集』
諸葛孔明の言行や政策、戦略、軍事に関する文書を集めたもので、彼の統治哲学や軍事戦略、トップや組織に対するコミットメント、法と道徳のバランスを重んじる姿勢が描かれ、戦略家としての知恵や国家運営におけるリーダーシップとフォロワーシップが強調されています。
4. 交渉、権謀術:逆境での生存戦略
ビジネスや人間関係において、時には厳しい状況や逆境に直面することがあります。そんな時に、戦略的に乗り越えるための知恵を学ぶのに役立つのが、ダークサイドスキルとも言える交渉、権謀術といった教えです。
主に諸子百家の一つで、縦横家と呼ばれる弁舌と野望をもって戦国時代の各国為政者にとりいった政略家、策士たちの知恵を集めた書書で、交渉や駆け引き、外交的な策略に優れた考え方を学ぶことができます。対人関係の複雑さに直面した際に参考になる内容です。

『鬼谷子』
縦横家の祖とされる鬼谷子の教えは、高度な交渉術により敵を欺き、策を練る知恵が詰まっています。競争が激しい環境で、勝つために必要な戦術や生存戦略を身につけるための洞察を提供します。
『兵法三十六計』
兵法三十六計は、困難な状況を乗り越えるための36の計略を説いています。ビジネスでも、逆境に陥った時に使える柔軟な戦術を学ぶことができます。コカ・コーラとペプシの覇権争い、マイクロソフトのビジネスモデルなど現代ビジネスの解説にも用いられ、各計略を身につけることで大局観が養われると思います。
『戦国策』
戦国時代の各国の策謀をまとめた『戦国策』は、外交や駆け引きの重要性を教えます。競争が激しい環境でのサバイバル術として、現代のビジネス交渉にも応用できる策略が詰まっています。
最後に
繰り返しになりますが、中国古典は、単なる歴史書ではなく、現代の私たちにも実際に役立つ多くの知恵を提供してくれます。
一方で、「歴史書なんて今の世の中では役に立たない」といったご意見をたまに聞く機会もあります。
例えば、ネットがデフォルトの時代に孫子でいうところの用間(スパイ活動)や離間(仲間割れをさせる工作)など馬鹿々々しいといった声ですが、中国やロシアなどが行っている外交戦術などはまさに孫子そのままの考え方という現実をあまりよくご存知ない方のご意見だと思います。
生活環境がどれだけ変化しようとも、人間の本質は変わらないのですから、2500年以上前に答えが出ていることを知らないままいるというのは機会の損失と言えます。
人生の指針、リーダーシップ、組織運営、さらには逆境を乗り越えるためのダークサイドスキルに至るまで、あらゆる面で中国古典は実用的な教訓を提供してくれます。
ご存知の方も多いと思いますが、ハーバードをはじめとするビジネススクールでは随分前から東洋哲学の学びを導入し、それが人気を博しています。ロジックに依存した思考が現代の複雑化した環境、特に対人関係に対応できないため、東洋的な学問を取り入れようという背景があるそうです。
*
私自身は現在52歳で、中国古典との出会いは20代後半でした。それまでは自分の人生について真剣に考えたこともなく、仕事においても自分が正しいと思うことをしていれば自ずと成果がついてくる、その程度の仕事観でした。
最初は定番の三国志の小説、次いで孫子や論語などを読むようになりました。以来、そんな書物もあるのかと芋づる式に中国古典のカテゴリーに入るものは貪るように読み耽って今に至るという感じです。(ちなみに韓非子が一番好きです。)
特に、悩んだ時や怒りがこみ上げてくるような心境の時に中国古典を読むと、頭が整理され、気持ちがスッキリするというのが私なりの感想です。そして、その甲斐あってか、仕事では成果を出し続ける人になり、会社員としては上位6%くらいの年収をもらい続けるような会社員人生を過ごすことができました。
その後、起業して逆境もたくさん経験しましたが、やはりそういう時にこそ中国古典が支えとなりましたし、これからも何度も乗り越えないといけない壁はあると思いますが、間違いなく中国古典の知恵を読み返すことになるはずです。
中国古典は役に立つことしか書いてないですし、自らの生き方やビジネスにおける戦略を見つめ直すことができると思いますので、今まで縁がなくてなんとなく手に取る機会がなかったという方には本当にお勧めしたいです。
数ある古典の中から個人的な好みで選書しましたが、何を読んでもきっと大きな気づきがあるはずです。ご自身の目下の課題に合わせて、ちょっと読んでみようかなと思う人が増えたら嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
中国古典を扱ったマガジンもありますので、お時間ある時に読んでくれると
嬉しいです。
