
References in AY2022
以下資料について、経緯は2022年度の概要へ。
ーーーーー
帰国子女受け入れ校である元所属(高校基督教大学高等学校、通称ICU高校、ICUハイ、ICUHS)や「人権」や「多様性」を謳っているはずの国際基督教大学(通称ICU)法人における感染対策にかかるパワハラ追い出しとハラスメント対策の機能不全について全体的なことはFrom middle of nowhereへ。
ーーーーー
・呼び出し①(9/10)翌日 科主任へ 9/11

不可能な事態に状況が掴めないので必要な情報を教えたものの無視されたので、限られたリソースの中で想定できるものをまとめて提出した。

普通の1条校(カリキュラム、教員共に)でしかないのに来ても大丈夫だと広報して呼び込むだけ呼び込み、サポートをしない。学習言語の習得には時間がかかるのに、語学の科目は1年次に置かず、現代文も当時3単位→現行2単位しか無い上に「日本語」の視点を持たない(日本語教員養成を経ていない)「国語科」の教員が「国語」を行うのみ。それでどれだけのことがなしうるのか。

「国語」は教員生徒共に母語で行う教科であり、教員養成に「外国語教育」の視点は全く入らない。免許のある教科であれば「英語」のほうがまだ「日本語」の視点に近い。ただし、継承語は「外国語」でも無い。この微妙なところを、そもそもの知見を持たない者は捉えられないし、それで自分はやれていると(思うだけ)思えてしまうのが生徒の不幸。

ただでさえ授業時間が限られる(上に大人数の)現代文でできること、環境的な制限をふまえた上でその中で合理的な範囲の目標を、生徒の必要性と擦り合わせながら調整していくことが必要なのだが、「理」の無い集団は、生徒の状態やニーズを精査することも環境的な制約について自覚することも無い(自分達に都合が悪い/お気持ちを削ぐから)。教員のご都合にのみ固執して現実も生徒も見ないから機能不全が起きる。

この時点では、いくらなんでも「口頭」のメッセージを、2年生になっている生徒が理解できていないとは、夢にも思えていなかった。私ですら。それくらいの異常事態。

あの過酷な環境の中で生徒達に必要なのは「全部わからなくても、わかることを確実に掴み、それと自分でできることを掛け合わせて最大化していくスキル」。言語運用能力形成向上期間を設けることもなく、入学後即、英語以外の全ての授業を日本語で受けなければいけない環境なのだから。非道。

情報が伝えられないので、色々想定しながら書いている。2020年度から最後まで、情報伝達、隠蔽のことはついて回った。

メタの視点を入れると伸びる子は飛躍的に伸びる。メタ認知を持つ自律的な学習者は強い。感染対策も一緒。メタも自律も効かない層は、、

私は被害者にも加害者にもなりたくない。

コロナ対策について、再度伝えている。換気、ノーマスクは苦痛を何度伝えても全く変わらなかった。「万全の対策」を演出している「緊急事態宣言」がでているような時期から、一貫して。
ちなみに文書を渡しても回答はおろか何のリアクションも無かった。無視である。
・呼び出し②(10/8)後 週明けコースチーフへ
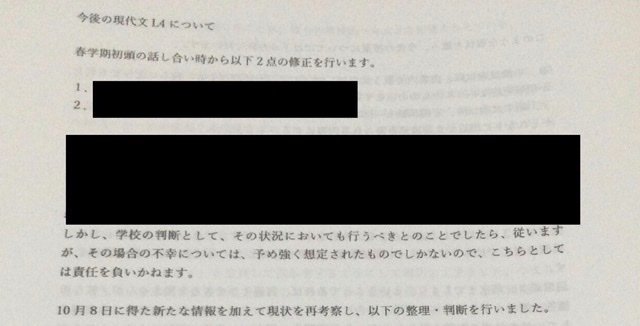
私は自分の都合のみをごり押しする「お気持ち」人間ではなく冷めた現実主義者なので、「現実」や「根拠」に合わせて適宜調整、適応していく。そして業務である以上、きちんと専任に報告もしている。相手が無視隠蔽を徹底していたとしても。この年の2年現代文コースチーフは2020年度の科主任と同じ。

私が語彙表現調整をして行う指示が理解できていないということは、教科学習全般が機能不全に陥っているということ。そしてそれをずっと、入学時から、教員に直接言えなかったということ。一年時の関係構築やトリートメントがなかったのだと気付き、やっと状況が掴めてきた。口頭指示も伝わらない(「聞く」が未伸長な)状態で「読む」が必須なカリキュラム習得が可能なわけがない。それなのに一年半も、つらさを言うこともできずに我慢し続けてきたんだと思うと、本当に不憫でならなかった。

生徒の現状に合わせた軌道修正を行う報告。状況や理由がわかれば対応できる。だから情報が必要だしそれを伝え続けてきたのに、コロナでもこの件でも一貫して拒否され続けた。
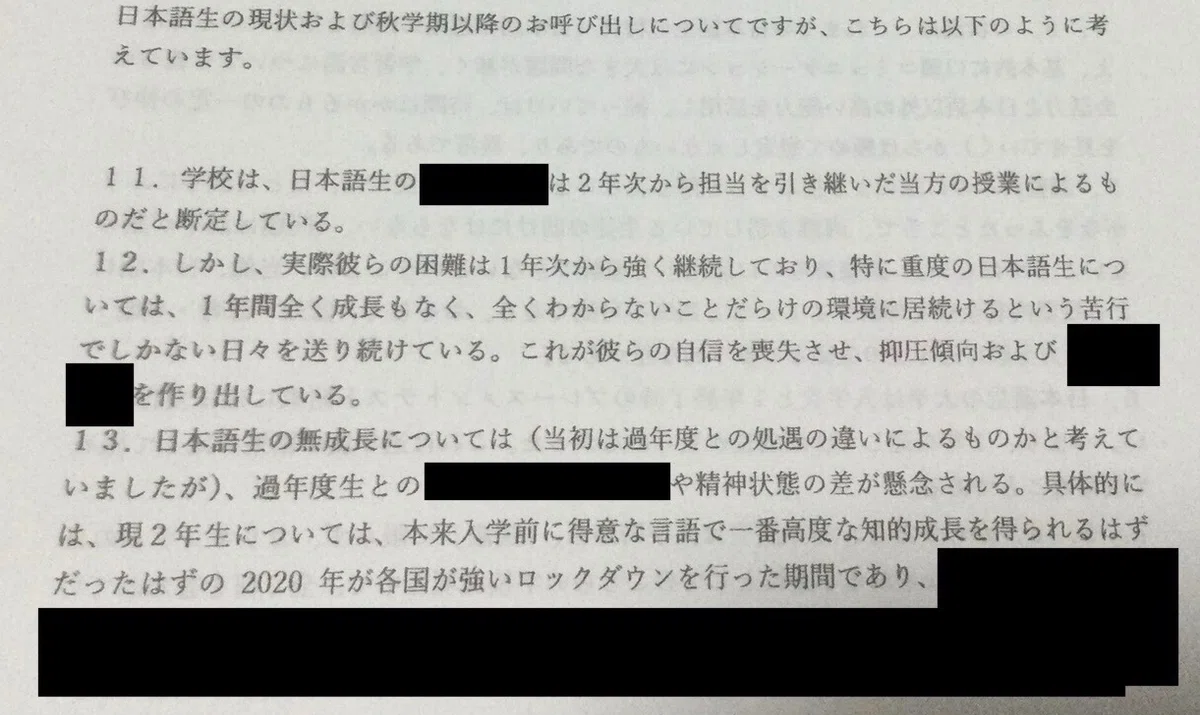
彼らの1年次=現代文L4が設置されて以降、初めて「国語科」専任が担当した年度、である。そして、その翌年の1年現代文L4も「国語科」専任が担当し、多数の転学者が出た。2023年度以降どうなっているかは知らないが、これ以上の犠牲者が出ないことを祈るばかりである。そしてそのために、ここを書いている。

もっと早く状況がわかっていれば、その時点で対応が可能だった。それを行政部専任が拒否した。

行政部専任の姿勢は一貫している。捨て駒である非常勤講師は「嫌なら出て行け」であり、情報は求められても与えず隠蔽して検証不能にさせればよい、対話も拒否で全て無視すれば片がつくというわけだ。これが「人権」や「対話」や「多様性」を尊重するということ。全て口先、形だけ。体制そのもの。

自分達(専任、仲間)のためだけではなく、「生徒のため」に考え、少しでもできることをしていけば開けるものはいくらでもあるのに頑なに拒絶する。不透明な墨塗りだらけの、公正さには程遠い「お気持ち」村社会。どこが「国際性」、「インターナショナル」、「グローバル」だ。

私は(たとえ捨て駒の非常勤講師であっても)生徒の側からは生じうる権威性を意識して、自由にしていけるように対話を行ってきた。教員も生徒もただの一人の人間である。本来は、専任も非常勤も同等であるはずだが、この高校や法人ではそうではなかった。大学は、私が過ごした時期は、身分も立場も越えて個として繋がりが対話できる環境だった。ただ、今でもそれが維持できているのかはわからない。
・生徒と話す&「山月記」後エッセイ→状況判明→科へ(日本語支援について)

・日本語支援について再び科へ



「呼び出し」後に生徒との対話で彼/彼女達の状態を作り出していた原因に気付き、科に「日本語支援」の機能不全について正面を切って(初めて)伝えたことが、行政部だけでなく科からも「敵認定」され、その後「組織集団の敵を追い出すための時間割」を設定させるきっかけになったのだろうと推測している。(それまでは、国語/日本語問題を顕在化し、科のアレルギーを逆撫でしないように気を付けていた。)
2022年度の時間割は「残す」ための時間割だった。
2023年度の時間割は「追い出す」ための時間割だった。
Further references will be uploaded later.
2020〜2021年度の概要
References in AY2020
References in AY2021
2022年度の概要
References in AY2022
2023年度の時間割について(行政部文書と返答)
人権委員会申立書
From middle of nowhere
人権委員会不受理後
