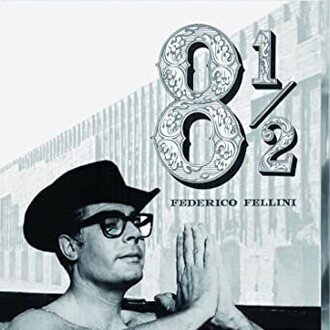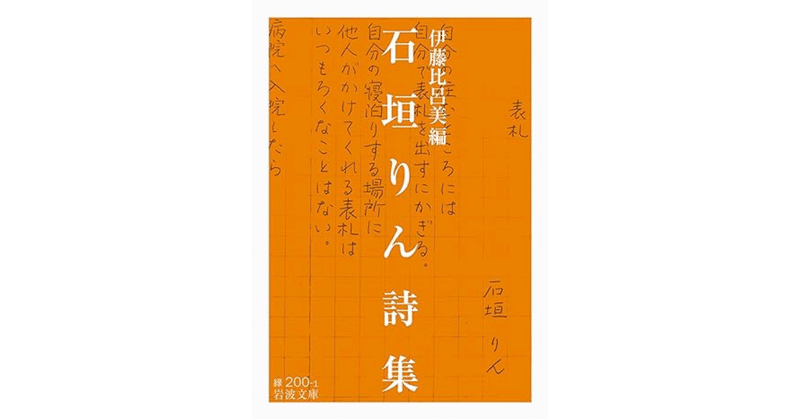#読書感想文
ダンテ「地獄」温泉で李白と一杯
『ダンテ、李白に会う 四元康祐翻訳集古典詩篇』四元康祐
詩の言葉は他者の言葉として神に近い信仰と愛があるのは、先日読んだ古井由吉と大江健三郎の対談『文学の淵を渡る』で読んだのだが、その延長として詩の翻訳が神から授けられた言葉の伝達ということで、本来神の言葉は翻訳不可能なのである。
それでも詩人たちは、その言葉を翻訳して伝えようとすることは神秘主義のドグマに似ているのかもしれない。この本に掲載さ
ディキンスンの兄の浮気相手が編集して世に出した詩人
『エミリ・ディキンスン :アメジストの記憶』大西直樹
ディキンスンの評伝なのだが、大西直樹がアマースト大学出身(ディキンスンの父が経営)で「日本エミリ・ディキンスン協会」の会長でもあるのでかなり詳しい。アマーストという土地がピューリタン的であり「自由と伝統」をモットとするような、その思想は同志社大学やクラーク(「(青年よ、大志を抱け」)の教育にもみられ、ディキンスンが宗教的でありながら個人の自由