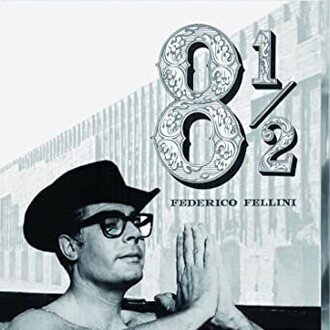2024年10月の記事一覧
シン・現代詩レッスン77
T・S・エリオット「荒地(部分)」鮎川信夫翻訳
『(続続) 鮎川信夫詩集』 (現代詩文庫 )からT・S・エリオット「荒地(部分)」鮎川信夫翻訳。何よりも冒頭の「四月はいちばん酷い月」が有名だった。でも今回注目したのはエピグラフの言葉。普通ここは有名人の言葉とか引用するのだが、これはエリオットの言葉なのか(エリオットはすでに偉大な詩人なのでそれを見越して書いたのか)?「クマエ」はギリシア悲劇の。ウ
シン・現代詩レッスン76
鮎川信夫「詩がきみを」
『(続続) 鮎川信夫詩集』 (現代詩文庫 )から「詩がきみを」。副題に「石原吉郎の墓に」とある。鮎川信夫と石原吉郎を結びつけたものが「詩」という世界なのだ。石原吉郎は失語症の詩人というよりも、コミュニケーション障害の人だったと思う。同じことは鮎川信夫にも言えるのではないか。戦時を生きて死んでいったMとの世界。その世界から戦後復興のアメリカがもたらした豊かさへ。その中の自分
シン・現代詩レッスン75
鮎川信夫「泉の変貌」
『(続) 鮎川信夫詩集』 (現代詩文庫 )から「泉の変貌」。いつもと違うのは、今日はイメージの方が先にあった。それは日記に書いた夢の話。
「泉の変貌」を選んだのは、この詩が恋愛詩であり、泉といいうイメージが湧く詩であるとおもったからだった。
エピグラフが冗談のような言葉だな。詩人って誰だよと思う。そんな詩人は滑稽な詩人のような気がしてしまうのは、ここには恋の欲望しか書か
シン・現代詩レッスン74
鮎川信夫「この涙は苦い」
『(続) 鮎川信夫詩集』 (現代詩文庫 )から「この涙は苦い」。この詩は本屋の思い出の詩か。本屋はどんどん潰れていく。それは仕方がないことなのだろう。かつては月に一万円ぐらいは本を買っていたけど(それもAmazonだった)、今では図書館専門だ。めったに本は買わない。買うとしたら古本屋でか?実際に部屋には積読状態の本が散らばっているのだ。それを読まねばと思うが、図書館で本
シン・現代詩レッスン73
鮎川信夫「小さいマリの歌」
『(続) 鮎川信夫詩集』 (現代詩文庫 )から「小さいマリの歌」。この詩は『一冊で読む日本の現代詩200』にも収められているので鮎川信夫の代表作であり、この時代の代表作なのかと思う。戦後詩から高度成長期にかけて男性詩人で子供を詩を読むのが多いのは、ちょうど結婚して幸福感に包まれるからであろうか。それを生理(欲望)と捉えていたのが「私信」であり、その詩では生理に堕する鮎
シン・現代詩レッスン72
鮎川信夫「私信」
『(続続) 鮎川信夫詩集』 (現代詩文庫 )から「私信」。この詩は「囲繞地」の書き換えであり「私信」というのが、Kuwahara Hideoに捧げられており(のちの「私信」には桑原英夫にと明確にしめされていた)、それは「荒地」の編集者だったかもと思える。それは6冊の雑誌を送ってきた6人の仲間ということで「荒地」のメンバーを指しているのだが「囲繞地」を詩ではなくエッセイと言ってい
シン・現代詩レッスン71
鮎川信夫「ミューズに」
「ミューズ」というのは詩神でホメロスの時代から登場してくる、詩の女神なのだ。なにゆえ女神か?男が詩を作ったからか。女は詩を作らなかったのか?女の詩人は巫女であるから現実的なのか(予言という実際に当たらないと人柱にされたりするのか)。
男性のミューズを検索したら、ミューズメンという石鹸が出てきた。加齢臭を消す石鹸なのか?ミューズも泡のようだし、なかなかこれはいいのではない
シン・現代詩レッスン70
鮎川信夫「寝ていた男」
『続続・鮎川信夫詩集』から。先に「続」を読むべきだったのだが見当たらなくてこっちを先に借りてしまった。「寝ていた男」は鮎川信夫の戦後詩の代表作「死んだ男」のパロディかと思う内容である。「死んだ男」の初稿が書かれたのが1947年で、『鮎川信夫詩集』で改編された完成稿が1955年であったという。完成稿と書いたが初稿にかなりの自信があり、それを広く一般的にしたのが1955年版か
シン・現代詩レッスン69
鮎川信夫「あなたの死を超えて」
人はファザコンかマザコンというのは以前書いたが、本当にマザコンと思われるのは嫌なので(もう遅いか?)今日はシスコン(シスター・コンプレックス)。これは少女マンガの洗脳か?だいたい姉は勝ち気で弟は軟弱みたいな。自分には姉はいないのだが、従兄妹の姉ちゃんが姉代わりみたいな。バリバリの不良でキャロル時代の矢沢命みたいな(今でもコンサートに行くようだ)。横須賀だったし。
シン・現代詩レッスン68
鮎川信夫「囲繞地」
「囲繞地」は読めない。(いにょうち)と読む。学生時代に植木屋でバイトしていたときにこの「囲繞地」を巡って争いがあり大ケヤキが植えてあったのだが、その木の枯葉が家に入ってくるので切れとかいう苦情で伐採したのだが、そのあとブロック塀で通れないようにしたのだ。そういう争いが好きな人達がいるんだと思って、仕事は仕事と割り切って根っこ堀りに苦労していた。
このあなたはM=自己だろ
シン・現代詩レッスン67
鮎川信夫「アメリカ」
この詩は文学の引用をカットバックして組み立てた詩であり、それまでの抒情詩(四季派)の日本の抒情詩に比べて非常に衝撃的だったと吉本隆明が述べている。
ただそれが誰の引用だかわからない。最初の引用はトーマス・マン『魔の山』からとするのだが、それは年号から推測したのかな?
引用の部分が「」で区別されているがそれが地の文の中に融合してしまう。まさにそれが日本という国の特性なのか
シン・現代詩レッスン66
田村隆一「九月 腐刻画」
この詩はもともと1956年に書かれた「腐刻画」のリライト作品であり、戦後の廃墟の街を徘徊している隠居老人というような詩であるという。田村隆一は戦時世代の人だから敗戦の記憶や復興の記憶が鮮明にあるのかもしれない。われわれがそれに倣うことが出来るのか?
戦後の暗いイメージがないのは田村隆一の特徴かもしれない。ただそれは遠く過ぎ去ったイメージがもたらすものかもしれない。スズ
シン・現代詩レッスン65
鮎川信夫「橋上の人」
「橋上の人」は「繋船 ホテルの朝の歌」に後に書かれた長編詩(実際は掲載順なのでよくわかない。初出は「橋上の人」の方が古いということだった)。で、「橋の上」から「繋船 ホテル」を見る感じなのか?そう言えば映画『泥の川』は橋の上から始まっていた。原作ではどうなんだろう。宮本輝は苦手なんだよな。読む前から苦手。
それほど難解ではないと思う。語彙の意味が不明なのはあるが。溝渠は跳
シン・現代詩レッスン64
鮎川信夫『死んだ男』
『討議 詩の現在』城戸 朱理/野村 喜和夫から鮎川信夫『死んだ男』。ちょっと集中的に鮎川信夫をやろうと思う。あまり関係ないのかもしれないが、英字になったときayuなんだと思ってしまった。「荒地」派のayuだった。「同時多発テロ」の映像がくり返し流れていた2001年にそれ以前とまったく違う世界を生きている感覚になったという。そういうトラウマにも似た外傷が一番だったのは、やはり