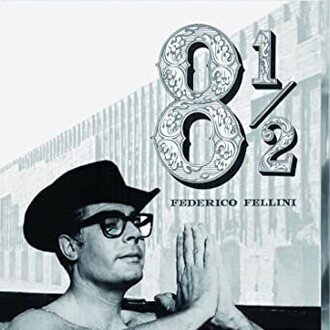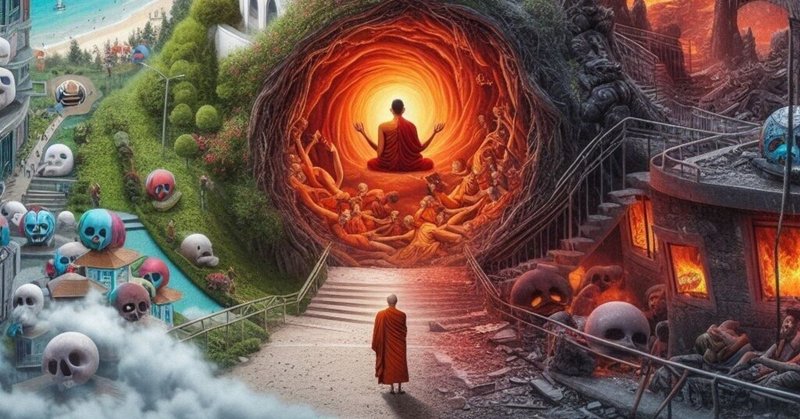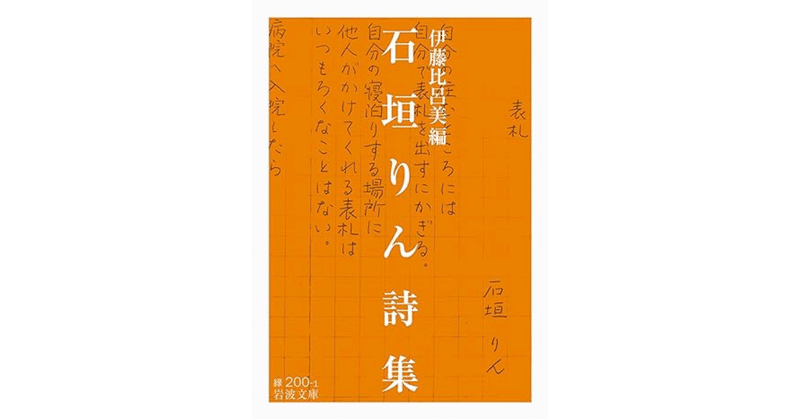2024年4月の記事一覧
シン・現代詩レッスン10
今日も『春と修羅』から「小岩井農場(パート九)」。
「小岩井農場」は賢治の地元にある酪農農場。
『春と修羅』の中に「小岩井農場」と題の詩は「パート1」から「パート9」まであるのだが、5,6,8が欠落している。賢治が小岩井駅から小岩井農場までを歩いた歩行詩であり、その中に回想や心象スケッチが含まれる。例えば5.6は欠落しているのだが、後の別の形で「第五綴」「第六綴」と題されて宮沢賢治の学校(教師
シン・現代詩レッスン9
今日も『春と修羅』から「原体剣舞連(はらたいけんばひれん)(mental sketch modified)」。
今日はAIに絵を描いてもらった。現代の地獄絵図をリクエストしたら出てきた。今野勉『宮沢賢治の真実、修羅を生きた詩人』を借りてきたがこれは参考になる本だ。まだ二章まで読んだだけなのだが、『春と修羅』は『銀河鉄道の夜』に繋がる重要な作品で、妹トシを追悼した詩であるのは間違いないようだ。
シン・現代詩レッスン8
今日も『春と修羅』から「青い槍の葉(mental sketch modified)」。
宮沢賢治『春と修羅』は「心象スケッチ(mental sketch modified)」という詩なのだが、同じように(mental sketch modified)で示されている詩は三篇ある。
宮沢賢治の最愛の同志というべき妹の宮沢トシが亡くなったことによってそれまでの賢治の信じていた宗教(法華経)が危うくな
シン・現代詩レッスン7
今日も『春と修羅』から。
本当はこの後に続く行が面白いのだが長くなるので、ここまで。「mental sketch modified」というのが心象スケッチということだった。
「心象のはいいろはがねから」は妹トシが亡くなって喪の気持ちというようなことか。宮沢賢治は「青」の使い手なのだが、それはモダニズムの青で、憂鬱な色というような灰色がかっているのだった。けっして明るい青空のイメージではないのだ
シン・現代詩レッスン6
梯久美子『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』を読んで宮沢賢治の詩が良かったので『春と修羅』から。『春と修羅』は妹の死から当時宮沢賢治が信仰していた日蓮宗の教義が信じられなくなって、そこから立ち直っていくサハリンまでの旅をする中で、膨大な詩を書くのだけど、一番有名なのは、「永訣の朝」で、梯久美子の本で感動したのは「青森挽歌」「オホーツク挽歌」なんだが、妹の死とある程度の長さがあって難しいので、
もっとみるシン・現代詩レッスン5
今日は石垣りんを読んだので総仕上げだ。
伊藤比呂美の解説で石垣りんは最初の二行が素晴らしくラストの二行が決まっているということだった。掴みは驚きの言葉で、言いたいことは最後までいわずに置く、ということかな。そのへんを注意しながら今日は見ていこう。
平沢貞通という固有名と帝銀事件という事件は、もっとも詩になりにくいテーマだと思う。そのことにまず驚く。だれが興味を持つのだろうと。こんなテーマの詩に
シン・現代詩レッスン4
今日は表紙の写真はあまり関係ないです。聴き逃しで「ゴンチチの世界快適セレクション」を聴いていたら、浅川マキ「裏窓」が流れました。この詩が寺山修司で、けっこう好きな曲だったので、今日はこの詩に挑戦したいと思います。
長いので一番だけです。前半は裏窓から見える情景のリフレインですね。詩は単純ですけど浅川マキの語りかける歌い方がしみじみ響いてくるのです。これを詩で表現するのは難しいかもしれない
萩原
シン・現代詩レッスン2
2回目もやるということでヘルン君です。青鷺はアイルランド出身の小泉八雲のハーンという名字は「ヘルン」ということで青鷺の紋章だったのだ。そのことを映画『君たちはどう生きるか』で問題にしてない考察が多すぎる。つまり深層世界は多様性に富んでいる様々な物語があるということだった。それを象徴するのが青鷺のヘルン君なのだ。
今日も石垣りんの続きで、100分でもやっていた「シジミ」からをやってみようか。
俳
シン・現代詩レッスン
100分de名著で石垣りんをやっていたので、詩も作ってみたくなった。シン・俳句レッスンで富澤赤黄男をやっていて富澤赤黄男も俳句と短歌と詩の境界を無くそうとしていたと知ったから。今までやってきた中で、そうした各ジャンルでの枠組みがそれぞれの分野を閉鎖的にしているのではないのか?ゲームとしてやるのなら、いろいろな制約(ルール)も必要だとは思うが表現行為とした場合はそれらの制約から自由になる必要がある。
もっとみる