
【読書記録】エフェクチュエーション-優れた起業家が実践する「5つの原則」
今回は、2023年8月に出版された吉田満梨、中村龍太著『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』(ダイヤモンド社)の読書記録です。
本書は、アントレプレナーシップ及び「起業家個人の意思決定」の研究に従事しているサラス・サラスバシー教授(Saras D. Sarasvathy)によって提唱された『エフェクチュエーション(実行理論:Effectuation)』という思考様式の入門書です。
本書『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』出版以前の2015年には、サラス・サラスバシー著『エフェクチュエーション-市場創造の実行理論』(碩学舎)が出版されています。
しかし、こちらは学術書であるため、一般のビジネス書と比べて読むのにハードルが高いものでもありました。
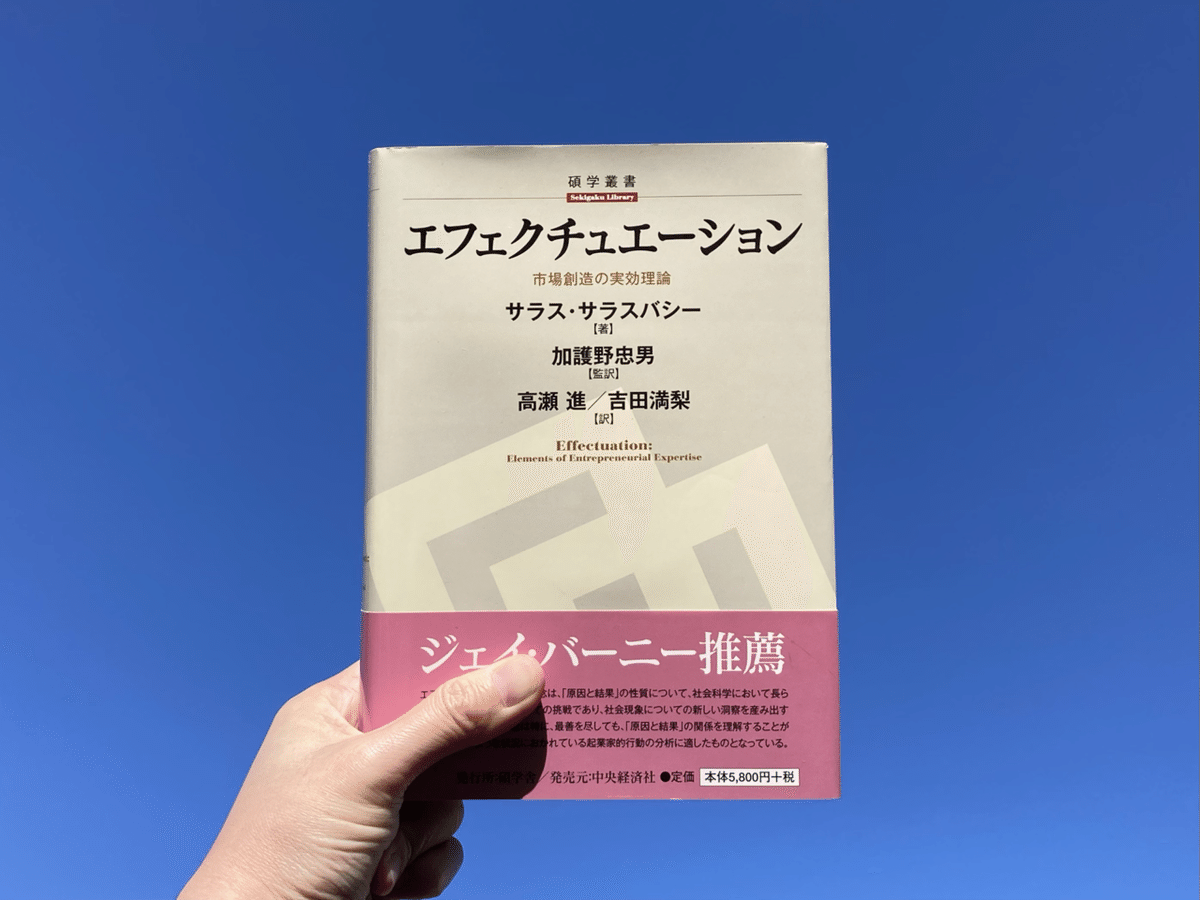
『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』は、サラスバシー教授の提唱する『エフェクチュエーション』の日本における入門書として企画された書籍です。
著者の一人である吉田満梨氏は、サラスバシー教授の書籍翻訳に携わらた経歴を持つ、日本におけるエフェクチュエーションの研究者・教育者であり、これまで講演・セミナー・執筆等を通じてエフェクチュエーションを紹介されてきました。
また、『エフェクチュエーション 優れた起業家が実践する「5つの原則」』では、サイボウズ執行役員でありエフェクチュエーション活用の実務経験である中村龍太氏をもう一人の著者として迎え、後半部で実践事例を紹介しています。
以下、本書を読んでの印象的な気づき・学びについてまとめていきます。
エフェクチュエーションとは?
エフェクチュエーションの発見
エフェクチュエーションは、サラス・サラスバシー教授(バージニア大学ダーデンスクール)が発見した、不確実性の高い状況における意思決定の思考様式です。
氏がカーネギーメロン大学の博士課程在学中に、ノーベル経済学賞受賞者のハーバート・A・サイモン教授(Herbert Alexander Simon)の指導のもと実施した研究から発見されたと言います。
2001年、氏の論文『Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency』がアカデミー・オブ・マネジメントレビュー誌に掲載されたことをきっかけにエフェクチュエーションは注目を集め、アントレプレナーシップや価値創造をはじめとする幅広い領域にインパクトを与えました。
2008年に氏の書籍である『Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise』が出版された後、日本では2015年に同書が邦訳出版されました。
また、2022年には『Effectuation: Elements of Entrepreneurial Expertise』の新版が出版されています。
起業家の熟達に関する研究
サラスバシーによるエフェクチュエーションの発見は、起業家およびアントレプレナーシップの熟達(expertise)の研究からスタートしました。
そしてエフェクチュエーションの発見は、優れた起業家、熟達した起業家(expert entrepreneur)の成功は彼らだけの優れた資質・遺伝特性・性格によるものではなく、 問題解決のための共通の論理・思考プロセスを活用した結果であり、誰もが共通の論理・思考プロセスを通じて「熟達した起業家」の思考様式を身につけられることを示唆するものでした。
起業家的熟達についてのプロセス要素について、サラスバシーは著書で以下のようにまとめています。
熟達した起業家は、「自分が誰であるのか(who they are)」、「何を知っているのか(what they know)」、「誰を知っているのか(whom they know)」、からスタートし、すぐに行動を起こし、他の人々と相互作用をしようとする。
彼らは自分ができること(what they can)にフォーカスして、実行(do)する。何をすべきか(what they ought)については、思い悩むことはしない。
彼らが交流する人々の一部は、自発的にそのベンチャーにコミットし、プロセスに参画する。
上記のコミットメントの1つひとつは、新しい手段(means)と目的(goals)をそのベンチャーにもたらす。
ネットワークの拡大で資源が蓄積されるにつれ、制約条件がついて回るようになる。その制約条件は将来の目的変更の可能性を減じ、誰が関与者のネットワークに入って良いか/良くないかを制限する。
関与者が増えるプロセスが時期尚早に停止しない限りは、ゴールやネットワークは新しい市場や企業へと同時発生的に収束する。
コーゼーションとエフェクチュエーション
2001年、サラス・サラスバシー氏がエフェクチュエーションの概念を広く紹介した論文のタイトルは『Causation and Effectuation: Toward a Theoretical Shift from Economic Inevitability to Entrepreneurial Contingency』であり、エフェクチュエーション(Effectuation)の概念にはコーゼーション(Causation)が対置されています。
ビジネスのさまざまな意思決定には成功するかどうかを事前には正確に予測できない不確実性が伴いますが、従来の経営学ではこうした不確実性への対処の基本方針として「追加的な情報を収集・分析することで不確実性を減じる」ことが目指されてきました。
このような前提をもとに、吉田氏は以下のようにコーゼーションについて説明しています。
それゆえ私たちは一般に、不確実な取り組みに際しては、まず行動を起こす前にできる限り詳しく環境分析し、最適な計画を立てることを重視します。目的(たとえば、新事業の成功)に対する正しい要因(成功するための最適な計画)を追求しようとする、こうした私たちの思考様式をサラスバシーは「コーゼーション(causation:因果論)」と呼びます。
また、エフェクチュエーションとコーゼーションの関係について、サラスバシー氏は端的に以下のように述べています。
「エフェクチュエーション」は「コーゼーション」の反意語である。コーゼーションに基づくモデルは、「作り出される効果(effect to be created)」からスタートする。そして、あらかじめ選択した目的を所与とし、その効果を実現するために、既存の手段の中から選択するか、新しい手段を作り出すかを決定する。他方、エフェクチュエーションに基づくモデルは、逆に、「所与の手段」からスタートする。予測をもとにしない戦略を用いて、新しい目的を創り出そうとする。
従来の経営学で重視されてきた、目的に対して最適な手段を追求するコーゼーションは、企業にとって当初から目的が明確であり、また、環境が分析に基づいて予測可能な場合には効果を発揮します。
一方で、新しい事業や市場が創造されるような不確実性が高い場合には、コーゼーションの思考様式の効果は限定的となります。
エフェクチュエーションは熟達した起業家が好んで活用する思考様式であるものの、エフェクチュエーション、コーゼーションはいずれかが優れた方法というわけではありません。状況に応じて双方の思考様式を使う分けることが重要な相補的なものであると、サラスバシー氏、吉田氏は述べています。
また、エフェクチュエーションとコーゼーションは、それぞれ異なる世界観に則った思考様式でもあります。この世界観の前提についても、サラスバシー氏は以下のように紹介しています。
ここで、論理(ロジック)とは、「世界で行為するための明確な基盤となる内的に一環した考え」を意味するが、コーゼーションの論理(causal logic)の前提は、「未来を予測できる範囲において、われわれは未来をコントロール(制御)することができる」というものである。一方、エフェクチュエーションの論理の前提は、「未来をコントロール(制御)できる範囲において、われわれはそれを予測する必要がない」というものである。
エフェクチュエーションとコーゼーションの思考プロセスの違いについては、以下の記事の中でも紹介されています。
エフェクチュエーションの5つの原則
以上のような前提を踏まえつつ、熟達した起業家が従っている原則として見出されたのが以下の5つの原則です。
手中の鳥の原則(Bird in Hand)
「目的主導(goal-driven)」ではなく既存の「手段主導(means-driven)」で何か新しいものを作る。
許容可能な損失の原則(Affordable Loss)
期待利益の最大化ではなく、損失マイナス面が許容可能かに基づいてコミットする。
レモネードの原則(Lemonade)
予期せぬ事態を避けるのではなく、むしろ偶然をテコとして活用する。
クレイジーキルトの原則(Crazy Quilt)
コミットする意思を持つすべての関与者と交渉し、パートナーシップを築く。
飛行機のパイロットの原則(Pilot in the Plane)
コントロール可能な活動に集中し、予測ではなく、コントロールによって望ましい成果を帰結させる。
以下の記事の中では、飛行機のパイロットの原則(Pilot in the Plane)はその他4つの原則を貫く1つの世界観として紹介されています。
エフェクチュエーションとソース原理
今回、エフェクチュエーションに触れるきっかけとなったのは、私がこれまで探究し、実践してきたソース原理(Source Principle)の質感ととても近しいものを感じたことです。
ソース原理(Source Principle)について初めて国内で体系的に紹介した『すべては1人から始まる』は、日本の人事部「HRアワード2023」に入賞するなど少しずつ広がりを見せつつあります。
以下、私のこれまでの実践を、ソース原理とエフェクチュエーションの観点から振り返れればと思います。
ソース原理(Source Principle)とは?
『ソース原理(Source Principle)』とは、イギリス人経営コンサルタント、コーチであるピーター・カーニック氏(Peter Koenig)によって提唱された、人の創造性の源泉、創造性の源泉に伴う権威と影響力、創造的なコラボレーションに関する洞察を体系化した知見です。
2022年10月、ピーター・カーニック氏に学んだトム・ニクソン氏による『すべては1人から始まる―ビッグアイデアに向かって人と組織が動き出す「ソース原理」の力』が出版されて以降も、ソース原理(Source Principle)に関連したさまざまな取り組みが国内で展開されています。
今年4月にはソース原理提唱者であるピーター・カーニック氏の来日企画が実現し、システム思考・学習する組織の第一人者である小田理一郎さんや、インテグラル理論・成人発達理論の研究者である鈴木規夫さんとの対談、企画の参加者との交流が活発に行われました。
日本での流れに先立ち、ソース原理(Source Principle)が世界で初めて書籍化されたのは、2019年にステファン・メルケルバッハ(Stefan Merckelbach)『A little red book about source』のフランス語版が出版された時でした。
その後、この『A little red book about source』は2020年に英訳出版され、2021年3月に『すべては1人から始まる』の原著であるトム・ニクソン著『Work with Source』が出版され、『すべては1人から始まる』の出版につながります。
また、2024年1月にはステファン・メルケルバッハ氏の来日企画が実現しました。
ソース原理にまつわる潮流は、このような背景を持ちます。
ソース(Source)
トム・ニクソン『Work with Source(邦題:すべては1人から始まる)』を参照すると、ソース(Source)とは、あるアイデアを実現するために、最初の個人がリスクを取り、最初の無防備な一歩を踏み出したときに自然に生まれる役割を意味しています。
The role emerges naturally when the first individual takes the first vulnerable step to invest herself in the realisation of an idea.
また、本書中の用語解説では、『脆弱なリスクを取って、ビジョンの実現に向けて自らを投資することで、率先して行動する個人のこと』と説明されています。
An individual who takes the initiative by taking a vulnerable risk to invest herself in the realisation of a vision.
ステファン・メルケルバッハ氏の書籍においては、この役割を担うことになった人について、特に「ソース・パーソン(source person)」と呼んでいます。
A source is a person who has taken an initiative and through that has become the source of something: we can call this a "source person".

Tom Nixon「Work with Source」
トム、ステファンの両者に共通しているのは、ソース(Source)は特別な人だけがなれる役割ではなく、誰もがソース(Source)である、というものです。
アイデアを実現するために一歩踏み出すことは、社会を変えるような大きなプロジェクトの立ち上げに限りません。
友人関係や恋人関係、夫婦関係などにも、誘ったり、告白したり、プロポーズしたりと主体的に関係を結ぼうと一歩踏み出したソース(Source)が存在し、時に主導的な役割が入れ替わりながらも関係を続けていく様子は、動的なイニシアチブと見ることができます。
さらに、自身の研究課題を決めること、就職を思い立つこと、ランチを作ること、休暇の予定を立てること、パートナーシップを築いていくこと等、日常生活の様々な場で誰しもが何かのソース(Source)として生きていることをトム、ステファンの両者は強調しており、日常生活全般にソース原理(Source Principle)の知見を活かしていくことができます。
This applies not only to the major initiatives that are our life’s work. Every day we start or join initiatives to meet our needs, big and small.[…]Whether it’s making a sandwich or transitioning to a zero-carbon economy, we start or join initiatives to realise ideas.
We take initiatives all the time: deciding on a particular course of study, going after a certain job, starting up a business, planning a special dinner. I can initiate a friendship or partnership, change my housing situation, make holiday plans, decide to have a child. Or I might step forward to join a project sourced by someone else.
ソース原理×エフェクチュエーションの実践
私の実践は、父から家業である米農家の事業承継を行ったことから始まりました。4年前の出来事です(それ以前は、京都のNPOにてワークショップのファシリテーション、『ティール組織』という新しい組織運営モデルに関するリサーチや講演を行なっており、現在は米農家との複業中です)。
父の病気がきっかけとなった事業承継は混乱の最中に始まったものの、『父が大切にしていた土地や景色を大切にしたい』という願いはおそらく父にも私の中にも双方に共通して持っており、この感覚を大切にしつつ、『自分が田んぼをやっていくよ』と父に切り出したことから継承のプロセスは始まりました。
このあたりが、ソース原理で言うところのソースの継承(succession)にあたるのではないか、と捉えています。(上記のエピソードは、『すべては一人から始まる』著者のトム・ニクソンにもシェアすることができました)
また、予期せぬ出来事を積極的に引き受けようとしたと言う点で、エフェクチュエーションのレモネードの原則(Lemonade)に則った意思決定を行った、と言えるかもしれません。
家業を継いだ当初は、家族関係の大きな変化、継承に伴う業務プロセスの変革、公私共に新しい体制へのトランジションなど大きな混乱、高い不確実性の中にありました。
そして、明確な目標を定めて実行するよりも、自分の手元にある手段を用いていかに新しい体制を軌道に乗せていくか?という考えのもとで進めていたように思います。
この当時を振り返ると、コーゼーションと言うよりエフェクチュエーション、それも飛行機のパイロットの原則(Pilot in the Plane)や手中の鳥の原則(Bird in Hand)を採用することで、感覚的に助けられていたように思います。
また、家業の米農家を継ぐ以前から、私には農や自然に関心を強く持つ経営者仲間がいました。
彼らのご縁によって『すべては一人から始まる』著者であるトムを地元である伊賀に招くことができ、対話をしながらソース原理の実践に関する理解を深めていくことができました。
リスクを引き受けて自らのビジョン実現のために一歩踏み出したソースの周りには、人を惹きつけるフィールドが生まれると言います。
「クリエイティブ・フィールド(creative field)」とは、『ビジョンを実現するために必要な人やその他のリソースを引き寄せ 、努力を束ねることで一貫性を生み出す魅力的なフィールドのことを指し、ソース(Source)がイニシアティブ(initiative)を取ることで確立されるものです』
Creative field
The field of attraction that draws in the people and other resources needed to realise a vision and creates coherence by binding an effort together. Established when a source takes the initiative.
仲間たちが地元で農や自然に触れる体験を実現できたのは、ソース原理の観点から見ると、フィールドに集った仲間たちの助けの成せる業であり、エフェクチュエーションの観点から見ると、クレイジーキルトの原則(Crazy Quilt)に則ったパートナーシップによるものだったと言えるかもしれません。
唯一、許容可能な損失の原則(Affordable Loss)に関しては、当時は損失度外視でとにかくできることをやる、と言う精神状態だったため、許容量を大きく超えたさまざまなリソースを投下してしまったように思います。
以上、あくまで個人的な経験と仮説からではありますが、ソース原理とエフェクチュエーションの実践について振り返ることができました。
今回、エフェクチュエーションの書籍に触れ、上記のような振り返りを行うことができたことでより一層、当時の体験が鮮明になり、地肉にできたように感じます。
今後もじっくり探究を深めると共に、都度開催している読書会などで扱っていければと思います。(読書会については、Xの投稿もぜひご覧ください)
このまとめを最後まで読んでいただきありがとうございました。
ご覧いただいた皆さんに、何か気づきや発見などがあれば幸いです。
さらなる探求のための参考リンク
偶然を味方につけて、不確実性の高いプロジェクトを成功させる『5つの原理』 ー エフェクチュエーション
「手段」ありきvs「目的」ありき:エフェクチュエーションという考え方。
①エフェクチュエーション・エッセンシャルズ講座【エフェクチュエーションの理論的基礎】
全米の起業家調査でわかった、成功者の「意思決定」の共通項 不確実性の高い状況で、イノベーターが好んで使う「ロジック」
いいなと思ったら応援しよう!

