
C.G.ユング著『個性化とマンダラ』を読む
ここ最近、ふとしたことからユングの著書を読んでいる。
ユングの著作に最初にふれたのは、随分むかしのことである。
まだ中学生の頃、とあるところから「読むべし」とアドバイスを受け、読み始めたものである。
読み始めた、といっても当時は「文字がならんでいるなあ」以上のことは理解できておらず、どうにもならなかったのであるが、それでも1ページ1ページ、一文字一文字、言葉の透明な流れに手を突っ込むように、読む。というか、「この向こう側になにかある!」という直観だけで、とっかかりになりそうな言葉を探そうとしたものであった。
・・・あれから四十年!
・・・・・・いや、それほどでもない。
その後、弘法大師空海の著作(『吽字義』や『秘密曼荼羅十住心論』を読み、クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を読み直しているうちに、「おや?これはもしかして。」と、ユングが見ていたであろう光景を、ユングの思考の流れを、その著作からありありと再現することができるような感じになってきたのである。
そういうわけでこのところ『赤の書』、『自然現象と心の構造』、『心理学と錬金術』、『パウリの夢』、『変容の象徴』などをおもしろく読み直しているのである。その話は下記の記事にも書いているのでご参考にどうぞ。

それにしても『変容の象徴』が文庫本になるとは、よい時代に生きていることを実感するものである。
ちなみにしばしば「ユングを初めて読む場合にどの本がよいか」と尋ねていただくことがあるが、おすすめは『赤の書』である。『赤の書』は「読む」という営みを、表層意識における記号の線形連鎖生産という様式から解き放ち、無意識で脈動する何かに触れることへと転換する。

これを「読む」のは今日の「Googleレンズ」の手書き文字認識機能と翻訳機能を使ったとしても容易なことではないが、それがよいのである。通常の読みを超脱するというか、表層の分別の出来合いのところにスポットライトを当てるような”読み”ではなく、マンダラがゆらゆらとうごめく表層の一番底にして深層の一番上澄で眼識の分別をゆさぶり解くようなつもりで「みる」のである。
そのための一冊として人類史に残るべき本であると思う。
ちなみに、どうしても書いてある文字列の意味を知りたい、という場合は『赤の書』のテキスト版(日本語翻訳版)も用意されているのでご参考にどうぞ。

「私」の変容、主体感の生産として個性化
というわけで、今回はC.G.ユングの著作『個性化とマンダラ』を読む。
*
『個性化とマンダラ』は「生まれ変わりについて」という章からはじまる。
生まれ変わりというと、人間の存在のすべてを自然科学的な物質の観点からのみ理解しようという立場からすると、なにやら胡散臭いことを言っているように思われる向きもあるだろうが、ユングはいたって大真面目に、心理学の議論をしているのである。
* *
ユングはまず、いわゆる「生まれ変わり」ということは自然科学的な方法で感覚的に測定できることではない、と強調する。
生まれ変わりは、なんらかの方法で観察できるような現象ではない。われわれはその長さや重さを測ったり、写真に撮ったりすることはできない。それは感覚によってはぜったいに掴まえることができない。それは純粋に心的な現実であって、それをわれわれは述べられた言葉から間接的にしか知ることができない。生まれ変わりについて語る人、生まれ変わりを告白する人、生まれ変わりによって 満たされた人がいるそれだけでわれわれにとっては十分な現実である。われわれはここでは「生まれ変わりは何らかの方法で感知しうる過程か」という問いには関わらない。
生まれ変わりとは、「純粋に心的な現象」である。
この心的現象としての「生まれ変わり」を観察する方法は「言葉」に依るのである。
語り、言説としての生まれ変わり
ユングが「生まれ変わりについて語る人、生まれ変わりを告白する人、生まれ変わりによって満たされた人がいるそれだけでわれわれにとっては十分な現実である」と書いているとおり、生まれ変わりということについて語る人が存在する、言葉で報告する人がいる、という「現実」について考えることが心理の科学のテーマとなるのである。
ユングは次のように続ける。
「生まれ変わり」ということは、そもそも人類が大昔から語ってきたことである。この大昔から語られてきたことは、私が「元型」と呼んでいるものに基づいている。超感覚的な事柄に関する発言はすべて、もっとも深い根っこのところではつねに元型によって規定されているので、生まれ変わりについての発言がありとあらゆる民族において一致するとしても、なんの不思議もない。
生まれ変わりについての「語り」のおもしろさは、それが古今東西、文化や宗教や言語や地域を超えて、さまざまな人々によってよく似たパターンで語られてきた、ということである。動物が、生まれ変わりということについて仲間たちと語り合っているのかどうかはわからないが(鳥や社会性昆虫や魚はそのようなことを語り合っているような気もするが、それこそ感覚的に測定するのが難しそうである)、人間には、人類のあいだには、古今東西どこでも「生まれ変わり」についての語りが生じる。
これはつまり人類が言語や文化といった表層の現実のコードの差異を超えて、そのはるかに手前で、表層に対する深層において共通してもっている「心」の動き方のパターンから、「生まれ変わり」として表現されるようなことを思いつき、考え、言語化するようにできている、ということである。
ユングのいう「元型archetype」とはこの表層に対する深層の心の動き方のパターンのことである。ユングは「超感覚的な事柄に関する発言はすべて、もっとも深い根っこのところではつねに元型によって規定されている」と書いている。

* *
自我とは、”自我-ではない-ではない”ということ
しばしば語られる”生まれ変わり”とは、自分自身が以前の自分とは大きく異なる人間に変容したと自覚できる、ということである。
精神科医であるユングが実践したように、心理療法を通じ、苦しい状態を脱して癒される経験もまた生まれ変わりのひとつである。
あるいは変容は、”自己同一性が予め確定され固定された「私」の内部での多少の構成の組み替え”といったスケールにとどまらず、やはり一度死んで生まれ変わるような、あるは過去に死んだ他者が憑依してくるような、私と私でないこととの境界線そのものが振動し、揺らぎ、引き直されるような、「生まれ変わり」と表現せざるを得ない振幅を描くことがある。
生まれ変わりとして語られることには、”私”の同一性を保った上での変容から、私の同一性そのものの変容まで、さまざまな幅がある。
◇
なぜそのような幅が出てくるかといえば、生まれ変わりということが、生まれ変わる前の私と生まれ変わった後の私、二つの私のあいだのちがい(差異)を区別できなければならないことであり、この区別のためには、かつての私(生まれ変わる前のもともとの私)/生まれ変わった新しい私の二項対立を、別の第二の二項対立(任意のX /非X)に重ねる必要があるためである。この第二の二項対立の位置に何をもってくるかによって、かつての私/生まれ変わった新しい私のあいだの距離が広がったり、狭まったりするのである。
かつての(もともとの)私 / 生まれ変わった新しい私
|| ||
X / 非X
ここでXと表記したものは「かつての私(もともとの私)」と完全にイコールになる「私ってXだから」と言えることに何の抵抗もないXである。それに対して非XはXの反対、Xの否定、Xの逆であり、「かつての私(もともとの私)」は自分のことを「私は非Xだから」とは決して言えないような何かである。
ところが、生まれ変わると「生まれ変わった新しい私」は「(生まれ変わった新しい)私は非Xだから」ということも言えるようになる。
**
元型は分けたり繋いだりすることのパターン
かつての私(もともとの私)が、まったく新しい別の私に「生まれ変わる」ということは、ある任意の時点での「私」と「私-ではない誰か」との二者の関係が、それに続く別の時点においては変容するということでもある。関係が変容する、あるいは境界が動く、境界線の位置が動き、境界線の形が変わる、などと喩えてもいいかもしれない。
この「私」と「非-私」、「自我」と「非-自我」の対立関係を組み、作り出すところに「元型」がでてくる。
分けられることで区切り出される
ここで念頭に置いておきたいことは、「私」「非-私」、「自我」「非-自我」なるものは、予め端的にそれ自体として固まって存在しているわけではない、ということである。
予めそれ自体としての同一性を固められて存在する「私」と、これまた予めそれ自体としての同一性を固められて存在する「非-私」とが、なにかのはずみに出会い対立関係に入りました、ということではないのである。
じつは、「私」ということは、「私」を「非-私」から区別する=切り分ける=区切り出す動きを通じて、はじめてその輪郭線を引かれるものである。「私」とは「非-非-私」である。そして「非-私」が動き、変化することに連れて、「非-非-私」である「私」もまた動き、その輪郭線の形も変容する。「私」と「非-私」の対立関係とは、「私」と「非-私」を未分節から分節しつつもまた未分節に送り返すような動き、その拍動が描く波紋の複雑なパターンのようなことである。

元型としてのマンダラは
「私」と「非-私」の分離と結合を振動させ、安定させる
ユングの「元型」、特に「マンダラ」という「元型」は、この「私」と「非-私」を(「非-非-私」と「非-私」を)分けるでもなく分けないでもないように浮かび上がらせる波紋を引き起こす振動のパターンのこと、というふうに読んでみたい。
[…]おとぎ話の老人のように、彼らはマンダラを描き、その包み込む円のなかへ自ら入っていき、そして避難所だと思い違いをして自ら選んだ牢獄に驚いたり悩んだりしなから、神に近い存在へと変えられる。マンダラは誕生の場所、まさしく誕生の器、仏陀が生まれる蓮華である。ヨーガ行者は、蓮華に座して不死の姿に変容する自らの姿を見る。
ユングはこの「生まれ変わり」という思考が、しばしば”一が「四」に分かれる”というビジョンや物語とともに表面化すると指摘する。「元型」の脈動には、一を四に分けたり四を一に統合する、”一にして四、四にして一”ということを言語で語らせたり、イメージさせたりする場合がある。
そしてこのイメージが「マンダラ」である。

* *
ちなみに、自我と非-自我だけでは「二」であって、「四」にするにはあと二つがなりたい。このあと二つとは何かといえば、少しややこしい話になるが、強いていえば「いつも常に選ばれる方」と「いつも常に選ばれない方」の対立二項である。
自我 / 非-自我
|| ||
ある経験的感覚的に二つに分別できる事象において
「いつも常に選ばれる方」 / 「いつも常に選ばれない方」
どういうことかといえば、「自我」と「非-自我」は、前述の通り、それぞれ予めそれ自体として固まっているわけではなく、自我は「非-非-自我」でしかない。ここで、端的身体においてある経験的感覚的に二つに分別できる事象を感知しているときに、そのどちらを非-自我に類することとして選んで遠ざけて、どちらをその対極に「非-非-自我」としての「自我」の位置に残すかは、予め一意に決まっていることではないのである。
言い換えると、「自我」と「非-自我」の分離は抽象的なことではない。
例えば、蕎麦屋で「天ぷらそば」を注文している最中に、親切なスタッフから「うどんにもできますよ」とオファーをいただくことがある。
これは大変なことで、そば/うどんの分別、Δ二項対立に圧倒され、意識を失いそうになる。もちろん健全な社会人の嗜みとして、「ありがとう。おそばでお願いします」と即答するようにしているが、心の底では、Δそばの概念とΔうどんの概念が、お互いに非うどん、非そば、非ー非ーそば、非ー非ーうどんの置き換え先となる感覚印象を探し求めて暴れているのである。

天ぷらというよりもフリッターに見える
要するに、そばを選ぶか、うどんを選ぶか、そばとうどん、どちらを「自我」の側に振り分けて結合するか、といったことから「そばを選んだ私」や「そばを選んでしまった私」という存在が立ち現れるのである。そしてそのそばを選んでしまった私は、潜在する「うどんを選ぶこともできた(非ー)私」の影から凝視され続けながら、そばを食うことになるわけである。
*
もちろんここで「それにしても、この天ぷらのエビは衣に対して過度に小さいのではないか」などと念じることで、選ばれた自我と選ばれなかった非ー自我の対立から「うどん/そば」の対立が剥がれ落ちて、「海老天/非ー海老天」の対立が新たに重来してくる。そして自我が「海老天(つまり衣に対して適切なサイズのエビが入っているもの)」を選びうる余地が元来封じられていること(つまりそばとうどんの区別に関わらず、乗ってくる「海老天」はこの非ー海老天以外選びようがない)、選択の余地がなかった、ということで、私は束の間、いまの自我に「これでいいのだ」と安住することができるような気がするのである。
要するに、身体的に感覚経験される対立する事象について、その対立を、「非-自我」/「非-非-自我」の対立に対して、どちら向きに重ねるのか、ということは、自在に向きを変えて、ひっくり返すことができる、できてしまうのである。
立体曼荼羅
私たちは、ある経験的感覚的に二つに分別される事象について、いつも常に自我に結合すべきこととして選ぶ方と、そうでない方とを分別するようにできている。記憶、学習、あるいは発達、というのはそのようなことであろう。ここに四項関係が登場し、マンダラが出てくる。
マンダラは、四項関係と、その四項関係を分けつつつなぐ第二の四項関係が重なり合った八項関係のビジュアルとしてイメージされたり、描かれたりする。
自然な変容過程はとくに夢のなかに現われる。私は他の機会に個性化過程を表わす一連の夢シンボ ルを示した。その夢のなかには一つ残らず、生まれ変わりのシンボルが使われていた。そのケースでは、別の存在への内的変容と生まれ変わりの、長期にわたる過程が表わされていた。その「別の存在」とはわれわれの内なる他者であり、未来のより広いより大きい人格であって、それをわれわれはすでに内なるこころの友として知っていたのである。
またマンダラは、特に「夢」においては、四人の登場人物が(そのうちの一人が「私」である)くりひろげる事件や出来事として意識の深層の一番上、表層の一番底に、浮かんでくることもある。夢のなかで「私」と私ではない他の登場人物とが(それがしばしば三人である)、ある場所において(しばしば円形の空間の中だったり、四角形の部屋の中だったり)で繰り広げる分離と結合、愛/憎の両極の間を揺れる。
◇
例えば『心理学と錬金術I』でユングが分析しているこちらの夢などが好例である。
15夢
母親が一つの盟(たらい)から別の盥へと水を移しかえている (夢見者は28の「幻覚像」の際にはじめて、別の盥 が姉[妹]のそれであったことを想い出した)。この行為は大変厳粛に行われる。というのもこの行為は 周囲にとっても極めて重大な意味を持っているからである。それから夢見者は父親に追い出される。
この夢には、
1夢見者(私、男性)
2父親(男性、つまり夢見者がいつも常に選ばざるを得ない方)
3母親
4姉(あるいは妹)
という四者が登場する。
この四者の間では、まず3母親と4姉あるいは妹との間では、それぞれのたらいの間で水を移し替える、という、別々に異なりながらも媒介項(この場合は水)を介してひとつにつながる=同じになるという、結合(過度な結合)の動きがある。その一方で、男性である夢見者はその母と姉妹との間に繰り広げられる光景を近く(付かず離れずの位置で)眺めていたのであるが、父親によってその場から追い出される、つまり分離される(過度な分離)。
父 / 母
↑ ↓
分離 / 結合
↓ ↑
夢見者 / 姉妹
この神話では親子兄弟という、異なりながらも同じ、同じでありながら異なるという、非同非異がぎゅっと一点に集まったような、(過度に)ひとつに結合した四者の間で「分離」ということと「結合」ということとの分離と結合が動き始めている。
ここで四者は、ある部分では分離しつつ、また別の部分では結合する、というぐあいに、おそらく円にきれいに接する正方形を描く位置に収まることを目指そうと、動き回っている。

自我と自己、個性化
この夢において、「夢見者」のことを「自我」と呼ぶ。いわゆる私である。
父に訳がわからないまま怒られ追われる「私」。
母と妹が女性たちだけで行っていることをよくわからないままじっと眺めている「私」。
これに対して「自己」とは、ここに登場する自我以外の三者、母と妹と父の間で、自我が、つかず離れずの安定した距離を保つことができるようになっている状態(つまり曼荼羅の円の中に(外)に正方形が描かれた状態を)であり、ユングはこれを「自己」という。
「自己」は四つに分かれつつひとつにつながり、その四極のうちの一つが「自我」なのである。ユングはこのように「自我」と「自己」という言葉を使い分ける。
*
この夢にあるように、自我と、自我に対立しつつも結びついている非-自我たちとの関係は、ある二項関係においては過度な分離に向かい、またある二項の関係においては過度な結合に向かう、というように激しく脈動し、大きな振幅を描いており、つまり縦に潰れて伸びたり、横に潰れて伸びたりと、美しい正方形の曼荼羅を描くことができない場合がある。
この「私-ではない」者たちとの過度な分離や過度な結合の急転換は、「私-ではない-ではない」である「私」の存在をおぼつかないものにしてしまう。
しかし、もし仮に、自我をその一極として安定的に切り出すことができる綺麗な円の中に収まった正方形を描く位置に、私-ではない、ものたちが互い分離しつつ結合し、付かず離れずおさまるとき、「自我」は安定することができる。このような状態がユングのいう「個性化」である。
生/死のどちらか一方にとどまらない
ユングは次のように書いている。
人間はディオスクーロイのペアーのようなものであって、半分は死すべき部分であるが、半分は不死なのである。二つの部分はつねに一緒にいるが、しかしけっして完全には一つにすることができない。変容過程とはその両者をたがいに近づけようとするものであるが、しかし意識はそれに対して抵抗を感ずるものである。なぜならその他者ははじめは異質で不気味に感じられるからであり、またわれわれは自分の家のなかのたった一人の主人ではないという考えに慣れていないからである。
現に生きている「私」にとって、最大最強の「非-私」とは、ひとつには「死んでしまった私」あるいは「私の死」である。私は「私の死」と常に一緒に、ともにいる。しかしまだ生きている限りそれと「完全に一つ」(過度に結合する)になることはできない。完全に一つになってしまっては「私」は「私-ではない-でなない」こととして区切り出されることがなくなってしまうからである。生きた私を生きた私として保ったまま死ぬことはできないのである。また一方で、生きている「私」は死と過度に分離しようとしても、それは叶わない(どこまで逃げても、決して切れることのない輪ゴムを伸ばすようなものである)。
ここで「変容過程」を通じて個性化が進む時、つまり生きた私が私の死ともまた親しく近づきつつ、しかしはっきりと分かれている状態に入ることができるとき、わたしたちは、生/死の分別もまた分別、そのように分けるから分かれたのだと知ることができる。
そのとき人は生きている私が、生でもなく死でもない「全体性」において、仮に、束の間「私ーではないーではない」として示現=限定されているのだということを知って、この全体性が脈動してマンダラ状に二項対立関係の対立関係の対立関係を浮かび上がらせ、その一極につどつどの「自我」が現れては消えていることそれ自体を慈しむことができるようになるはずである。
そしてここに生/死の分別を、分別するでもなく分別しないでもない、という境地がありありと「予感」されるようになる。
変容のさいに現われる不死の予感は、無意識の固有の性質と関係している。すなわち無意識にはどこか時空を超越したところがある。そのことの経験的な証拠として、いわゆるテレパシー現象がある。 この現象についてはたしかに依然として行きすぎた疑いがかけられているが、しかしじっさいには一般に考えられているよりはるかに頻繁に現われている。不死の予感は時空が広がるという特有の感覚に基づいているように思われる。私にはまた秘教の神化の儀式がちょうどこの心的現象の投影であるように思われる。
しかし、このような境地に達するのは難しい。
自我は、「私」という「意識」は、私の死に「抵抗を感じ」、「異質」さを感じ、私の死を「不気味」に思う。
なによりも自我は、「われわれは自分の家のなかのたった一人の主人ではないという考えに慣れていない」のである。つまり「自分の家」(自己)が、「自我」ひとりの独居世帯ではなく、実は「自我」以外に最小であと三人の同居者がいること(つまり、非-自我と、自我が常に自我であり非-自我は常に自我ではないということを可能にする「選ばれる方」と「選ばれない方」の対立二項)。しかも、同居人が三人いると言っても、それが床下や壁の中や天井裏に隠れているような具合に不気味に恐ろしげに居ることを、端的にゾッとするほど受け入れ難いと思ってしまうのである。
*
夢では、いきなり四者が一堂に会することはない。
夢は繰り返し、何ヶ月も、何年も、何十年もかけてみられているうちに、最初は「自我」(夢見手)だけがウロウロしていたところから、非-自我としてのアニマやアニムス(男性の場合は自己の中に潜む女性性:アニマ、女性の場合なら自己の中に潜む男性性:アニムス)との出会い、対立、過度な分離や過度な結合と、その両極の間での振れ幅を描く動きとしての二者関係が出てくる。

そこにさらに、この自我と第一の非-自我との間を取り持って、付かず離れずに媒介する第三の存在が登場する。
さらに、その第三の存在もそれ自体として即自的に存在することはできないため、第三の存在をそれとして”それではないところ”から区切り出す際に必然的に反対側に区切り出された第四の存在も、次第に姿を現す。
そしてうまくいけば私が、この自我が、表層の意識が生きているうちに、四者のうちのどこかだけが過度に結合するでもなく過度に分離するでもない円の外側(内側)に接する正方形を描くように均等に配置される「自己」をみることができるようになることもある。
非-自我は友でもなく敵でもなく
上の引用に続けて、ユングは次のように書いている。
われわれは、つねにただ自我であって、それ以外のものではないというほうを好む。しかしわれわれは内なる友や敵と対決しているのであって、それが友となるか敵となるかはわれわれしだいなのである。
非-自我たちを、自己という円形競技場の中で「敵」として、過度に分離しようと逃げ回ったり、過度に結合しようと追いかけ回したりしながら生きるのか、それとも「友」として、つかず離れずに分離しつつ結合する均衡状態のマンダラを描くのか、それは「われわれしだい」である。
* *
「われわれしだい」といっても、その「われわれ」は、孤立した「自我」が何か意識的に努力する、といったことを超えている。この非-自我と、非-非-自我と、選ばれる方と選ばれない方を均等に分離しつつ結合するマンダラを描くのは、半分は無意識の過程である。
この無意識が対立関係の対立関係の対立関係を分けつつ繋ぎ調和させるように自ずから動く動きを妨げず、自由に動き回らせること、私たちの無意識が祖先から受け継いだ動き方の癖が妨げられることなく自在に躍動することができるようにしておくことが重要である。
ちなみに、この無意識が自ずから動く対立の対立の対立としての八項関係を描く動きこそ、クロード・レヴィ=ストロース氏がひろく南北アメリカからユーラシア、オーストラリア先住民にまで、言語や文化や宗教の違いを超えて共通する「構造」として取り出した神話の語りを生み出す野生の思考の論理と異なるものではない。野生の思考の神話論理も、このユングのいう元型とおなじこと(対立関係の対立関係の対立関係を分けつつ繋ぎ調和させる)を別の資料、別のアングルから捉えたものであると読める。
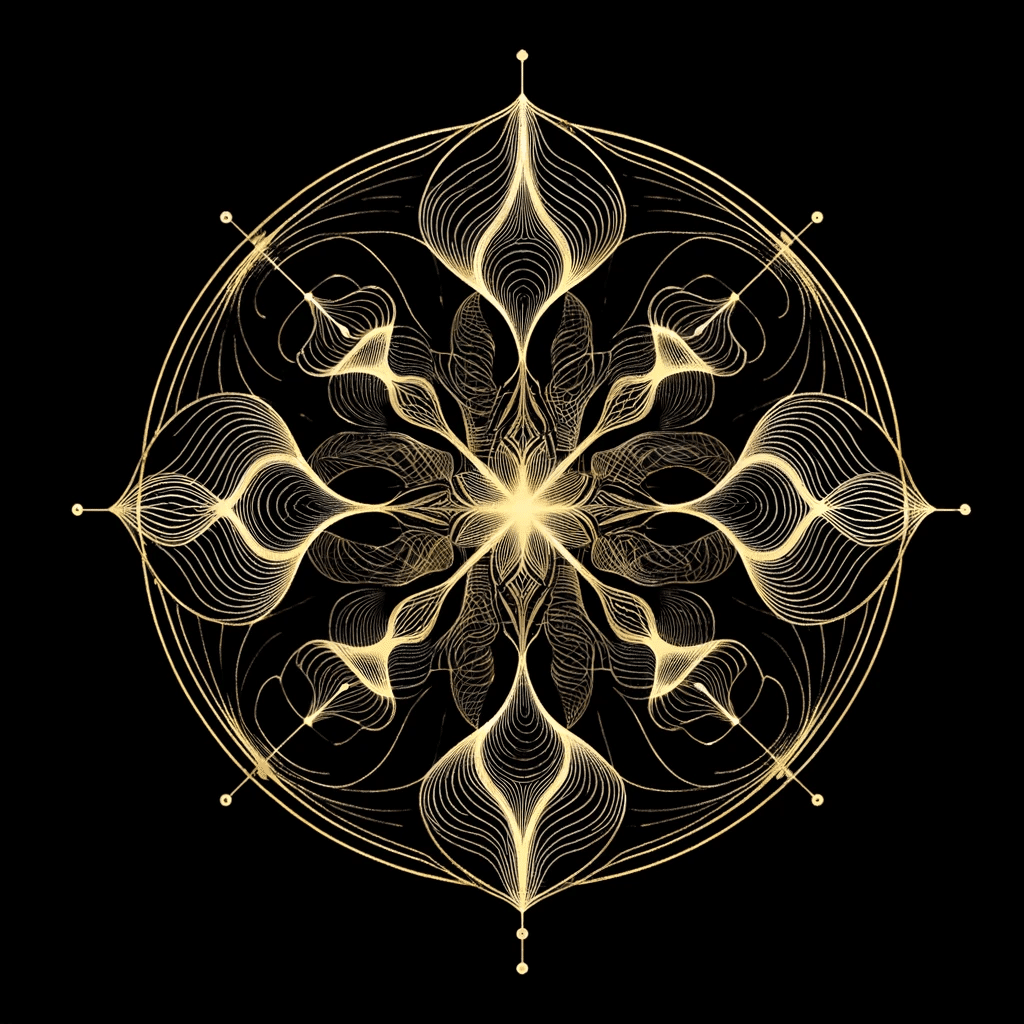
*
言葉を聞いて、無意識にマンダラ状の振動を引き起こす
ユングもまた、患者の夢にとどまらず、さまざまな神話や宗教の言説を参照し、そこに対立関係の対立関係の対立関係を分けつつ繋ぎ調和させる分離と結合の分離と結合の調停を読み取っていく。例えば下記に引用する「変容過程を示す一連のシンボルの例」という節では、イスラムのコーランの言葉や、ミトラ信仰のビジュアルや、錬金術の思考を縦横に引きつつ、そこに共通するマンダラを描こうとする動きをとらえていく。
洞窟は生まれ変わりの場所、秘密の空間であって、そこに閉じ込められると、卵のように抱かれて暖められ、新しく生まれることができる。洞窟についてコーランはつぎのように述べている。「汝は、彼ら(眠っている人々)が広々とした中央に止まっていると、なんと太陽が昇るときは洞窟を避けて右側を通り沈むときは左側を通るのを見るであろう。」「中央」とは宝玉の置かれている中心であって、抱卵または供儀すなわち変容の起こる場所である。 このシンボル体系のもっともすばらしい発達は、ミトラ教の祭壇画と、つねに太陽と月のあいだに現われる変容物質についての錬金術の描写のなかに見られる。
「卵」を抱く「洞窟」という中央の空間があり、その両側に左/右が分節される。左右は「太陽」がめぐることによって分かれつつも一つのことの二つの側面として結び付けられる。
そしてユングは、洞窟を「変容の場」とする儀式が、北米先住民のナヴァホ族にも見られることを指摘する。ナヴァホの儀式では洞窟中に「七人」の人が入り込み、眠り、変容を体験するという。これについてユングは次のように書く。
眠っていた人々の数が七であったということは、七という数が聖なる数字であることによって、彼らが神であることを暗示している。この神々は眠っているうちに変容し、それによって永遠の若さを 得る。このことを確認することによって、われわれはここで語られているのが秘儀であるということを、あらかじめ知ることができる。ここで語られているヌミノースな人物たちの運命は、聞く者の心を捕らえる。というのはここに描かれているのが、聞く者の無意識のなかにある同じような現象を表現しており、それによってその現象をふたたび意識に統合するからである。
洞窟の中に、自我以外の七人の神々が集まり、眠る。
この七人に、この語りを聞く者の自我を加えると、ちょうど自我をその一極に収めた四項関係と、その四項関係を分けつつつなぐ四両義的媒介項からなる八項関係になる。
*
そしてこのような語り、神話的な語りを聞くということだけで、その聞き手は知らず知らずのうちに自分の「無意識」で生じている、表層に対する深層で生じている過程の微振動を励起され、それを意識化(言語化)することができるようになる。
さらにユングは、縦横無尽に宗教の言説に登場する二項対立関係を分離しつつ結合する両義的媒介項たちの振幅を描く動きとその媒介項自体の変容を軽快な筆致で描き出していく。
彼らが食べようとした魚は無意識の内容であって、それは根源にまで戻ってそれとの結びつきを 回復させてくれるものである。魚は生まれ変わった者であり、新しい生に目覚めた者である。このことが起こったのは、注釈が述べているように、生命の水に触れたからである。魚は海のなかへ滑りこむことによって、ふたたび無意識の内容になり、その子孫は一つの目と半分の頭しか持たないという特徴をもっている。
「錬金術も同じように海のなかの珍しい魚を知っている。すなわち「骨も皮もない丸い魚」であり、 それは「丸い元素」、「生きた石」・《哲学者の息子》・の胚芽である。生命の水は錬金術の《永遠の水》に当たる。この水は《生気を与える者》として讃えられ、そのうえにすべての固体を溶かし、す べての液体を固させる性質を持つ。コーランの注釈が述べているように、魚が消え去ったところの 海は堅い大地となり、そこには今でも魚の痕跡を認めることができる。その島には、その中心の場所 には、今ではハディールが坐っているのであろう。ある神秘家の解釈によれば、彼は「上の海と下の海のあいだの、光でできた増(玉座)に」、つまり中心の位置に坐っている。彼の出現は魚が消え去ったこととひそかな関係を持っているようである。というより彼自身が魚であるかのように見える。 この推定は、注釈が生命の源泉を暗闇の場所に置いていることと符合している。すなわち海の底は暗いのである。この暗闇は錬金術のニグレドに当たるものである。ニグレドとは、女性 的なものが男性的なものを自らのうちに受け入れた、《結合》のあとに現われるものであ。ニグレドからは「石」が、不死なる自己のシンボルが、生ずる。しかもその最初の出現は「魚の目」に喩えられる。
この「魚」という両義的媒介項が、その動き回る後に上/下、水/陸、そして生/死、自/他などの経験的分別を区切り出していく様に注目したい。
無意識で、つまり表層の意識に対立する限りでの深層の意識の中を動き回る「魚」(と、表層の意識には射影されるなにか)のことを思う。
あるいはこの魚が動き回ることで、上/下などと同様に
意識 / 無意識
この対立関係も姿をあらわす。
すなわち魚とは、無意識的内容の「『養分を与えるような」影響力であって、それが、自分のエネルギーを自分では作れなくなっている意識の生命活動の絶えざるエネルギーの流れを維持してくれるのである。この変容の力をもったものが、意識のあの見栄えのしない、ほとんど見えない(無意識の)根であって、そこから意識に対してあらゆる力が流れ込むのである。無意識は何か異様なものとして、非自我として感じられるので、それが何か異様な姿で表現されるのもまったく当然である。 それはたしかに一面では無意味きわまりないものであるが、しかし他面ではそれが意識に欠けている「丸い」全体性を《潜在的には》含んでいるという意味では、重要きわまりないものである。「丸い」ものとはもともとは無意識の洞窟のなかに隠されていたあの大いなる宝物であり、それを擬人化したものこそ、意識と無意識の高次の統一をなす人格的存在なのである。
意識と無意識が分かれつつも一つにつながり、調和したつかずはなれずの関係を保てるようになるために、おそらくある種のパターンを描く「魚」の、「魚たち」の泳ぎ回り方が必要であり、その泳ぎが水面に浮かび上がらせる波紋のパターンは、マンダラ状になるのである。

このユングの記述を読んでいると、改めて、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で描き出す神話の論理の動きが、二重の四項関係=八項関係としての「マンダラ」を浮かび上がらせるものであることに気付かされる。
つづく
関連記事
関連文献
*
いいなと思ったら応援しよう!

