
コミュニケーションの"失敗"が役に立つとき / 誤解された言葉・バレない嘘・バレる嘘・空耳 -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(38_『神話論理2 蜜から灰へ』-12)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第38回目です。いまは第二巻『蜜から灰へ』を読んでいるところです。
これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

この一連の記事では、レヴィ=ストロース氏の神話論理を”創造的に誤読”しながら次のようなことを考えている。則ち、神話的思考(野生の思考)とは、Δ1とΔ2の対立と、Δ3とΔ4の対立という二つの対立が”異なるが同じ”ものとして結合すると言うために、β1からβ4までの四つのβ項を、いずれかの二つのΔの間にその二つの”どちらでもあってどちらでもない両義的な項”として析出し、この四つのβと四つのΔを図1に描いた八葉の形を描くようにシンタグマ軸上に繋いでいく=言い換えていくことなのではないだろうか、と。
そういう意味では…
*
わたしたちが言葉を聞いたり喋ったりしていると、
しばしば「そういう意味ではない」ということがある。
これを書いているわたしも、どちらかというと言葉は字面通り受け取る方なので、例えば次のようなことがある。
わたし:「恐縮です。定時なので帰らせていただきます」
上司 :「まだ皆仕事していますよ。協調性のない方は帰ってください」
わたし:「帰って”ください”!ご丁寧に恐縮です。ではまた明日。」
上司 :「そういう意味ではない!」
私たちの言葉は、(1)"字面通りの意味"と(2)「そうじゃない」"本当の意味"のようなことの狭間で揺れ動いている。「本音と建前」なんて言葉も、あるいは「ほめごろし」とか「慇懃無礼」とか「無言の指導」とか「空気を読む」とか「言われなくてもわかるよね」なんてのもある。そして昨今の「コミュ障」などというのも、誰かの言葉をこの(1)と(2)のどちらで聞くのかという問題なのだろう。
字面通りの意味 / 本当の意味
言葉を発しておきながら字面通りの意味で受け取るのではなく「隠れた本当の意味、本心をお察しください」というのはそれこそ集団的な「コミュ障」のような気もするが…などというとそれこそ「コミュ障」だと言われそうであるが、いまはどちらでもよい。大事なことはこれである。
言葉は、話者の意図とは異なった意味で解釈されることが多々ある。
同じ言葉でも、話し手と聞き手の間で、意味がずれる
話者が思っている「正しい意味」が、思うように通じない。
この事実は神話の昔から変わらない。
通じなさをおもしろがる
この「通じなさ」に顔を顰めるのではなく、むしろ「通じなさ」をおもしろがるくらいが、旧石器時代から地球上の至る所でサバイバルしてきた人類の祖先たちの知恵だったのかもしれない。
レヴィ=ストロース氏は『神話論理2 蜜から灰へ』に次のように書いている。
「今日わたしたちは、言葉の特性は不連続性であることを知っている。しかし神話の思考は、そのようには考えていなかった。注目すべきは、南アメリカのインディアンは、言葉の可塑性を楽しむということである。あちこちに男性と女性の方言がある。たとえばナンビクワラの女性は、好んで言葉の形を変えて解りにくくし、明瞭な話し方より、マツィゲンガの植物の言葉のように、聞き取りにくい話し方をする。[…]」
言葉の可塑性を楽しむ。
言葉を柔らかくして、その固まったようにみえる形を変えて「解りにくく」する。その解りにくさが「言葉には可塑性があるのだ」ということを思い知らせる。あえて不明瞭で「聞き取りにくい話し方」をしては、お互いにおもしろがる。
不連続性に支配されたΔ線形配列を、グニャリと捻り曲げて、β振動状態に励起する。
通じることを前提とするのではなく、通じないことを前提とする。
言葉の「通じなさ」を仲間と確認しあうようなコミュニケーション。
わたしもそうだが、人間、そうそうよくは聞いていないし、読んでもいない。そして十分に語ることも、書くことも、うまくできない。「通じるはずだ、わかってくれるはずだ」とか「言われなくても分かっているべきだ」といった話は、少々人類に期待しすぎではないかとも思う。
「たぶん、通じないよな」と思いつつ、しかし諦めることなく、絶望することもなく、もちろん期待することもなく、「通じないと思うけど、いや、そもそも聞いていないと思うけれど、いちおう言っておく」という感じで言葉を発する。発し続ける。それで相手がぷいとどこかにいなくなってしまったとしても、それもまたヨシ。
◇
言葉の意味というのは、決定済みに固まったものではなく、常に動いている。動いている動かざるを得ないことに、止まることを要求しても、苦しむばかりという話である。
言葉の意味が定まらず、意味が揺れることを厭う必要はない。
ブレるとか、揺らぐとか、決まらない、などと言うと、この効率重視の現代世界では「よくないこと」の側に振り分けて固定されがちだが、それもまた一つの「そういう分けて振り分ける仕方もありますね」という話以上ではない。
言葉をもっと揺らす。
その揺れる振動から、波紋状に
あれこれの意味を、意味分節システムを、
自在に発生させてこそおもしろい??
今回取り上げるのはそういう話である。
* *
「雨が降るとよく眠れる」
レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』p.320に掲載された神話M278をみてみよう。
あるところにひとりの男が妻と暮らしていた。
妻の二人の兄弟も、一緒の小屋に暮らしていた。
ある日、雨が降りそうな雲がでると、男はうれしそうに言った。
「雨が降ると、いつもよく眠れる」
そう言って男は小屋の中につったハンモックで眠り始めた。
雨が降ってきた。
妻は、夫が気に入るようにと、兄弟に手伝わせて、夫を縄で縛った。
そして、雨が降る小屋の外に出した。
夫は一晩中雨ざらしにされた。
M278より
主人公の男は「雨が降るとよく眠れる」と言った。
男は、雨の夜が好きなのである。しかし、雨の夜が好きだからと言って、それは何も”雨が降り頻るなかで、雨に打たれながら、雨ざらしになりながら眠りたい"という意味ではない。
雨が好きだというのは、雨が降る(ことによって外が涼しく、程よい湿度になって、屋根に当たる雨音も耳に心地よく、だから家のなかでぐっすり)とよく眠れる、ということを、あいだの( )の中身を、文頭の「雨がふる」にまとめて(こういうのも比喩の技法の一つである)いるのである。
*
ところが!!
妻と妻の兄弟たちは、この夫の「雨が降るとよく眠れる」を文字通りに、字面通りに、受け取った。
そして、そんなに雨で寝るのが好きなら、大好きな雨の中に放り込んであげましょう、と、夫(兄弟たちからみれば義理の兄)をわざわざ縛り上げて、外に放り出し、一晩中雨ざらしにする!

夫の立場からすれば、とんでもない誤解である。
ここで妻は、心の底から夫に良かれと思って縛り上げて雨ざらしにしたのか、それとも恨みや憎しみに基づいて酷い目に合わせてやろうとしたのか。それはよくわからない、というかどちらでも大した違いはない。
ここで問題になっているのは文字通りの意味 / 比喩的な意味 の対立である。比喩的な意味で受け取られることを期待された言葉が、文字通りの意味で受け取られるという誤解。前回の記事でも触れたが、あまり親しくない者同士が言葉でコミュニケーションすると、しばしば言葉は文字通り、字面通りの意味しか伝達できず、比喩的な意味をともに楽しむようなことができなくなる。
数年前の音声AI、
「アレ○サ、私は雨が好きです」
「アマ◯ンでameXXXが見つかりました、いますぐ購入しますか?」
「はい??ええ???」
「注文しました。明日到着予定です。」
というような感じである。
この「誤解」がこの神話の第一番目の極端な言葉である。
* *
続きをみてみよう。
一晩中雨ざらしにされた夫の運命やいかに?!
雨ざらしの男は夜明けに目を覚ますと、自分の置かれた状況に驚愕したが、
平静を装って 「よく眠れた、縄と解いてくれ」と妻に言った。
男は内心、怒り狂っていたが、怒りを隠した。
*
そし仕返しがはじまる。
雨ざらしの夫は「ワニ漁に行こう」と妻を誘い出し、妻に命じてワニの燻製を作るためと称して大きな調理台と燻し用の木を用意させた。そして料理の用意が終わるや否や、ワニではなく、妻を捕まえて調理台に載せ燻製にしてしまった!
*
妻の二人の兄弟たちは、事態を知り、怒り、義兄を捕まえようとした。
しかし雨ざらしの夫はすでに村から遠くへ、カヌーに乗って逃げたあとだった。逃げる時、雨ざらし夫は他のカヌーの舫い綱をすべて解いておいた。
義理の兄弟たちはなんとか一艘のカヌーを用意して、追いかけた。
追いつかれた雨ざらしの夫は、カヌーから地面へ飛び移り、地面から木へ昇り、叫び始めた。義理の兄弟たちが捕まえようとしたときにはもう雨ざらしの夫はもうホウカンチョウという鳥の一種に変身していた。
いまでもホウカンチョウの鳴き声は
「妹はここだ」と言っているように聞こえる。
M278より
怒りを隠し、平静を装って喋る ー嘘をつく
まず、内心は怒っているのに、言葉や態度に怒りを表さない、というところに注目しよう。怒りを隠して、平静をよそおって喋っている。この時の「よく眠れた、縄と解いてくれ」という冷静な言葉は”字面通り"ではない。これから始まる復讐を用意周到に進めるために、あたかも妻たちに対して敵意がないかのように嘘をついている。
顔はニコニコ笑って、実は怒っていました
顔で笑って、心で怒り狂って
というのはよくある話だが、それである。
「よく眠れた、縄と解いてくれ」
と、雨ざらしの夫が言う時、夫においてはこの言葉は怒りと復讐心に結びつきながら、それを覆い隠すものである。一方、これを聞く妻にとっては平穏な日常の言葉である。同じ言葉が、一方では「嘘」であり、他方で「非-嘘」である。そしてこの嘘は、嘘だとバレていない。
この「バレない嘘」がこの神話の第二番目の極端な言葉である。
嘘、騙し騙される言葉は、因幡の白兎がワニを騙している最中ように、嘘(うさぎにとっては嘘)と本当(ワニにとっては本当)という対立する両極のどちらでもあるという点で、先ほど「よく眠れた、縄と解いてくれ」と同じくβ振動状態に入っている。

嘘を重ねる
バレない嘘はさらに続く。
「ワニを調理するから燻製台を用意してくれ」というバレない嘘である。この嘘が、妻に自分用の燻製台を用意させるというとんでもないくだりに展開する。ここでなぜ燻製なのかといえば、それはこれが神話だからである。
夫が雨ざらしにされたのだから、妻は煙で燻されないといけない。
夫は、妻の言葉で、上から下へ落ちる雨に全身をこれでもかと曝された。
妻は、夫の言葉で、下から上へ上がる「煙(火)」に、これでもかと曝される。
夫 / 妻
||
上から下へ / 下から上へ
||
天の水 / 地上の火(煙)
話の中身は命に関わるとんでもないことばかりだが、そこは一旦脇に置いておいて、四項関係だけを見てみると、綺麗に真逆に対立している様子が見事である。
*
ここで思い出すのは日本の民話「かちかち山」である。「嘘」つきのタヌキ(嘘で老婆を油断させて酷い目に遭わせる)が火で炙られたかと思えば水没させられる。これも人間の老夫婦と過度に接近結合し人間の生業を崩壊させかけているタヌキ=”人間とも動物ともつかないβタヌキ”を、その励起された振動状態から確定的分離状態へと転換する話になっている。
* *
バラされる嘘
さらにショッキングなので上の要約には詳しく書かなかったが、ここに第三の嘘が続く。雨ざらしの夫は、燻製になった妻の肉を「これはワニの肉ですよ」と言って、妻の兄弟たちに食べさせてしまう!
雨ざらし夫の嘘に騙されて義理の兄弟たちは「燻製肉」を食べてしまう。
つまりワニの肉だと思って妹を食べてしまう。
ここにも第三の「嘘」が、嘘と本当の両極のあいだで振動する言葉がある。妻の兄弟たちにとって「燻製肉」という意味するもので、「ワニ肉」が意味されるはずであったが、しかし…ということである。文字通りならワニの肉であるが、実はこの場合の「ワニ肉」は、ワニ肉ではないものを代わりに象徴している。
そしてこの嘘は、雨ざらしの夫自身によって嘘であると暴かれる。雨ざらしの夫は、義理の兄弟たちに、彼らが食べた肉がワニのものではなく、本当は何であるかを、わざわざ教えるのである。
とんでもない復讐である。
この「バラされた嘘」がこの神話の第三番目の極端な言葉である。
ソラミミ
そして神話はクライマックスへ向かう。
雨ざらしの夫と、義理の兄弟たちが、カヌーで追いかけっこをする。
逃げる雨ざらし夫と、追う義兄弟。
二艘のカヌーは遠かったり、近づいたり。両者の距離は伸びたち縮んだりする。これぞβ脈動。
水面に浮かび水平方向に移動するカヌーは、上/下の中間であり、水平軸のあちら/こちら(遠/近)の中間であり、神話ではよく使われる両義的媒介項である。その両義的なβカヌーが二艘セットになって、遠く分離したり、近く接近したり、その間の距離を伸び縮みさせる振動を描くように動く。
そうして追うカヌーが逃げるカヌーに追いつくと、つまり二つのβ項が最終的に過度に結合し、その結合状態が固定されると、β脈動は止まり、Δ四項関係の分離が始まる。
ただし、カヌーが追いついただけではまだ二つのβ項が処理されただけであり、残りの二つのβ項の結合または分離の固定化も必要になる。
ここでこの神話が選ぶのは、雨ざらしの夫がカヌーを降り(カヌーとの結合状態から分離し)、木に登る(義兄弟を含む人間たちが生きる地上界から分離する)という猿かに合戦ー鳥の巣あさり式の分離を固定化する動きである。
β雨ざらしの夫とβ義理の兄弟たちとの分離が決定されたことで、β雨ざらし夫は「Δ鳥(ホウカンチョウ)」に変身する。そして義理の兄弟たちは、Δ「今日に続く人間(鳥の声を聞く者)」に変身する。鳴く鳥と、その声を聞く人間との関係は、Δ的に、安定的固定的定常的に、今日でも私たちの生きる世界の一部を秩序づけている。
*
さて、このホウカンチョウの鳴き声に注目しよう。
ホウカンチョウの声は「妹はここだ」と言っているように聞こえるという。日本にもブッポウソウ(仏法僧)とか「ホケキョウ(法華経)」とかいう鳥がいるが、鳥の鳴き声が、人間の言葉のように聞こえるという現象がある。
この場合、鳥の鳴き声は、それを耳にする人間にとっては明らかに「意味があるもの」として聞こえるが、しかしそれを発声しているのは「鳥」であり「人間」ではなく、つまりその音声には本当は(鳥にとっては)「(人間が聞き取っているような)意味はない」ということを人間たちはよく知った上で、その「空耳」を楽しむのである。
この「空耳」がこの神話の第四番目の極端な言葉である。
人間の言葉のように聞こえる鳥の鳴き声
||
人間 / 鳥
意味内容がある / 意味内容がない
空耳を楽しめるというのは、言語の可塑性を楽しむことができる人間の智慧である。
1)「意味するもの(signifiant)」があって、「意味されること(signifié)」がひとつに定まってある。これが通常の「意味内容がある(意味を確定できる)」字面通りの言葉である。
2)「意味するもの(signifiant)」があるのに、「意味されること(signifié)」が定まらない(あるともないともわからなくなる)。
通常1)のような姿をしている言葉を、強いて2)の状態にする。これは言葉を「悪用」することにみえるかもしれないが、実は2)こそが、1)を可能にする条件なのだということを、学ばなければならないというのがこの神話のメッセージなのかもしれない。
四つのβ振動状態
この神話には四つの奇妙な言葉が出てくる。
「雨が降るとよく眠れる」
→字面通りの意味で言われたのではないのに、字面通りの意味で聞き取られた言葉(誤解された言葉)「よく眠れたから縄を解いてくれ」〜「ワニ用の燻製台を用意してくれ」
→嘘でありながら、騙すことに成功した言葉「これはワニの肉である」
→嘘であり、その嘘がバレて騙すことの失敗した言葉「妹はここだ」と聞こえるホウカンチョウの声
→字面通りの意味で言われているのに、字面通りの意味で聞き取られない言葉(誤解され”ない”言葉):…人間はそれを鳥の声の空耳だと知っている
1.と4.が、2.と3.が、きれいに真逆に対立しているのがおもしろい。
四つの奇妙な言葉、Δ二項対立に対してβ振動状態に入っている言葉が、四つ順番に登場して、ぐるりと一巡する。

この四つのβ振動状態の言葉を順番に並べて、互いを分離しつつ結びつけるのが主人公たちの動きである。
最初に、義兄弟と同居している雨ざらしの夫とその妻は、すでにβ振動状態に入っている。この夫婦は二つの氏族という経験的で感覚的なΔ二項の対立に対して、そのどちらか一方に固定できない曖昧さのもとにある。
このβ夫とβ妻が区別できないほどに過度に結合した状態が、二つの振動状態にある言葉「雨が降るとよく眠れる」と「よく眠れたから縄を解いてくれ」〜「ワニ用の燻製台を用意してくれ」によって過度に分離される。
その分離は「天からの水に雨ざらし」と「地からの煙(火)に炙られる」という、垂直軸方向の上から下へ、下から上への逆向きのふたつの動きが描くβ二極間の一方通行の移動によって果たされる。
さらに、主人公と義兄弟の過度な結合が、水平方向と垂直方向それぞれでのΔ分離によって切られる。そうして人間の言葉のように聞こえるが”言語的意味のない自然音”の極に固定されている鳥の鳴き声というΔ項が確定する。この人間の声の様に聞こえるが人間の声ではない鳥の鳴き声こそが、それと対立する限りのものとして、通常の人間の意味ある言葉というものを分節化する。

* *
この神話の「字面通り」の内容は、もしこれが「客観的事実」だとしたらとんでもないことであるが、神話は事実の報告ではない。
現代の効率化された社会では、言葉は事実報告のためのツールのようなものに化けているが、神話の言葉は、事実と非-事実のようなことを区別し、語られることと語られないことを区別する、この区別しながらも重ね合わせるということを自在に組み替えることが人類には可能なのだということただ一点を、教えようとしている。
事実について報告するような一義的な言葉というのは、その区別しながら重ね合わせる、分離しながら結合し結合しながら分離する、神話的の思考にも現れているような、二重の四項関係として記述される意味分節の最小構成単位がぐるりと動いた後に、はじめて使えるようになる。
二重の四項関係は、言語をアクティベートする。
あるいは
二重の四項関係は、言語のブートストラップである。
そのための素材として、ブリコラージュに適した、つまり神話の語りを聞くさまざまな人が、その経験的身体的感覚的日常的な分節の業(カルマ)的な記憶の中で「あ〜ありえるなあ〜」と感じられる対立関係として、なにを借りてくるかである。


対立関係でブリコラージュ(日曜大工)
日曜大工。ブリコラージュ。
よい言葉だと思う。
例えば、日曜大工で、玄関のドアが壊れたのを直すとしよう。
材料はない。
納戸をみると、「脚が折れて壊れたテーブル」があるとしよう。
そのテーブルから脚を切り落として、ただの板のようなものにして、玄関に立てかけ、うまく蝶番をつけてドアの代わりにしたとしよう。
こういうのがブリコラージュである。
このブリコラ・テーブル=ドアに対して、
「それって、あなたのテーブルですよね?」
ということもできる。
そのように言われればその通りである。
はい、テーブルです。
しかし、もしそこに「おい、ここにテーブルがあるぞ」と熱々のおでんが詰まった土鍋を持ってきて、垂直に起立するドアに対して(重力方向に対して)90度に”置こう”としている人がいたならば、わたしなら、止める。
いや、止めないかもしれない。
「アインシュタインによれば重力とは…」とボソっと青い鳥のように囁いてみるかもしれない。
いや、やはり、止める、止めるそぶりは見せる。
あるいは「止めようとしたが、間に合わなかった」という言葉を用意する。
もちろん、止めようとしたのは嘘である。
いや、嘘ではない。字面通りなら、そのとおりである。

何をどういうにせよ、神話の論理は、二重の四項関係は、とても美しい。
この美しさが、「意味するもの/意味されること」「上/下」「落下/上昇」「近づく/遠ざかる」のような経験的に極めて基本的な二項対立の重畳した連鎖を、はるか振動状態に転換した後でないと見えてこないのだとしたら。
そしてこの美しさが見える前までは、言葉が「私」を縛り付け閉じ込める牢獄のようなものに見えてしまうのだとしたら。
例えば、ある社会が、個々人の人生の節目の通過儀礼で、神話の語りを耳に注ぎ込まれる時間というものを用意している場合、それは大変に価値のあることだっただろう。
いま、この日常から、神話の言葉たちはどこにいったのか。
なくなってしまったわけではない。
やりようによっては私たちは美しい世界を常に念頭に置きながら、身体的に分節が切り固められた世界をもまた、そういうものとして通り過ぎていくことができるようになるのかもしれない。

ー文字通りの意味/比喩的な意味×意味するもの/意味されること
レヴィ=ストロース氏は『神話論理2 蜜から灰へ』第三部「八月は四旬節」の一節で、次のように書いている。
「先住民の思考法にあっては、蜂蜜という観念にありとあらゆる曖昧さが含まれている。まず自然状態で「料理できている」食べ物であり、ついで甘かったり酸っぱかったり、無毒であったり毒があったりして、そのうえ新鮮なままで食べたり、発酵させて食べたりする。」
1.料理されている/料理されていない
2.甘い/酸っぱい(刺激)
3.無毒/有毒
4.新鮮/発酵-腐敗
蜂蜜は、これら対立する二極のどちらでもあり、どちらでもなく、二極の中間であり、中間でない。蜂蜜はこれらの二極に対して曖昧、不可得な項で、二極の間をあちらへこちらへ振動している。
先ほどの図でいえば、蜂蜜は、上記1.〜4.の対立関係に対してその中間の「β」項の位置におさまりやすいということである。
二項対立関係を区切ったとして、そのどちらか一方の極に固まらない、ということが重要である。
「ダイヤモンドのように、たくさんのカットの面からさまざまな意味を放射しているこの物質(蜂蜜)は、同じように曖昧な、他のいろいろな物質に自らを反射させている。その物質は、あるときは、代わる代わる、男性であったり、女性であったり、食物を供給したり、死をもたらしたりするプレヤデス星団という星座であり、ある時は、悪臭のする母親オポッサムであり[…]」
この曖昧な「蜂蜜」は、ダイヤモンド、すなわち「金剛」のようである。
それが「意味を放射」し、その放射された意味が他のあれこれに「反射」し、また蜂蜜の方へと返ってくる。
そうして映すものが映されるものとなり、映されるものが映すものとなり、互いが互いを写し合う「インドラの網」のようになる。
そしてこの映しあう関係に入ったすべての項が「AではないがAでなくもない」という二極のどちらにも固定されない振動状態に励起される。
「蜂蜜の曖昧さを表現するのに、神話はいろいろな意味に対応する単語をつかうだけではない[…]。メタ言語的手段も使うのであって、固有名詞と普遍名詞、換喩と暗喩、隣接と類似、文字通りの意味と比喩的な意味の二重性をも使う。M278は、意味論のレベルと修辞法のレベルの接点になっている。文字通りの意味と比喩的な意味の取り違えが、はっきりと神話の登場人物のせいにされ、筋が展開する動機になっている。」
「単語をつかう」説明の仕方であると、仮にそれが「曖昧さ」についての説明であったとしても、「曖昧さとはΔ1であり、Δ1はΔ2であり、Δ2はΔ3である」式のΔ線形配列を容易に呼び出してしまう。そこから逃れるために、神話は蜂蜜の「曖昧さ」を、たとえば男と女、白と黒、のような単語と単語の対立関係の両極を行き来して表現する。
そしてそれでも振幅が際立たないとみたばあい「メタ言語的手段」にうったえる。上に紹介した神話にあるような、互いに異なる二つの言葉の曖昧さのあり方は、神話の思考が好んで選んでくるものである。二つの対立するメタ言語的手段の一方と他方が取り違えられるようなことによっても表現される。
固有名詞 / 普遍名詞
換喩 / 暗喩
隣接 / 類似
文字通りの意味 / 比喩的な意味
これらの対立する両極が鋭く真逆に対立しながら、一つに重なる、二重になる。そして先ほどの、誤解された言葉、バレない嘘、バラされる嘘、空耳もまた、これに連なる。
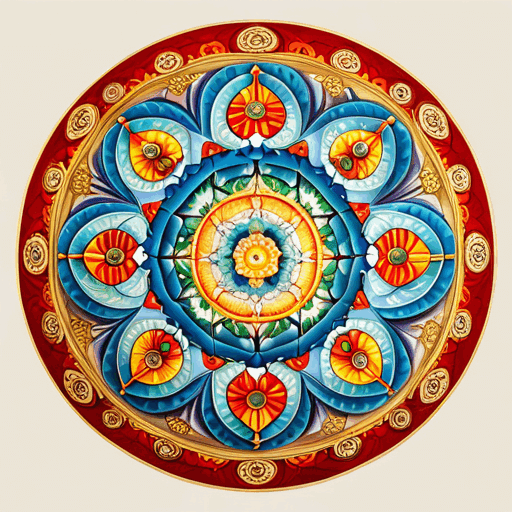
β四項関係で思考する
言葉にはその内部と外部があり、そしてこの内部と外部を境界領域において「分節された言葉以上」のコトバを動かし、分節のありとあらゆる可能性を、無分節とも分節ともどちらであるともはっきり分けることができない曖昧さのなかで試すこと。
そういう未顕現の可能性を試し続けるコトバは、いわばそれ自体がβ振動の干渉系となったコトバ、β言語であり、それはΔ四項関係を固める安定したコードとしての通常言葉・分節された言葉とは似て非なるものである。
神話は、経験的で感覚的な日常の言葉、その外観はΔ四項関係の固定したシステムと寸分違わぬ後たちを、並べて、過度に接近させて、過度に分離させて、分離させつつ結合させ、結合させつつ分離する。それによって距離の最大値と最小値の間の振幅を描く振動をΔの線形配列としての口から出て耳に聞こえる言葉でもってシミュレートしていく。
* *
β振動状態に励起された語で思考することで、人類は、人間は、「分節された言葉が伝えることのできなかった情報」に、いわば自在にアクセスできるようになる。
いうなれば、言葉を、前五識の桎梏から解き放つ。
言語は、事実の報告のためのだけの道具ではない。
これを徹底すると、それこそ「時間」や「空間」のようなコトバもまたβ振動状態に励起することができる。
時間や空間は、人間の言葉とは無関係に、それ自体としてあるだろう!と、言いたくなるところであるが、そこは理論物理学者の言葉に耳を傾けよう。
「現実は往々にして見かけとまるで違っている。地球は平らに見えるが、じつは丸い。太陽は空を巡っているように見えるが、回っているのはわたしたちのほうだ。そして時間の構造も見かけとは違い、一様で普遍的な流れではない。」
時間は全宇宙で同時に一様に流れているものではない。
単一の時間の流れの中の"現在の瞬間"に、地球や、地球から50億光年の彼方に見える星々が、それぞれ"同時"に”今ある”ということでははない。
時間は、全宇宙のどこでも同時に同じ時刻であるような単一の流れではない。
わたしたち一人一人が「今ここ」で、「現在」を「さっき」とは違うと感じているという意味での"時間"は"ある"。ただし、それが"ある"のは、太陽が私の上を移動しているように"見えている"のと同じようなことである。
つまりそれは「見かけ上」の姿であり、その見かけ上の姿が、世界の果て、宇宙の果てまでそのまま連続しているわけではない。
「「本物の時間」も存在しない。異なる時計が実際に指している二つの時間、互いに対して変化する二つの時間があるだけで、どちらが本物に近いわけでもない。」
宇宙の隅々まで均一単一に流れている時間が宇宙の至る所で同じ瞬間に、同じ時刻を全宇宙の全時計に表示するわけではない。
ちなみに、このカルロ・ロヴェッリ氏は別の『世界は関係でできている』という著作で、この理論物理学のアプローチを龍樹の中論にひきつけて論じている。
もしロヴェッリ氏が、空海の『吽字義』を読んだら…と思うと、おもしろいことを論じてくださりそうである。
* * *
それにしても。
時間も妄分別、空間も妄分別だとしたら。
現在とか、過去とか、未来とか。
こことか、そことか、近いとか遠いとか。
手が届く、届かない。
そのようなことの一切が、
「この」人間としての「この」身体×心×言葉だからこそ
「そのように分節されている」のだとすれば?
今ここと、例えば「宇宙の果て」のようなことは、区別してもよいし、区別しなくてもよい、ということになる。「今ここ」が虚妄で、影で、実在しない偽物だ、などという必要はない。あるとかないとか、本物とか偽物とか言うことからして分別であり、分節であり、区別であり、差別であり、ようするに分別の典型例である。
分別というのを、するかしないか、どちらか一方を選べ、という筋合いの話にしてはならない。分別はしても良いししなくても良い、したからといってどうと言うことはないが、しなかったからといってどうと言うこともない。すればよいし、しなくてもよい。
このことを忘れて、ある何かの分別することが区切り出した二項対立をまた別の二項対立と重ね合わせて、その重ね合わせの向きを変えてはいけない動かしてはいけない、とする。そうする二つに分けた二極のうちの一方に固まる。そこに妄分別が固まって執着ということがはじまる。
*
今ここと、はるか彼方の遠い遠い過去のようなことも、区別してもよいし、区別しなくてもよい。「今ここ」が、あるいは「遠い遠い過去」が、対立する二極のどちらでも構わないが、一方が虚妄だとか偽物だから価値がない、他方が真実で本物だから価値がある、という具合に分けて、振り分け先を固めるのが妄分別。
* *
もちろん、時間と空間が妄分別だとして、それは言語以前の、八識で言えば前五識からしてすでに相当強固に固まった鉄格子のような分節枠であり、それについて「分節しても、しなくてもよい」などというと、それこそ軽挙妄動と感じられるだろう。しかし、それで構わない。
重いも軽いもない。
そして妄分別などというと、なにやら悪いことのように意味分節されがちであるが、特に一方的に悪いということでもない。「衆生は総じて諸仏の現覚の法に迷へり」ともいうこともできる。

妄分別 / 正しい?分別
|| ||
ダメ / 良い
こういう具合の四項関係を固め続ける義理はない。
言葉は、ぽんと一言、何か発せられると直ちに
Δ / Δ
|| ||
Δ / Δ
という具合の既知の、予め学習された(Pre-trainedな)四項関係を呼び出してきてはどんと据えてしまう。「てしまう」などと書くと、それこそまた悪いことで良いことではないように思われてしまうだろうから、言い換えよう。四項関係を呼び出してどんと据える。
そして、この据付をあくまでも「仮」だと考えて、ちょっとどけてみたり、転がしてみたり、ひっくりかしてみたり、どこかに持って行って置き忘れてきてしまっても、それはそれで構わない、と考える。
このような「確かに厳然とあるけれども、分別の仕方を変えれば、あるともないとも言えない」といえる智。
こうなってくると「今ここ」に「あり」ながら、遠い過去の、至る所が、「今ここ」と異なるものではない、という感じがしてくる。
*
仮に、現在と過去を分節しつつ、Δ線形言語を生成する。
現在/過去
人間は、かつて、猿のようなものだった。
その猿の前は、また別の何かの動物であり、ずっと「遡って」いくと魚のようなものだった。その「前」は、水中のすごく小さな生き物。
生き物がタンパク質の分子を合成する物質的なメカニズムだとすれば、水中の細胞の手前は、鉱物だったり、地球上の分子、原子。
私たち人間は、地球ができた頃から概ねこの惑星に揃っていた原子たちを組み合わせて、いまもこうしてできている。私の爪の先、髪の毛一本の分子からして、地球ができた頃からだいたい「ずっと」「ここ」にある。
Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-
いや、「ここ」ではない「どこ」か地球外から飛んできたかも?
それならそれでよい。
地球であれ、地球外であれ、太陽の周りを周っているようなものであれば、そう大した違いではない。地球ができる「前」には、太陽系ができる「前」には、地球と地球「外」の区別などしようもない。
Δ-β-Δ-β-Δ-β-Δ-β-
太陽系を構成する分子たちだって、「もとを辿れば」銀河の歴史、そしてそしてずっと辿っていけば「ビッグバン」と記述分節されるなにかへ。そこから「光」で観測できる距離と時間の分節を区切ることができる。
時間軸上でも、ビッグバン的な何かから「いまここ」まで、ちょうどいくつもの紐を編んで組紐を作るようにずっと繋がってるというか、分かれていない。
Δ-β-Δ-β-Δ-β-Δ-β-Δ-β-Δ-β-Δ-β-Δ-β-
こうして「今ここ」と遠い時間、遠い距離が、つながっているとか、分かれているとか、同じとか、別々とか、そういうことを「今ここ」の自分の「心」、自分の「心」ともにある「言葉」や記号を武器にして道具にして言えるようにする、分節できるようにする。
この心と言葉と感覚的身体分節の組み方次第で、はるいか大昔の、太古の生命、さらにこの惑星の始まり、銀河の始まり、幾つもの銀河のはじまり、星を生む宇宙そのものの始まりまで「今ここ」が「今ここ」であるがまま、そのまま直接、何の妨げもなくつながっている。
β-β-β-β-β-β-β-β-
そしてもちろん実のところは、始まりも今もない。
分かれていることもなければ分かれていないこともない。
いまここで一瞬にして、全体構造そのものを身体に、言葉に、心に、「あるがまま」響かせる。
β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-
β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-
β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-
β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-β-
簡単に言うな、と思われるかもしれないが、簡単なこと。
「響かせる」といったが、そこに主語的なもの、主体、成す者は、いてもいなくてもどちらでもよい。全体構造は常にすでに、身体に、言葉に、心に、直接響いている。身体も、言葉も、心も、全体構造そのものの一つの振動数のようなことに例えられる。あとはそうと知るメタレベルの記述のための言語を、高次元の振動系を、つまり心を、限りなく多重化して共鳴させることができるかどうか。
経験的で感覚的なΔ二項対立の両極を振動状態に高めることで、Δ四項関係の只中にありながら、β脈動をシミュレートする。そういう「心」の発生を促すのが神話の言葉なのかもしれない。


* *
つづく
続きはこちら
関連記事
この記事が参加している募集
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。
