
柱を四本立てる動きが現世を非現世から分離する -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(78_『神話論理3 食卓作法の起源』-29,M458太陽と月の休暇)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第78回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第五部「オオカミのようにがつがつと」の最後を読みます。
これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
はじめに
レヴィ=ストロース氏が論じる「神話論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のパターンを、波紋のように浮かび上がらせる脈動たちが共鳴する”コト”と見立てて読んでみる。
神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。このΔ1〜Δ4というのは例えば天/地、生/死、人間/動物、男/女、上/下、明/暗、寒/暖といった経験的感覚的に端的に存在すると感じられる物事である。
神話は、こうした経験的な諸々の存在者の「起源」を語ろうとする。つまりこれら諸々のΔがもともと「ない」ところから「ある」ように「なる」経緯を言語でもって語ろうとする。ここで神話はある/ない、有/無の分別の始まりを問うという、きわめて高度な哲学の問いをひっぱりだしてくるのである。

そのためにまず図1に示したβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。
お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つのβ項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。
そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。
ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。
*
ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。
私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を新たに再生し続ける動きが決して止まることなく動いている。

夢
マンダラ
立体マンダラとしての小屋
神話は、私たち人類の心の深層の脈動が、言語意識の表面に映し出した影のようなもので、それは”対立関係の対立関係の対立関係の分離と結合の分離と結合”とでもいうべき動き方をする。
この深層の脈動が、対立関係の対立関係の対立関係という姿で表層に浮かび上がるという現象は、神話以外にもみられる。
例えばユングが分析するように「夢」であったり、また「マンダラ」状のイメージとして幻視されたり、描かれたり、場合によってはヴォルフガング・パウリがユングとの共著『自然現象と心の構造』に書いているように科学の理論を生み出す思考もまたそのひとつである。あるいはまた、寺院であったり都城であったり、小屋であったり、建築物の形で表現される場合もある。
『神話論理』の今回読むところでは、レヴィ=ストロース氏は神話が語る対立関係の調停の様子を再現するような、祭儀用の小屋の作りに注目する。
* *
六本の柱
『神話論理3 食卓作法の起源』の334ページでレヴィ=ストロース氏は「M430b ヒダッツア 天体の妻たち(二)」という神話における一人の母から生まれた三人の息子と三人の娘、六人の子供の関係と、別の諸部族が儀式用にもちいる「あずまや」の構造とのあいだに、おなじ思考が働いていることを論じる。
長男は昼を、三男は夜を含意し、長女は東を、三女は西を含意している。このことから息子たちは「昼夜平分的」様相(本書カバーの絵を参照のこと)、娘たちは「至点的」様相を示していることがわかる。[…]彼らは全員で、アラバホ族が儀式で使うあずまやの四本の主柱の配置と似た配置をとる。マンダン族は太陽の踊りは踊らないが、オキーパとよばれる特別な性格をもった年祭を執りおこなった。これもやはり夏であったが、仮設のあずまやではなく、常設の小屋でおこなわれた。一年中閉ざされているこの小屋の木組みは六本の支柱で支えられており[…]、その数はマクシミリアンの言うところによれば (Maximilian, p. 359-360) 「けっして死ぬことのない老婆」 の子供の数、また、アイダン族の万神殿の主神たちの数と同じである。
儀式用の小屋の柱の数に注目しよう。
部族によって儀式用の小屋の柱の数は四本であったり、六本であったりする。
このうち6本柱の数の由来について、「けっして死ぬことのない老婆」から分離した(生まれた)6人の子供(男子3人、女子3人)たちを表すとの伝承が報告されている。神話の語りにおける一と六の分離と結合の関係と、建物の構造とのあいだには関連があると語られているのである。
この6人は男女の子供は、6に分かれつつも一つにつながっている。
つまり全員が「けっして死ぬことのない老婆」つまり生/死の分別を超えた存在と親/子の関係で分離しつつ直結ている。そしてまたこの6のうちにいくつかの対立関係が織り込まれている。
子供の数は、男のペアと女のペアそれぞれの項のあいだに、第三の項が入り込んで、昼の天頂(正午の太陽)あるいは夜の天頂(北極星のお供)を占めることに由来していることがわかるであろう。
まず男/女の分別、そして上の子/下の子の区別、さらには両極(一番上か一番下か、長男長女か三男三女か)/中間(次男次女)の区別も折り重なっている。この両極と中間の区別は図1でいうΔとβの区別になるわけである。
親 / 子
老 / 若
男 / 女
長子/末子
両端/中間
つまりこの6は(圧縮して4にしてもよいし、引き延ばして8にしてもよい)いくつかの二項対立関係にある二項を分離しつつも離れすぎないように繋ぎ止めるように、一方から他方へ、他方から一方への交代(変容)が生じるよう、一次元的には単一軸上の二点間の往復として、二次元平面でいえば時間軸上に正弦波を写像するような円運動を描きながら、交代、あるいは追いかけっこをしているのである。

この連続的アナログ的に変容していく対立二項の関係については、この二項の間にいくつもの「中間項(対立二極のどちらでもあってどちらでもない両義的な項)を挟むよう、別の二項対立を両局とする軸を直行させることができる。このアナログ的な過程をどう区切るかによって、6のうちの二つの項をそれぞれ引き延ばしてその両極の項へと圧縮して全体で4にしたり、6のうちの二つの項を引き延ばして8にしたりすることもできる。6を4にすることもできるし8にすることもできる。
4は6であり8でもある。
4=6=8
・・・このようなことを書くと、「いやいやいや、4は4であって、6ではないし、8ではないでしょう!本の読みすぎでアタマが⚫︎⚫︎⚫︎くなった」などとご指摘をいただくことになるのだが、いやいやどうして。
何を隠そう、この「4=6=8」のようなことこそが、「1+1=2」と言えることを可能にしているのである。
私たち人類が、例えば「1」と「一」と「壱」と「One」と「uno」を、みんな違うけれども同じことなのだ、と感じることができるということは、「4=6=8」と言いうることと同じことなのである。「1+1=2」というときの、一つ目の「1」と二つ目の「1」が別々に異なりながらも同じことである、と言えるのは、「4=6=8」と言いうることと同じことなのである。
異なるが同じ、同じだが異なる。
非同非異。
同じであるということは、二つに区別できた事柄を分離しながらも重ね合わせて結合して区別できないくらいにする、ということである。
異なる(同じではない)ということは、二つに区別できた事柄を分離したまま、重ね合わせて結合することはできない、とすることである。
ここにあるのは、
分離する / 分離しない(結合する)
この両極の間で、
分離する / 分離しない(結合する)
の二極を速やかに切り替えることである。
分離と結合を分離する。
○
↑
○
/ ← // → ||
○
↓
○
分離と結合を結合する。
○
↑
○
/=//=||
○
↓
○
分離と結合を分離する相と、分離と結合を結合する相とが、交互に入れ替わる。そうすることで二項対立関係の対立関係(四項関係)がパイ生地をこねたりモチをこねたりするように、自在に様々な方向に伸びたり縮んだりする。
神話では、この四つの○で表現したことが、様々な登場人物や動物たちや物の姿で登場し、過度に結合したかと思えば過度に分離し、あちらで分離したかとおもえばこちらで結合する、といったぐあいに動き回っては、最後に対立関係の対立関係がうまい具合に調停されて、安定的に付かず離れず、分離しすぎることもなく結合しすぎることもない位置に配置される。そこに正方形、四つの○を四極とする四角形が出現する。
○=/=○
|| ||
/ /
|| ||
○=/=○
そしてこの四極のあいだを繋ぐように、諸々の媒介項たちが順番にめぐり、円環を描いていく。

方角を意識して四本の柱が垂直に建てられ、
その柱の間の一つの方向のみが横倒しの柱で結ばれる。
そして全体が円環で囲われている。
この円環上をいわば移動中であるかのような月と太陽の象徴が配される。
上の儀式用の小屋の配置も、円の中に正方形を納めた曼荼羅も、神話の語りにおけるめでたしめでたしの場面も、この四局の分離と結合が分離されつつ結合された状態の安定を物語る。
ちなみに、柱を四本立てることと、神話的思考のつながりについては、中沢新一氏が『アースダイバー神社編』の諏訪大社の章で詳しく書かれている。
四本の柱は、四本立って安定している姿ももちろん重要だが、同じくらい、この四本を「立てる」動きが重要であると中沢氏は指摘している。
すなわち、柱を水平に倒して、横移動させる。
そして、水平移動してきた柱を「斜め」に滑らせたりする。
そしてそして、水平に寝ていた柱を、垂直に立てる。
水平軸を引き、垂直軸を引くような述語的様相=動き。
この動き、こそ対立関係の対立関係の対立軸を発生させる、神話的思考の表現なのであろう。

*
振幅を一定にする・軸の長さを定める
『神話論理3 食卓作法の起源』からM458「マンダン 太陽と月の休暇」をみてみよう。
造化の神コヨーテは地上に住んでいたころ、太陽を訪問しようという気まぐれをおこした。彼は太陽の昇る東に行き、太陽が昇ってくるのを見た。
太陽は豪華に身を飾り立てている男であった。
次の晩、コヨーテは呪術を使い、太陽のものとそっくりな衣装を作り、前日の太陽のコースを先回りしてたどった。
太陽はいつもパイプでタバコを吸うために天頂で休憩するので、コヨーテはそこで太陽を待った。
すぐに太陽はやってきたが、自分の歩く道にずっと足跡がついているので不審に思った。そして天頂に造化の神コヨーテがいるのを見ると、腹を立て、そこでなにをしているのかと、 ぶっきらぼうに訊ねた。
コヨーテは、自分は、大地の深いところからやって来た、自分も地下で輝くものの役を務めている、太陽が上の世界で自分と同じ役割を果たしていると聞いて、知り合いになって、話をしてみたいものだと考えたのだ、と答えた。
*
太陽は、自分はいつもひとりだったし、友だちなどいらぬ、と答えた。
そして コヨーテをひどく殴ったあと、天から追い払った。
コヨーテは真っさかさまに落ちて気を失った。
・
・
・
コヨーテが気がついたときは夜だった。
大地に聞くと、自分がどこにいるのか教えてくれた。
傷ついたコヨーテは這ったり、足をひきずったりして、ある泉の方に向かった。
*
途中で、儀式をおこなっているグズリたちに出会った。
コヨーテとグズリは知り合いで、クズリたちはコヨーテを歓迎し、十分な手当てをしてくれた。けがが治ると、コヨーテは太陽に仕返しをするために、クズリの助けを求めた。
クズリたちは彼にトネリコの棍棒と、 植物性繊維の輪差(狩猟のわな)と、草の葉の大きさに縮めたポプラの木で武装するようにと勧めた。
コヨーテと「黒い輪差」 という名のクズリは天頂で待ち伏せをした。
罠用の輪差を、ポプラの木が変身している小さな草の葉に付け、その罠を太陽が休息する場所にしかけた。
*
太陽は怒り狂ってやって来た。
というのも、またもや足跡を見つけたからである。
輪差は太陽を絡めとった。
草の葉はふたたびポプラの木にもどり、太陽は宙吊りになった。
コヨーテは棍棒で太陽を殴りつけた。
しかし、コヨーテの保護者であるクズリたちは、太陽にあまりひどい怪我をさせないようにと、やわらかな木でできた棍棒を選んでいたので、おおごとにはならなかった。
そして、コヨーテは太陽の手と足を縛り、背中にしょってクズリの小屋まで連れていった。そこで、太陽は縄を解かれ、すわるようにと言われた。そして、友だちになろうとしてやって来たものに対してひどい態度をとったことを非難された。
太陽はクズリの歌と踊りが気に入った。
そこで、太陽は彼らの好意に甘えることにした。
*
月は兄弟である太陽がいなくなったので心配になり探しに出かけた。
偶然、クズリの小屋を見つけたが、そこで太陽は出入り口のそばにすわっていた。月は招き入れられ、昼食を食べるように言われる。
そして月は、なぜ太陽がそこにいるのかの説明も聞いた。
月は悪いことをした太陽を叱るが、太陽に上座を譲り、自分は出入り口のそばにすわりたいとクズリの長に言う。
なぜなら、昼間の天体は誇り高いので、プライドを傷つけるようなことはしてはいけないからだ、と説明する。
*
さらに月は、ふたりとも帰るときには、自分たちの代わりにシンボルをおいていくと言う。それらのシンボルはいまでもワシ狩りの小屋に見られる。それは壁にかけたふたつの輪差で、 太陽のシンボルは出入り口の反対側に、月のシンボルは出入り口の上にかけられている。そして、野営地で狩人たちがときに太陽、ときに月を演じるのはこの話があるからなのである。
太陽と月、ふたりの兄弟はクズリのところがたいへん気に入ったので、狩りの季節が終わるまで、空の方では役をかわってもらった。彼らはコヨーテに来年もまた、木の葉が黄色くなる頃に来ると約束した。
そして皆は別れた。
ワシの狩人であるクズリたちは家に帰り、太陽と月は空を照らすという仕事に帰っていった。
コヨーテはその後も放浪生活をつづけた。
・
・
・
ある日、コヨーテが一休みして、しあわせだったワシ狩りの季節のことを懐かしく思い出していると、 蔓植物の中に彼には黄葉しているように思われる葉が見えた。それが一年中黄色の葉だということはわからず、もう秋が来ると思ったのである。コヨーテはいきおいよく立ち上がって喜びの歌を歌いながら、野営地まで走った。
しかしそこにはだれもいなかった。
ある魔法の植物が「まだその時期は来ていない」とコヨーテにいう。
がっかりしてコヨーテは立ち去った。
M458「マンダン 太陽と月の休暇」を要約

レヴィ=ストロース氏はこの神話から「対称性」を備えた神話の「骨格」を明らかにする。この神話では、下記の三つの対立が同じこととして重なり合っている。
天 / 地
||
天上界の鳥であるワシ / 地上の動物であるグズリ
||
天の照らす者”太陽” / 地の照らす者”コヨーテ”
この神話の前半では、この天/地の両極に分離された「ふたつの項の媒介は不可能なように思われる」語りが続く(p.341)。
地の者であるコヨーテは太陽に接近しようとするが激しく拒絶され、過度に分離される。コヨーテはわざわざ太陽と似たような衣装まで用意して、太陽が休憩する場所に先回りして、そしてやってきた太陽に対して丁寧にお話しましょうと申し出る。しかし太陽は「友達などいらない」とコヨーテを拒み、地上に叩き落とす。ひどいはなしである。
しかしこれはコヨーテが可哀想で太陽が悪いやつ、という話ではなくて(表層の見た目はそうなのだが)、過度に分離している天/地の間が過度な結合へと急転換して(天頂でのコヨーテと太陽の邂逅)、そこから転じてまだ過度な分離へ(太陽に殴られ、コヨーテは地上に叩き落とされる。天から激しく分離される)、過度な分離→結合→分離、という、分離と結合の二項対立における両極の間を高速で往復しているのである。
*
再び地上にもどった地の王であるコヨーテは、グズリと同盟して(結合して)、この二重化した状態で太陽を罠に捕らえて、地上へと降ろしてくる。この時、太陽を捕らえるために使われる罠、「輪差」は、しばしばワシ狩りに用いられる道具であるという。この太陽狩りの際に、大きな樹木を小さな葉に変身させて、捕らえた獲物を木にぶら下げるタイプの罠であることを隠していることも興味深い。
大 / 小
眼に見える / 眼に見えない
このあたりの分別も自在なのである。
この狩りの様子について、レヴィ=ストロース氏は次のように書いている。
「彼ら(グズリとコヨーテ)は太陽をあたかもそれがワシであるかのように扱い、コヨーテ自身はあたかも自分がグズリであるかのようにワシ狩人としてふるまう」
この「であるかのように」というところに注意しておこう。
AがまるでΒであるかのうように。この比喩や演技は異なった二つのことが異なったまま一つになる、二即一一即二の二項が非同非異になっている、ということである。
このように激しく対立していた二項を”二即一一即二”にして”非同非異”の関係へと変換するのが、この場合は狩猟道具としての「輪差」であり、輪差とセットになって用いられる小さな葉っぱに変身した樹木である。この輪差が「高と低を媒介する項」であるとレヴィ=ストロース氏は書く(p.342)。セットで使われた「小さな葉っぱに変身した樹木」もまた、垂直に立ち上がり、天地を媒介しつつ、その中間に、獲物を宙吊りにしている。
*
囚われた太陽の休暇
そして太陽はグズリの家に連れて行かれる。
地上の小屋に、輝く太陽が入り込む。
そしてそこで、太陽はコヨーテから仕返しをうけるものの、太陽がコヨーテに対して行った時とは比べものにならないほど、穏やかな暴力にとどまっているところに注目しよう。すなわち、コヨーテが太陽を殴りつけるのに使った棒は「やわらない」のである。
つまり、ここではコヨーテと太陽はケンカの続きという点では対立し、真逆に分離しようとしているようにみえて、実は柔らかい棒でぽこぽこと叩いているだけで、まるで遊んでいるようになっている。
そしてグズリに説得されて、太陽はコヨーテと仲直りというか、友達になる。
そこへ、太陽の兄弟である月もやってくる。
太陽、月、グズリ、コヨーテ、という四者が一堂に会するのである。
四項関係の分離と結合をみてみよう
この四者について、神話の始まりでは、まず太陽と月が兄弟同士の天体ということで過度に結合し、またグズリとコヨーテも地上の仲間ということで過度に結合していた。そして天地の間ははっきりと分離していた。
太陽=/=月
↑
・
・
・
/
・
・
・
↓
コヨーテ=/=グズリ
次にこれが、コヨーテが天に昇り、太陽に近づくことで、分離しているところと結合しているところが切り替わる。
太陽=/=月
|| ||
コヨーテ/( )
↑
・
・
・
/
・
・
・
↓
( ) =/= グズリ
( )で表現した空席が二つもできていることからして、この相はじつにおさまりがわるい。綺麗な正方形を円の中に収めるのが理想だとすれば、程遠い姿である。この状態はすぐに終焉を迎える。コヨーテが太陽によって地上に落とされるのである。
コヨーテは次には自分だけではなく、地上でペアを組んでいたグズリと一緒になって、天に昇る。そして罠(開いているのに閉じている輪差と、小さいのに大きい獲物吊るし用の木のセット)を使って太陽を捕える。
太陽=/=月
|| ||
コヨーテ=グズリ/( )
ここで太陽とコヨーテとグズリの三者が、開閉不可得な輪差と大小不可得な木という二つの両義的媒介項を介して一点に凝集しているが、ここにも3と2がずれて重なっており、綺麗な四項関係の正方形は描けていない。
そこに「月」が登場する。
太陽、月、グズリ、コヨーテ、という四者が一堂に会する。
太陽=/=月
|| ||
/ /
|| ||
コヨーテ=/=グズリ
月は、太陽の非礼を詫びる。
そして太陽と月の兄弟は、グズリとコヨーテと友好な関係を築き、そして次の紅葉の季節に再会する約束をして、それぞれの場所に帰っていった。
最後に、コヨーテは約束の季節を勘違いしてグズリの仮小屋に戻るわけだが、その時にはまだ、太陽も、グズリも、月も不在であった。時間的な周期性は厳格なのであり、勝手にそのリズムを早めたりすることはできないのである。
*
決まった時期に毎年再会する
ここでもともと空間的に遠く分離し鋭く対立していたところが、周期的に再会するという形へ、つまり「時間軸」上での「両立という関係」へと「変化する」とレヴィ=ストロース氏は書く。
「神話の冒頭でコヨーテと太陽という登場人物によりしめされる対立は、技術=経済的、時間的面での両立という関係に変化する。ワシ狩りがつづく限りは、そのおかげで、不可能なことはもはやなにもない。相反するものが共存できるのである。しかしこの第一の主張をおこな ことが神話の主たる目的なのではない。ワシ狩りがあらゆる矛盾、これ以上の矛盾はないと思われるような矛盾までも解消するものである、ということを公理として立てながら、この主張は、さらに本質的な、時間軸に位置するあるひとつの仕事のための地均しをしているのである。」
距離的位置的な遠/近の軸上で対立して分離したり、過度に結合したりしていた関係が、時間軸上での循環・規則的な交代という形に調停された。そうして「相反するものが共存できる」ことになった。
しかしこの神話の目的は「矛盾を解消すること」だけではない、という。
どういうことだろうか。
神話が目指していることは単に対立する二項のあいだを付かず離れずに調停する(対立する二極のあいだの矛盾を解消する、対立二極のどちらも「あり」と宣言する)ではなく、この調停がうまく行ったり行かなかったりする手前に、対立軸を設定するということである。
しかもその対立軸は、一本ではなく、直交する二本の軸である。

対立関係を調停するために
付かず離れずの距離を一定に保つ
先ほどの神話では、太陽とコヨーテとグズリと月のうごきは、時間軸を定め、空間軸を定めていた。
この空間軸から時間軸への変更は、ワシ狩りの儀礼と、天体の妻たちに関するマンダンやヒダッツアの神話とのあいだに見られる結びつきからすでに姿を現わしている。[…]そこでは、人間の女の天上行きを象徴する、あずまやの中心にある杭が結びつきを媒介していた。ところが、ワシ狩りの儀礼もまた丸太を使うものの、丸太は水平で、地面に横たえられており、 垂直に、立てて使われるのではない。狩人たちによって建てられた枝でできた小屋の中には、炉の両側に平行に並べられた丸太が二本あった。二本の丸太は狩人たちが足を壁に向けて寝るときに枕として使われたのである。丸太を置くのは、それらが表わしているヘビの加護を祈るためであった[…]。
小屋の「柱」が、二極を分離しつつ結びつけること、二極を分離しつつ結合することを象徴しているらしい。しかもおもしろいのは、柱は一本だけだったり、二本セットだったり、四本セットだったり、垂直に立てられたり、水平に寝かされたりする。
ワシ狩りの儀礼は、この神話の天上にかかわる部分ではなく、地上にかかわる部分を思わせるもので、立てた丸太の代わりに寝かせた丸太でそれを意味していることがわかる。狩りの小屋の地面に掘られた炉が、落とし穴を表わしていることが明らかになると、そのアナロジーはさらに明確になる。じじつ、太陽の踊りの祭壇にも穴があって、それは、ある人たちの証言によれば、太陽の妻が落ちて来たときにできた穴だという。
二極を分離しつつ結合することを象徴する柱、あるいは軸。
この軸は一本だけでは済まない。神話の語りがフォーカスする点の違いによって、たとえば天/地の二極の間での分離と結合が問題になっている場合には、その間の両義的媒介項として、地上から天界へと聳え立つ垂直方向の柱のようなものが神々しく登場することもある。しかし、そうだからといって、この垂直の柱が全宇宙全世界を発生させる根源的な「一」なのであるかといえば、かならずしもそうではない。
それもそのはず、垂直方向の柱(軸)が垂直方向の柱(軸)であるのは、それが”垂直方向の柱(軸)ではないものではないものであるかぎり”においてである。そしてここに垂直方向の柱(軸)に対立する、垂直方向の柱(軸)の「逆」のものとして、水平方向に置かれた棒(軸)が呼び出される。人間のサイズで地球上にいるとしばしば忘れてしまうが、垂直と水平もまた左右と同じで、視点の据え方次第で入れ替わる、互いに他方ではないーではないとしてのみ”ある”ように”なる”ことである。
この水平方向について、先ほどの神話の小屋の配置を参照しつつレヴィ=ストロース氏は次のように書く。
「ふたつの輪差の配置も、また、水平軸を尊重している」
太陽と月をそれぞれ象徴する二つの輪差が、儀礼用の小屋の入り口の上と入り口の反対側に掲げられる。軸は必ずしも木の棒を建てたり寝かしたりして表現されなくてもかまわないのである。二つの輪差が向かい合っていることで、その間に「軸」の存在が感じられる、ということでもよい。
*
そしてこれらたがいに交わる複数の軸は、自ずから勝手に伸びたり縮んだりしてはならない。複数の軸は、お互いの「長さ」を規定し合うように動く。
レヴィ=ストロース氏は、上の神話で太陽と月とコヨーテとグズリが再会の約束そた「ワシ狩りの季節」が、「秋分(昼夜平分時)を含むこと」に注目する。
このようにして、この神話は、われわれが先住民の哲学のなかにワシ狩りを位置づけるために挙げた媒介のさまざまな型にひとつの新しい型を付け加える。つまり、それぞれ、昼の優位、夜の優位、昼と同じ長さの夜、を含意するさらなる三項を提示しているのである。
時間の軸は、昼と夜を両極として、その間で伸び縮みする。昼がどんどん伸びていく、夜がどんどん縮まっていく、逆に、昼が縮まって、夜が伸びていくこともある。天体運動の科学的な理論を知っている現代人は、冬と夏の交代が必ず訪れることを確信しているが、いにしえの人々はもしかすると、冬にむかってどんどん昼が短くなり夜が長くなるのを感じて、このまま永遠に長い夜だけが続くようになってしまうのではないか、と不安を感じることもあったかもしれない。
そのような時間軸が夜だけあるいは昼だけの方向へ伸びていってしまうことを止めて、伸びすぎる昼夜の伸びを止めて短く切っていくのが「昼と同じ長さの夜」をつくりだす、秋分・春分の力である。
「文化英雄たちにとって昼夜平分時が理想的形態であり、彼らが確立しようとしているものがそれであるとするならば」

そして例の、太陽と月、昼と夜をそれぞれ象徴する二つの罠の「輪差」が、円形の小屋の直径上に向かい合うように置かれるという様子も、伸び続ける昼を捕まえ、伸び続ける夜を捕まえる、秋分と春分のあり方をあわらしている。レヴィ=ストロース氏はこの『神話論理3 食卓作法の起源』のカバー絵に「昼夜平分」の図を掲載している。それは下記のものである。
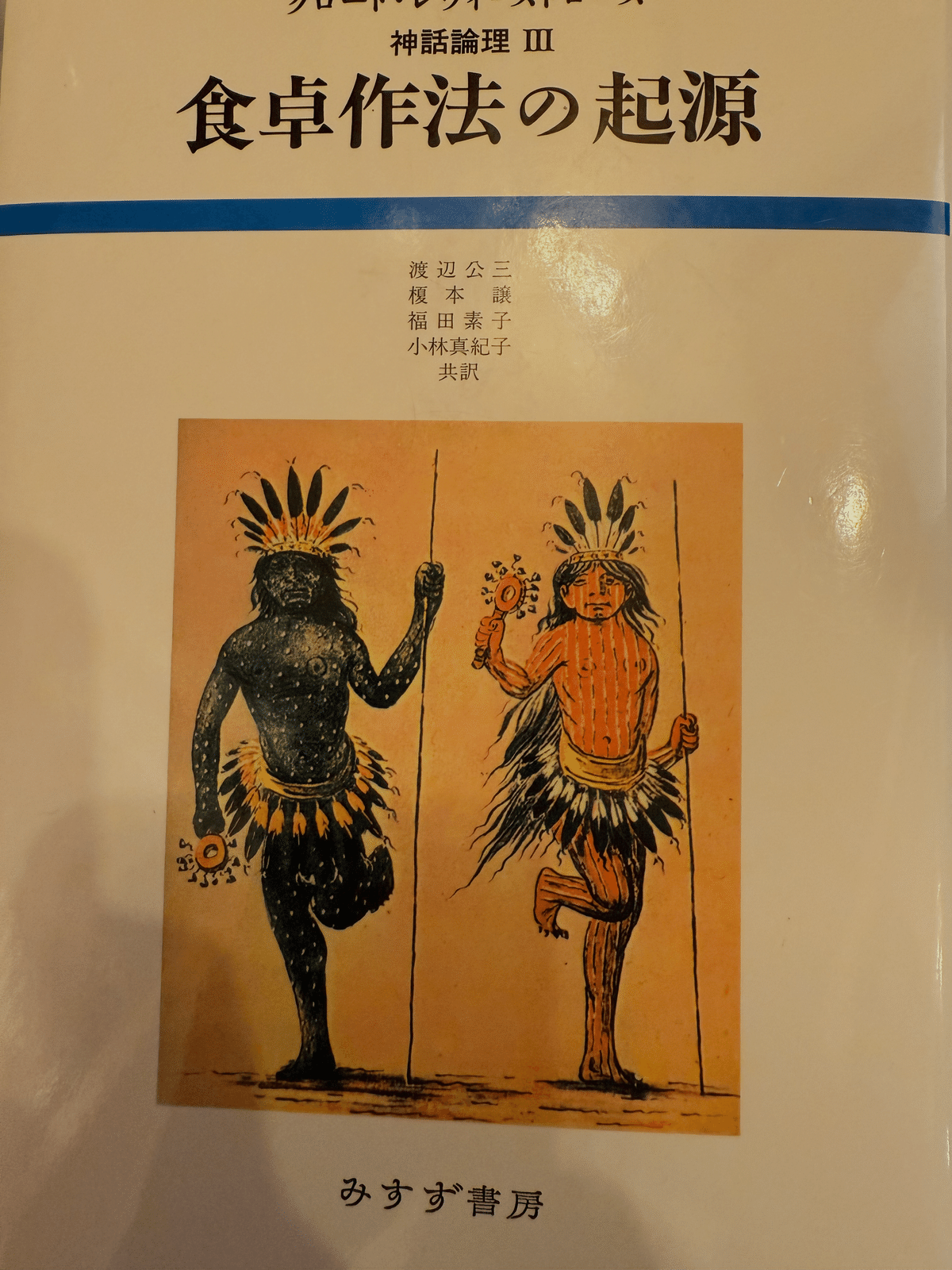
夏至と冬至を両極として、夏至から冬至へと遷移するプロセスの中間に秋分があり、冬至から夏至へと遷移するプロセスの中間に春分がある。
夏と冬、昼と夜の対立に関して、昼でも夜でも、どちらか一方が極端に長くなって=強まって、他方が短く=弱まってしまう状態(夏至と冬至)は、対立する二極の間の付かず離れずの関係がバランスを崩している状態である。このバランスを取り戻すために春分と秋分が、つまり昼夜の長さが同じに、昼夜の強さが同じになることが、対立する二極の分離と結合の分離と結合を調停して付かず離れずの二項関係を安定させる上で重要な役割を演じていると見られるのである。これは三兄弟、三姉妹のうち、長子と末子に対して中間の子が強い力をもつという神話と重なる。
これについてレヴィ=ストロース氏は「カヌーに乗った月と太陽の旅」を想起せよと書く。
この配置はカヌーに乗った天界の旅人たちの配置を思わせる。「高いところの人々」の儀式が天体の諍いの神話を創造神話としていることを軽視はできない。儀式自体はマンダン語でハプミナケ/HapminakE/と呼ばれるが、「昼の舟」または「昼の旅人」を意味する。
川を移動するカヌーの先頭と最後尾に月と太陽が乗る。
両端に一人つづ、二人を乗せている。どちらか一方でも不用意に動くと、すぐさまカヌーはバランスを崩して転覆してしまう。
カヌーの両端に分かれて川を登り下りする太陽と月は、一つに、ワンセットに結合しながらも、カヌーの両端という真逆の位置に分離している。カヌーの軸上では両端に分離しつつ、流れる川という軸上ではひとつに結合している。
分離しながら結合し、結合しながら分離する、という太陽と月の関係をカヌーは媒介している。
カヌーの媒介作用によって、月と太陽、つまり夜と昼は、過度に結合したり、過度に分離したりすることを回避される。昼と夜は過度に結合してしまってもいけないし(つまりどちらかが他方を飲み込んで消してしまいかねない)、過度に分離してもいけない(夜だけの世界と昼だけの世界が、全く無関係に別々に独立自存するようになってしまう)。
昼と夜がちょうど同じ長さに、同じ強さに、バランスをとるようになることが理想である。この昼/夜を「平分」に、バランスを実現するのがカヌーであり、春分であり秋分である。
*
軸も独立自存するものではなく、三軸がたがいを伸びすぎず、縮みすぎないよようにする
軸は一本だけしか存在しない場合、どこまでも伸び続けたり、縮んで一点に凝集したりする。ぐにゃぐにゃと変形しつづける神話の世界では軸は伸び縮みする。
……-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-……
そこで軸の両端を定めること、軸の長さを一定にすることが必要になるわけであるが、神話の世界場合、ある軸の長さを設定するために別のあらかじめ両端の間の距離が固定された物差しのような軸をどこかからもってくることができない。仮に物差しのようなものがあったとしても、それも伸縮自在であり、固定された標準・基準にはならない。
そういうわけで平分、半分が出てくる。
伸びたり縮んだりする線を、ある時点で、ちょうどその真ん中で捉える。罠猟の輪差のようなものでとらえる。
➖┸➖
そしてこの中間点もまた、所与の「点」それ自体として単立自存することができるものではない。この点を点として浮かび上がらせるのは、この点を一方の極とする二項対立関係であり、つまり一定の振幅を描いて振動する運動である。この振幅が繰り返し区切り出す最大値と最小値が、それぞれある軸の中間を捉える点になる。
|
|
➖┸➖
そしてそして、この振幅もまた振れすぎてどこまでも広がってしまったり、振れなくなって寝てしまったりすることなく、常に一定の幅で振れつづけるようにするために、また別の、伸び縮みを抑えて長さを限定された軸が必要であり。
➖┰➖
|
➖┸➖
こうすることで、見事に「6」が出てきていることがわかる。
三兄弟と三姉妹のように、長子と末子の両終端と、その中間の「3」があり、この3が二つ並んで、同じ親から生まれた子どもたちであるという点では「同じ」でありながら、男/女の差異があるという点では「異なる」という点で、付かず離れずにバランスされる。同じカヌーに乗りながら、舳先と船尾とに分かれるように。
「この神話は、地、自然、女性性と天、文化、男性性とのあいだに、三重の等価関係があることを暗に表わしていることになる。」
レヴィ=ストロース氏は三重の等価関係と書く。
そしてこの三つの二項対立関係をつなぎ合わせる中で、たとえば文化/自然の軸上で、自然から文化へ、男性から女性へ、といった具合に対立する両極の間の転換が生じている様子も見えてくる。このことをレヴィ=ストロース氏は「極の反転」と呼ぶ。
カエルはもっとも扱いにくい形での自然であるが、月に張りつくとき、月を女性化するからである。しかし、男性で昼夜平分的である存在(太陽や月の結婚が祝われるのは秋分のときである)と、女性で完全に[…]非周期的である存在との結合からは月経、周期性を実現する生物的手段、という結果が生まれることになる。したがって、どの観点に立つか、また、神話のどの時期を考察するかによって、自然/文化の極は反転し、対立する意味を担わされるのである。

ここにカエルが出てくる。
カエルは、対立する二極の間を近づけたり遠ざけたりする動き、述語的様相を象徴するのである。

またこのカエルと結合する煮込み料理というのも、水をはった鍋や土器を火にかけることによってできた、火と水をひとつの結合したような存在である。

カエルと煮込み料理の結合は、両義的媒介項(β項)同士の過度な結合であり、つまり対立する述語的様相ふたつをひとつに重ねるような事態である。
この火と水を短絡する煮込み用の土器の話は、『神話論理』の続編にあたる『やきもち焼きの土器作り』の主題となる。
+
カエルや、「焼石に水をかける」といった話については、次回の記事で詳しく紹介する。
このようにして対立関係の対立関係の対立関係が、一つの円のうちに収まる三つの軸(四つの軸からなる正方形でもよいが、三つの軸があればH字型にひとつの円のうちにおさめるのには十分である)が、均等な長さになる、即ち二極に引き裂かれながらもどこまでも分離していくことなく、ある距離で対峙するようになる。
[…]神話的思考はふたとおりに読めるひとつの骨格を使用している。ある神話とべつの神話で、あるいはときには、ひとつの神話の中のある部分とべつの部分で、神話的思考は、その意味をひっくり返す権利を自分に与えているのである。
対立軸の両端の位置に、経験的で感覚的に分別され対立させられざるを得ない二つの事柄の「どちら側」をもってくるかは、自由にひっくり返すことができる。

以上で『神話論理3 食卓作法の起源』の第五部「オオカミのようにがつがつと」の第一節「困難な選択」が終わる。これにつづけて第二節「マンダン風臓物料理」に入る。
つづく
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!

