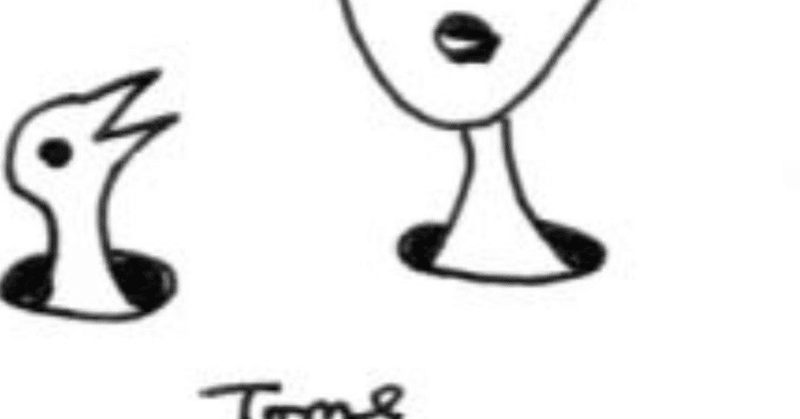2020年10月の記事一覧
それは振り向くと消える亡霊の様に
吐き出した息は白く
それだけで容易に心が踊った
ザクザクと踏み散らす霜柱の上で
高揚した声は一瞬にして屋根まで弾んだ
氷柱は折っては剣となり
氷の騎士として悠然と私を強くした
降り続く白雪の景色の中には
無駄な音などなく
人の気配もない
私一人の銀世界
幼き頃の銀世界
「私はつい
幼少の私に逢いたくなった」
しかし
あの頃の冬の神は
今はきっと違う神
あの頃の冬の私は
今は
沼地の牛はただそっと
沼地を歩く大きな牛は
歩みを止めると
四肢に浸る冷たい沼に冷やされ
風邪を拗らせ倒れてしまう
歩けども
歩けども
暗い沼地に光は見えぬ
重たい泥水に脚をとられてはもう体力はない
大きな牛は唸り声を出しては
蛙達を驚かせた
どこまでも続く広い沼を越えれば
忙しくも穏やかな生活が待っている筈だ
沼地でこのまま倒れてたまるかと
ゆっくり歩みを進めてる
それはそれはゆっくりと
イカロスはすぐに忘れる
揺れた気球が落ちてくる
オレンジ色がゆらゆらと
本当はどっしりと落ちてくる
揺れは私の勘違い
私は澄んだ空に魅入られ
上をずっと向いたまま
頭の中の血が廻る
くらくら揺れる
オレンジは
私の元に落ちてくる
迎えに来たなら
乗り込んで
私もゆらゆら浮遊したい