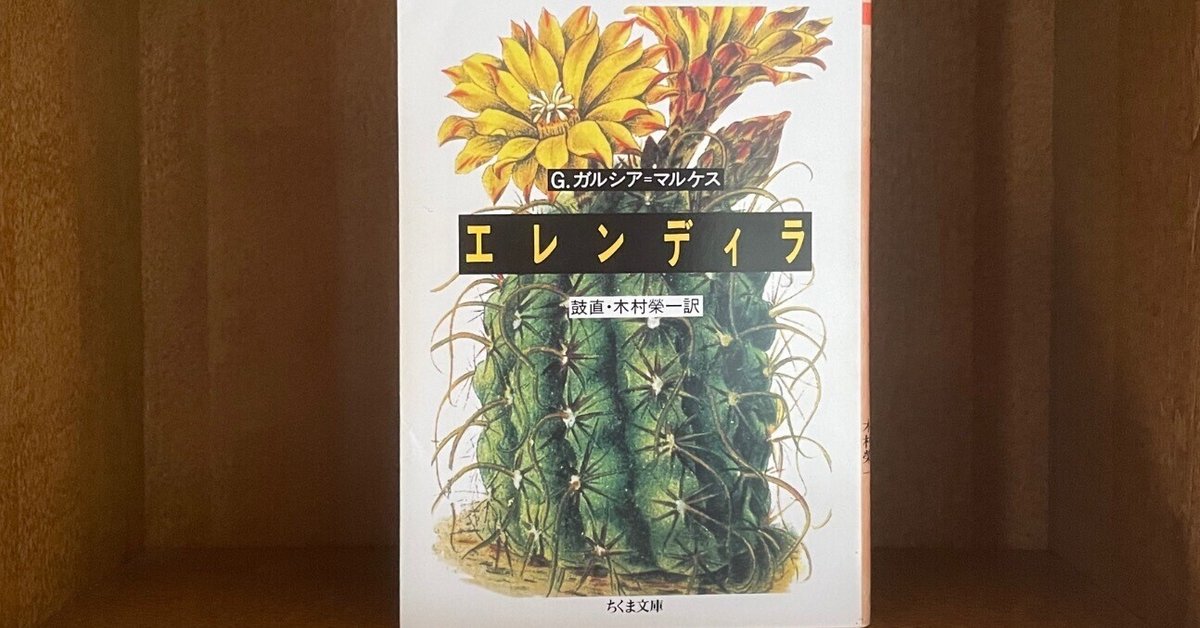
『エレンディラ』所収の短篇 ガブリエル・ガルシア=マルケス
ちくま文庫から出ている、ガブリエル・ガルシア=マルケスの『エレンディラ』を読みました。
文庫本の小説には、よく表紙に「あらすじ」と見せかけたネタバレが書いてあることがありますが、このちくま文庫『エレンディラ』の背表紙には、「あらすじ」でも「ネタバレ」でもない、絶妙な「紹介文」が記されています。
“大人のための残酷な童話”として書かれたといわれる六つの短篇と中篇「無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語」を収める。『百年の孤独』と『族長の秋』の大作にはさまれて生まれたこの短篇集は、奇想天外で時に哄笑をもさそう。
これ以上コンパクトに、この一冊をひとに勧めることはかなり難しいと思います。
…まあ、《哄笑(大声で笑うこと)》は流石に言い過ぎかな〜という気がしないでもないですが。でもたしかに、思わずとくすっと笑ってしまうような場面はありました。
そしてそんなユーモアと同時に、どこか胸が締め付けられるような悲哀といいますか、懐愁といいますか…。ちょっと上を向いて溜息をついてしまいたくなるような読後感もあります。
今回は長くなりそうなので、2回の投稿に分けることにしました。中篇『無垢なエレンディラと非情な祖母の信じがたい悲惨の物語』については次回!
ここでは、六つの短篇を順番に紹介していきます。
(ちょっとだけネタバレも含みますが、問題ない程度だと思います)
『大きな翼のある、ひどく年取った男』
すごいタイトルですね。(笑)
実際、翼の生えたぼろぼろの老人が〈天使〉として登場します。それも、本人が「天使です」と名乗ったりしたわけではなく、村の〈生と死に関わりのあることならなんでも心得ている女〉がそのように認定した…という事実のおぼつかなさ。
しかも読者は、そのアンバランスさに中々ツッコミを入れさせてもらえません。物語は淡々と進んでいきます。
〈天使〉は人々の見せものになったかと思えば、すぐに飽きられたりする。言葉が通じず意思の疎通が出来ないことから、神父からも本物の〈天使〉であることを疑われたり、子どものいたずらの対象にされたり、見物人から死んだと思われて烙印で脇腹を焼かれたり…と散々な目に遭います。
そんな中、最後はバッドエンドともハッピーエンドともとれないような、浮遊感のある描写で幕を閉じる…という感じ。
僕個人としては、今までにこういう物語を読んだ記憶もないですし、もちろん実際にこんな状況を体験したこともないのですが、それでも何故か、どこか懐かしさを感じてしまうような、不思議な気持ちになりました。
**
『失われた時の海』
ストーリーとしては、一番捉えどころのない作品かもしれません。しかし、描写は非常に詩的で美しい。
舞台は海沿いの村です。普段は悪臭を放つはずの海が、その年だけはバラの香りを放ちます。当初、村人でその香りに気付いたのは、トビーアスとヤコブ老人の妻だけ。
ヤコブ老人の妻はその香りに自らの死の予兆を感じ取り、夫を悩ませる頼みごとをします。自分を生きたまま、村から離れた土地で埋葬してほしい…と言うのです。
ヤコブ老人は、村で唯一、妻と同じようにバラの香りを嗅いだというトビーアスに頼んで、その香りが死の予兆とは関係ないということを妻に説得させようとしますが、上手くいきません。
夫人の話によると、村中の人がトビーアスのこと嘘つき呼ばわりしているのだとか。
トビーアスは自らの正直さを証明するために、再び海からバラの香りが漂ってくるのを待ち続けます。ある時遂に、村人全員が気付くほどのバラの香りが海から漂ってきました。
バラの香りは大きな話題となり、村外から観光客もやって来て大賑わいになります。
ただ、その前にヤコブ老人の妻は息を引き取っており、遺体は埋葬されることなく、海へ流されました。老人は妻の最後の願いを叶えてやれなかったことを悔やみ、村の賑わいとは対照的な感情を抱えます。村から出ていきたい…。しかし、それにはお金が足りない。
そんな時に現れたのが、億万長者のハーバート氏。彼は特殊な方法でお金を村民に分配しようと提案しますが、それは少なからずリスクを伴うものでした。(面白いのは、それがいわゆるギャンブルでは無いこと)
望み通りお金を手に入れる者もいれば、より多くの借金を抱えることになる者もいました。
とにかく、このハーバート氏が何かとてつもなく神秘的。彼が長い時間の眠りにつくと、バラの香りはしなくなります。
のちにトビーアスと仲良くなり、一緒に海に潜ったりしますが、ハーバート氏と一緒だと海中も不思議な世界に変わります。水没した村がぼんやり光を放ち、無数の死体が漂う水域があったり…(そこでは、ヤコブ老人の妻の遺体も、若返った美しい姿で流れています)。
幻想的な描写に溢れており、六つの短篇の中で、この作品を一番のフェイバリットとして挙げている方も多い印象です。
**
『この世でいちばん美しい水死人』
またまた、すごいタイトルです。水死人の形容詞が「この世でいちばん美しい」…とは。
村に流れ着いた水死人の美しさに呑まれて、まずは女たちが、そして遂には村全体が団結し、大規模な葬儀を執り行なうまでの過程を描いています。
個人的には、『エレンディラ』所収の作品群の中で、最も読みやすく、最もユーモアに溢れた一篇であると感じました。
**
『愛の彼方の変わることなき死』
六つの短篇の中では、一番純粋な悲哀というか、救いのない読後感かなあ…という感じ。
冒頭で、上院議員オネシモ・サンチェスには、既に死期が迫っていることが明かされます。
エリートコースを歩み、しあわせな家庭を築いた彼でしたが、3ヶ月前に医師から余命宣告を受けてしまったのです。オネシモ・サンチェスはそのことを誰にも話さずにいますが、死の恐怖は次第に彼を蝕んでいく…。
そして、そんな彼を罠に陥れようとする者がいます。不安に駆られた人間が、一番逃れることが難しい罠…。
自らの奥深くに葛藤を抱えた、上院議員オネシモ・サンチェスの末路を描きます。
これを、過度な感情移入はさせないような文体で描くというのが、ガルシア=マルケスの凄さです。
**
『幽霊船の最後の航海』
冒頭は少し読みにくいですが、最後には盛り上がりを見せる作品かな、と思います。
一篇の中で、段落が一度も変わらない作品です。台詞に鉤括弧はなく、主人公が死んだ〈おふくろ〉に対して呼びかけるシーンなど、ところどころ『族長の秋』に向かっていく側面を感じました。
あらすじは割愛(笑)。
主人公は、自分の主張の正当性を認めさせたいという点では、『失われた時の海』のトビーアスに近いかも知れませんが、もっともっと強情で荒っぽい感じがします。
**
『奇跡の行商人、善人のブラカマン』
他の短篇とは打って変わって、「暴力性」や「残虐性」が全面に押しだされたような印象を受けました。
物語は全体を通して、〈ぼく〉の回想として語られています。
占い師を目指していた〈ぼく〉は、ある日曜日に街に現れた行商人、ブラカマンに弟子入りをします。ブラカマンは、言葉巧みに毒蛇に効く薬などを人々に売り捌いていますが、実はこれはインチキ。
一見、この作品のタイトルと矛盾するようですが、作中で〈ぼく〉はこのように語っています。
行商人のブラカマンは煮ても焼いても食えない悪党だが、この僕はいたって善良な人間である。
〈ぼく〉が占い師になれることを見込んで、身柄を引き取ったブラカマンでしたが、〈ぼく〉が思うように成長しないことに苛立ち始めます。
商売も上手くいかなくなったのをキッカケに、〈ぼく〉を引き取ったせいでこんなことになったのだと罵り、拷問まがいの虐待をするようになったのです。
〈ぼく〉はブラカマンに恨みを募らせていき、ある時それが爆発しました。その時、奇跡的な、魔樹のような能力を開眼したのです。
その後〈ぼく〉は、《善人のブラカマン》として、幾らかのお金と引き換えに人々の病気を治したりしながら各地を巡り、富と名声を得ることになります。
そして、かつて自分を拷問にかけた、あの〈悪党ブラカマン〉に対して、無限地獄のごとき罰を与えるのです。この作品の文末はぞくっとします。
どこか恐ろしさのある、神話的なニュアンス。六つの短篇を締め括り、そして次の中篇『無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語』に向かっていくための助走をかけるような作品であると感じました。
『エレンディラ』に収められた短篇は、誤解を恐れずに、めちゃくちゃ大雑把に言ってしまうと、「忙しい人のための『百年の孤独』」という感じ。
(うわー、結構失礼なこと言ってるし、本当に心配になるくらい大雑把だ…笑)
かと言って、これらの短篇にハマらなかったとしたら『百年の孤独』もハマらないのか…、と言われると、それはまた違うだろうなとも思います。
感覚としては、『百年の孤独』を読んで、面白かったけれど、再読するには分厚いし、大変だなあ…という人が、気軽に『百年の孤独』の雰囲気だったりを「再体験する手がかり」として読むことができるのが、これらの短篇作品なのかな…と思います。
作家の入門として、短篇が勧められることは多いと思うのですが、ことガルシア=マルケスに関しては、短篇、特に『エレンディラ』に収められた短篇を「初読」の手がかりにしてしまうのは、ちょっと危険かなあ…と思います。
ある程度、ガルシア=マルケスの語り自体に耐性がついていて初めて入り込める側面もあるかも知れません。
ちょっと大変ですが、長篇『百年の孤独』か、中篇『予告された殺人の記録』などの方が初読時には向いている気が…。それを面白がれた人が、手軽にトランス状態に入る(って言い方は中々やばいな笑)ためにこれらの作品群を読んでみてはいかがでしょうか。
(…と思って、ネットで検索かけたところ、何件か「ガルシア=マルケス初読でしたが楽しめました!」みたいなレビューを見つけました!まじか!…やっぱり人によるのかも 笑)
**
次回は中篇『無垢なエレンディラと無情な祖母の信じがたい悲惨の物語』について書きます。
