
【本という名の大樹】仏像と日本人
はじめに
題名からして地味に過ぎる本だと思います。
もし、本書『仏像と日本人』が、島国日本における仏像の歴史的変遷を辿るだけの本であったなら、長らく仏像彫刻を嗜んできた僕ですら、所有する気持ちにはならなかったはずです。
しかし、僕は本書を手に取り、そして買い求めました。

この顛末に至るきっかけは、題名『仏像と日本人』に対して、ある種の不自然さを反射的に感じてしまったことにあります。この不自然さとは、”日本” ではなく ”日本人” になっていたことを指します。
この些細にして大きな差異から、著者の強い意図と明確な指向性を感じないわけにはいかなかったのです。
この反射的な感情の動きに対処すべく、本屋さんの棚から本書を取り出した僕は、そそくさと斜読みを済ませ、些かの逡巡もせぬままにレジの方へ向かったのでした。
そして、今日まで再読を重ねているのです。

#1:本書の特長
本書は、仏像に関する知識を羅列しただけの本でもなければ、年表や図録といった資料を掲載しているだけの本でもありません。
ただ、本書のあらましを綴るとすれば『6世紀頃から現代に至るまでの仏像と日本人の関わり方の変遷が、冷静な筆致で過不足なく記されている。』と一行余で済んでしまうのも事実で、「それじゃぁ、単なる仏像史になってしまっているのではないか!」と、疑念を持たれる方がいたとしても何ら不思議はないでしょう。
しかし、懸念はご無用です。
著者 碧海 寿広 氏は、ともすれば平面的になってしまうであろう仏像史に、宗教的・日本史的な切り口とは異なる視点を加えることで、仏像と日本人が織りなした物語を、より立体的かつ包括的に紡ぎあげたのです。
しかも、内容を著しく劣化させることなく、230余頁にまとめ上げている点もまた、本書の特長として挙げたいと思います。
#2:多彩な表情
本書は多彩な表情を有しています。
基調としては、美術史や文化史の趣が強いと言えますが、その時々に、文学史や地方史、観光史、サブカルチャー史といった多彩な表情を垣間見ることができるはずです。
これらの表情の変化をより強力に印象付けさせているのが、各時代の要所で起きたエポックメイキングな出来事、即ち『境界』の前後で何が起こったのかを明晰に描いているところだと感じています。
そのお陰で、変化の前と後の様相が露わとなり、点と点が結びつくような感覚や、知的好奇心が満たされる快感に浸らせてくれるのです。
筆者は、こうした表情の変化を以て、仏像に対する日本人の価値観や関わり方の変遷を明々白々にしていくのです。
#3:仏像を取り巻く個性豊かな登場人物
前項で挙げた多彩な表情は、本書に名を連ねた人物を一瞥しただけでも容易に窺えるはずです。
その一部を以下に挙げてみましょう。
まずは、歴史の教科書で見たことがある豪族、仏法僧、武将らの名前から始まり、文化財保護の礎を築いた政府関係者、有識者のお歴々や、仏像に美術的概念をもたらしたフェノロサや岡倉天心といった美術史に名を刻む偉人たちが華々しく登場してきます。
更に時代を経ると、巡礼ブームに火をつけた和辻哲郎を主役に定め、高村光太郎や坂口安吾といった各界著名人たちに脇を固めさせたと思いきや、ドラマの中弛みを払拭すべく、土門拳や入江泰吉といった名うての写真家たちに助演を務めさせ、ついには白洲正子や梅棹忠夫といった文化人・学者の面々を、芋づる式に友情出演させるといった具合です。
しかし、それだけでは終わりません。
いわゆる表舞台で活躍する論客や文人たちの対極に存在しているであろう みうらじゅん・いとうせいこう といったサブカル系著名人のアクティビティーをも拾い漏らさないのだから堪りません。
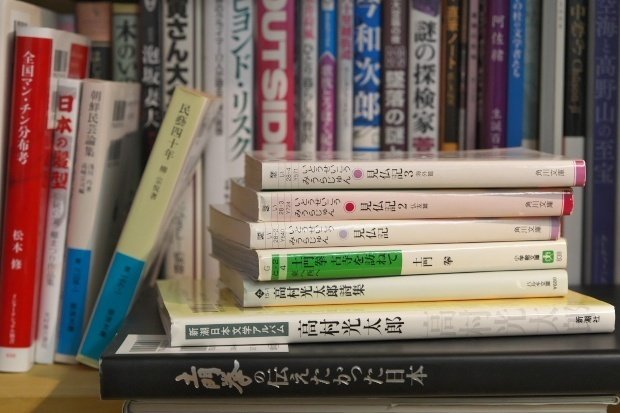
さわさりながら、手放しで褒めてばかりもいられないのです。
本書の何れの項にも、仏像を製作した側の人間(職人・彫刻家・僧侶など)の出番が設けられていない点を指摘しておくべきでしょう。
彼らは、仏像に一番近い位置に存在した人間たちだと言えるからです。その点が、作り手の顔を持つ一人間として遺憾に思いました。
※本書を再読する度に、著者の潔さと本書の主旨に合点がいったこともあり、早い段階で一応の納得に至っております。
そもそも、”仏像にまつわる話” とあらば、奇想天外な演出でも加えない限りは、地味に始終するであろうことは容易に想像がつきます。
しかし、著者の幅と奥行きを感じさせる手練手管のキャスティングによって生まれた嫋やかな起伏と適度な緊張感は、仏像と日本人が連綿と紡いできた歴史物語を、躍動感溢れるものに仕立て上げていると僕は感じています。
#4:私的核心部から伺える著者の筆致と視座
本書を読み進めていく中で、琴線に触れた事柄『私的核心部』を幾つか見い出すことができました。
その一例として、混沌の明治期に起きた仏像と日本人の関係性におけるダイナミックな変容について触れておきたいと思います。
特に、仏像に与えた物理的影響の大きさを尺度にした場合、明治新政府が主導した廃仏毀釈・神仏分離が挙げられるでしょう。

そして、この負の産物ともいえる排斥運動のベクトルに、正の変化をもたらしたのが文化財保護という思想・制度なのです。
こうした歴史的変遷を辿ってみると、正と負が綯交ぜとなった混沌の中にこそ、芳ばしい出来事が勃発しているという事実に行き当たるのです。
そこで、僕が考える明治期を舞台にした代表的かつ象徴的なエピソードについて、著者がどの様に書き記しているかを検証すべく本書から抜粋してみましょう。(美術史を嗜まれている方なら周知のエピソードです。)
特に、1884年の6月から9月に実施された調査の過程で起きたとされる、法隆寺夢殿開扉のエピソードは、岡倉が携わった一連の古社寺調査を象徴する出来事として、これまで何度も繰り返し言及されてきた。
夢殿の救世観音は、秘仏として人々の目に触れなくなって久しかった。フェノロサや加納鉄哉とともに法隆寺を訪れた岡倉は、この秘仏の公開を寺院の僧侶に要請した。だが、僧侶は、これを開くと必ず雷が落ちると言い、すでに明治初年にその前例があるとして、要求を拒もうとした。岡倉らは、この忠告を意に介さず、しぶる僧侶からの許可を何とか得て、堂の扉を開いた。恐怖に駆られた僧侶たちは、その場から逃げ去ってしまった。だが、岡倉たちは雷鳴に打たれず、美術史上の価値の高い古代の彫像との対面に、見事に成功させた。
神仏に対する前近代的な畏怖の念が、美術をどん欲に探し求める近代的な意識によって、駆逐されたかのような場面である。近代知性の体現者である岡倉やフェノロサにとって、秘仏開扉をめぐる僧侶たちの信心深き逡巡など、取るに足らなかった。
筆致は冷静 かつ 公明正大な視座 を感じさせる文章だと思います。
既に仏像を美術的に鑑賞することに慣れている現代人なれば、日本の美術史において英雄的な扱いを受けることが多い岡倉天心やフェノロサを賛辞する側に立つ方が容易だと思われます。
また一方では、日本人らしい情緒性(判官贔屓的な感情)を発揮して、天罰を恐れる僧侶たちに肩入れすることも可能でしょう。
実際には、こうしたケースであれば、著者の重心が相反する何れかの側へ偏心していたとしても違和感はないですし、その方が読み手にも話の構図や展開が分かりやすくなる場合も少なくないものです。
しかし著者は、そうした安楽を選択しません。
ただただ、その当時の状況や出来事の経過、そして考察を冷静に淡々と綴っているのです。
それが研究者の姿勢として妥当であると断じるのは簡単でしょう。
しかし、数多の研究者・専門家が、確証バイアスの罠に陥った例を、僕たちは知っているはずです。その有様を思い起こす時、ニュートラルな立場で論じ、そして綴ることの困難さを、改めて確認するのです。

いずれにしても、著者の冷静な筆致と公正な視座によって、僕の脳内補完能力が刺激され、社会的な責任や要請のみならず、自身の好奇心や欲求を原動力に開扉を断行した岡倉たちの心境にも感情移入できたし、一方では、天罰を恐れ、三々五々と逃げ隠れてしまった僧侶たちの有様をも色鮮やかに想像することができたと言えるのです。
最後に
折しも、この秋 創立150年 を迎えた東京国立博物館では『国宝 東京国立博物館のすべて』と題した特別展(2022年10月18日〜同年12月11日)が開催されています。
当然の事ながら、国宝の中には仏像も多数存在します。
東大寺の廬舎那仏座像 や 広隆寺の弥勒菩薩半跏像 を筆頭に、石仏や摩崖仏等も含めれば、枚挙に暇がないほど登録されています。
こうした記念すべき節目に際して、国宝や重要文化財の存在に思いを致すわけですが、想像を超える時間を積み重ねてきた宝物・文化財に対して、僕自身が真正面から向き合えるだけの丹力・姿勢・視座 等々を備えているのかと問われれば、甚だ疑わしいとしか言いようがないのです。
しかし、本書を一読したことによって、仏像に相対した時の焦点だけは自在に動くようになったという事実も、蛇足ながら記しておきましょう。

仏像は祈りの対象でもあり、美術的鑑賞の対象でもあります。
この前提が構築されているからこそ、価値観が多様化した今を生きる僕たちは、作法を厳格に問われることなく自由闊達に仏像の前に立てる幸せを享受していると断言できましょう。
こうした嫋やかな恩恵は、有名無名の先人たちが膨大な時間を費やして築き上げた礎の上に存在していることを本書は教えてくれています。
然るに、本書が『仏像と日本』ではなく『仏像と日本人』となった理由もまた ”そこ” に通奏低音していると、私は頑なに推測しているのです。
さて、些か長くなり過ぎたでしょうか。
と言うことで、これにて僕がお薦めする『今こそ読んでほしい、この本』を締めさせて頂きます。
ご一読ありがとうございました。
