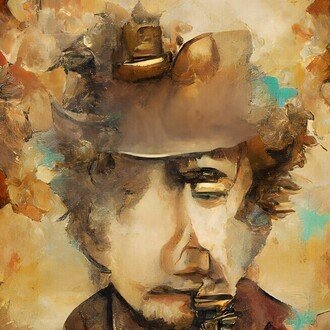- 運営しているクリエイター
#有料記事書いてみた
高等遊民のための映画鑑賞法
映画は誰のためのものか
映画とは何だったのか。かつてそれは大衆のための娯楽であり、芸術であり、社会を映す鏡だった。誰もが映画館に集い、笑い、泣き、怒り、感動を共有することができた。それは特別な体験であり、生活の中の大切な一部でもあった。
しかし、現代の映画を見渡すと、その役割が大きく変質しているように感じる。NetflixやAmazon Prime Videoなどの配信サービスが映画館の代替と
情報に呑まれる 流行には最後尾で追い付け!
情報が溢れる時代に生きる私たち
私たちは情報の洪水の中で生きている。朝起きた瞬間からスマートフォンを手にし、SNSをスクロールしてニュースや友人の投稿を眺める。仕事や通勤の合間にはイヤホンを耳に入れ、音楽やポッドキャストを聞く。帰宅してからも、テレビや動画配信サービスで映像を楽しむ。これらすべてが、意識的であれ無意識的であれ、私たちの脳に膨大な情報を注ぎ込んでいる。
しかし、この情報量はもはや
創作と肉体労働 書く時間がない!
創作と肉体労働の現実「書く時間がない!」と叫びたくなる日々がある。朝から晩まで肉体労働に追われ、帰宅する頃には疲労困憊。頭の中では次々と物語のアイデアが浮かぶのに、それを形にする時間も体力も残っていない。そんな状況を経験したことがある人も多いのではないだろうか。
肉体労働は特に、創作に向き合う時間を奪う。長時間の労働で体力が削られるだけでなく、単調な作業の繰り返しによって、想像力や創作意欲も失わ
創作と商売の食い合わせの悪さとそれでも生きていく方法
創作と商売の矛盾
創作と商売。この2つはしばしば「水と油」のように例えられる。それもそのはず、創作は個人の感情や想像力から生まれる自由な行為であり、商売は顧客ニーズに応えることで成立する現実的な活動だからだ。この対立構造の中で、創作者は自分の作品を「売るための商品」に変えることを求められる。そこには喜びもあるが、しばしば葛藤や苦しみも伴う。
たとえば、小説家は自分が書きたいテーマだけでは食べて
脳の使い道 最近自分で文章考えてる?
最近、自分で文章を書いているだろうか?日記でも、メールでも、何かしらの形で自分の言葉を紡いでいるだろうか?スマートフォン一つで情報が手に入り、AIが文章を作る時代に、私たちは「自分で考える」という行為を忘れかけているのではないだろうか。
もっとみる継続は力なりとはいうけれど
「継続は力なり」。この言葉を初めて聞いたのは、いつだったのだろう。子どもの頃、学校の先生が何かを諭すように言ったのかもしれないし、家族が日常の中で口にしたのかもしれない。身近な言葉ではあるものの、実際に何かを続ける中で、この言葉の意味を深く理解することは案外難しい。
もっとみる寿命と天命といのちの線引き
「寿命」と聞いて何を思い浮かべるだろうか。それは、一つのいのちが自然に終わるまでの時間であり、「人間がコントロールできないもの」の象徴と考えられることも多い。一方で、「天命」という言葉は、いのちの長さではなく、その質や目的、役割に焦点を当てて語られる。これらに加えて、「いのちの線引き」という問いが生じるのは、生と死、価値と無価値の境界をどう決めるのかという難しいテーマがあるからだ。
もっとみるシングルタスクの禍福
「一度にいろんなことをやれるようになりたい」――その思いを抱いたことは何度もある。周囲を見渡せば、同時に複数のことを器用にこなしていく人がいる中で、自分はどうしても「一つずつ」しか進められない。それが私自身の特徴なのだと気づいたのは、比較的最近のことだ。
もっとみる