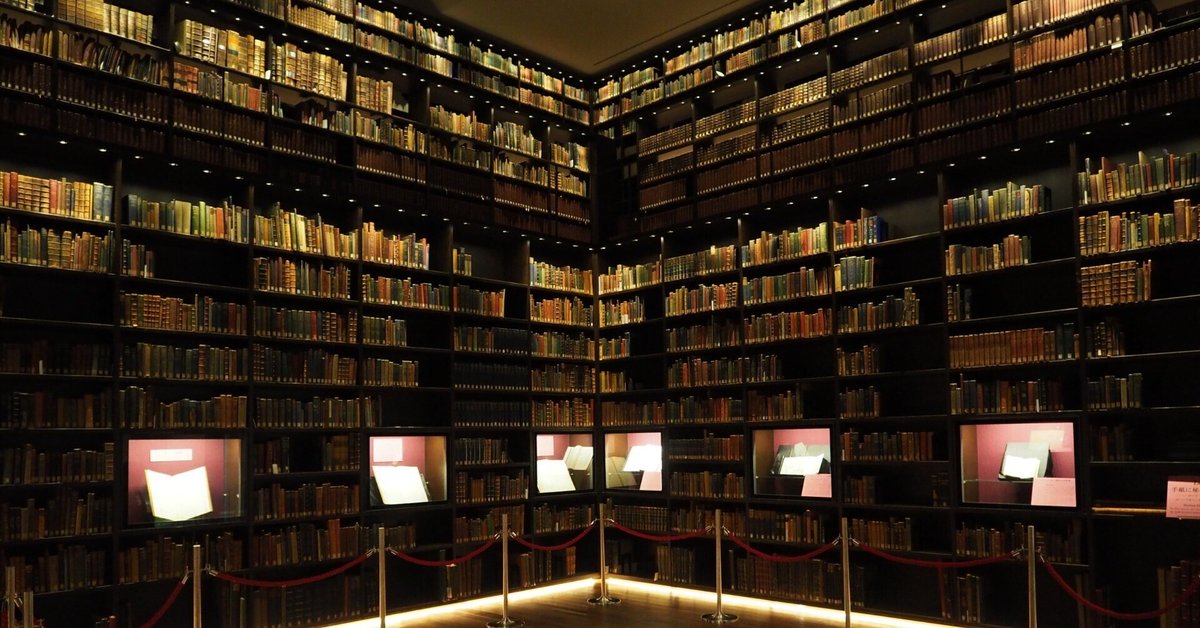
魏志倭人伝の「遠くてよくわからない国々」を古代の発音で調べるー続編: 古事記・日本書紀の地名と比べる
探せミッシングリンク
概要
先に筆者は「三国志」中の「魏書」中の「烏丸鮮卑東夷伝」倭人条 (通称: 魏志倭人伝) に記載の音訳とみられる国名について、当時の発音に基づいて位置と地名の推定を試みたが、その検証のために古事記と日本書紀に記載の第10代崇神天皇期の遠征関連(いわゆる四道将軍など)の地名との比較を行う。両者の地理的分布には強い相関が見つかった (i)「崇神天皇期の遠征範囲」は、特に古事記に従って播磨・吉備を除く場合には、魏志倭人伝の「女王に属する国々」とほとんど重ならない、(ii) 前方後円墳の1期の分布は、両者をを合わせた領域におおむね一致する。この強い相関は初期のヤマト政権の勢力範囲の拡大を反映するとみられ、いくつかの記紀の記述がこれを支持するほか、魏志倭人伝の国々のリストに播磨・吉備地域が後から追加された痕跡があり、この地域の遠征が崇神天皇期より前とする上記の古事記の説を支持する。邪馬臺國については進捗ありません。
背景
陳寿 (3世紀末)著「三国志」中の「魏書」中の「烏丸鮮卑東夷伝」倭人条(通称: 魏志倭人伝) [三國志v30]は3世紀前半の倭の情勢と言語を知る貴重な資料となっております。この中には、当時の倭の国々の名を音訳したとみられる語30件(と朝鮮半島の国名1件)が含まれております。このうち大部分を占める21か国は「遠く隔たって詳しく知ることができない」(遠絶21か国)とされ、距離や移動方法に関する記載がなく、国名だけが羅列されています。
これらの場所を知るために、筆者の前回のブログで国名の当時の発音をもとに地名を推定するという調査を行いました (詳細は上記の記事をご覧ください)。手法の概要は以下の通りです。結果は次の節に再掲します。
中国語: 上古音と中古音(魏晋期)の混在
倭人語: 日琉祖語(6母音モデル)
地名の選択基準: 大地名(郡以上)、古代豪族(国造など)、互いに隣接する地名を優先。
しかしながら、中国語の魏・晋期の発音は不明な点も多く、上古音や日琉祖語などは現在も研究が進展しているところです。また使用した地名選択基準も一定のバイアスを免れません。そこで、今回得られた国々の推定地を発音以外の方法で検証するために、日本側の文献と比較したいというのがこの記事の趣旨です。残念ながら同時代の日本の文献は残っていないため、古事記と日本書紀という8世紀初頭の歴史書に記載の古い部分の話に登場する地名と、魏志倭人伝の国々の推定地を比較します。
古事記[古事記712]と日本書紀[日本書紀720]は共通の伝承や皇室の資料を基に8世紀初頭に編纂されたと考えられています。両者はおおむね同じ内容で、日本神話と古い時代の天皇(大王)のことを記述していますが、一部に食い違いもあります。これらの文献では天皇ごとに章が構成されていますので、文献中の時代の流れを表すために「第N代○○天皇期」と表記することにします。
また古事記と日本書紀に関連して、ヤマト政権の勢力分布を表すとみられる前方後円墳の分布とも比較してみます。
比較
魏志倭人伝の「遠くてよくわからない国々」とは
前回の結果をこちらに再掲します。マップのマーカーの色は以下の通りです。マーカーをクリックすると詳細が出ます。
赤系: 女王に属する国々。
濃い赤: 既存有力比定地あり
赤: 既存研究のどれかと一致
オレンジ: 既存研究と一致せず
黒系: 女王に属さない国々、その他。
黒: 既存有力比定地あり
灰色: 既存研究のどれかと一致 (日本列島内は狗奴国のみ)
$$
\begin{matrix}
ブ & \text{ID} & 国名 & 推定 & 古代名称 \\ \hline
\text{A} & 1 & 狗邪韓國 & 既存有力 & 伽耶・加羅・金官国 \\
\text{A} & 2 & 對馬國 & 既存有力 & 対馬県主・対馬国 \\
\text{A} & 3 & 一支國 & 既存有力 & 壱岐県主・壱岐国造 \\
\text{A} & 4 & 末盧國 & 既存有力 & 松浦県主・肥前国松浦郡 \\
\text{A} & 5 & 伊都國 & 既存有力 & 伊都県主・筑前国怡土郡 \\
\text{A} & 6 & 奴國 & 既存有力 & 儺県主・筑前国那珂郡 \\
\text{A} & 7 & 不彌國 & 推定 & 筑前国穂波郡 \\
\text{B} & 8 & 投馬國 & 推定 & 尾張国海部郡津嶋 \\
\text{B} & 9 & 邪馬臺國 & 既存有力 & 畿内説と九州説 \\
\text{C} & 10 & 斯馬國 & 推定 & 島津国造・志摩国 \\
\text{C} & 11 & 已百支國 & 推定 & 摂津国島下郡の荊切の里 \\
\text{C} & 12 & 伊邪國 & 推定 & 伊勢国造 \\
\text{C} & 13 & 都支國 & 推定 & 刀支県主・美濃国土岐郡 \\
\text{C} & 14 & 彌奴國 & 推定 & 美濃県主・三野前国造 \\
\text{C} & 15 & 好古都國 & 推定 & 美濃国方県郡 \\
\text{C} & 16 & 不呼國 & 推定 & 信濃国安曇郡の穂高神社 \\
\text{C} & 17 & 姐奴國 & 推定 & 科野国造 \\
\text{C} & 18 & 對蘇國 & 推定 & 肥前国養父郡鳥栖郷 \\
\text{C} & 19 & 蘇奴國 & 推定 & 佐那県造 \\
\text{C} & 20 & 呼邑國 &推定 & 加夜国造・備中国賀陽郡 \\
\text{C} & 21 & 華奴蘇奴國 & 推定 & 長国造(*)・佐那県 \\
\text{C} & 22 & 鬼國 & 推定 & 紀国造 \\
\text{C} & 23 & 爲吾國 & 推定 & 伊賀国造 \\
\text{C} & 24 & 鬼奴國 & 推定 & 毛野国 \\
\text{C} & 25 & 邪馬國 & 推定 & 陸奥国耶麻郡 \\
\text{C} & 26 & 躬臣國 & 推定 & 久自国造・常陸国久慈郡 \\
\text{C} & 27 & 巴利國 & 推定 & 針間国造・播磨国 \\
\text{C} & 28 & 支惟國 & 推定 & 吉備国 \\
\text{C} & 29 & 烏奴國 & 推定 & 吉備穴国造・備後国安那郡 \\
\text{C} & 30 & 奴國[2回目] & 推定 & 仲国造・常陸国那賀郡 \\
\text{D} & 31 & 狗奴國 & 推定 & 久努国造 \\
\end{matrix}
$$
このうち「推定」とある国々が前回調査を行った部分で、「既存有力」は既存の有力説をそのまま採用しています。「C」は「遠くてよくわからない国々」です。また狗邪韓國を除くA, B, Cは女王に属する国々とされ[松尾2014]、Dは女王と不和な国です。これらについて地理的な特徴として以下の結果を得ています。
(a)東西に長く東山道沿いの東国地名を含むこと、
(b)文中での出現順序と国々の位置には部分的な関連があり、一部は資料への追加によるものとみられること、
(c)狗奴国の位置に関する魏志倭人伝の記述「南にある」と後漢書東夷伝の記述「東へ海を渡る」が両立するとみられること
崇神天皇の遠征範囲
第10代崇神天皇は日本書紀、古事記の登場人物で、和風諡号をミマキイリヒコイニエノスメラミコト(御間城入彦五十瓊殖天皇)といいます。文献中では国土の最初の統治者と位置付けられています[井上2003a]。実在するか確認されていませんがいたとすれば3世紀後半から4世紀前半の人物と考えられています。日本書紀、古事記ともに第2代 - 第9代までは系譜(家系)以外の記述が著しく少なく、その和風諡号も後世風であること(つまり後世の付け足しの疑い)が指摘されていることに比べると、エピソードの記述も豊富で名前が実名風、当世風であることから実在する可能性が高いとされています[井上1973c]。
日本書紀を基準にすると、崇神天皇は四道将軍と呼ばれる4人の将軍たちに地方遠征を命じたことになっています。
九月丙戌朔甲午、以大彥命遣北陸、武渟川別遣東海、吉備津彥遣西道、丹波道主命遣丹波。
(九月の丙戌(ひのえいぬ)の朔甲午(きのえうま)(九日)に、大彦命(おおびこのみこと)を北陸に遣わし、武渟川別(たけぬなかわわけ)を東海に遣わし、吉備津彦(きびつひこ)を西道に遣わし、丹波道主命(たにはのちぬしのみこと)を丹波に遣わした。)
地名が分かる記述はこれだけで、遠征中の詳細などは分かりません。しかも古事記では遠征の実施時期に関して記述が食い違っています(後述)。史実性に関して(i)北陸・東海は阿部氏の家記、(ii)丹波はワニ氏の祖先伝承、(iii)吉備は吉備地方の氏族伝承ベースにした可能性が高く、四道将軍としてまとめて日本書紀に記載したのは後世の創作であるという指摘もありますが[前田2013]、地域豪族らの祖先の伝承などにこれらの将軍名が現れることから、個別の遠征活動自体はあっただろうとも考えられます[荊木2019]。また将軍の名前が遠征先の地名と同じ人がいますが、これは遠征先に土着したからと考えられます[荊木2019]。
同じ時代に、もう一か所遠征のような行動が記載されています。
則遣吉備津彥與武渟河別、以誅出雲振根。
(即座に吉備津彦と武渟河別とを遣わして、出雲振根を殺した。)
これの文脈としては、崇神天皇が出雲大社に納められている神宝を貢上するように出雲を支配する兄弟に要求し、貢上に反対する兄の出雲振根(イヅモノフルネ)が、貢上に応じた弟を騙し討ちにした、というシーンを受けてのものです。
以上の日本書紀の第10代崇神天皇期の遠征地域を地図に色分けして塗ってみました。色の違いは古事記との時期の齟齬を表します。色分けの単位は令制国としましたが現在の自治体境界を参考にしたため、大雑把な目安という程度のものです。具体的な範囲は以下のように決めました。
<スカイブルー>古事記も日本書紀も第10代崇神天皇期に記載のあるもの
東海道: 詳細な範囲は不明なため機械的に東海道に属する令制国を塗った。古事記では「東方十二道」とあり具体的な範囲は不明である。古代には武蔵国は東山道に属したため除外してある。伊賀、志摩は含めるべきか分からないが含めてある。また尾張、伊勢については以下の日本書紀本文の記述より除外した。
尾張: 崇神天皇妃の一人が「尾張大海媛」である(日本書紀)。
伊勢: 「伊勢麻績君」が3人同時に見た夢について崇神天皇に報告するくだりがある(日本書紀)。
北陸道: 北陸道に属する地域を塗った。古事記の「高志」(越)も同じ意味と思われる。佐渡島は含めるべきでないかもしれないが一応含めてある。近江国は遠征経路上にあった可能性が高いが東山道所属のため除外してある。
丹波: 古代の丹波国造は丹波、丹後、但馬を含むとのことなのでこれらをすべて塗った。ただし第9代開化天皇の后が丹波の人であったとあるため、実際の遠征対象は部分的か、もしくは第10代崇神天皇期より少し前に実施された可能性もある。
<サーモンピンク>古事記では第7代孝霊天皇期になっているもの
西道: 西道は山陽道のこととされるが、古事記ではより具体的に播磨・吉備とされているため播磨から備後までを塗った。
<ライムグリーン>古事記では第12代景行天皇期になっているもの
出雲:

この地図は女王に属する国々と第10代崇神天皇期の遠征範囲を比較したものです。御覧の通り、両者はあまり重ならないことが分かります。特にサーモンピンクで塗った部分(播磨・吉備)を除くとほとんど重なりが無いことが分かります。前述の通りサーモンピンク部分は日本書紀と古事記で記述が食い違っていて、古事記に従うと第10代崇神天皇期には遠征が行われなかったとされます。
前方後円墳の分布との関係
文献から取れる情報は限られているので、それ以外の情報で裏付けがないか探してみます。日本書紀において第10代崇神天皇の章には箸墓古墳の伝承があり、前方後円墳の出現との関連が示唆されます。

こちらの図は前方後円墳のもっとも初期の分布です[出田2015]。ここで編年には"集成編年"という方法が使われていて、これは畿内の前方後円墳について古いものから1期 - 10期に分類したものです[広瀬1991]。西暦との対応でいえば、筆者が畿内古墳の推定年代[白石1999]と比較すると、1期==3世紀下旬、2期==4世紀上旬ごろになるようです ([付録]参照)。他の推定年代を基準にすれば変わる可能性があります。
それで、この図の1期の前方後円墳の分布(上の図)と、前節にある地図を比較しますと、女王に属する国々と崇神天皇の遠征範囲を合わせた範囲が前方後円墳1期の分布とおおむね一致することが分かります。つまり「女王に属する国々の範囲」 $${\cup}$$ 「第10代崇神天皇期の遠征範囲」 $${\approx}$$ 前方後円墳1期の出現範囲、です。この法則がよくあてはまるのは例えば以下のエリアです。
$$
\begin{matrix}
\text{地域} & \text{女王に属す} & \text{崇神期遠征} & \text{前方後円墳1期} \\ \hline
会津付近 & \text{Y} & \text{-} & \text{Y} \\
東山道 & \text{Y} & \text{-} & \text{Y} \\
北部九州 & \text{Y} & \text{-} & \text{Y} \\
関東南部 & \text{-} & \text{Y} & \text{Y} \\
北陸 & \text{-} & \text{Y} & \text{Y} \\
丹波 & \text{-} & \text{Y} & \text{Y} \\
出雲 & \text{-} & \text{Y} & \text{Y} \\
中国西部 & \text{-} & \text{-} & \text{-} \\
鳥取県 & \text{-} & \text{-} & \text{-} \\
\end{matrix}
$$
ここで各地域の定義は東山道 (美濃、信濃、上毛野)、北部九州(筑前、筑後、肥前)、関東南部(相模、上総、下総)、中国西部 (長門、周防、安芸、石見)、鳥取県(因幡、伯耆)です。
しかし前方後円墳1期の分布が上記の法則と異なるエリアもあります。例えば以下の地域です。
$$
\begin{matrix}
\text{地域} & \text{女王に属す} & \text{崇神期遠征} & \text{前方後円墳1期} \\ \hline
東海 & \text{-} & \text{Y} & \text{-} \\
関東北部 & \text{Y} & \text{-} & \text{-} \\
瀬戸内南部 & \text{-} & \text{-} & \text{Y} \\
\end{matrix}
$$
ここで各地域の定義は、東海 (伊勢、遠江、駿河、伊豆)、関東北部 (常陸、下毛野)、瀬戸内南部(讃岐、伊予、豊前) です。これらの地域については後ほど考察しますが、全体として前方後円墳の分布との相関は認められるものの前述の崇神天皇期の遠征範囲と女王に属する国々の強い相関に比べるとはっきりしない印象です。
仮説と文献調査
仮説
なぜ「女王に属する国々」と「第10代崇神天皇期の遠征範囲」は重なりが少ないのでしょうか。恐らく、一番単純な解釈は以下のようなものです。
仮説1: 卑弥呼政権期の「女王に属する国々」は第10代崇神天皇期より前にヤマト政権に引き継がれた。よってこの地域は遠征する必要がなかった。
仮説2: 第10代崇神天皇期にヤマト政権は「女王に属する国々」以外の地域に遠征をおこない支配領域を拡大(追加)した。
この仮説はもちろん、卑弥呼政権==ヤマト政権の初期段階、のケースも含みますが、別物であっても良いです。
ただし以下のような解釈も可能なので、先に検討しておきます。
(仮説0): 日本書紀・古事記の編纂者は魏志倭人伝を参照し、上記の仮説1,2と辻褄が合うように第10代崇神天皇の遠征地を"創作"した。
実際、日本書紀は神功皇后の章で魏志倭人伝を引用しており、よって編纂者たちが魏志倭人伝の知識を持っていたことは明らかです。しかし[井上2003a][松尾2014]の解説によると、日本書紀の編纂者たちは卑弥呼を神功皇后のことだと思っていたとのことで、それに合わせて在位年代などが調整されています。神功皇后は第14代仲哀天皇の皇后で第10代崇神天皇より後の人物ですから、少なくとも仮説1を想定した創作になっておらず、よって仮説0は成り立たないと考えてよいと思います。前述の初期の前方後円墳の分布もおおむねこの見方を裏付けるように思います。
そこで以下の節では仮説1,2を支持するような記述が文献中にあるか、特に四道将軍の遠征のうち、西道(播磨・吉備)遠征については古事記の言うように第10代崇神天皇期より古い時代に実施されたことが分かるかを調べます。
各文献の記述との比較
前述のように、日本書紀の記述から尾張と伊勢を第10代崇神天皇期においてすでに支配下にあったとみて遠征範囲から除外しています。この場所は実際、「女王に属する国々」として投馬國(推定: 尾張国海部郡△津嶋)、伊邪國(推定: 伊勢国造)、蘇奴國(推定: 佐那県造)があると推定しています。
古事記での記述を見ます。4つの遠征については個別に扱われており、それぞれの記述は日本書紀よりやや詳細になっています。北陸道(高志)と東海道(東方)の遠征軍について以下の記述があります。
故、大毘古命者、隨先命而、罷行高志國。爾自東方所遣建沼河別與其父大毘古共、往遇于相津、故其地謂相津也。
(かくて大彦の命は前の命令通りに越の國にまいりました。ここに東の方から遣わされたタケヌナカハワケの命は、その父の大彦の命と會津で行き遇いましたから、其處を會津というのです。)
この会津の名前の由来が正しいかはともかく、なぜ海沿いを進んでいたはずの北陸遠征軍と東海道遠征軍が内陸の会津に集まったかを考えますと、やはり畿内に帰還するためだろうと考えられます。
東山道は畿内から近江、美濃、信濃、毛野、陸奥に至る内陸の街道で、古代には東北地方から畿内に至る最短ルートとされていました。よって遠征軍たちが内陸から東山道を通って帰ろうとするのは合理的な行動ではあるのですが、仮に東山道沿いの諸国が敵国だらけだったらこの話が成立しません。一方、会津および東山道エリアには女王に属する国々がいくつもあることが分かります:
邪馬國(推定: 陸奥国耶麻郡(会津郡より分離))、鬼奴國(推定: 毛野国)、姐奴國(推定: 科野国造、信濃国)、不呼國(推定: 信濃国安曇郡の穂高神社)、好古都國(推定: 美濃国方県郡)、彌奴國(推定: 美濃県主・三野前国造)。
彼らが帰還ルートとして会津および東山道を選んだとすれば、それらの女王に属する国々は敵国ではなく味方であろうと推測できます。つまりこれらの遠征活動の前にヤマト政権が女王に属する国々を引き継いでいたことを支持する記述になっています。
同様に東山道に関して古事記、および日本書紀に崇神天皇の皇子トヨキイリヒコノミコトによる東国統治の記述があります。
次豐木入日子命者、上毛野君、下毛野君等之祖也。
(次にトヨキイリ彦の命は、上毛野・下毛野の君等の祖先です。)
以豐城命令治東、是上毛野君・下毛野君之始祖也。
(豊城命をもって、東国を治めさせた。これが上毛野君・下毛野君の始祖である。)
古事記では実際に東国統治の命令がいつ出たのかは分かりませんが、日本書紀の記述では第10代崇神天皇期であることがわかります。恐らくその拠点が毛野国 (群馬県、栃木県)であろうと思います。毛野国は遠征地域からは外れていますが、すでに支配がされているような書き方になっています。一方、女王に属する国々には鬼奴國(推定: 毛野国)が含まれています。これも仮説1を支持する記述です。
魏志倭人伝の国々の記載順序

[前編]でも少し言及しましたが、魏志倭人伝の国々の文中での出現順序とその推定位置には部分的な関係があることがわかっています。この図は国の推定位置の経度を、本文中での出現順にプロットしたものです。国の分布は東西に長かったので主に経度を検討します。全体的には、一つの方向へ並んでいる傾向は認められませんでしたが、部分的には西から東(右肩上がり)へ並ぶ傾向が見られました。
一方、サーモンピンクで色を付けた3か国については逆順(右肩下がり)になっており、躬臣國(推定: 常陸国久慈郡、サーモンピンク領域の左)と奴國[2回目](推定: 常陸国那賀郡、サーモンピンク領域の右)の間に割り込んだ形になっているなど特異的です。この3か国は巴利國 (推定: 針間国造・播磨国)、支惟國 (推定: 吉備国)、烏奴國 ((推定: 吉備穴国造・備後国安那郡)で、ちょうど今回注目している播磨・吉備遠征地域にあります。
恐らくこの不自然な配置は、巴利國、支惟國、烏奴國を、ブロックC (遠くてよくわからない21か国) のリストに後から付け足したからではないかと思います。このように仮定するとそれ以降の順番は理解できます。おそらく最初はリストは18か国で躬臣國の次は奴國[2回目]があったのでしょう。そしてその後にはこの文章が続いています。
…。次有奴國。 此女王境界所盡。 其南有狗奴國。
(…。次に奴国がある。これが女王国の境界の尽きるところである。その南に狗奴国があり、)
このため、巴利國、支惟國、烏奴國を追加する際に奴國[2回目]をリストの最後から動かすことができず、その直前に挿入したと解釈できます。
仮にこの3か国の追加が起きたとすると、魏志倭人伝において播磨・吉備地域が女王に属したのは3か国ともほぼ同時期で「女王に属する国々」の中でも最後であると推測できます。また、追加の痕跡が魏(または晋)の資料に残っているわけですから、播磨・吉備が女王に属したのは卑弥呼と魏に交流があった期間(238年-247年)ごろであると推測できます。
前節の検討結果と総合すると、「女王に属する国々」がある地域は第10代崇神天皇期より前にヤマト政権の支配地域になったとみられ、したがって卑弥呼も第10代崇神天皇期より前の人物ということになります。そのうち播磨・吉備は卑弥呼の時代に一塊で最後に「女王に属する国々」に追加されたことが示唆され、これは古事記が主張するように播磨・吉備遠征が第10代崇神天皇期より前に実施されたことを支持しています。それが第7代孝霊天皇期であるとまでは言えませんが、吉備津彦など遠征した将軍らの世代を考えるとそれに近い時期でしょう。
なお、播磨・吉備地域には呼邑國(20番目、推定: 加夜国造・備中国賀陽郡)というのも見つかっていて、順番からすると、より古い時代に女王に属したと考えられますが、これと播磨・吉備遠征との関係はよく分かりません。日琉祖語の発音とのマッチングも良くなかったので、間違いの可能性も含め今後も検討する必要があります。
考察
前方後円墳の分布と合わない地域
前方後円墳の初期の分布を日本書紀・古事記に見えるヤマト政権の勢力範囲の拡大と関連付けるにあたって、いつ遠征されたか記述上は不明な領域 (会津、東山道、尾張、北部九州…)でも古墳が出現していますが、これらは女王に属する国々に相当していて、これを含める(仮説1)ことで大雑把には説明できることが分かります。しかしながらヤマト政権ならば前方後円墳であるというのは単純化しすぎとも言え(逆は真?)、部分的には合わないところもあります。以下に細かく見ますが、不明点が多く矛盾があるのかないのか現時点では断定できないです。また今回は令制国ぐらいの粒度で見ていますが古墳時代の地域支配者の単位はより小さかったはずで、詳細に見れば不一致はもっとあるかもしれません。これらは今後の課題となります。
東海地方 (伊勢、三河、遠江、駿河)
前方後円墳1期: 少ない
第10代崇神天皇期の遠征範囲、または女王に属する国々: あり
この地域では前方後円墳でなく前方後方墳が多かったとのことです[赤塚1996][白石1999]。よってこれらの地域では古墳の形態から政権帰属を判断するのは難しそうです。
また、遠征といっても相手勢力を滅ぼし代替するようなものだったかもよくわかりません。古事記では北陸・東海遠征の命令のシーンには「和平…」という語がつかわれていて交渉・説得が重視されたという解釈もあります[前田2013]。既存の在地豪族が遠征後もとどまり、墓制を維持した可能性があります。
北関東 (常陸、下毛野)
前方後円墳1期: なし
第10代崇神天皇期の遠征範囲、または女王に属する国々: あり
前方後円墳は上毛野(群馬県)にのみあります。前述の日本書紀に「豊城命をもって、東国を治めさせた。」とあることから、上毛野地域から北関東エリアを広域的、集中的に統治していたのかもしれません。そうであれば矛盾というほどでもないですが不明点がおおいです。
補足: [若狭2018] によると、上毛野地域では畿内庄内式後半から布留0式土器並行期に東海西部から利根川などの低湿地への大規模かつ組織的移民があり、故地との情報交流を続けたとみられる、とのことです。S字口縁台付甕や廻間II式新段階などの伊勢・尾張の土器の出現や、墳墓が前方後方墳に転換することを根拠としています。S字甕は下毛野・那須、常陸北部、三浦半島、南武蔵の東京低地でもみられ、前方後方墳は那須にも多いとのことです。これは時期的には卑弥呼期 - 前方後円墳1期のころにあたりますから、この地域が伊勢や尾張と同じ政治勢力に属していた可能性はありそうです。前述のように伊勢や尾張と北関東エリアには女王に属する国々が見つかっています。また同時により詳しく調べるためには前方後方墳の初期の分布も見る必要がありそうです。
瀬戸内海西南部(讃岐、伊予、豊前)
前方後円墳1期: あり
第10代崇神天皇期の遠征範囲、または女王に属する国々: なし
上記と逆パターンです。第7代孝霊天皇期から第10代崇神天皇期まで半世紀ほどあるので、この間に記紀に記述のない遠征が別途行われたのか、もしくは日本書紀の第10代崇神天皇期にある「西道」がこの地域を表しているのかもしれません。
モデルケース年表での整理

話の前後関係が複雑になってきたので、モデルケースの年表を作って整理します。これは大雑把に前後関係を再現するためのもので、絶対年は筆者が適当なパラメーターを導入して推計したものです。推計に使用したパラメーターは以下の通りです。
古事記の播磨・吉備遠征と魏志倭人伝の巴利國、支惟國、
烏奴國が服属した年代を同一視し西暦240年ごろ?とした魏と交流があった西暦238-247年ごろとの推測から。([魏志倭人伝の国々の記載順序]節を参照)
卑弥呼と第7代孝霊天皇期の即位年代を西暦220年ごろ?~とした。
卑弥呼の在位は魏と交流があった西暦238-247年を含むから。
第7代孝霊天皇期は古事記説によると播磨・吉備遠征を含むから。
かつ在位期間が30年を超えることはまれなので。
記紀の天皇の在位期間は第7代孝霊天皇を基準に、機械的に1代あたり平均在位年数20年で計算した。
平均在位年数の見積もりは[付録]参照。
魏志倭人伝の「倭国乱」を「梁書」より西暦180年ごろ?とした。
邪馬台国でもともと男子の王がいた年代を、魏志倭人伝の記述に従って「倭国乱」から80年前とした。
前方後円墳の集成編年の1期 / 2期境界は前述の[広瀬1991]による標式的古墳と[白石1999]の近畿大型古墳の推定年代を比較することで、西暦300年ごろ?とした。
詳細は[付録]参照。
色々微妙な仮定がありますが、前方後円墳の広がりと卑弥呼政権の広がりおよび初期ヤマト政権の遠征活動が対応付けられ、矛盾のある記述も特定しやすいと思います。
結果的に、初代神武天皇と邪馬台国にもともと男子の王がいた年代が一致したように見えますがこれは偶然で、実際には卑弥呼や第7代孝霊天皇の即位年に10-20年程度の自由度があり、天皇の平均在位年数も10%ぐらいずれてもおかしくないので、20-40年程度はずれることがあり得ます。
既存研究の想定年代との関連
第10代崇神天皇は実在したとすれば3世紀後半から4世紀前半と推定されるとのことです。在位年代について具体的には以下のような説が出ています。
[井上1973c] 270年 - 290年ごろ
比較的実在性が高いとされる応神天皇(370年 - 390年ごろ)から1世代20年として5世代さかのぼったもの。
[笠井1953] (?) - 318年 "記註干支" (崩御年のみ)
古事記の註にある干支「戊寅」より60年の整数倍の自由度を考慮し258年または318年とする。
[笠井1953] 285年 - 301年 "原書紀"
日本書紀の在位年数から引き延ばしによって生じた空白の年を削除したもの。
[笠井1953] (293~296)年 - (309~312)年 "訂正紀年"
上記の"原書紀"に百済資料による修正と古事記の干支の影響を加味し、さらに宋書の倭の五王記述による補正を行ったもの (大変複雑)。
[小沢2007] (?) - 364年 (崩御年のみ)
指数関数型の回帰モデル。
(筆者の印象では仁徳天皇前後では継承パターンが異なることがモデルに反映されていないように思われる。-> [付録]参照)
[本調査結果] 280年-300年ごろ
魏志倭人伝の魏への朝貢期間(238年-247年)が第7代孝霊天皇の在位期間に重なるように220年ごろ即位として1世代20年で3世代下ったもの。20年程度後ろにずれうる。
本調査結果は大雑把な計算ですが、既存研究と違い魏志倭人伝の値を含めたわりには、近い結果になっています。これで崇神天皇の在位年代の精度が上がるわけではないのですが、少なくとも魏志倭人伝の魏への朝貢期間に播磨・吉備遠征が起きた、という仮定が他の説の年代感から大きくずれているわけではないということは分かります。
結論
前回のブログにて魏志倭人伝に含まれる「遠くてよくわからない国々」21か国を含む国々の位置の推定を、当時の中国語(上古音と中古音(魏晋期))および倭人語(日琉祖語6母音説)の再構音に基づいて行いました。これの有効性を検証するために、得られた国々の場所を日本書紀の第10代崇神天皇期の遠征範囲、およびその古事記における対応物と比較しました。その結果以下のような特徴がありました。
第10代崇神天皇期の遠征範囲は、特に古事記に従って播磨・吉備遠征を崇神天皇期より前とする場合には、魏志倭人伝に登場する「女王に属する国々」とほとんど重ならない。
前方後円墳の1期の分布は、「女王に属する国々」と第10代崇神天皇期の遠征範囲を合わせた領域におおむね一致するが例外がある。
これらの特徴は以下の仮説により説明することができます。またそれと整合する記述・特徴が各文献から見つかっています。
仮説1: 卑弥呼政権期の「女王に属する国々」は第10代崇神天皇期より前にヤマト政権に引き継がれた。よってこの地域は遠征する必要がなかった。
古事記、および日本書紀のいくつかの記述のうち「女王に属する国々」に対応する地名を持つ地域については、第10代崇神天皇期より前からヤマト政権に属していたことを示唆するものが複数ある。
仮説2: 第10代崇神天皇期にヤマト政権は「女王に属する国々」以外の地域に遠征をおこない支配領域を拡大(追加)した。
魏志倭人伝に登場する国々の文中での出現順序との関係を調べると、播磨・吉備に相当すると推定した巴利國、支惟國、烏奴國には資料に付け足した痕跡が見られ、卑弥呼の在位期間の最後の方で3か国まとめて「女王に属する国々」に加わったことが示唆される。これは前述の播磨・吉備遠征が崇神天皇期より前とする古事記の記述を支持し、重複を解消する。
当初の目的に戻ると、前回発音から推定した魏志倭人伝の国々のうち、「女王に属する国々」の部分の位置が、第10代崇神天皇期の遠征範囲と強い(負の)相関を持っており、これは偶然ではなく共通の事象 (初期のヤマト政権の勢力拡大) が関連しているからと見られます。よって個別の魏志倭人伝の国の推定位置・地名を正当化するには至りませんが、大半の国々は妥当な推定ができていると期待できます。
今後の課題ですが、筆者の知識不足やデータ不足などで今回の仮説にはまだ多くの不明点や不整合が含まれます。今回の話の信頼性を高めるには、これらを理解していく必要があると思います。今回、例えば前方後円墳の分布を時代を区切って全国レベルで表示するだけでも結構難しいことを実感しました(今回は論文を引用させていただいています)。学術の進歩を気長に待ちつつ、既存研究などご存じの方がいらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。(他力本願)
前方後円墳は卑弥呼の時代から半世紀近く離れているが、より同時代の考古学的な遺物で「女王に属する国々」の分布を確認できないか (鏡? 庄内式土器? 布留式土器?)。またそれに関連した電子化データの整備。
魏志倭人伝と古事記を繋ぐとみられる、播磨・吉備遠征の実態はどのようなものか。
初期のヤマト政権における東国、特に関東北部の統治の仕組みはどのようなものか。
前方後円墳と前方後方墳はどのように使い分けられているのか。
讃岐・伊予・豊前地域では1期から前方後円墳が出現するが、そのヤマト政権とのかかわりはどのようなものか。
付録
集成編年と西暦の対応
"集成編年"とは近藤義郎 (編) (1991-)「前方後円墳集成」山川出版社という本のシリーズで使用されている前方後円墳の編年法の通称です。これは古墳の形状、埴輪の形式、副葬品の特徴などの組み合わせで古墳時代の古墳を古いものから1期 - 10期に分類したものです。以下に1期、2期の定義を引用します[広瀬1991]。
1期:
円筒埴輪はまだみられず、都月式すなわち特殊器台型埴輪や特殊壺形埴輪をともなう場合がある。仿製鏡はなく、中国鏡のみが副葬される。バチ形の前方部を持つ。
標式的な前方後円墳: 奈良県箸墓古墳・中山大塚古墳、京都府椿井大塚山古墳、兵庫県権現山1号墳、岡山県浦間茶臼山古墳
2期:
円筒埴輪のI式。三角縁神獣鏡・方格規矩鏡・内行花文鏡などの大型仿製鏡や車輪石・石釧などの碧玉製腕飾類、紡錘車・玉杖などの碧玉製品、筒形銅器などが出現する。
標式的な前方後円墳: 京都府寺戸大塚古墳、奈良県桜井茶臼山古墳、大阪府平尾城山古墳・玉手山9号墳、滋賀県安土瓢箪山古墳
標式的な前方後方墳: 大阪府紫金山古墳
集成編年は相対的な時代の前後関係だけを定義します。西暦年との対応で業界標準があるのか筆者にはよくわかりません。今回は、集成編年の1期 / 2期境界を、前述の[広瀬1991]による標式的古墳と[白石1999]の図17「近畿中央部における大型古墳の消長」の年表の古墳を比較することで、西暦300年ごろ?としました。集成編年の1期あたりの間隔はおおむね1/3世紀ぐらいのようなので、1期==3世紀下旬、2期==4世紀上旬ごろのようです。
これらは畿内の古墳の年代に基づきます。畿内古墳の編年と西暦の対応を全国同一としていいかは微妙です。
古代の平均在位年数の見積もり
実在性がはっきりしている継体天皇以降の日本の飛鳥・奈良時代の天皇の平均在位年数は約11年であることが知られていますが、これは諸外国に比べるとかなり短いです。これは他国では親子・世代間の継承が基本なのに対し、日本では兄弟間の皇位継承が多いためと見られます。これが本格的に始まったのは、日本書紀や古事記によると第16代仁徳天皇の次の世代からとなっています。少なくとも第10代崇神天皇以前は系譜の上では全て親子継承となっているため、今回の平均在位年数としては周辺各国のおおよその平均値である約20年を採用しました。
百済: 16.5年 (標準偏差13.6年)
第13代近肖古王 - 第31代義慈王 [Wikipedia朝鮮の君主一覧]
高句麗: 23.7年 (標準偏差14.7年)
第7代次大王 - 第28代宝蔵王 [Wikipedia朝鮮の君主一覧]
新羅: 23.3年 (標準偏差12.5年)
第2代南解次次雄 - 第30代文武王 [Wikipedia朝鮮の君主一覧]
後漢: 14.0年 (標準偏差11.6年)
第1代光武帝 - 第14代献帝 [Wikipedia後漢]
(参考)日本: 10.8年 (標準偏差9.2年)
第26代継体天皇 - 第49代光仁天皇 [Wikipedia天皇の一覧]
女王国 - 狗奴国紛争のその後
先の地図中で魏志倭人伝の狗奴国をグレーのマーカー (静岡県袋井市久野、久努国造と推定) で示しています。この推定と文献中の記述に関する考察は[前編]をご覧ください。[若狭2018]によると相模、東京湾西岸では弥生後期前半から中葉にかけて (つまり卑弥呼の時代より少し前に) 東海東部系土器の移入がおきたとされています。この頃狗奴国があったか分かりませんが、考古学的には同じ文化圏が東海東部から関東南部まで広がっていた可能性が示唆されます。
それで、よく知られるように狗奴国と女王国は対立していました。
其南有狗奴國。男子爲王。其官有狗古智卑狗 。不屬女王。
(その南に狗奴国があり、男を王とする。その官に狗古智卑狗がある。女王に属さない。)
…
倭女王卑彌呼、與狗奴國男王卑彌弓呼、素不和。 遺倭載斯烏越等、詣郡說相攻擊狀。
(倭の女王卑弥呼は、狗奴国の男王卑弥弓呼ともとから不和である。倭(の)載斯烏越らを遣わして郡にゆき、たがいに攻擊する状態を説明した。)
今回の地図では狗奴国はスカイブルーで塗った東海道遠征の対象地域に入っていることが分かります。よって今のところ、最もシンプルな解釈としては、この対立関係がその後も解消せず、仮説1,2と整合的にヤマト政権もこの対立を引き継いだとみられます。狗奴国の場所の推定が正しく、東海道遠征が史実とすれば、紛争は40年近くかかって狗奴国の敗北で終わったと思われますが、前述の通り東海地方は前方後円墳1期の出現が少なく、前方後方墳の文化圏だったとのことで[赤塚1996][白石1999]、そのまま地域豪族として生き残った可能性もあります。この間の両国のパワーバランスの変化などいろいろ気になりますが今回のトピックの範囲を超えています。
参考文献
[赤塚1996] 赤塚次郎 (1996). 「前方後方墳の定着--東海系文化の波及と葛藤」, 『考古学研究』第43 巻第2 号. pp.19-35
デジタル画像 (国会図書館利用登録が必要) https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6057664
東海地方、特に伊勢湾沿岸地域の土器と墳墓の独自性と他地域への波及について、狗奴国とヤマト政権の緊張を背景として考察している。
[広瀬1991] 広瀬和雄 (1991). 「前方後円墳の畿内編年」 in 近藤義郎 (編)「前方後円墳集成〈中国・四国編〉」山川出版社.
全6巻からなる。
古墳の構造、埴輪、鏡など副葬品の種類、形態から区分される定性的な順序で、西暦との対応は記載されない。
[荊木2019] 荊木美行 (2019). 「「四道将軍伝承」再論 : 王族将軍派遣の虚と実」 皇学館論叢 = KOGAKKAN RONSO 52 (6), 1-30, 2019-12 皇学館大学人文学会
日本書紀、古事記の記述について各地の氏族伝承と比較し四道将軍という形は後付けであるものの、個別には史実としている。時期についても吉備が早いと考えている。
吉備津彦と丹波道主命が遠征地と同じ名前なのは土着したからとしている。
[出田2015] 出田 和久 (2015). 「前方後円墳の地域性 ―分布論的アプローチから― 」, 人文地理学会大会 研究発表要旨 2015(0), 14-17, 2015
https://www.jstage.jst.go.jp/article/hgeog/2015/0/2015_14/_article/-char/ja/
古墳時代1期の分布の地図が載っている。
前方後円墳(前方後方墳を含む)5,200 基についてGIS データベースを構築、とある。
[井上1973c] 井上光貞 (1973).『日本の歴史1 神話から歴史へ』中央公論社〈中公文庫〉、p.267-292、1973年10月。ISBN 4-12-200041-6。
崇神天皇実在論、3-4世紀初めとする。根拠は和風諡号の傾向で、1-9代までは地名と尊称・敬称部分を除くと固有名詞の成分が継体天皇以降のそれと類似しており、後世に付けられたとみられるが、崇神天皇、垂仁天皇、景行天皇に関しては応神天皇以降のそれと同様で同時代の本名に基づくことみられることから。
一方で、政務天皇、仲哀天皇、神功皇后はやはり後世風の名前に戻り倭建命と共に架空で、応神天皇の実際の継承は古事記の注から景行天皇-五百木之入日子命-品陀真若王-中日売、つまり婿入りだとする。
在位は応神天皇(370-390?)からの逆算で1世代20年として270-290としている。古事記の干支「戊寅」より258, or 318は信用できないとしている。
[井上2003a] 井上光貞(監訳)、川副武胤(訳)、佐伯有清(訳)。日本書紀(上)中央公論新社、2003
[井上2003b] 井上光貞(訳)、笹山晴生(訳)。日本書紀(下)中央公論新社、2003
[石原1951] 石原道博(編訳)「新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝-中国正史日本伝(1)」岩波文庫 (1951)
[笠井1953] 笠井 倭人 (1953).「<論説>上代紀年に関する新研究」. 史林 36, 4, p.333-356. 25-Oct-1953. 史学研究会 (京都大学文学部内) .
[岸本2014] 岸本直文、倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス 国立歴史民俗博物館研究報告-第185集、2014。 https://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185012.pdf
[古事記712] 稗田阿禮、太安萬侶 (712)「古事記」。
[松尾2014] 松尾光(訳)「現代語訳 魏志倭人伝」KADOKAWA (2014)
[日本書紀720] 舎人親王ら (720) 「日本書紀」、
:: 日本書紀、全文検索 http://www.seisaku.bz/shoki_index.html
[小沢2007] 天皇崩年の数理モデル 小沢 一雅 情報処理学会研究報告人文科学とコンピュータ(CH)2007 78(2007-CH-075) 23 - 30
元は安本1953の線形回帰モデル。今回は非線形(指数関数型)でなめらかに近似してある。
:: 情報学広場:情報処理学会電子図書館 https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=54979&item_no=1&page_id=13&block_id=8
[三國志v30] 陳壽 作(西晉時代), 裴松之 註 (南朝劉宋時代). 三國志/卷30
以下は電子化テキストデータ。
维基文库,自由的图书馆
https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B730#%E5%80%AD%E4%BA%BA底本不明
:: 魏志倭人伝 - Wikisource
https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%AD%8F%E5%BF%97%E5%80%AD%E4%BA%BA%E4%BC%9D出典:三国志魏書巻三十東夷伝(国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/899855/59
[白石1999] 白石太一郎『古墳とヤマト政権』(文春新書、1999年)
[武田1956] 武田祐吉(訳)、(現代語譯)古事記、角川文庫、角川書店 1956
[若狭2018] 若狭 徹 (2018).「東国における古墳時代地域経営の諸段階 : 上毛野地域を中心として (第3部 倭の地域社会)」 in 国立歴史民俗博物館研究報告 Vol. 211, p.307 - 350, 2018-03-30. 国立歴史民俗博物館
[Wikipedia天皇の一覧] 天皇の一覧 - Wikipedia
[Wikipedia朝鮮の君主一覧] 朝鮮の君主一覧 - Wikipedia
[Wikipedia後漢] 後漢 - Wikipedia
更新履歴
2022/09/21 末盧の盧を廬と書き間違えていたので修正。
2022/06/19 遠絶21か国という語を追加。
2022/06/19 [若狭2018]を追加。「考察」の前方後円墳の分布および「付録」の狗奴国のくだりから引用。
