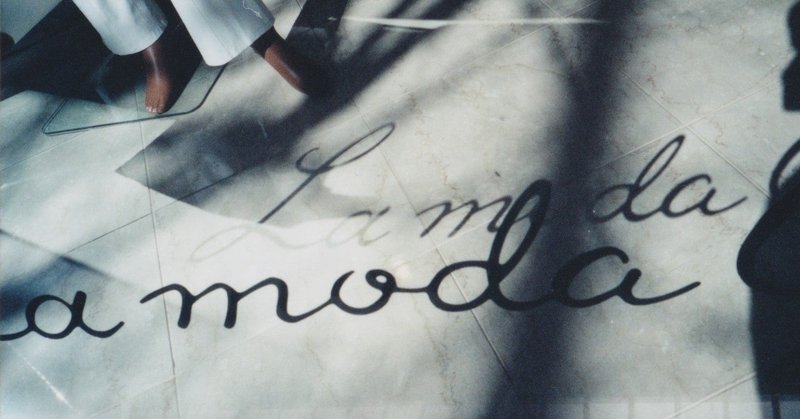- 運営しているクリエイター
2020年7月の記事一覧
今月読んだ本一覧(2020.7)
今月読んだ本の覚え書き。なぜか国内外の文化理解に時間を割いた月間でした。あとライトめなエッセイもいくつか読んだので、軽いものも読みたいぞ〜という方はぜひ。
もっとみる小売企業のオンライン化を阻むもの
世間ではデジタルトランスフォーメーションが盛んに叫ばれているけれども、小売企業、特に中小企業のデジタルシフトを阻んでいるのは、みんな公には口に出さないけれど意外とこれだよね、とよく話題にでるのが
今月の #あさみのまなび ベストセレクション
今月もSlackコミュニティ内でのつぶやきを一部抜粋してご紹介します。
Slackでは、ツイートには書ききれないけれどnoteに書くほどまだ考えがまとまっていないことを思いつくままに書き綴ったりしています。
「レンタル」について考える
シェアの概念が広がってきたとはいえ、実生活でレンタルサービスを積極的に取り入れている人はそう多くないのではないかと思う。
かくいう私も、仕事柄いくつか試してみたサービスはあるものの現在まで続けているサービスは皆無である。
自分の消費行動を振り返りながら、どういう仕組みであれば長くレンタルサービスを使いづつけたくなるのかを考えていて、ふと気づいたことがある。
競合の施策をリサーチする際の視点
ビジネスにおいて「他の企業がどうやっているか」をリサーチするのは基本中の基本である。
その上で、何を参考にすべきか取捨選択するところにセンスがでるとも言える。
競合リサーチと聞くとどうしても「何を取り入れるべきか」を追随する印象を受けやすいが、もっとも重要なのは何が現在のスタンダードであり、ユーザーの期待値がどこにあるかを探る方が重要なのではないかと思う。
「本は名刺代わり」と言うけれど
ここ数年、とんと新刊を読まなくなった。理由は複数あるけれど、「ビジネス書の広告化」が一番大きな理由であるように思う。
いつの頃からか、「名刺がわりに出版する」という考え方がビジネスパーソンの間で一般的になった。出版するにはある程度の実績が必要なので、書籍を出すことで権威性や信頼性が増すこと自体は疑いようもない事実である。
しかし出版がマーケティング的にハックされてしまったことで、消費者側もその
今週読んだ海外記事と雑感(2020.7.18)
今週もピックしたニュースとコメントを転記してまとめておきます。
有料部分はニュースへの雑感です。
スターバックスがパンデミックから学んだこと大手メーカーがD2Cに参入する理由
日米における生活雑貨への認識の相違について
無印良品の米子会社破産が日本でもニュースになった。日本では優良企業の代表選手とも言える無印良品だが、日経の記事を読んだ限りではコロナ前から厳しい状況ではあったようだ。
日経の記事では中国で作った製品をアメリカへ輸出するかたちだったこと、アメリカの家賃の高さから商品価格が割高になってしまったという構造的な問題が取り上げられていたが、そもそも生活様式の違いもあるのではないかと個人的には感じている。
私たちは、「お手本」にすべき相手を間違えているのかもしれない
以前この記事でも書いた通り、私はなるべく国内外の事例をすべてフラットに見るように心がけている。
この視点を持って日々のニュースを見ていると、そもそも欧米を先進事例として見習うことが正しいのだろうか、と疑問に感じることが増えた。
なぜ日本で「ソーシャルグッド」な思想が広がらないのか
差別問題やフェミニズムなど、企業が社会課題に対して意思を表明するケースが増えてきた。もともとLUSHやスターバックスなど環境問題に力を入れる企業はあったが、SNSを通して明確にポジションをとるブランドが増えたのはD2Cをはじめ、顧客と直接つながる企業が増えたからなのかもしれない。
顧客側もサスティナビリティや女性支援など「ソーシャルグッド」なものを選ぶようになりつつあり、その割合は急激に上昇して
今週読んだ海外記事と雑感(2020.7.11)
今週もピックしたニュースとコメントを転記してまとめておきます。
有料部分はニュースへの雑感です。
百貨店の撤退がもたらすショッピングセンターの受難パリコレがデジタル配信に特化したメンズコレクションを実施
民族衣装化していくスーツというファッションについて
ブルックスブラザーズの破産が日本で大きな話題となった。日本事業は国内オリジナル商品が多く事業母体も異なるため影響ないとはいえ、名門の破産はスーツ文化の衰退を象徴しているように思う。
公式声明にもあったとおりこのパンデミック前からオフィスコードのカジュアル化やアスレジャー人気によって伝統的なスーツブランドは苦境に立たされてきた。スーツそのものの需要が減っているのだから、スーツをメインで取り扱ってき
自他をフラットに見るために
「消費文化」を自分のテーマにしていることもあり、日本と海外を比較考察する機会が必然的に多くなる。海外事例を見て日本市場でどう取り入れるかを考えることもあれば、日本企業の戦略を海外市場でもマッチさせるにはどうするべきかを考察することもある。日課であるオンライン英会話で様々な国の先生と話しながらそれぞれの文化の違いを知り、その違いが消費文化に与える影響に気付いたりもする。