
#64 「ほうれん草」のガチ解説
※”ガチ解説シリーズ”では、栄養素や食材についての解説を行なっています。
現代の社会では、健康を害するようなものが、店頭に置かれていたり、TVでも
平気で紹介されていたりする時代です。
この現状を僕一人で変えることはできません。
しかし、僕が自己投資をして学んだことを発信することで、僕の周りにいる人に正しい情報が伝わり、その人たちの健康を守ることができたらいいなというつもりで、このnoteを書いています。
残念ながら、まだまだ影響力がないので、この”ガチ解説シリーズ”が良いと思っていただけたら、シェアをしていただいてより多くの人に情報が届けばいいなと思っています。ぜひ協力をお願いいたします。
と、言いますことで。早速今回も解説していきまっしょ。
今回は「ほうれん草」についての解説です。
「ほうれん草」といえば、『鉄分』が豊富なんて言われたりしますね。
これは間違いなく正解です。
では、それ以外に「ほうれん草」を食べることで良い効果があるのか?
せっかくなら、一石二鳥。いや、一石三鳥、四鳥くらい合ったら最高ですよね!
果たして、それだけの効果があるのか。見てみましょう。
○「ほうれん草」について

「ほうれん草」は、アカザ科ほうれん草属の野菜で、原産地はペルシャ地方とされ、日本には江戸時代の初めごろに伝わったとされています。
ヨーロッパやアメリカなど、世界的に各地で食用とされている野菜の一つです。
「ほうれん草」の品種について、普段気にすることはなかなかないと思いますが、よくみると「ほうれん草」にも微妙な違いがあります。
「東洋種」・・・葉の切れ込みが深く尖った形をしていて、アクが少なく、お浸しにしても美味しい品種です。
「西洋種」・・・葉は切れ込みがなく丸みを帯びていて、少し厚みがあります。アクが強いため、ソテーなどの調理方法の方が相性がよく、魚や肉料理の付け合わせに向いています。
「寒じめちぢみほうれん草」・・・主に関東で冬だけに露地栽培されている品種になります。
「サラダほうれん草」・・・アクをより少なく改良し、生でも美味しく食べられるように改良されたものがいくつかあります。赤軸または赤茎のサラダホウレンソウもその一つです。
「ほうれん草」の栽培が盛んな地域としては、
1位は『千葉県』で年間約39,000t。
2位は『埼玉県』で約32,000t。
3位は『群馬県』で約20,000t。
4位は『茨城県』で約15,300t。
となっています。
上位4県は、いずれも関東地区で、栽培が盛んとなっています。
また、「ほうれん草」の旬は、全国で様々な品種が地域を変えながら栽培、収穫されているため、年間を通して市場に出回っていますが、
本来の旬は11月〜1月です。
この時期は、「ほうれん草」の色味も濃くなり、栄養分も増して甘味もあります。
○「ほうれん草」の栄養価と効能
「ほうれん草」は、見た目からも分かる通り、”緑黄色野菜”になります。
”緑黄色野菜”は、ビタミンやミネラルなどの栄養価が非常に高いという特徴があるので、「ほうれん草」はとても優秀な食材と言えます。
では、具体的にどのように優秀なのかを解説していきます。
・鉄分(非ヘム鉄)
「ほうれん草」と言えば、『鉄分』じゃないでしょうか?
『鉄分』は、”貧血”の予防には欠かすことができない栄養素ですが、現代の日本人は不足しがちな栄養素と言われています。
理由としては、単純に”『鉄分』の摂取量が少ない”ということや”『鉄分』は吸収がしづらい”ということがあると思います。
「ほうれん草」に含まれる『鉄分』は、”非ヘム鉄(植物性鉄分)”です。
『鉄分』は元々吸収しづらいという特徴がありますが、”非ヘム鉄”に関しては、さらに吸収がしづらいです。
”貧血予防”で「ほうれん草」を食べることも良いですが、その場合は吸収がよくなるように食べ合わせが重要になります。
・β–カロテン
「ほうれん草」には、『β-カロテン』が含まれています。
『β-カロテン』は、体内に入ると”ビタミンA”に変換されます。
『β-カロテン』には抗酸化作用があり、効果としては
★体の老化現象(しみ・そばかす・しわなど)の予防
★粘膜や皮膚の健康維持による美肌効果
★髪の健康維持
★視力機能の維持
★呼吸器系統を守る働き
・骨の形成、健康維持
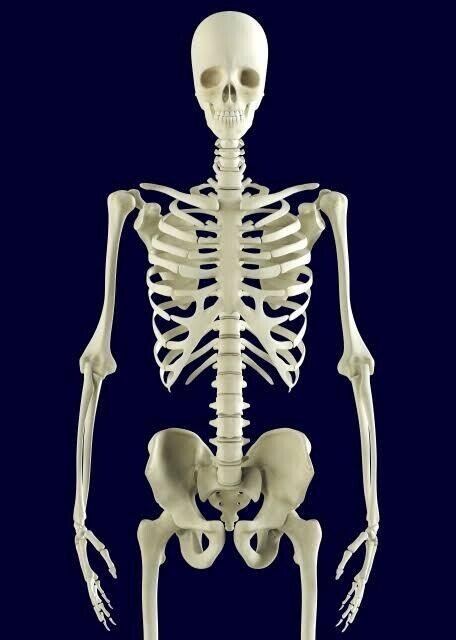
「ほうれん草」には、『カルシウム』や『マグネシウム』といった”骨の形成”に必要な有名な栄養価が多く含まれている他、『マンガン』なども含まれています。
”骨の形成”と言えば、牛乳などをイメージすると思いますが、「ほうれん草」も”骨の形成”には良い食材だと思います。
(ちなみに過去の記事でも紹介していますが、牛乳は”骨の形成”には向いていない食材です。理由が知りたい方はぜひ過去の記事を探して読んでみてください。)
・ビタミンC
「ほうれん草」には、『ビタミンC』も含まれています。
『ビタミンC』には、
★免疫機能を向上させる
★体の老化現象の予防
★動脈硬化などの生活習慣病予防
★美肌・美容効果
★副腎皮質ホルモンの生成促進
★抗発がん作用
などの効果があります。
健康や美容などを意識している人にとっては、とても大切な栄養価になると思います。
また、『ビタミンC』は、水溶性であり、体内に貯蔵することができないので、コンスタントに摂取する必要があります。
毎食の食事で「ほうれん草」含めて『ビタミンC』がある食材を食べる、もしくは、サプリメントなどで補うなどの工夫が必要です。
さらに、『ビタミンC』には、『鉄分』の吸収をよくする効果もあるため、吸収がしづらい”非ヘム鉄”が含まれる「ほうれん草」も『ビタミンC』が含まれるので、吸収はしやすい状態だと言えますね。
○「ほうれん草」の注意点
最後に「ほうれん草」についての注意点。
「ほうれん草」にあるアクには『シュウ酸』というものが含まれます。
この『シュウ酸』は、大量に摂取すると最悪の場合、”結石”の原因になる可能性があるものになるので、注意が必要です。
この『シュウ酸』は、水溶性の物質であるため、茹でて水にさらすことで除去することができます。なので、お浸しなどの要領で調理してもらえれば心配はありません。
ただし、炒めるだけでは除去ができないので、炒め物にする場合であっても一度茹でてから調理することをお勧めします。
生食用として販売されている『サラダほうれん草』に関しては、『シュウ酸』の含有量が少ないので、した茹でをしなくても食べることができます。
「ほうれん草」についての記事は以上です!
「ほうれん草」は、栄養価が高く、調理がしやすい食材であり、一度湯がけば冷凍保存などもできるので、便利な食材だと思います。
ぜひ日頃の食事の一つに「ほうれん草」を取り入れてみてください!
この記事がいいなと思ってくれた方は、ぜひスキ(♡ボタン)&フォローお願いします!
もしよければシェアしてください!
次回の記事もお楽しみに❗️
いいなと思ったら応援しよう!

