
「この女性は美しい」とはどういう判断か?
カント的なことを書きます。「的な」と書いたのは、『判断力批判』の趣旨をきちんと理解しているという自信がないからです。「的な」には、あくまでも「私が理解した範囲で」「読んで考えた限りにおいて」というニュアンスを込めています。
この記事を読んで「カントはそういうことを言っているのか!」と早合点しないように念を押します。
以後「私の理解した範囲では」という言葉を付け加えることはありませんが、すべてのセンテンスにおいて、この留保条件がついていることに対して注意喚起しておきます。
3つの判断
「美学的判断力」は、3つの「判断」から成り立ちます。
すなわち、「趣味判断」「論理判断」「感官判断」の3つです。
簡単に言うと、次の通りです。
「この女性は美しい」(趣味判断)
「女性は一般的に美しい」(論理判断)
「この女性は好ましい」(感官判断)
「趣味判断」とは、個別具体的な「美」に対してくだされる判断のことです。私が「この女性は美しい」と言うとき、そこにあるのは、あくまでも私の「主観的な判断」ですよね?
しかしながら、「この女性は『私にとって』は美しい」という意味ではありません。
もしも「この女性は美しい」ということと、「この女性は私にとっては美しい」ということが同じならば、言い方こそ違うものの、「この女性は好ましい」という「感官判断」と結局は同じことになってしまいます。
「趣味判断」と「感官判断」とが異なるのは、次の点です。
「この女性は美しい」という趣味判断は、あくまでも私の主観的な判断ではありますが、「この女性は美しい」という言葉には、他の人にとっても美しいものに違いないという判断があります。換言すれば、私の主観的な美の判断に、あたかも「普遍性」があると考えていることに他なりません。
それに対して、感官判断である「この女性は好ましい」という言葉は、他の人にとっても好ましいものであってほしいという判断ではありませんね。他人がどう判断しようが、「私にとって好ましい」ならば、それでいいわけです。

「この女性は美しい」という趣味判断が主観的判断でありながら、普遍性を要求する判断であるのに対して、「この女性は好ましい」という感官判断は主観的判断を超えた普遍性を求める判断ではありません。
論理判断とは、いわば客観的な判断です。歴史的なものにせよ、経験的なものにせよ、世の中でいう「あるべき姿」のことを論理判断と言います。私がどう思おうが、一般的に妥当だと考えられているものか、いないものかを判断するのが「論理判断」です。
論理判断に関しては、この記事では深入りしません。この記事で問題にしたいのは、「趣味判断」と「感官判断」に関してです。

2つの主観的判断
主観的な判断には、「この女性は美しい」という趣味判断と「この女性が好ましい」という感官判断があります。
趣味判断と感官判断は、どちらも主観的な判断ですから、どちらの判断が上か下かということはないはずなのですが、
カントは、趣味判断を感官判断より上位にあると考えています。というのは、趣味判断が「普遍性」を持ち得る判断であるのに対して、感官判断は一時的であれ何であれ、「今、好ましい」ならばそれで良いという判断だからです。
語弊はありますが、もっと言えば、感官判断は「今さえ楽しければよい!」ということなので、何度も感官判断を重ねても「精神的な成長がない」。
それに対して「趣味判断」は、他の人にも共通する、普遍的な美に近づいていける可能性があります。
カントは「価値」的に、
「趣味判断>感官判断」と考えています。
私も趣味判断のほうが感官判断よりも上にあると思っています。
(比喩として適切かどうかは分かりませんが)すごく俗なことを言えば、感官判断は「性的な判断」と言えないこともありません。
「好ましい」という判断は性欲に似ていなくもありません。その場限りの快楽に溺れることを繰り返しても、成長があるとは思えないからです。もっと強い言葉で言えば、自分さえ心地よければよい、ということです。
他の人に対して「普遍性」を求める趣味判断は、「他の人にも『この女性の美しさ』」を伝えたいという判断があるだけ、精神的な成長につながります。
しかし、趣味判断が感官判断より本当に上位だと言えるかどうかは分かりません。
人間が生きていく喜びは、普遍性を求める中にこそある、とは言い切れませんし、刹那的ではあっても感官判断による楽しみもあるからです。
また、もしも「趣味判断」が普遍性を持ちうるならば、それは別に私がいなくても成り立つ判断だと言えなくもない。それに対して「感覚判断」は、「個性的な判断」と言うことができますね。
ほかでもない私が、私のためにくだす判断だからです。
後書き
美学的判断を「趣味判断」「論理判断」「感官判断」というように分けたとき、現代という時代には、
論理判断>趣味判断>感官判断
という序列があるように思います。
カントの言葉ではありませんが、世の中は、高尚なもの(形而上の欲求)を低俗なもの(形而下の欲求)より上位においている、と言えるでしょう。
たとえば、酒とかタバコ。
論理判断では、健康に悪いから酒やタバコを排除する認識がありますね。特にタバコは、喫煙者でさえ「普遍性」を求めているわけではありません。
しかしながら、「タバコが好ましい」という「感官判断」をすべて無くした社会は、本当に住みよい社会と言えるかどうか?
社会全体の判断という観点からは、各人の「感官判断」はないほうが都合が良いかもしれません。しかし、それはまったく個性のない社会だ、という言い方もできます。
論理判断で感官判断を抑えつけることは、「多様性を認めない」ことに繋がる可能性があります。
すべての人が「趣味判断」と「感官判断」について、理解し尊重できる社会になれば良いな、と思います。
話は飛躍しますが、「愚行権」をいっさい認めない社会は、まったく自由がない社会になりそうです。論理判断が支配する世界は、全体主義の社会に近いと思われます。
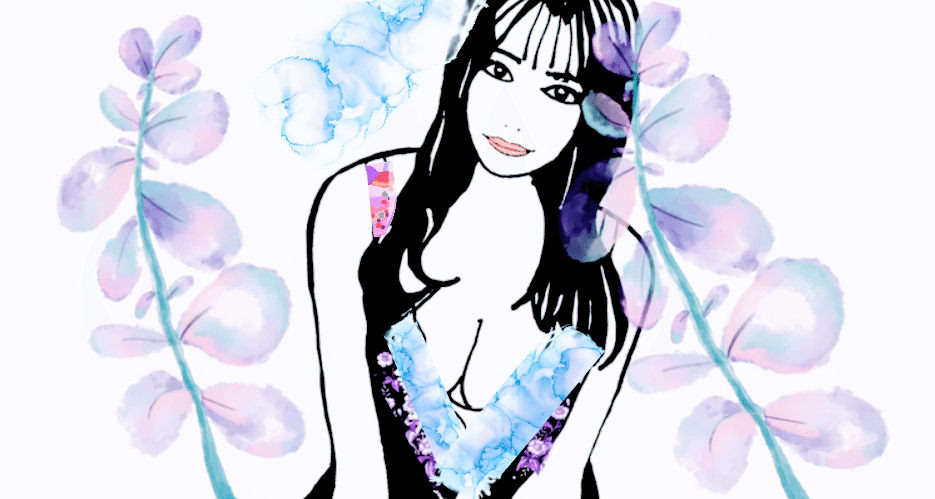
だいぶ単純化して書きました。
「そんなことはどこにも書いてないぞ!」という感想を持たれる方もきっといらっしゃることでしょう。
また、カントの哲学は、私の認識では、社会にとって望ましい均衡点を求めるものではなく、純粋理性にせよ実践理性にせよ判断力にせよ、あくまでも個々の理性的存在者の枠内での哲学です。
理性的に考えるための3つの格律
「判断力批判」の中に、理性的に考えるための3つの格律(格率)が書かれています。
①『自分の頭で考える』という格律。
②『他人の立場になって考える』という格律。
③ 『①と②の格律から総合的に考える』という格律。
①から③までの格律には「他者と議論しながら考える」という格律はありません。
もちろん、他人との議論を否定しているわけではありませんが、たとえ自分の考え方より優れた考え方であっても、他律的であってはなりません。
他律的な考えをそのまま受け入れることは、『自分の頭で考える』というプロセスのないものは自律的ではありませんね。
自分の頭で考えに考えた末に『間違いない!』と思えれば、他律的な考えを受け入れても「自律的」だと言えます。
哲学は学問ではありません。カントであれどんな哲学者であれ、哲学者が考えた末に出した結論を覚えることは哲学ではありません。私は考えるプロセス自体が哲学だと考えています。
人に説明するには「単純な図式化」も必要かもしれませんが、自分の頭で考えることがなければ、「カントを理解すること」はできても、自らの哲学にはなり得ない。そう思います。
と言いつつ、だいぶ大雑把な話になり申し訳ないと感じています。
疑義がありましたら、ぜひ「判断力批判」に直接あたっていただきたく思います。その他の研究書も汗牛充棟です。

#多様性を考える
#学問への愛を語ろう
#カント
#判断力批判
#美学的判断力
#美とは
#趣味判断
#論理判断
#感官判断
#愚行権
#この女性は美しい
記事を読んで頂き、ありがとうございます。お気持ちにお応えられるように、つとめて参ります。今後ともよろしくお願いいたします

