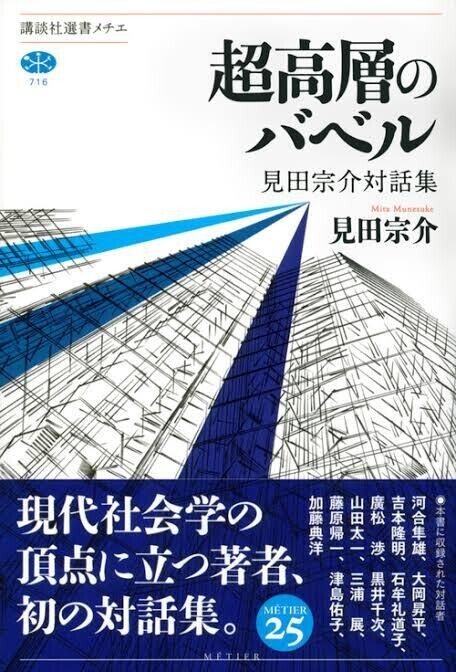見田宗介 『超高層のバベル 見田宗介対話集』 : 〈対話者〉の資質に非らず
書評:見田宗介『超高層のバベル 見田宗介対話集』〈講談社選書メチエ〉
著者の著作は、まだ『気流の鳴る音 交響するコミューン』(真木悠介名義)と『まなざしの地獄 尽きなく生きることの社会学』の2冊しか読んでいない。その2冊が面白かったので本書を手に取ってみたのだが、正直なところ、期待はずれの感が否めなかった。著者は、あまり「対話」上手ではないようだ。
つい先日、初めてまとめられたという(文庫オリジナルの)、和辻哲郎の対談・座談集『和辻哲郎座談』(中公文庫)を読んだが、これも期待はずれだった。それで、同書のレビューに、
『本書解説者の苅部直が『この文庫本は、和辻哲郎(略)の没後六十年にあわせて刊行された。和辻の対談・座談会を集めた本はこれまでないから、本書は初めての貴重な機会ということになる。』(P405)と書いているのは、決して故なきことではない。
端的に言えば、和辻の話は、勉強にはなっても、面白くはないのである。だから、これまでまとめられることはなかったのだ。』
と書いたのだが、それと同じことが、本書『超高層のバベル 見田宗介対話集』言えるのではないか。
事実、本書も、著作のたくさんある人気社会学者にしては『初の対話集』だし、実質的な全集にあたる「定本 著作集」の刊行もすでに終えているのだから、いわば「落ち穂拾い」に近い「余技としての対談」集成的な企画だったのではなかったろうか。
本書対談のつまらなさは、いつでも見田と対話者のどちらかが、ほとんど一方的に話し、もう一方が「お話をうかがう(拝聴する)」という形になってしまっていて、四つに組み合い火花を散らすとか、丁々発止とやりあうといった「スリリングな展開」が皆無だからである(編集者が、それを期待して組んだ、廣松渉との対談ですら、そうはならなかった)。
しかし、本書の最後に収録された、加藤典洋との対談を読んで、なぜ見田の対談はつまらないものになるのか、その理由が了解できた。
加藤はここで、見田の個性を、長所として褒めつつ、その限界や問題点も、暗に指摘している。
『 見田 (前略)僕は学生に対してだけではなく、他の著者や過去の思想家など、その人のいちばんポジティブなことにしか興味がないのです。他の欠点にあまり興味がなくて、その人のいちばん素晴らしいところ、こちらが学ぶべきもの、可能性はどこか、ということだけにしか興味がない。学生のレポートを見ても、その学生のいちばんいい可能性はどこか、と考えます。例えば、90パーセント大したことのないお勉強論文を書いていても、1パーセンチのきらめきがあったりすれば、僕はその1パーセントに対してだけ、「あそこはすごい。あそこをもうちょっとやれば、誰もやっていない仕事になる」とコメントしたりします。絶対に嘘は言わないけれど、学生に限らず、人のいちばん優れた可能性がどこにあるか、ということにしか興味がないのです。それによって自信をつけた学生もいるかもしれません。
加藤 批判することと肯定することがあるとして、七割くらいは批判よりも肯定することのほうが意味があるし、また難しいことかもしれないですね。肯定するということは、批評として難しいですし、高度です。
お話をうかがっていて、見田さんの方法に、まさにそういうものを感じました。先ほどヨットの話を出しましたが、見田さんの若い頃の『思想の科学』周辺での渾名は「幸福の王子」だったと聞いています。それは当たっている(笑)。本当にどんなところからも前に進む力を受け取る力、ポジティブなところを作り出す力がある、というのが見田さんの方法の根源かもしれません。
前出の『すばる』のインタビューで「吉本さんは「殺す」思想家」で、「鶴見さんは「生かす」思想家」とおっしゃっていますが、確かに殺されて生きる人と生かされてそれがいいかどうか分からない人がいるので、それはどちらがいいか分からないにせよ(笑)、見田さんも「生かす」人なんだろうと思います。そういう教育者的な側面の他に、非教育者的側面一一挑発者、誘惑者的側面一一をもっている。そのことが人を引き寄せ、人を育てたのだと思います。シノモン、誘惑の力ですね(笑)。やはり社会学と見田さんの組み合わせというのは、異種格闘技ではありませんが、非常に異質な人が学者になって仕事をしてきた。その落差のダイナミズムが大きいですよね。やはり、見田宗介=真木悠介という非近代的なあり方に、人が集まり、育ったことの可能性が秘められていたのだと思います。
すでに教員を辞められているから、うかがっていいと思うのですが、ゼミナールなどの選考においては、どんな基準でもってあたられていましたか?
見田 ゼミのメンバーを選考する基準は、今だから言うと(笑)、センスの良い人です。批判されると思いますけど(笑)。それから、もっと批判されると思いますが、人柄のいい人です。人間がいい、ということは、とても大切なことです。頭がよくても、シニカルな人や攻撃的な人は(東大生などに多いのですが(笑))他の学生を萎縮させる、特に後輩たちやデリケートなセンスのよい人を萎縮させるので、のびのびとした自由な空気をだめにしてしまうのです。
その人一人を見るのではなく、ゼミという場の自由な空気をイメージして選考しました。そこから百花斉放で、さまざまな創造をする若い人たちが出発していったのだと思います。』(P283~285)
要は、見田宗介という人は、全体としてつまらないものでも、決して「つまらない」とは言わない人だし、そのようなことで「他者と正面切ってぶつかる」ということの出来ない人なのである。
見田は、「自分の内部」での「文学的なセンスと学術的な論理性のぶつかり合い」は求めても、「他人」との間での、現実的なぶつかり合いは求めない。むしろ、そういう意味での「直接的肉体性」には、嫌悪すら覚える人なのではないだろうか。だからこそ、彼は時に「霊的=感性的」であったり、はたまた「精密論理的」ではあり得ても、いずれにしろ「肉体的」ではないのである。
もちろん、誰に対してであろうと「円満具足の完全性」を求めるのは、無理な話なのだろう。だが、見田宗介(=真木悠介)という才人が、その力量のわりに、思想・批評界において主流を歩けなかった理由は、このあたりに存するのではないか、と疑ってみる必要はあろう。
なるほど「人柄のいい人」「人間がいい」人たちとの付き合いの方が、心穏やかに、伸びやかにいられるというのは間違いない。しかし、世の中は「人柄のいい人」「人間がいい」人ばかりではないし、そうではない(嫌な)人の存在を無視し(排除し)て、この世界を考えることもできない。誰もが「恵まれた環境」を選べるわけでもない。そもそも、芸術家や思想家だって「人柄の悪い(嫌な)人」は少なくなく、それでいて無視できない才能を持っている人は確かにいる。そうしたものが、この世の現実なのだ。
それなのに、こうも簡単に『人柄のいい人です。人間がいい、ということは、とても大切なことです。』などと言ってしまっていいのか。
もちろん、ゼミを運営するプロの教育者としては「一人を切り捨てて、十人を救う」というやり方もありだろうが、一方で、逆に「教育者」としては、それでは「目先の問題回避」でしかないと批判されても仕方なかろう。
『『すばる』のインタビューで「吉本さんは「殺す」思想家」で、「鶴見さんは「生かす」思想家」とおっしゃっていますが、確かに殺されて生きる人と生かされてそれがいいかどうか分からない人がいるので、それはどちらがいいか分からないにせよ(笑)、見田さんも「生かす」人なんだろうと思います。』
と加藤が、ちょっと「ひねった言い方」をしたのも、見田のそうした「共感しあえる人たちの中だけで、楽しくやっていきたい」という、思想家としては少々「問題含みの性格」を、ハッキリと見抜いていたからではないだろうか。
この加藤との対話においては、「主役」の見田を肯定的に評価するための必要上『批判することと肯定することがあるとして、七割くらいは批判よりも肯定することのほうが意味があるし、また難しいことかもしれないですね。肯定するということは、批評として難しいですし、高度です。』と、加藤が「褒めることの美徳」という(きわめて常識的かつ耳障り良い)側面を強調していたとしても、だから言って、読者までが「私も、褒めるタイプです」などと良い子ぶって、慌てて「褒め」にまわったのでは、見田宗介=真木悠介という思想家についての正しい(客観的な)評価など、到底かなわないのではないだろうか。