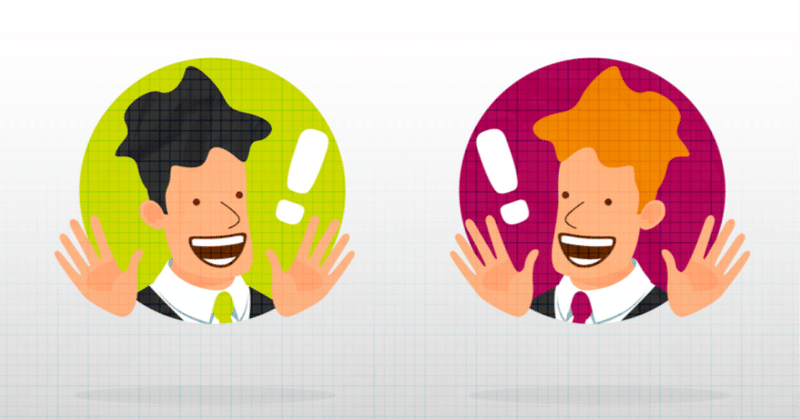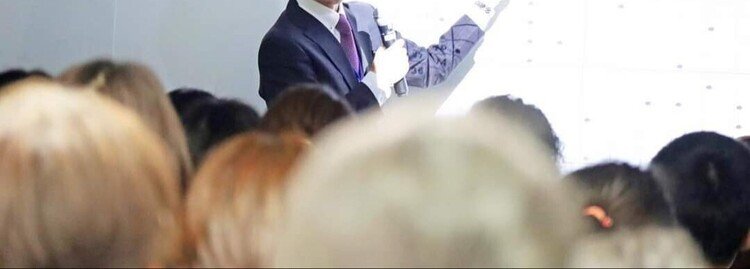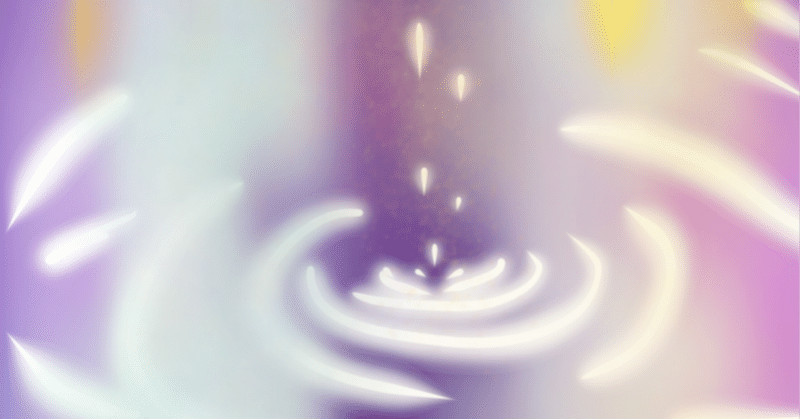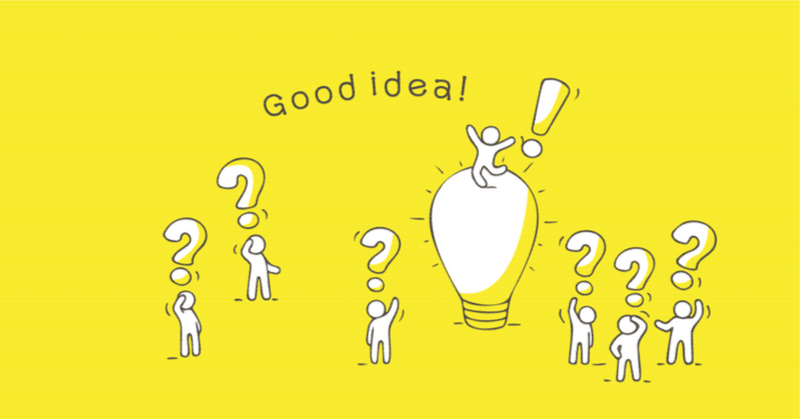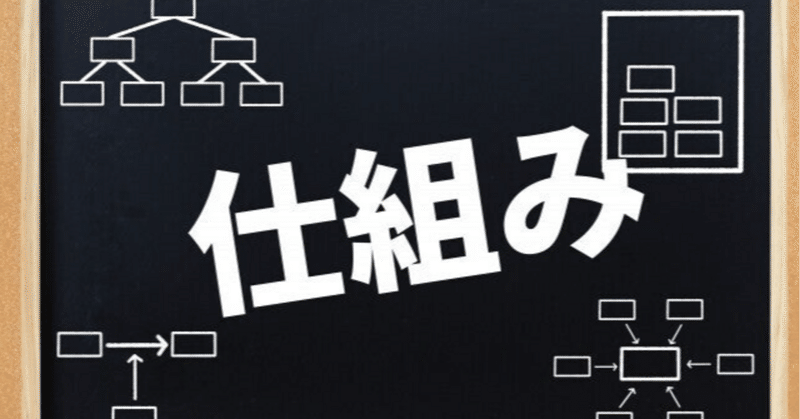- 運営しているクリエイター
記事一覧
【経済・経営】ヤマト(運輸)の2025年3月期決算を読む【インフレの負の側面は出つつある・経済危機は近い?】
これもインフレの負の側面ですよね。インフレの好影響を享受する局面は去りつつある。個人消費は減りコストは上昇。しかし物資の輸送なしでは私たちは生きられない。
1号、2号、3号などで女性の分断工作に乗っかっている間に、足元で火はついてる(は言い過ぎか?しかし個人的には気になる。
【経営・決算】2024年7月〜9月期インテル2兆円以上の赤字決算【この世に絶対的に永続的な企業などない】
アメリカのインテル。半導体メーカー。かつてマイクロソフトのWindowsを並んで、ウインテルと呼ばれ業界に君臨した企業が、AI時代の半導体製造に遅れをとり、なんと二兆円以上の赤字決算。
インテルが右と言えば右。という時代を私は知っているだけに、この世に永続的に続く企業などない、と改めて思った。
【経営】ホンダと日産の経営統合の話が出る【ホンダによる日産の救済?】
ホンダ・日産の経営統合。まえからうわさにはなっていたけど、ホンダにメリットあるのかな。。。
早速、12月18日の朝
ホンダ株値下がり
1,261前日比-22.5(-1.75%)
日産株価、買い気配
そりゃそうですよね、、、
日産は11月にこんなニュースが流れたばかり。
ホンダの決断やいかに。
【参謀】講演(プレゼン)資料は自分で作る【人前で講演する際に大事な5つのことのうちの1つ】
以前、こんな記事を書きました↓
今回は、講演資料は自分で作る。です。
当たり前と思われるかたもいらっしゃるかも知れませんが、意外と業務効率のためにどこからか資料を引っ張って来ることはあるもの。それが悪いことではなく、その場合でも一工夫ほしいところです。
1。ゼロから資料を作る場合
もちろん本記事のお題通りです。
この効果は、
・講演するのが自分自身なので話全体が頭に入っていて話がスムーズにでき
【参謀・講演・覚書】人前で講演する際に大事な5つのこと。1資料は自分で作る。2練習は口に出してするだけが練習ではない。3講演を録音して後から自分で聞く。4講演開始直後には、いきなり本題には入らず、今日のあらすじと○○を話すと効果的。5講演中は聴衆の方を見ながら。詳細は後日。
【参謀】良い結果が出た取り組みの共有は言うほど簡単じゃない1。「重要なのは取り組みを考えてから結果の振り返りまでのプロセス全体の共有」
まだ今の会社で超末端弱小支店長(苦笑)だった時、属している支店グループ群の会議で、ひたすら「何をどう考えて(必死に)取り組んで成果を出したかを隠さずに発表してました。」一年半後ぐらいに、それを真似するところが出て来て部全体が良くなっていきました。
ここで重要なのはその取り組みを実施してみようと考えるに至った
1。問題意識
2。考えたこと=仮説
3。実行
4。実行したことを受けての結果をどう捉えた