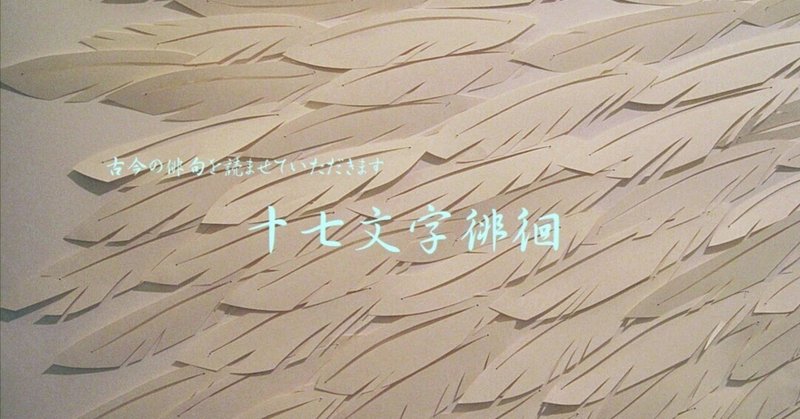古今のふれあった俳句作品についての所感を記録しておくノートのまとめです。作品にふれあうというのは、きわめて個人的なことで、古典として名高い名句とか、コンクールの優秀作品とか、そう…
- 運営しているクリエイター
記事一覧
#25 別るるや柿喰ひながら坂の上 惟然
別るるや柿喰ひながら坂の上 惟然
誰との別れかというと「翁に別るるとて」とあるから、師の芭蕉との別れである。
別れの時が来て、柿を齧りながら坂の上から去ってゆく人を見送った。それだけのできごとだが、とても好きな句だ。
別れてゆくのは、敬慕してやまない師である。
惟然の人となりを思い合わせると、この句を初見した時のおおらかなものだという第一印象とは、ちょっと違ってむしろペーソスの漂う感じ