
【新シリーズ】例えば、手書きで『書いて⇨忘れて⇨ひらめく』を試してみたら?
この度は、数ある中からご覧頂き、誠にありがとうございます。

【まえがき】
今回の記事内容はコチラ
1️⃣《こんなお悩みを持つ方にオススメ》
アイデアが思いつかない
いい文章を書きたい
手書きのメソッドを知りたい
2️⃣《学び》
とにかく書くことの大切さが分かります
3️⃣《記事を読んだ後、どうなって欲しいか?》
いい文章をたくさん書いて欲しい
以上を踏まえてご覧頂ければ幸いです。

【悩み】
僕は、駆け出しのホラー作家だ。スティーヴン・キングに憧れて、この世界に足を踏み入れた。だけど今、僕はただ座っているだけだ。
今日も柏木由紀似の女性編集者がハリセンを持って「先生‼️原稿はまだですか‼️」と急かしてくる。
全く良い文章が浮かばず、「もうどうにでもなれ‼️」そんな気持ちで、パソコンの電源を切り、手書きを始めたら変化が起こった。

【結論】伝えたいこと
✅【手書きすればするほど『書いて⇨忘れて⇨ひらめく』のサイクルを生み出すことが出来る】

【理由その① 何故そう思うのか?】ツァイガルニク効果とは?
手書きをしたら、まずまずの原稿が出来上がり、女性編集者は上機嫌で町田の合コンへと向かった。
前から不思議に思っていた。脱稿する度に、作品の内容が頭から抜けることがある。まるで、鰻がスルスルと手から抜けていくように。
その理由を、僕は知ることになる。
旧連の心理学者ツァイガルニクは、いつも行くカフェである発見をします。カフェの店員は、客の注文をメモもとらずに何人分も正確に記憶しているのに、注文の品を出した途端、その内容をすべて忘れてしまう、ということです。
この発見を、心理実験で裏付けして「目標が達成されない未完了課題についての記憶は、完了課題についての記憶に比べて想起されやすい」ということを明らかにしました。これは、「ツァイガルニク効果」と呼ばれています。
テレビ番組で、ちょうど盛り上がってきたところに、「続きはCMの後で」と入ります。連続ドラマで「この後どうなるのか?」と先が気になるところで終わってしまうのも、ツァイガルニク効果を利用して、視聴者の記憶と注意を強化しているのです。
人は課題を達成しなくてはいけないという場面において緊張状態となり、この緊張は課題が達成されると解消され、課題自体を忘れてしまいます。反対に途中で課題が中断されたり、課題を達成できなかったりすると、緊張状態が持続してしまうため、未完の課題は記憶に強く残ることになります。
ツァイガルニク効果を言い換えると、進行形の出来事は、脳の記憶スペースを占拠するが、完了した出来事は、脳の記憶スペースからきれいサッパリ消去されるということです。
「そういえば、今日中に出さないといけない書類があった」とか、「今日のランチはラーメンにしようかな」という雑念が何度も浮かんでくるのは、「未完了課題」なので脳が緊張状態を維持しているからなのです。
そんな雑念を脳内から消去するにはどうすればいいのでしょうか。
先ほども述べたように、雑念を紙に書き出せばいいのです。紙に書くことで、「進行形」が「完了形」に変わります。
〜中略〜
「ラーメン食べたいな」「ラーメン食べに行こうかな」という思考は「進行形」なので、頭の中から離れません。「ランチはラーメンに決めた!」と決定する。そうすると、まだラーメンは食べていませんが、「食べに行くことが決まった」ということで、脳の中では「完了形」に書き換えられます。
「未完了課題」が「完了課題」に変わると、脳の緊張はとれて、その雑念がすっきりと消去されるのです。
多くの人は「忘れない」「覚える」「記憶する」ことに執着しますが、「書いたら忘れていい」のです。むしろ、書いたらスッカラカンに忘れて、頭を空っぽにしていいのです。
〜中略〜
頭の中の「ツァイガルニク断片」を、残さず編除すると頭が実に軽くなります。
〜中略〜
書いたら忘れていい。いや、書いたら忘れるのです。
忘れたとしても、書いたものを見た瞬間に、読み返した瞬間に、知識はありありと思い出されます。
私たちの「記憶の本体」は、そう簡単にはなくなりません。「記憶の索引」を忘れるだけなのです。「書く」ということは、無数の「記憶の素引」を物理的に複製する作業なので、書いたら忘れても、すぐに思い出せるというわけです。
これを知った時、『頭に溜め込まずに書いて忘れることが、作家として重要な要素になる』と思った。

【理由その② 科学的根拠は?】手書きのメソッドとは?
手書きで執筆を終えて頭をクールダウンする為にスタバのドリップコーヒーを飲んだ。芳醇な香りに案内され、現実の世界へと戻ってきた。
そして、手書きスタイルに興味を持ち、パソコンで手書きのメソッドについて調べてみたら、色々分かった。
まず、
ラクに早く書くにはデジタルの方が便利ですが、紙に書き出すことは脳に創造・洞察の刺激を与える効果があるのです。
ここでは「大脳基底核」と「内臓感覚」という2つのキーワードから、手書きの効果を考えていきます。
脳科学者のマシュー・リーバーマンは、脳の「大脳基底核」という部分が潜在学習と直感の両方の神経基盤である証拠を見つけました。
また心理学者のダニエル・ゴールマンは、「大脳基底核は、私たちがやることなすことの一切を観察し、そこから決定の規則を引き出す。・・・・・どんなトピックに関するものであれ、私たちの人生の知恵は大脳基底核にしまわれている」と言っています。
これはつまり、直感や潜在学習(深い部分の無意識による学習)が「大脳基底核」で行われているということです。
脳科学的な解説は専門書に譲るとして、私たちが潜在能力や直感、気づき(洞察・着を引き出すための1つの鍵は、「大脳基底核」を刺激することだと言えるようです。
では、その「大脳基底核」から知恵を引き出すためには、どうすればいいのでしょうか?
結論からいうと、「手で書く」ことです
ダニエル・ゴールマンによれば、「大脳基底核」というのは言語を司る大脳皮質とつながっておらず、言葉で伝えることができないのだそうです。一方で、情動中枢や内臓とはつながっているので、気持ちという形で「これは正しい」「これは間違っている」ということを直感的な感覚として語りかけてくるのだと言います。
これは、逆に言うと頭の中だけで考えるより、手を動かしながら考えた方が「大脳基底核」を刺激できるということであり、インスピレーションも湧きやすいということです。
手で書きながら新しい気づきが生まれたり、連想的に発想したりしやすいのはこうした理由があるのです。
デジタルは一度決まった枠組みを整理していくのには向いていますが、自由に創造したり、深い気づきを得たりするためには手書きの方が効果的だといえそうです。
さらに、カール・ロジャーズは、自分で気づくには「内臓感覚」が大切だと強調します。
心理学者の諸富祥彦氏はそれを『カール・ロジャーズ カウンセリングの原点」で「内臓感覚は、論理的思考だけよりもはるかに精緻で、的確な判断を可能にする」「自分の内臓感覚から言葉を発し、この感覚にしたがって生きていくことは、人がより深く、賢明に生きることを可能にする」と解説しています。
深い内臓感覚を感じていくには、自分の中で「しっくりくる」とか「ピンとくる」という感覚、感情を大切にすることです。情動中枢につながるということです。
言ってみれば「腹に聴く」ようなもので、内臓感覚には多くの知恵が眠っていて、人生の方向感覚や洞察が生まれる源泉があります。
しかし、多くの人は論理的な考えだけに終始し、混迷していきます。
論理一辺倒から抜け出すためには、自分が何を感じて、何を求めているのか、内臓感覚を手掛かりに深く感じる習慣が必要です。
〜中略〜
大脳基底核をより刺激して、私たちの潜在的、直感的な脳の力を発揮し、感情・内臓感覚を鋭敏にして、新しい気づきを生み出すことを可能にするのが手書きなのです。
これは、感覚的に感じていた。手書きすると、突然パッとひらめく感覚があり、良い文章になることが多かった。
プリンストン大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス校の共同研究では、大学生を対象に、講義を 「手書きでノートをとる学生」と「ノートパソコンでノートをとる学生」にわけて比較しました。
結果は、手書きの学生のほうがよい成績を上げ、より長い時間にわたって記憶が定着し、新しいアイデアを思いつきやすい傾向にあることが明らかになりました。
また、スタヴァンゲル大学 (ノルウェー)とマルセイユ大学 (フランス)の共同研究では、被検者を「手書き」群と「タイピンク」群にわけ、20文字のアルファベットの文字列を暗記してもらい、 3週間後、6週間後に、その文字列をどれだけ記憶しているかテストしました。
結果は、タイピングよりも手書きのほうが記憶に残りやすいことが示されました。
また、手書き中とタイピング中の脳の働きを MRI(磁気共鳴画像)でスキャンしたところ、手書き中のみ、ブローカ野という言語処理にかかわる部位が活性化していることも明らかになりました。
書いていると、頭の中に空いたスペースが出来て、そこに新たなアイデアが入ってくることが可能になる
手書きが脳を強化するのも納得だ。タイピングよりも圧倒的に多くのアイデアが出たし、書いていく内に、脳が空いていく感覚もあった。
書くことで自ら気づくオートクライン効果
コーチングでは、自分で話した言葉で自ら気づくことをオートクラインといいます。
オートクラインとは医学用語で「自己分泌」を意味する言葉ですが、まさに書くことでも自分の内側から答えを分泌できるのです。
思っていること、感じていることを言語化することで、それまで感じなかった気持ちや、その深層にある理由に気づけます。
誰からアドバイスを受けるわけでもなく、たった1人で紙の上で言語化するだけですが、書くことが別の知性を駆動させるわけです。
紙の上で「あっ、そうか!」と気づくことこそオートクライン(自己分泌)効果です。
ドラマなどで黒板に数式をいっぱいにして話す場面があるが、現実の数学者も同じことをしていると言える。
自分の字って不思議だ。頭の中は見えないからバーッと書き出して目で見ると、思わぬ発見があるものだ。
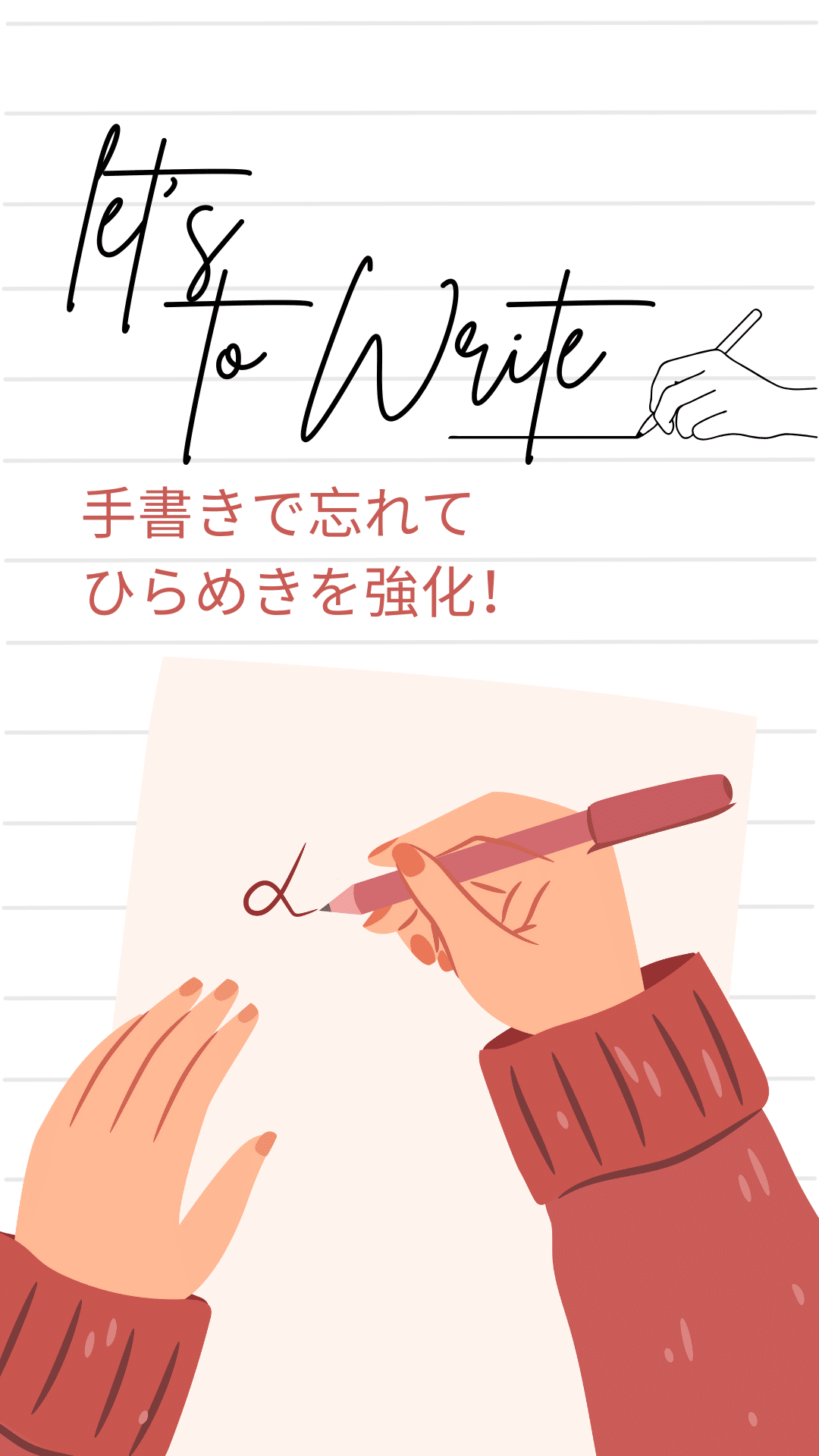

【方法】アイデアは手書き。入力はタイピングで。
僕は、早速手書きのスタイルに変えるために、渋谷のLOFTでパイロットの万年筆とキャンバスのノートを購入した。
そして、下書きやプロット出しは全て手書きに変更して、入力はタイピングに変えた。
僕はこのやり方で、早く文字を入力しながらも、たくさんのアイデアをひらめくようになり、質の高い文章が書けるようになった。


まとめ
僕は、このスタイルを3年間貫き通して、念願の新人賞を獲得することが出来た。
手書きになったのは、偶然じゃなく必然だったと今では思う。
この時、憧れのスティーヴン・キングの言葉を思い出した。
作家になりたいのなら、絶対にしなければならないことがふたつある。たくさん読み、たくさん書くことだ。私の知るかぎり、そのかわりになるものはないし、近道もない。
作家とは、自分のスタイルを貫いて、いい文章を書くために、『書いて→忘れて→ひらめく』を繰り返す気高き生き物だと、僕は思った。
例えば、手書きで『書いて⇨忘れて⇨ひらめく』を試してみたら、こうなると思う。
《今回の自己啓発のまとめ》
1️⃣手書きするほど『書いて⇨忘れて⇨ひらめく』のサイクルを生み出せる
2️⃣手書きのメソッドは、『脳に空きスペースが出来る』『手書きは脳を強化する』『自分の字を見て気付ける』この3つである。
3️⃣手書きしてからタイピングすることで、早く文字を入力出来て良い文章が書ける。
私の記事が、今後の皆様の成長に繋がることを心より願っております。
参考文献
↓↓↓
✳️マガジン一覧
過去記事をまとめたマガジンを掲載致します。
宜しければご覧ください。
✳️自己啓発ソムリエ 言葉で動くのコンセプト紹介
自己啓発ソムリエ 言葉で動くの
自己紹介になります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「私が何故、自己啓発を記事にするのか?」その理由が書いてある記事となります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「何故、本を読み続けるのか?」その理由が書いてある記事となります。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
「私が知識にどういう思いをかけているのか?」を書きました。
宜しければご覧ください。
↓↓↓
以上になります。
最後までご覧頂き、誠にありがとうございました
いいなと思ったら応援しよう!

