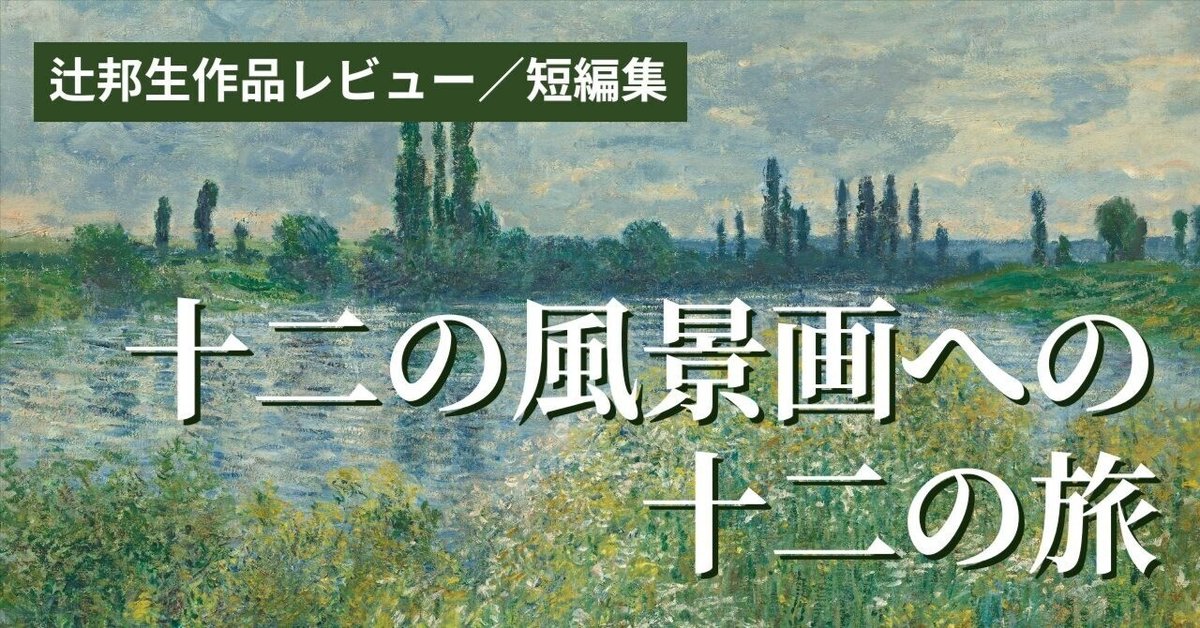
『十二の風景画への十二の旅』<人間の魂の反映として>見られた十二の風景画による物語
発行年/1984年
前回の『十二の肖像画による十二の物語』に続く企画『十二の風景画への十二の旅』です。
現代アートにおいて、風景画というのはその役割を終えた感があります。かつて大抵の風景画は、画家がどれだけ感情移入するかといった点が大きな命題でした。見たものにどれだけ迫ったとしてもそこには必ず画家の心情が込められており、風景画の美しさはその心情の美しさだったと言えるのではないでしょうか? そこから現代絵画への移行について、辻邦生さんは『十二の風景画への十二の旅』の「物語のはじめに」で次のように書かれています。
風景の美にのめりこむようになってから、絵画は、かえってその内部空間に湛えていた詩情や、人間ドラマの喚起する情念の色彩を失うことになった。絵画外の内容は希薄となり、感覚的表層の美を追求する存在となってゆき、やがて絵画性を純粋に目ざす現代絵画へと移ってゆく。
そして、続けて風景及び風景画の持つ意味、風景画をテーマに小説を書くに至った理由について述べられています。
しかし風景は人間の魂の反映として見るとき最も詩的な表現を取り戻す。こうした情念に彩られた風景画には現実においてはむろんのこと、単に写し取られた表層的風景には存在し得ない人間情念の物語が隠されている。こうした風景画のなかへ架空の旅をしたいというのがかねてからの私の夢であった。
このようにして紡がれたのが、以下にご紹介する十二の物語です。
1.『十二の肖像画による⎯』との違い
①『十二の風景画への十二の旅』の特徴
『十二の肖像画による⎯⎯』の場合はそれぞれの物語に象徴する言葉が充てられていました。しかし『十二の風景画への⎯⎯』では、モチーフそのものがタイトルに選ばれています。それは以下の通りです。元になった絵画とともにご紹介します。
第一の旅 金の壺/ある旅立ちの物語
「シバの女王の船出」クロード・ロラン
第二の旅 地の掟/ある山里の物語
「サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール」ポール・セザンヌ
第三の旅 風の琴/ある森と湖の物語
「蛇に噛まれて死んだ男のいる風景」ニコラ・プッサン
第四の旅 氷の鏡/ある雪国の物語
「雪の狩人」ピーター・ブリューゲル
第五の旅 愛の棘/ある光と風の物語
「嵐」ジョルジョーネ
第六の旅 貝の火/森に変ったある沼の物語
「風景」トーマス・ゲインズボロ
第七の旅 幻の果/ある草原と砂漠の物語
「アレキサンダーの戦い」アルブレヒト・アルトドルファー
第八の旅 地の装/地平線の見えるある野の物語
「ドレスデンの大猟場」カスパー・ダヴィド・フリードリヒ
第九の旅 霧の柩/森に囲まれたある沼の物語
「モルトフォンテーヌの思い出」カミーユ・コロー
第十の旅 海の貌/ある嵐のなかの海辺の物語
「嵐の海の風景」アレッサンドロ・マニャスコ
第十一の旅 緑の枝/ある洪水に襲われた山野の物語
「冬またはノアの洪水」ニコラ・プッサン
第十二の旅 馬の翼/ある帰還の物語
「デルフトの眺め」フェルメール
風景画には、肖像画などよりもたくさんの情報が盛り込まれています。中にはそれ自体何らかの神話や民話、出来事をもとに描かれた作品もあり、その意味では既に物語を持っていると考えてもよいでしょう。しかしそれはそれとして、それとは関係ないところで辻さんが感じ取った情念を新たな説話的なものに作り上げたのが、それぞれの物語というわけです。
②『十二の肖像画による⎯⎯』にはない難しさ
「既に物語を持っている絵画」、そこから全く新たな物語を創造するのは、先の『十二の肖像画による⎯⎯』とは違う難しさがあったかとおもわれます。そのもとになった神話などを全く意識しなかったかというと、まずそんなことはないでしょう。さらに、
絵画自体が持つ情報の意味
それをどう処理するか、そこはかなり苦心されたのではとおもいます。例えば「第三の旅 風の琴/ある森と湖の物語」のもとになった絵には<蛇に噛まれて死んだ男>が描かれていますが、物語の焦点は必然的にそこに集められてしまいます。文庫本末尾の図版解説の中で、この点について辻邦生さんは、
本書の物語はあくまで空想によるもので、直接プッサンの画題とは関係ない。
と断っておられます。
また、例えば「第二の旅 地の掟/ある山里の物語」のもとになったセザンヌの「サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール」のような誰もが知る作品では、一般の人々の中にある印象を損なうことなくどう物語を作り上げるか、それもまた苦心のしどころだったことでしょう。逆に言えば読者として、
自分がよく知っている絵にどんな話をつけてくれているのか
ということ、そこがまた興味をそそる点でもあると言えるのです。
2.物語のご紹介
前回の『十二の肖像画による十二の物語』でもそうでしたが、掲載の絵画は「パブリックドメイン」作品を扱っているこちらのサイトにあるもののみダウンロードしています。
パブリックドメインとは、
著作物や発明品などの知的創作物について、知的財産権が発生していない、または消滅した状態のこと
で、誰でも自由に利用することができます。
そうしてダウンロードした絵に合わせて、いくつか物語をご紹介します。
①第二の旅 地の掟/ある山里の物語

人間になりたかった巨人族の女が、自分の代わりに自分の娘を子どものいない村長夫婦の家にそっと預けます。ステラと名付けられた少女は巨人になることなく、人として美しく成長しますが、巨人族には一つ問題がありました。本気で人を愛してしまうと巨人に戻ってしまうのです。年頃になって言い寄ってくる男を断り続けた末に、どうしても断りきれずステラはエンリケという立派な男と結婚します。二人のあいだに男の子が生まれますが、それでもステラはエンリケに本気の愛を表そうとはしません。そんなとき、些細な事故で男の子が亡くなってしまいます。それもこれも本気で自分を愛してくれないステラのせいだと、エンリケは罵倒するのですが・・・
これは、日本の古い昔話にもありそうな物語に仕上がっています。
②第七の旅 幻の果/ある草原と砂漠の物語

絵画のテーマは有名な「イッソスの戦い」です。マケドニアのアレクサンドロス3世(アレキサンダー大王)がペルシア軍を破った古代の合戦で、絵画上方の看板にはラテン語で、合戦の結末が書かれています。
<私>は大王直属の武将スキュタリオスから、今で言う記者のような立場で遠征に参加する許可を得ます。初めのうち、遠征隊は大王を神と崇め、士気も上がって揚々と進軍するのですが、次第に疲れが見え始めます。そして、ある時点でこれ以上東方への遠征はやめるべきと進言した兵士たちを、大王がその日のうちに絞首刑にしてしまったことで士気が落ち、兵士たちは帰還を望むようになります。そんなとき、スキュタリオスが失踪してしまうのでした。誰もスキュタリオスの失踪の理由がわからず困惑するばかりです。
そうして何年か経って軍隊から離れた頃、<私>は思わぬところでスキュタリオスと再開するのですが・・・
この絵はイッソスの戦いを描いたものの中でも有名な作品で、僕が好きな絵でもあります。絵自体は大会戦の高揚感というよりは右奥の太陽と空の雰囲気によって、終末論的気分に支えられており、辻邦生さんはその点を反対から描こうと試みたとおっしゃっています。物語としても好きな作品です。
③第八の旅 地の装/地平線の見えるある野の物語

宗教的雰囲気に包まれた作品です。絵自体にそんな感じがあるからかもしれません。森の奥から現れた男が、一晩の宿と食べ物を提供してくれた農夫の妻が、産後の身持ちが悪く死にかけていること、さらに農夫の母親が足を悪くして歩けないでいることを知って、そのために一晩中祈りを捧げます。翌朝、男が礼を言って去っていったあと、二人とも突然病が癒えてしまうのでした。古い映画でも見た記憶があるような、それこそ説話のような物語です。もとより絵画自体にその意味はないのですが、完全に辻さんが受けたインスピレーションによる作品でしょう。
3.作品全体に対する僕の感想
十二の物語全部が読み応えがあるかと聞かれると、そこまでは、と言わざるを得ません。中には誰でも考えつきそうなものもあります。しかし、先の『十二の肖像画による十二の物語』もそうでしたが、これは十二作揃うことで一つの味わいが生まれてくるのだとおもいます。そこには、
・絵画そのものを味わうこと
・物語を物語として楽しむこと
その二つの意味がありさらに、
それぞれの相乗効果でひとつの協奏曲的情感が得られること
が本作の一番の特徴なのだと考えます。絵画に限らず、例えばクラシック音楽を聴いてそこにどんな物語を想像するか、それもまた味わい方の一つなのではないでしょうか? そんな楽しみを、本作は読者に提供してくれているのだとおもいます。
【今回のことば】
私はかの碩学のもとで研鑽を積んだにもかかわらずこの娘の知恵にも及ばぬ自分を感じた。渇けば飲み、飢えれば食す。この天地の大道を娘も村人たちもごく自然に行っている。私はつくづくこの人たちが羨ましくなった。愚かしい野心に憑かれ、挙げ句の果は、自分が何を望んでいたのかも忘れ、ただ苛立って生きている人間にくらべ、天地の運行とともに生きるこの人たちは、なんと健やかで安らかな生き方を楽しんでいることか。
『十二の風景画への十二の旅』収録作品
・文藝春秋「十二の風景画への十二の旅」大型本 1984年
・文春文庫「風の琴: 二十四の絵の物語」1992年
・岩波書店「辻邦生歴史小説集成 第1巻」1993年
今回もお読みいただきありがとうございます。
他にもこんな記事。
◾️辻邦生さんの作品レビューはこちらからぜひ。
◾️詩や他の創作、つぶやきはこちら。
◾️大して役に立つことも書いてないけれど、レビュー以外の「真面目な」エッセイはこちら。
◾️noterさんの、心に残る文章も集めています。ぜひ!
