
スターバックスの魅力をつくるミッションの特徴〜マネプロ#5
こんにちは! DeNAでHRビジネスパートナーをしている坪井(@tsubot0905)です。
マネジメントの進化を探求するnote
『マネプロ』は今回が第5回目です。
このマネプロnoteのシリーズでは、5分で分かりやすく学べるシンプルな構成と、相手とのコミュニケーションで使えるようなシンクロしやすい問いを意識した内容を心がけています。
さて、前回は「企業理念/MVV」のテーマでお伝えしました。
今回のテーマは「ミッション」。
企業の生き様とも言えるミッションについて、ユニークな事例とともに探求していきます。
目次はこちら!
<ミッションとは生き様>
ミッションの持つ意味は、使命や存在意義を示すこと。
前回お伝えした通り、企業理念へのWhy?の問いかけです。人が呼吸をするためだけに生きているのではないように、会社も売上・利益を出すためだけに存在しているのではありません。会社は必ず使命を持っています。
使命なのですから、ミッションには日々の命を使ってでもやる価値があると信じていること、いわゆる生き様が現れていると良いですよね。
生き様なんて言うと少し大袈裟な表現ですが、命を時間と置き換えてもらうと良いかなと思います。
ミッションは、MVVの中でも不変的な考え方を示す概念です。
そのため、経営や事業が長期的に一貫性を保つ際の拠り所となり、企業としてブレない価値提供の追求につながります。
それでは、特徴的なミッションを掲げている企業の事例から探求を深めたいと思います。
<ミッションの事例:スターバックス>
私もちょくちょくお世話になっているスターバックス。
いわゆるスタバですが、スタバがお客さんに届けている価値はなんでしょうか?
スターバックスラテ!という好みのコーヒーを答える人もいるでしょう(ちなみに、私はキャラメルマキアートが好き)。
それはそうかもしれませんが、実は、スターバックスは創業時からコアコンセプトとして「サードプレイス」を掲げています。マネプロにおけるミッションの定義に近い、この「サードプレイス」という言葉に注目して話を進めたいと思います。
サードプレイスは読んで字のごとく「第3の場所」という意味。会社と家庭、学校と家庭という日常の生活に豊かさをもたらすもう一つの空間、ということなんですね。
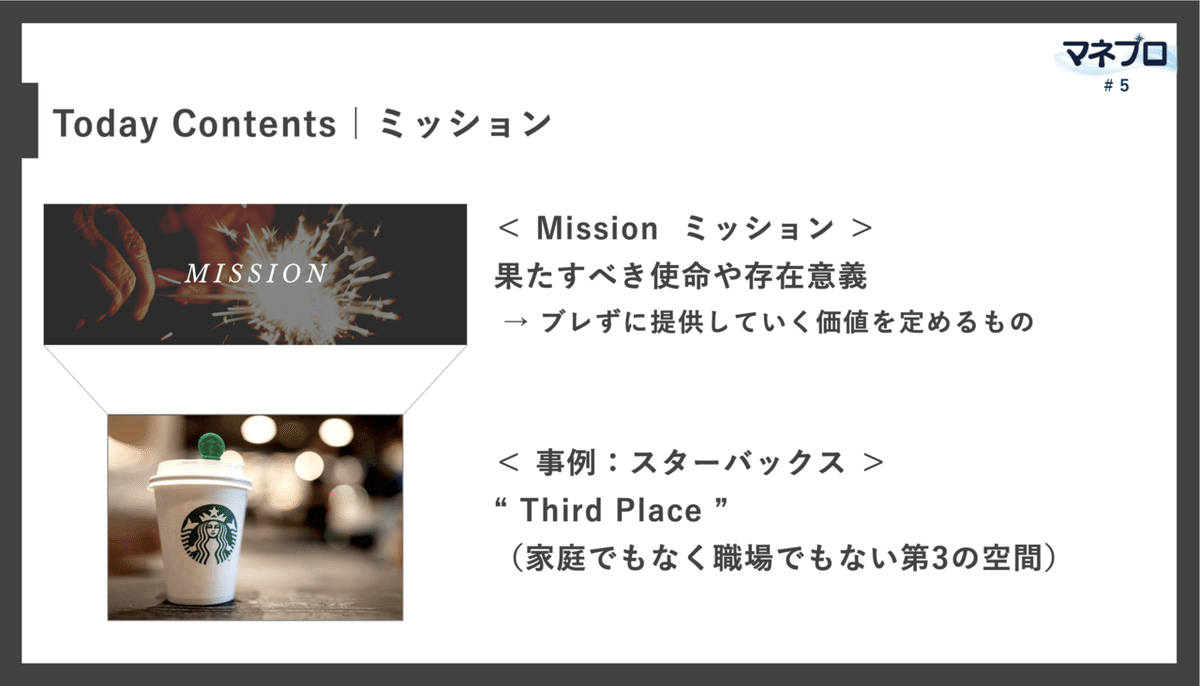
我々は単にコーヒーを売る企業ではなく、最高の顧客体験を提供する企業でありたいという企業のあり方がサードプレイスには込められています。
実際にスタバに行った時のことを思い出してみてください。コーヒーに顧客の名前やサンキューと添えてくれるサービス、ミルクやトッピングを変えられるコーヒー、広々としたスペースが確保された空間。どこかしらでサードプレイスを感じる体験ができたお店があったのではないでしょうか。
<ミッションは『PS』で夢中になる>
スターバックスの事例は、自分達が何を価値提供したいのか明確な事例だと思います。
それは、ミッションに「サードプレイス」のようなイメージしやすいシンボル(S)が組み込まれることで使命・存在意義を常に身近な存在、象徴として表現しているからです。シンボルとなる言葉の存在が際立ちはじめると唯一無二の強いミッションになるのではないかと考えられます。
私が働いていた今はなきグルーポンにも際立ったシンボルとなる言葉がありました。「我々は単なるクーポンサービスではなく、顧客に新たな発見をしてもらうサービスなんだ」という意味を込め「シティガイド」をシンボルとして掲げていたのです。長い文章を覚えられない私にとっては記憶しやすいシンボルでした(笑)
PSの「S」の方から説明してしまいましたが、
では、ミッションに込めたいPSの「P」とは何か?
それは、仕事の「目的」となるもの、つまりパーパスの「P」です。
目的が表面的に見える商品だとは限りません。
スターバックスのサービスはコーヒーを売ることが目的ではなく、顧客に最高の顧客体験を提供することが目的でしたね。
同じような例えだと、保険会社の目的は保険を売ることではなく、安心を提供することだ、と話されていた方がいました。
つまり
「なぜ顧客から選ばれるのか?」
「私たちはなぜ社会に存在するのか?」
の答えとなるものが目的です。
顧客視点や社会視点のある価値を持つ「目的」を込めることで、使命として揺るがないミッションが語られていくのだと思います。
私が子供の頃、PS(プレイステーション)に夢中になっていく人が増えたように、企業がPS(パーパス・シンボル)のあるミッションを掲げて仕事に夢中になれる人が増えてほしいものです。

<ミッションと事業内容の関係性>
ミッションを作るときに事業内容がそのままミッションにならないように、という考え方もあれば、私たちが何者かを示す意味で事業ドメインを明確にすべし、という考え方もあります。
個人的には、企業としてのスタンス次第だと思っています。伝わりにくいですよね、、、
わかりやすくするために対照的な2社の事例を紹介してみます。取り上げるのは鳥貴族と富士フィルム。
鳥貴族のミッションは「焼鳥で世の中を明るくする」。明確に焼鳥とともに歩むスタンスがあり、事業領域をここまで絞り込んでいるのには清々しさすら感じます。
一方の富士フィルム。事業内容をミッションにしていたら今頃世の中に存在しなかったでしょう。もはやフィルム屋のイメージではないです。もしミッションが「フィルムで世の中を明るくする」みたいなものだったら生き残れなかったはずです。
ちなみに今は総合ヘルスケアカンパニーと自社を表現するくらいに、技術力を生かして事業展開が多角化しています。そのため、不変の価値観と表しているミッションは抽象度が高めの表現になっています。
<ミッションと社員の関係性>
私自身ミッションに紐づく事業の意義を感じてスタートアップで働いていていたことがあるので、ミッションの強さは人を惹きつける力があることを実感しています。
一方で、全ての会社がスタートアップなわけではないので、企業のミッションがどこか身近に感じられない、崇高すぎる(世界平和的な…)、なんてこともあるかもしれません。
その場合は、自分自身のミッションを意識してみましょう。
自分自身のミッションを自覚している人は自然と企業のミッションに共感するかどうかを判断できます。一方で、自分自身のミッションに無自覚な人は曖昧な表現の企業ミッションだと共感にまで至りにくく、自分ごと化できにくいものだと思います。
企業が命を使ってやろうとする使命に対して自分も働く時間を使って貢献していくわけですから、自分が興味関心を持てることに時間を使いたいでしょうし、企業という同じ船に乗る仲間とはミッションを共にして切磋琢磨できる日々を過ごせると理想的ですよね。
ワンピースで言えば、グランドラインを目指す船なのだから、仲間と共に成長しながら命をかけてでも強い敵に立ち向かって勝つぞー!みたいな。
そう考えると、企業や事業にとっての生き様であるミッションは「価値のあり方を示したもの」とも言えると思います。
企業のミッションそのものの意味あいを解釈して、自分にとっての意義、自分が本当に価値のあることをしていると感じられているかどうか。その腹落ち度合いが大事なことなのではないでしょうか。
<今回のQuestions>
以上が5回目のマネプロでお届けしたかったコンテンツでした!
いかがでしたでしょうか?
ということでマネプロ恒例、最後の問いです。
今回のテーマを通じて、リーダーやマネージャーの方々に問いかけたい4つの質問を選びました。忙しい皆さんの思考の整理と、新たな行動の後押しになれますように!

※「自分はこう考える」「自分ならこれを問いかける」という考えはぜひTwitterにて「#マネプロ」を付けてつぶやいていただけたら嬉しいです!
<次回にむけて>
今回のマネプロではミッションをテーマにお伝えしてきました。
前回お伝えした通り第5,6,7回は企業理念を伝える切り口であるMVV(ミッション、ビジョン、バリュー)について一つずつお届けして参ります。
というわけで、次回のテーマはビジョン。
次回は2週間後の水曜日。
良かったらぜひnoteのフォローやシェアをお願いします。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました!
読者のみなさんと共にマネジメントの進化を探求できれば何よりです。Twitterのフォロリツ大歓迎です!DMでの感想も是非!(@tsubot0905)
noteで取り上げた内容について、みなさんの持論や新たな問いかけの視点をもらうことでマネジメントの探求がもっと楽しくなるはず。ですので、みなさんからのリアクションを心待ちにしております。よろしくお願いします!
