
【読書】大江健三郎 「死者の奢り」
先日、作家の大江健三郎さんが亡くなりました。
氏の作品は大学時代にむさぼるように読んだものです。
大学で「美術史概論」という講義を受講しました。
そのときの教授が、田中香澄先生という女性教授でした。
田中教授とは、講義だけでなく、わたしの友人を含めて、何度か美術展にも連れて行っていただきました。
ラファエル前派展や印象派の展覧会がよく記憶にあります。
新宿の伊勢丹美術館が多かったような。
また、お酒がおいしい新宿のお店にも度々ご一緒したものです。
その教授は、東京大学文学部仏文科時代に、大江健三郎氏とクラスメイトだったそうで、大江さんのことをよく教えてもらいました。
そして、教授は、大江さんについて、わたしたちとお酒を酌み交わしながら、懐かしそうに話をしてくれたものです。
大江さんのその人物像とは、こんな感じでした。
・東大在学中に、史上最年少で、著作「飼育」で芥川賞を受賞して、東大中が大騒ぎとなった。
・当時としては、背が高く、端正な顔立ちだったことから、東大の女学生から大変な人気で、相当モテていて、握手やサインをねだられていた。
・フランス語で書かれた作品をスラスラと読み、自身で翻訳していた。
・東大の生徒はみな、大江氏を尊敬のまなざしで見ていた。
・「稀に見る若き天才作家」として、沢山のマスコミやメディアから取材を受けていた。
などであったようです。
わたしは、初期の大江さんの作品がとても気に入っていて、自分が20歳前後には、氏の初期作品のテーマである「性と政治」には深い共鳴を受けたものです。
純文学の作家の中でも、とりわけ大江さんの作品は、衝撃的かつ、閉塞感や監禁状態にある世界観が強く謳われており、わたしの青春期の墓標のような存在となりました。
そのような、大江さんの初期作品の中でも、一番のお気に入りは、
「死者の奢り」です。
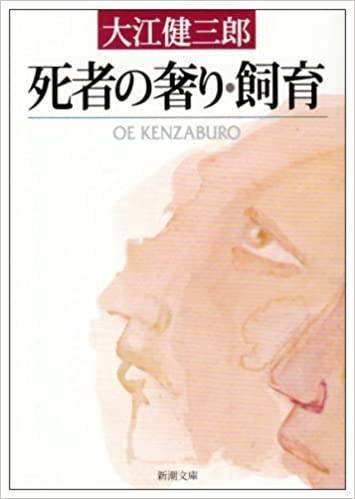
本作品をWikipediaからの概要を要約していきます。
『死者の奢り』(ししゃのおごり)は、大江健三郎の短編小説。大江の商業上のデビュー作である。1957年、東京大学新聞五月祭賞を受賞して同紙に掲載された作品『奇妙な仕事』が批評家平野謙に毎日新聞時評で絶賛されたことをきっかけに執筆依頼を受けて、文芸雑誌『文學界』の8月号に発表、第38回芥川賞候補となった。大学病院の解剖用の死体を運ぶアルバイトをする主人公の仕事が、結局は無益な徒労でしかなかったと分かる。サルトル流の実存主義の思想、時代の暗い閉塞感をよく表現し得る文体として評価が高かった。
サルトルに影響を受けたとされる実存主義からもたらされる、虚無感が全編に色濃く投影されていました。
「死者の奢り」あらすじ
<僕>は昨日の午後、大学の医学部の事務室に行って、アルコール水槽に保存されている解剖用の死体を処理するアルバイトに応募した。係の事務員によると、仕事は一日で終える予定で、死体の内、解剖の実習の教材になるものを向こうの水槽に移すということだった。
休み時間の間、<僕>は外へ出て、水洗場で足を洗っている女学生に出会った。女学生の話によると彼女は妊娠しており、堕胎手術の費用を稼ぐ為にこのアルバイトに応募したということだった。女学生は、もしこのまま曖昧な気持ちで新しい命を産んだら酷い責任を負うことになり、だからといってその命を抹殺したという責任も免れないという、暗くやり切れない気持ちでいることを話した。
午後五時に、全ての死体を新しい水槽に移し終え、附属病院の雑役夫がアルコール溶液を流し出しに来るまで、ひとまず管理人室に上って休むことにした。女学生が急に立ち上がって部屋の隅に行って吐いた。長椅子に寝させて看護婦を呼んだ。女学生は、水槽の中の死体を眺めていて、自分は赤ん坊を生んでしまおうと思い、赤ん坊は死ぬにしても、一度生まれてからでないと収拾がつかないと考えていたところだと告白した。
管理人室に戻ると、大学の医学部の助教授が、事務室の手違いで、本当は古い死体は全部、死体焼却場で火葬する事に、医学部の教授会で決まっていると管理人に話し込んでいた。管理人は狼狽したが、渋々、新しい水槽に移した死体を焼却場のトラックに引き渡す事を承諾した。助教授の話では、明日の午前中に文部省の視察があり、それまでに両方の水槽を清掃して、溶液を入れ替えなければならないということだった。管理人は<僕>に、アルバイトの説明をしたのが自分ではなく事務の人間だったことを覚えていてくれと言った。
<僕>は今夜ずっと働かなければならず、しかも事務室に報酬を支払わせるためには、自分が出かけていって直接交渉しなければならないだろうと考えながら、勢いよく階段を駆け降りたが、喉へ込み上げて来る膨れ切った厚ぼったい感情は、飲み込む度に執拗に押し戻してくるのだった。
作家の江藤淳は、「実存主義を体よく表現した小説」というよりも安岡章太郎や川端康成などの叙情家の系譜につらなる作品ではないかと分析しているようでした。
中期以降の大江さんの作品には、目を通す機会がありませんでしたが、川端康成に次ぐ世界的な作家となり、ノーベル賞を受けたのちも、それまでと寸分違わぬ思想や、反戦や右傾化に対する徹底した抵抗のスタンスを貫かれたまま生涯を終えたということには、深い意義があるように思えます。
このコロナ禍において、論敵であった石原慎太郎氏とともに、大江さんも物故され、いよいよ昭和の純文学の終焉を迎えたような気がしてなりません。
遅まきながら、大江さんのご冥福を心から祈りたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
