
アイヌの歴史11『古代の蝦夷-前編-』

蝦夷はアイヌと同じく統一された国家や集団であったわけではなく、外部の日本人が勝手に東日本の住民を呼んでいた語で、特に弥生時代の北海道では稲作は行われず「続縄文時代」が続き、東北北部では一時的に稲作が導入されたが、気候上の問題で行われなくなっていて、実際に文化的に異なった。
先述の通りエミシ最古の記録は5世紀、古墳時代の頃の雄略天皇が宋に送った文書の中の毛人の国々を征服したという記録で、雄略天皇は盛んに蝦夷を征服した事がわかり、間接的な最古の資料は日本書紀の中にある弥生時代の神武天皇と古墳時代前期の景行天皇の記録で、景行天皇の息子で隼人の古名であると思われる熊襲や出雲を併合したヤマトタケル皇子に蝦夷の征伐が命じられたがその途中で死亡したとされる。

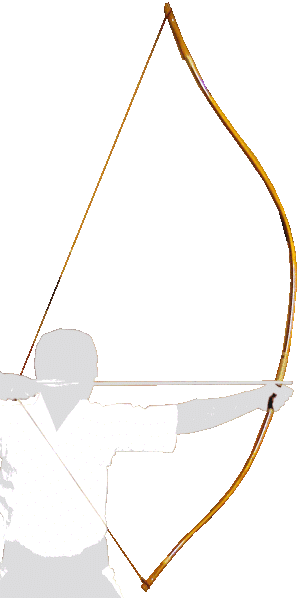

蝦夷は、由来が弓に関係するという説が出るほど弓が上手かった記録があり、蝦夷の使う弓は日本人の使う弥生人の「丸木弓」が戦争のために威力を付けるため大型化した「長弓」とは違って、速さ重視で威力が低い「短弓」を用い、これを古墳時代に中国から日本人と通して伝わった馬と組み合わせ強力な弓騎兵となり、柄と刀が一体として作られた「蕨手刀」という馬の上でも使い易い刀が開発された。

また、古墳時代の前方後円古墳の分布は大和朝廷の勢力圏の中のみで、古墳時代前期には越後平野、会津盆地、仙台平野まで分布しており、古墳時代が終わる頃には太平洋側では北上盆地、日本海側では山形盆地まで北に広がり、飛鳥時代以降には今まで古墳が造営されなかった東北北部や北海道の一部で末期古墳が作られた。

この頃の日本では地方の豪族が軍を持ち、行政や裁判を担う国造という小国家がヤマト朝廷の下に服属する状態であった。
当時の東国を見てみると、現在の南東北では現白河市あたりの白河国、岩瀬郡周辺を石背国、郡山市周辺を阿尺国、いわき市南部を菊多国、いわき市北部中部を石城国、かつての標葉郡を地域を染羽国、福島市の大部分を信夫国、相馬市や南相馬市周辺を浮田国、角田市周辺を伊久国、亘理わたり郡周辺を思国、
東関東地方では、つくば市周辺を筑波国、桜川市や筑西市周辺を新治国、水戸市や笠間市周辺を茨城国、ひたちなか市周辺を仲国、常陸太田市周辺を久自国、日立市の一部を道口岐閉国、日立市や高萩市・北茨城市周辺を高国、山武市周辺を武社国、千葉市周辺を千葉国、成田や佐倉など旧印旛郡を印波国、銚子市や旭市周辺を下海上国、
西関東地方では群馬県全域を上毛野国、大田原・矢坂・那須塩原・那須烏山・さくらなど旧那須郡を那須国、那須郡地域を除いた栃木県全域を下毛野国、小田原市などを師長国、神奈川県東部を相武国、秩父地方を知々夫国、埼玉県の中部を无邪志国、その他の武蔵国を胸刺国館山市周辺を阿波国、鴨川市周辺を長狭国、旧周淮郡を須恵国、袖ヶ浦市や木更津市周辺を馬来田国、市原市の一部を上海上国や菊麻国、茂原市周辺を伊甚国、
中部地方では岐阜の池田町周辺を額田国、不破郡周辺を三野前国、本巣市周辺を本巣国、関市や美濃市周辺を牟義都国、各務原市や岐阜市・可児市周辺を三野後国、高山市や飛騨市・下呂市周辺を斐陀国、長野県全域を科野国、名古屋など旧尾張国を尾張国、豊橋など東三河を穂国、岡崎や豊田など西三河を参河国、浜松市と磐田市を遠淡海国、掛川市や森町周辺を久努国、菊川市や御前崎市周辺を素賀国、旧清水市周辺を廬原国、富士宮・富士・沼津などを珠流河国、伊豆地方を伊豆国、山梨県全域を甲斐国、
北陸では加賀市周辺を江沼国、金沢市や小松市周辺を加我国、旧若狭国を若狭国、敦賀市周辺を角鹿国、丹生郡を高志国、坂井市周辺を三国国、羽咋市周辺を羽咋国、七尾市周辺を能等国、富山県全域を伊彌頭国、糸魚川市周辺を久比岐国、十日町市周辺を高志深江国、佐渡島を佐渡国が支配していた。



地図と照らし合わせて見てもらえばこの当時の日本領土の最北端は新潟県中部の高志深江国と離島の佐渡国、最東端は福島県沿岸部の石城国、菊多国、浮田国あたりだった事がわかる。

7世紀中期には、先ほど述べた領土の他にも山形県の最上(もがみ)と置賜(おきたま)が朝廷に服従、これを気に南東北全域を含む陸奥(みちのく)国が常陸(ひたち)国から分離される形で設置され、その後、宮城県にあたる地域の全域が平定され、日本海側沿岸では北陸にあった諸国を指す越国の国造軍と朝廷軍が連合して新潟県北部を制圧した。
この時期には朝廷から直接送られた知事、国司による各地の支配、つまり豪族を通した間接支配ではなく朝廷の直接支配が始まっており、新潟や東北では、本来、その地域の内政を行う国司が、蝦夷の懐柔や討伐などの外交も行なっていた。

当時、政治、軍事の拠点で多くの蝦夷が居住する中心都市にもなる「城柵」というものが設置されており、ヤマト朝廷に長く支配されていた近畿・中国・九州北部に見られた総領(すぶるおさ)や太宰師(だざいのそち)などの軍人が派遣された「古代山城」よりも政治・行政の拠点としての色が強かった。
また、先述したため詳細は省くが朝廷に服属した蝦夷は俘囚と呼ばれ、多くの俘囚が日本各地に移住した。
