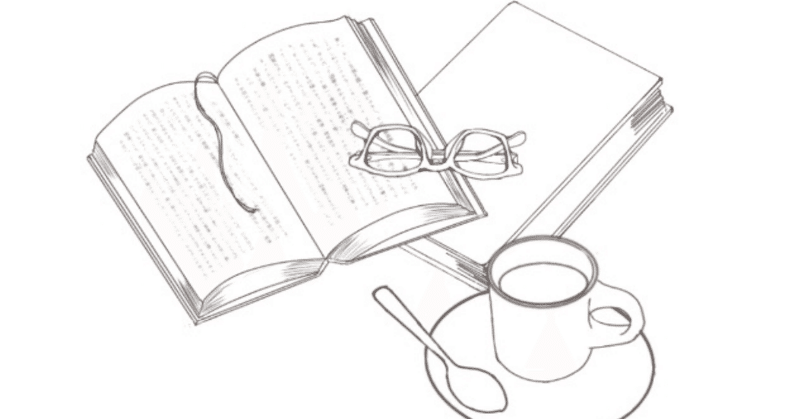記事一覧
リンクとの関係性から読み解く『ブレワイ』『ティアキン』のストーリー
(このレビューにはティアキン・ブレワイのネタバレがあります)
2023年も様々なゲームが発売された。その中でも、5月に発売された『ゼルダの伝説 ティアーズオブザキングダム』は一際注目を浴びた作品である。はじめに言っておこう。このゲーム、買って損はない。シリーズ続編としても単体作品としても楽しめる作品で、遊びのボリュームもたっぷり。僕は5月にこのゲームを買ったが、12月になった今でも全然楽しめる。
怒涛に怒涛を重ねた新年度が過ぎ去り、酒を飲み、束の間の安息を享受している。色々嬉しいことありがたいことあってこれからも頑張りたいと思う一方で、これからなんてなくていいとも思う。そんな気分。
https://spotify.link/wcTGS9Br5Ib