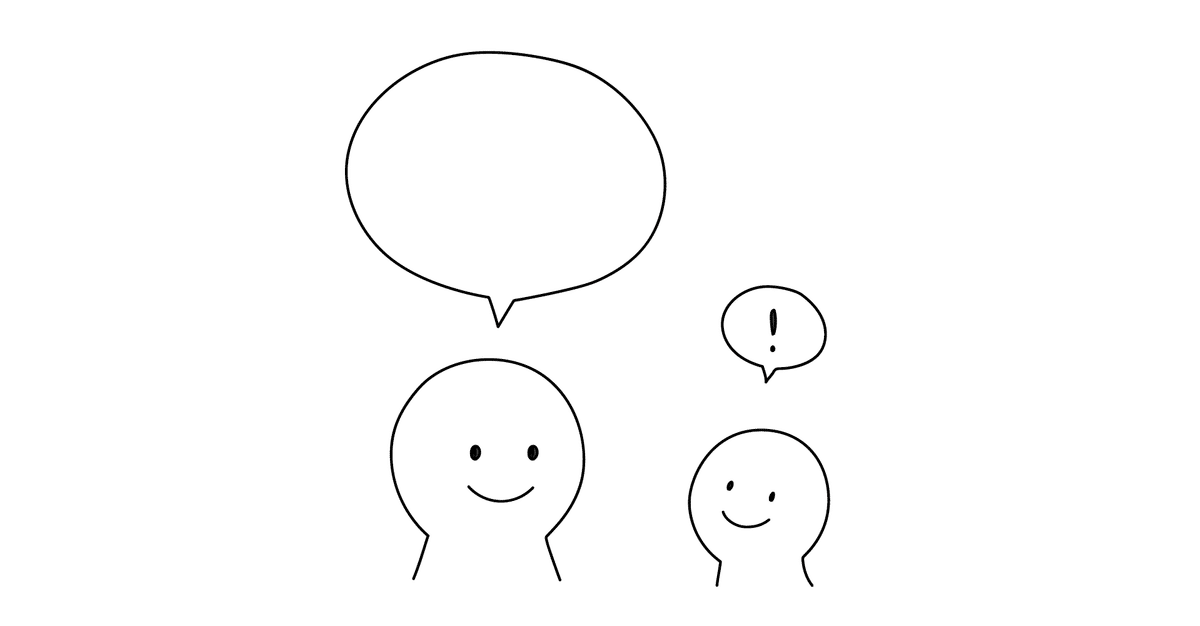
Photo by
norinity1103
学びませんか?射を行う態度
弓道には射を行うにあたり、「射を行う態度」「射法・射技の基本」などがあります。
それらの内容に関連し、的中の成否を決めるであろう「大三」や学科問題の参考になる項目などもまとめてあります。
A4サイズで全5ページ。
文字検索もできるように設定してあります。
(個人的に、複数枚あるPDF書類は文字検索できなければ活用性がないと思っているので)
🔶見出し
✅射を行うにあたって
✅基本体の必要
✅射法・射技の基本について
✅澄ましの方策について
✅間について
✅息合い
✅大三と引き分けについて
✅会の構成(詰合い、伸合い)
✅巻き藁の効用について
錬士や六段の学科問題に出題されるような項目もあります。
「射の成否は大三にある」と言われるように
✅大三と引き分けについての部分は少し細かく書いてます。
個人的には、「大三の成否=的中」と思っています。
なので、
「引き分けの感じがしっくりこない」
「会で弓手(または妻手)がうまく使えない」
「会で伸びられない」
「離れが弛む・引っかかる」
など、大抵の原因は経験上、
打ち起こしから大三への受け渡しの際に
どこかしら失敗している場合があります。
受け渡しの際
▶肩のラインがズレていないか。
▶肩の根(肩関節)で動かそうとしていないか。
▶両肘に位置(特に右肘)は左右高さが同じか。
などが要因として多い場合があります。
これを実践するとなかり引き分けがつらいと思いますが、
それだけ楽をして「手先の力」で引いていたとも言えます。
気に入ってもらえたら、応援お願いします!! 1年で100万貯めて借金繰り上げ返済ヒーローズジャーニーを実施中です。

