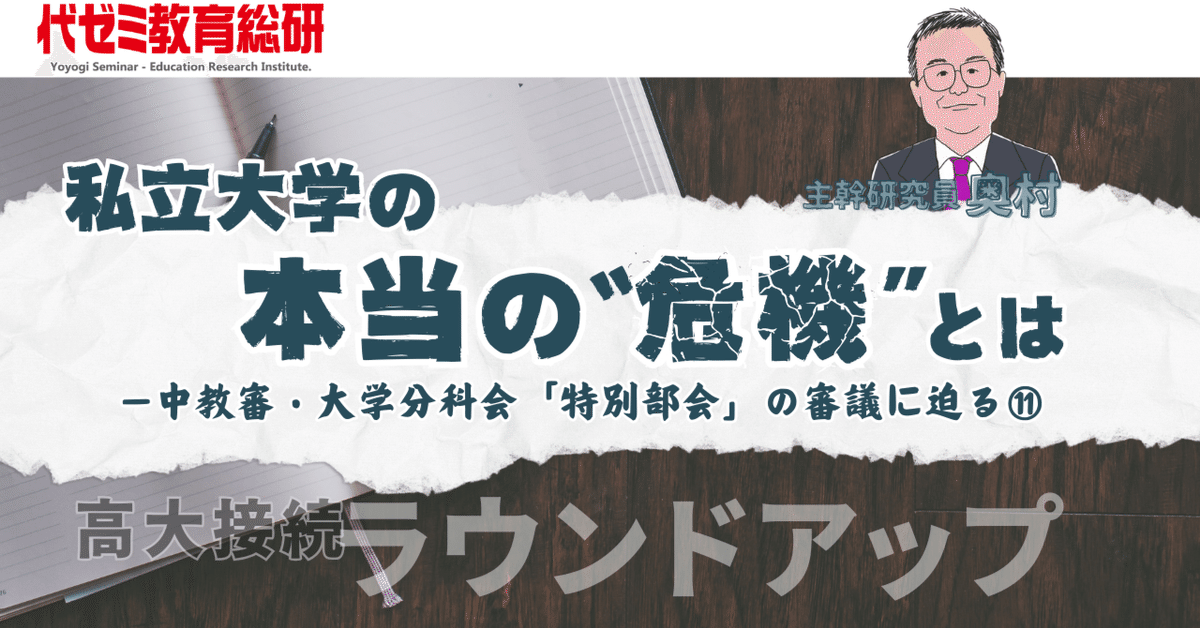
経営難の私大に縮小を促す策も明るみに。しかし、大学が絶体絶命の危機に瀕している現在、まず規模の適正化=総量規制に、再び取り組むべきでは
本シリーズでは、主幹研究員の奥村直生が文部科学省中央教育審議会の大学分科会で現在審議進行中の「高等教育の在り方に関する特別部会」を追いかけます。
この特別部会で挙がる数々のテーマや議論の方向性は、日本の高等教育の未来に多大な影響を及ぼすものであり、大学をとりまく全ての関係者にぜひ注目していただきたいのです。
特別部会の核心に迫っていきたいと思いますので、皆さまどうぞシリーズの最後までお付き合いください。

▶崖っぷちの大学の背中を押すことに
「高等教育の在り方に関する特別部会」の答申案の取りまとめの期限がいよいよ迫って来るなか、2024年12月29日、日本経済新聞は、「経営難の私大に縮小促す 文科省、「改善なし」は助成減額」との、私大関係者にとっては、刺激的な見出しのついた記事を掲載しました。
答申案自体はまだ完成していませんが、方向性はほぼまとまったということで、さっそく文科省がそれに対する具体的な施策を示した、ということでしょうか。
記事では、26年度からの配分基準を見直す、としているので、現在行われている25年度入学者選抜の募集結果が基になるのでしょう。
日本私立学校振興・共済事業団が給付する「私学助成」を絡めて規模の縮小&撤退を促す、とのことです。
現在行われている入試の段階で、出始めている結果がすでに芳しくない大学の関係者のみなさんは、まさに気が気でない記事ですね。
「収支が悪化した大学」に対して「経営改善計画」なるものを提出させ、改善が見られなければ私学助成の減額も検討する、とのことです。
本来、助成は経営が悪化した大学の支援のために使われてもよさそうですが、逆なのです!
仮に、計画書を提出させられた時点で校名が明らかになるようなことがあれば、それを知った受験生は、当然次の年からその大学への出願を避けることになるでしょう。
そうなれば、その大学はクローズの方向へ一気に加速してしまう可能性も・・・
まさに、崖っぷちにある大学の背中を押す、とも言える、とても冷酷な施策です。
▶学生に不利益を与えないように、とあるが・・・
以前からお伝えしていますように、募集が悪化している私立大は24年度入学者選抜においてすでに急増していますので、こうした現状を考えると、この施策が一気にあちこちの大学に適用されることも考えられます。
そうなると、そこにいま通っている学生たちは果たしてどのような心持ちになるのか、とても気になります。
施策の趣旨には、「突然の破綻により学生に不利益を与えないように」とはありますが・・・まさか、逆効果になりはしまいか。
適用される条件等詳細は記事からでは不明ですが、「収支が悪化」とありますので、必ずしも、入学者選抜の結果だけが基準となるわけではないようです。しかし、実質的には入学定員、収容定員の充足率とリンクすることは間違いないでしょう。
どのような施策になるのか、非常に気になるところです。
▶高等教育局長の耳を疑う回答
さて、前回は規模の適正化における設置者別の内容、特に、国立大学と私立大学の違いなどについて、見てまいりました。
規模(入学定員、あるいは収容定員のこと)について、適正化の具体的な内容、つまり、めざすべき数値が、残念ながら明記されていないのです。
残された会合の中で、数値目標などが加えられる兆しは、いまのところ見えません。
どうして、明確な数値が示されないのでしょうか。
実は、これについて、文部科学省の基本的な姿勢がうかがえる驚くべき場面に、最近出会うことになりました。
この特別部会と並行して開催されている『国立大学法人等の機能強化に向けた検討会』第5回の会議(11月26日)で行われた質疑の中でのことです。
日本私立学校振興・共済事業団理事長の福原紀彦委員(元中央大学総長)が、文部科学省の伊藤高等教育局長に対して、
・・・前略・・・・国立大学に配分される定員,あるいは,その時代のニーズを見て,こういう領域のこういう人材はこれだけ必要なんだと,そういう国家の政策の意思決定のプロセスというのは,具体的にどうなっているんでしょうか。
と尋ねたのに対し、伊藤高等教育局長は、次のように回答したのです。
・・・前略・・・いわゆる高等教育計画というような中で,国の意思を持って行っていた時代というのは,少なくともこの30年ほどは実はなくなってきている状況でございます。さらに,20年前に法人化をいたしましたので,法人化以降は法人化の趣旨をもって,国が直接に動く部分の関与という意味では,正直この20年間なくなってきてございます・・・中略・・・
福原先生がおっしゃったように,国全体として,文科省がこの分野が何人足りないからこういう要請をしていく。それを,各国立大学に言うことを聞かせていくという手法は,現時点において,現時点というか,しばらく取っていない・・・後略・・・
まさに、驚くべき発言です。
前半の「高等教育計画」ですが、実は、この30年ほどなくなっている、とのことなのです。
つまり、現在は計画そのものがない!
文科省は、大学を含めた高等教育全体の規模をどのようにしていくかについては、ノーアイデアということなのです。
▶いつのまにか消えてしまった、『高等教育計画』
この高等教育計画――昭和50年(1975年)代から平成16年頃までを対象に存在していたもので、文部科学省のHPでも紹介されています。
大きく4つの時期に分かれていたことが、文科省の表からわかります。
とくに後半の2つの時期は、18歳人口の減少期にさしかかり、それまでの政策から大きく舵を切っていることがわかります。

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/gijiroku/attach/1411679.htm
最後の区分、つまり『平成12年度以降の高等教育の将来構想について(平成9年1月)』をよく見てみると、「大学等の全体規模及び新増設については抑制的に対応」とあり、「臨時的定員は5割まで恒常定員化を認めつつ16年度位までの間に解消」とあるのです。
18歳人口が大きく増加する前半の2つの時期で設けた臨時定員増を、平成16年度までの5年間をかけて無くす、となっていたわけです。
しかし、この臨時定員増の解消は、結局行われずに、増えた定員はそのまま恒常的な定員に移行してしまったのです。
つまり、人口は減少しても、間口は広いままの状態が続くことになってしまったのです。
★このあたりの経緯や事情については、少し前の資料になりますが、元文部科学省の官僚でいらした合田隆史氏による講演記録が詳しいので参考になります。
第Ⅱ部大学の設置形態と財政より合田隆史「大学の入学定員を考える」
・・・・🏫・・・・
どうして、臨時定員増の解消から撤退することになったのか――そこには、さまざまな事情があったのです。
主な事情を私なりにまとめてみました。
■私立大には18歳人口の急増期に臨時定員などで受け入れを担ってもらった恩があるので、縮減期になっても、すぐに定員を元に戻せと言いづらかった。
■入学を希望しても入れなかったあぶれてしまった高校卒業者(浪人生)が膨れあがり、社会的に問題視された。
■大学に進学したいのなら、そのニーズをできるだけ掬うべきという声も大きくなっていた。
■大学進学率は、より上昇する可能性もあると考えられていた。 等々
▶自由競争の原理に委ねる「新自由主義的発想」の台頭
そして、もっとも大きかった事情は、
■設置したいところは条件さえクリアすれば設置させて、あとは自由競争の原理、つまり新自由主義的な考え方にゆだねるべきである、という考え方が台頭してきた。
ということでしょう。
不人気な大学については、自然淘汰されていくのを座視して待つ、という考え方です。
以前、このシリーズでもご紹介した平成24年(2012年)の田中眞紀子大臣の騒動が起きたころには、まさに、文科省において、こうした暗黙の方向性が定着していたわけです。
大学設置のための審議会を通過さえすれば、文科省は認可する。
いいかえれば、大学定員に関するコントロールから実質手を引いてしまっていたわけです。
つまり、“総量規制”から撤退してしまった、ということです。
そうした結果、高等教育計画で始まった臨時定員増が、最終的には撤廃ではなく、恒常化していってしまった。はっきりした方針がなくなっている、ということなのです。
▶露呈してしまった、文科省の無方針
福原委員は、おそらく高等教育計画なるものが消滅していることはすでにご存知だったのではないでしょうか。それでも文科省には、大学全体、あるいは国立大学の規模をどうしていくかについての方針を、一般には知られていないにしろ、きっと何か持っているはず、との思いで質問をしたのでしょう。
しかし、高等教育全般行政の責任者である伊藤高等局長の回答を受けて最初のご発言は、「投げたボールが返ってきたような思いがするご答弁であったのですけれど・・・」。
ここに、福原委員のかなり拍子抜けしたお気持ちが読み取れます。
つまり、文科省は、結局、無方針、無策なのである、ということなのです。
これは高等教育局長のご発言ですから、間違いなく、文科省には計画はないことが、露呈したわけです。
だからこそ、今回、この特別部会が緊急で催されたとも言えるのかもしれませんが。
しかし、待ってください。
このような、計画性のないところで、現在の大学の入学者募集活動が執り行われている現実を改めて知ることになり、私は背筋が寒くなる思いになったのです。
あまりに、無責任すぎないか・・・
残念至極です。
▶金縛り的状況から、一刻も早く、抜け出すこと
百歩譲って、上で述べたように諸事情や、時の政権による政治的圧力もあったとご推察いたします。文科省はいた仕方なく現在の金縛り的状況に至ってしまっている・・・。
しかし、そうであっても、高等教育の規模というものの責任を最後に取るのは、国、そして文部科学省しかいないのです。
もちろん、文科省ご自身も、高等教育全体をコントロールできなくなっている状況に、実は困り果てていて、何とかしなければいけないと思い至り、今回の特別部会を設けてもらうに及んだ、とも言えるのかもしれません。
ですが、仮にそうであるなら、アクションの始動があまりに遅すぎた、と言わざるを得ません。
でも、前を向いていくためには、文科省は現在の金縛り的状況から一刻も早く抜け出さなければいけない。
ただちに、行動を起こしてほしい、これに尽きます。
🏫「高大接続ラウンドアップ」マガジン👇
これから進学をされる未来の大学生の方々、そして保護者、大学・教育関係者やさまざまな皆様に、現在進行形の高大接続の現状をお届けしながら、その行方を探っていくマガジンです!
\フォローお待ちしております//✨

#代々木ゼミナール #代ゼミ教育総研 #教育総研note #大学 #高等教育 #文部科学省 #大学院 #私学助成 #高等教育計画 #国立大学 #私立大学
#新自由主義
