
ペポーゾと安心院の小公子 ~日伊の料理とワイン②トスカーナ編~
ボンジョルノー!
イタリアと日本の食について気ままに綴る「日伊の料理とワイン」の第2弾は、「トスカーナ」です。
トスカーナは、イタリア半島のブーツの付け根に近い位置で、西側はティレニア海に面する中部イタリアの州です。
イタリア20州のなかで、私はトスカーナ州のワインを一番多く味わっていると思います。これまで延べ200種類くらいでしょうか。
キャンティやブルネッロ・ディ・モンタルチーノなどのワインの産地としても有名ですが、海沿いのエリアのミネラル感のある白や、キャンティに名を連ねることにこだわらない赤も美味しいです。
今回は、トスカーナの郷土料理や農村などについてご紹介します。
トスカーナの郷土料理「ペポーゾ」
トスカーナ州の州都はフィレンツェ。
そして、フィレンツェといえば「ドゥオモ」が有名ですね。
「ドゥオモ」を建設する際に、レンガを焼く窯で煮込み、現場の職人さん達が食べたという料理が「ペポーゾ」です。
▼以前、ようこさんの記事でも紹介されていました。
ドーム部分は1446年に完成したそうです。
そのころ日本は室町時代!
そんな昔からある郷土料理なんですね。
Peposo(ペポーゾ)
は、コショウを指す「ぺぺ」から名付けられました。
今回、色々なレシピを検索して、「料理通信」で紹介されていたレシピをもとに、少しアレンジして作ることにします。
このレシピのポイントは「鍋底の汁が透明になる」まで、肉を10分程度炒めるとのこと。
よくレシピで、肉に焼き色をつけてから煮込む工程がありますが、「鍋底の汁が透明になる」まで炒めることを意識したことはありませんでした。
生肉を炒めると、肉汁が一度、肉の外に染み出します。時間をかけて炒めると、その水分が蒸発し、肉汁の旨味だけが再び肉に戻ります。この時、水分=味が入る隙間ができる。
鍋底が濁った汁から透明な汁に変わると、その準備が整った合図。赤ワインやブランデーを加え、味を入れ込んでいきます。しっかり味が染み込めば、無名の肉でも、深い味わいに仕上がりますよ。
「料理通信」の記事より
主な食材は、牛肉、コショウ、ニンニク、ローリエ、赤ワイン。

鍋にオリーブオイル、ホールの黒コショウを12粒ほど、ニンニクも入れて、香りが出たら、肉を加えて炒めていきます。

鍋底が、やや艶っとしたように思いますが、こんな感じでいいでしょうかね?
さて、レシピではこの後トマトペーストを入れていましたが、「ドゥオモ」を建設していた頃、イタリアにトマトはまだありませんでした。
そこで、今回は「ソフリット」で旨味を追加することに。


玉ねぎが飴色に
玉ねぎと人参を刻んで、オリーブオイルで炒め煮するようにして30分ちょっと。
玉ねぎが飴色になったら、半量を肉の鍋に追加。
(ソフリットの残り半分は、別の料理に使うため冷蔵庫に保存。)

赤ワインとローリエも追加して、2時間以上煮込みます。
蓋をして途中で混ぜつつ、様子を見て水分が少なくなると赤ワインを足します。
結局、ワインをボトル1本近く使いました。

柔らかく煮込まれたお肉にマッシュポテトを添えて、いただきましょう!

旨~い!!
お肉にワインほぼ1本とソフリットの旨味がしみ込んでいて、凝縮感があって濃厚です!
赤身の部分は肉らしい食べ応えがあり、すじのところは柔らかく溶けていきます。
たまに、ホールのコショウもありますが、よく煮込んだ後なので角がとれてそれほど辛くありません。いいアクセントになります。
塩分を控えめにしたマッシュポテトともよく合います~。
さて、この料理に合わせたのは、トスカーナの赤ワインです。
レ・マッキオーレ ボルゲリ・ロッソ(Le Macchiole Bolgheri Rosso)2019

(2018はブショネだったぽいですが)
「レ・マッキオーレ」のこのワインは、トスカーナの海沿いの「ボルゲリ」エリアで、メルロー、カベルネ・フラン、カベルネ・ソーヴィニヨン、シラーをブレンドして作られています。
noteでも何度もご紹介している、大好きなワインです。
豊かな果実味としっかりとしたボディで「ペポーゾ」に寄り添い、濃厚な料理にも負けませんでした。
貴族ではなく農家がつくったワイナリー「レ・マッキオーレ」のワインと、労働者のための郷土料理は好相性でした~♪♪
イタリアの都市と農村
トスカーナ旅行するとしたら、フィレンツェなどの都市にも行きたいですが、郊外にも行きたいです。
▼フィレンツェ郊外に暮らしていらっしゃる素敵なnoterさんも!
トスカーナには、「アグリツーリズモ」と言われる「農家風の宿泊施設」が数多くあります。
フィレンツェやシエナの郊外の農村でゆったりと滞在して、糸杉のある風景やブドウ畑などを眺めながらや現地のオリーブやワインを楽しめるそうです。
日本にも農家に宿泊する「農泊」はありますが、イタリアでは1985年にアグリツーリズモの法律ができてからイタリア全土に2万箇所以上の「アグリツーリズモ」ができ、なかでもトスカーナは多くのシェアを占めます。
(⇐この辺の具体的な数字が本の中に書いてあったように思うのですが、見返しても見つけられず…。うろ覚えで書いているので、見つけられたら訂正・補足しておきます。)
日本の農村は元気をなくしているように言われます。
イタリアの農村も一時は人口が大きく減ったものの、今は人口の減少がとまって、輝きを取り戻しつつあるとのことです。
そのキーワードになるのが「テリトーリオ」。
英語の「テリトリー」とも、フランス語の「テロワール」とも違う概念だそうです。
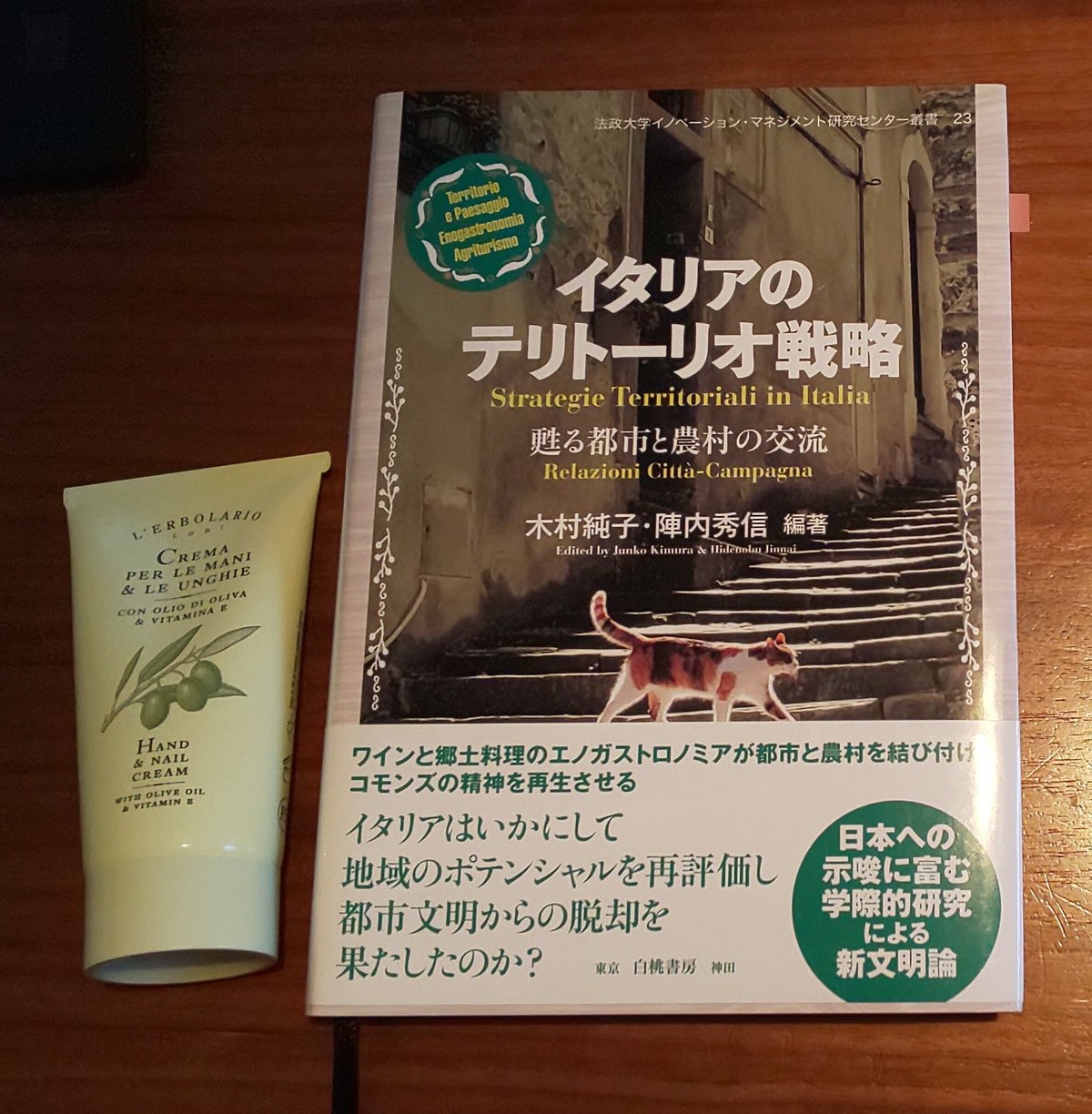
左にあるのはイタリア製のオリーブオイル入りハンドクリーム
いま、この「イタリアのテリトーリオ戦略」を半分読んだところです。
著者は、イタリアの建築や都市の研究者として有名な法政大学の陣内先生など。
複数の方の学術論文が集めてあって、テリトーリオについて多面的に解説・紹介されていて、とても面白い。
テリトーリオの定義や捉え方は、以下のように紹介されています。
「都市と周辺の田園や農村が密接に繋がり、支え合って共通の経済・文化のアイデンティティを持ち、個性を発揮してきたそのまとまり」
「経済目的の達成だけを目指す農業ではなく、地域コミュニティ維持と環境保全を含めた地域バランスの回復を目指す社会システム」
そのテリトーリオの例として、キャンティ地方の取り組みなどが紹介されています。
本の内容に触れると長くなるので今回はやめておきますが、消化できたことを後日まとめたいと思います。
安心院の小公子
さて、「ペポーゾ」を食べたときに、日本ワインと合わせるとしたら、と考えて注文したのが、こちら!
安心院葡萄酒工房 「安心院(あじむ)ワイン 小公子(しょうこうし)」2020

大分県の安心院葡萄酒工房のワインです。
このワインは「小公子」というヤマブドウをかけあわせた品種から作られています。
以前飲んだ時、日本ワインの赤にしては凝縮感があり、ボディがあって美味しかったのが、印象に残っていました。
一部、冷凍保存しておいた「ペポーゾ」をあたためて、ワインと合わせてみます。
こちらのワインは濃い色調、プラムやカシス、黒コショウの香りがして、ドライで厚みがあります。
想像どおり、コショウのきいた「ペポーゾ」に合いました~♪

この「安心院葡萄酒工房」は、「いいちこ」で有名な「三和酒類」が、2001年に安心院町につくったワイナリーです。
実は、「安心院ワイン」の歴史はワイナリーより長いのです。
ブドウ栽培が盛んだったことから、「三和酒類」が地元産のブドウで「安心院ワイン」をつくったのが1971年。
「いいちこ」ができたのが1979年だそうなので、「安心院ワイン」の方が先輩なんですね。
その後、高齢化などでブドウ栽培をする農家が減っていくなか、地元産のブドウでワインをつくり続けたいと、ワイナリーの自社畑を大きく拡張することにしたのが2011年。
自社畑で様々な品種を安心院で育てて、その可能性を模索されており、現在栽培している品種は20種類ほどだそうです。
この取り組みを「嚆矢(こうし)」や「諸矢(もろや)」というシリーズで知ることができます。
「嚆矢(こうし)」はチャレンジワイン、「諸矢(もろや)」はチャレンジワインよりも生産量やクオリティが安定してきたネクストステップのワインという位置づけです。

右:安心院ワイン 諸矢 テンプラニーリョ 2019
これらのワインはまだ試していませんが、どんな味わいか楽しみです。
小公子もかつては作り始めのチャレンジだった訳ですが、今では生産量も安定しており、とっても美味しいワインでおススメです。
この安心院ワインと、先ほどのトスカーナワイン、それぞれその地域の良さを活かしたワインづくりはつながっているところがあると思うんです。
・・・
今回は、トスカーナの郷土料理と日伊のワイン、さらに農村エリアについて思いを馳せてみました。
3週間余りかけて、少しずつ書きためてきた記事です。
話があっちこっちに行って分かりにくかったかもしれませんが、私なりに日伊のワイナリーや農村について考える、いい時間になりました。
テリトーリオの本も、まだ半分残っていますし、新しい気づきなどありましたら、またご紹介したいと思います。
長くなりましたが、今回もお読みいただきありがとうございました🍷
